【物の怪の『源氏物語』】 Text By 水沼真有美
『源氏物語』を読んでいて、「物の怪」の動静が気になっていた。なにかピントこないのである。これはあくまで創られたものにすぎない。「物の怪」とは実際何であろうか。
文学作品を読んでゆくのに、事実としての裏付けは必ずしも必要ではない。しかし、千年も前の作品の中で、生霊や死霊が暗躍し、かつ、それによって重要な物語展開がなされてもいるのである。
文学作品の中の「物の怪」は虚構化されたものである。
例をあげてみると『源氏物語』では、例えば六条御息所の「生霊」の様態が問題である。それは克明・リアルに描かれていて、読む者が引き込まれ、生霊の強い存在感を訴える。しかし、「生霊」とは何であるのか。『源氏物語』以外に生霊の実現が記されることはなかった。多くの「死霊」の記事があるもの、記録類から「生霊」を見出すことは、まずできない。
生霊の具体的な描写、それは『源氏物語』のみである。紫式部の創作なのである。むろんそこには、それを承知の上で人間と「物の怪」を交錯させて表現する作者の意図があり、思想があったと言える。現実には生存者の怨念は、生霊としてではなく、「呪詛」つまり、「のろい」のかたちで伝えられたのである。
紫式部の独自の「物の怪」観を表すものとして、「紫式部集」44番歌が知られている。
『絵』に物の怪つきたる女のみにくき図(=絵)書きたる後に鬼になりたるもとの女(=妻)を小法師のしばりたる図書きて、男(=夫)は経読みて物の怪責めたるところを見て
亡き人の託言はかけて(=かきつけて)わづらふををのか心の鬼にやあらぬ
これし「物の怪」に憑りついた亡き前妻(鬼になりたるもとの妻)が描かれ、夫は経を読んで「物の怪」を調伏しようとしている。という絵に対して、「紫式部」は『亡き人に』の歌を詠む。夫がこのような憑霊を見るのは「をのが心の鬼、すなわち、その人の「疑心暗鬼」が生み出す現象としている。
また、史書・記録類に記された憑霊はかなりの数にのぼるが、正体が判明するものの全ては死霊であり、その大半が政治がらみのものであった。正体不明の例の多くは、被憑者が政界の中枢に位置していないなどで、発霊の予測がつけにくく、正体を特定できなかったものと考えられる。
史書・記録類には決してなかった、女性の生を見つめる作者の鋭いまなざしが、生霊の必然性を導き、『源氏物語』の際立った独自の世界を築き上げたのである。
ここで、「柏木の病」について、少しふれたいと思う。柏木の病に、父大臣は原因を知らぬまま、多くの修験者などを招き、加持をさせたりする。憑霊を考えるのは、あるいは、自然かもしれないが、柏木の病の特殊性は映えるのである。
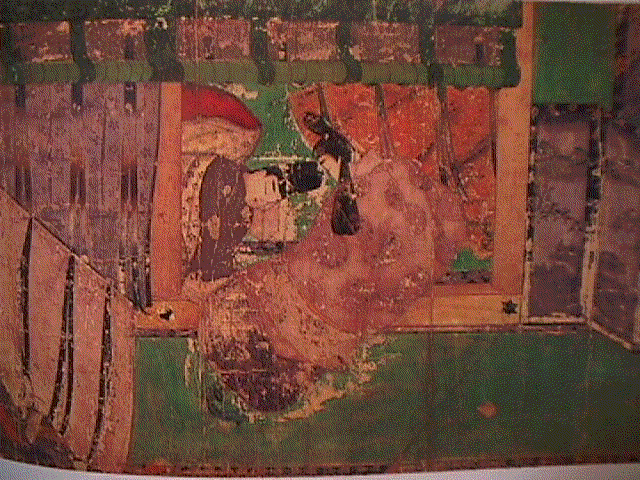 国宝『源氏物語絵巻』柏木(左が柏木、右、夕霧)
国宝『源氏物語絵巻』柏木(左が柏木、右、夕霧)
『わづらひたまふさまの、そこはかとなくものを心細く思ひて、音をのみ時々泣きたまふ。陰陽師なども、多くは女の霊とのみ占ひ申し上げれば、(父大臣は)さることもやと思せど、さらに物の怪のあらはれ出て来るもなきに思出て、わづらひて、かかる隈々をも重ねたまふなり』(柏木・283)
訳 「柏木の病状には、何ということもなくただ心細い面持ちで声をもらして時々お泣きになる。陰陽師なども、多くは女の霊がとり憑いているとばかり占い申したので、父大臣はそうかもしれないとお思いになるが、少しも物の怪が正体を現してくるものもないのに困りはてる」
陰陽師などが「女の霊の仕業と占申したが、全く物の怪が現れる様子はない。柏木自身も『あれ、聞きたまへ。何の罪とも思しよらぬに、占いよりけん女の霊こそ、(284)』と言って、その占申の見当違いに失笑するのある。
そもそもね「女の霊」はどこから出されてきたのかというと、先の波線部のように、何となく心細げにさめざめと声を出して泣く様が、女の様態に似ていると言うことからであろう。実は、このような表現の類例ががいくつもあるのである。夕顔が物の怪にとり殺された後、源氏は悲嘆に沈み、1ヶ月近くも病床の様子など次のように描かれている。
『いといたく面や痩せたまへれど、なかなかいみじくなまめかしくて、ながめがちに音をのみ泣きたまふ。見たてまつりとがむる人ありて、『御物の怪なめり』などいふもあり』(夕顔257)
「御物の怪なめり」と見たのは、むろん、直前の波線部が源氏の様態によるところが大きい。特に、先の柏木の場合と同様、きわめて女性的な様子で泣くところが見とがめられているわけだから「女の霊でも憑いたのか」と考えられたといえよう。
柏木の病が、その典型的な例であるように、真相を知らされていない者たちにとって、原因不明の病や死などは、物の怪憑依によって起こされたものと考えられがちであった。これはまず、時代背景がそのようなものであったといえると同時にも、『源氏物語』自体も、そのことを常に念頭において、場面を構成しているということである。
「物の怪」は人間関係などの暗部を照らし出すといった意義を荷わされていた。男社会といえる王朝貴族社会の、階層的一夫多妻制の下に、翻弄される女性達の痛みは、時に理解されぬまま、物の怪憑依という原因が持ち出されることによって、韜晦{とうかい}されることがあったと思われる。『源氏物語』は、史書や記録類が記すことがなかった、これらの女性の逼迫した{ひっぱく}した苦痛と物の怪との関わりを物語化したといえるだろう。病を語り、その悲劇的精神史を象徴するものとしても、物の怪を介在させたと考えるのである。
ここに「物の怪の文学」としての『源氏物語』の独自性があったと言えよう。
参考文献 藤本勝義『源氏物語の物の怪』(青山学院女子短期大学学芸懇話会・1994)