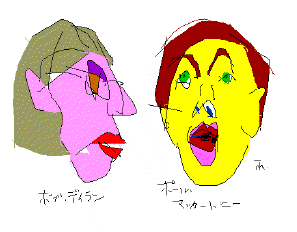
9. 彷徨うものとしての人間 窪山 潔
陰欝なる静寂の立籠むなかで,ポープの煙だけが軽快に存在者としての己を固持しつつ,結局は触媒にすぎないとしても茫漠とした曖昧さを感じさせない。ウエスタン,カンバス,ボブディラン,そしてポール・マッカートニー‥‥‥全てポテンシャルは不変なのに断片のみしか保てないのは,所詮形而下的条件が,形而上的存在に込まれないためだろうか。どうしようもなく曖昧である。 子供の頃,快いぬくもりのある寝床を離れて用を足したあと,カチカチ歯を鳴らしながら,突き刺すような空に浮ぶ月を眺める時,やすらぎを覚えるということが,今は対物的にしかありえなくて,熱烈なる願望に変わったのを"年令"という言葉で説明づけるのは,単なるノスタルジアにすぎないと思う。むしろフッサール的思考………もし我々が心的過程の諸法則を確実に凝視することができるならば,それらは論理的自然科学的な諸法則と同じように,永遠,かつ不変のものであろうし,また心的過程がないにしても,それらは同様な行動である。――のほうが,慰めの形而上学であっても頷けるようだ。 1970年11月某日,マスコミ的安保闘争の終焉を物語るかのように,三島由起夫は決定的な物質的自己破壊である自殺を遂げた。彼の偏狭なまでも知的な風貌と,一種独特な美学を追求してきたと云われる文章は,それを契機にして永遠に文学史的なものとなったのである。 彼の文学的完全性が,生活的完全性に移行しないはずはないという論点においては,43年前の芥川竜之介の死と対比されるかも知れない。彼もまた嘗って古代ギリシャ人が,人工の翼を太陽の光に焼かれた為に海に落ちて死んだように,ヴォルテェルの人工の翼を広げ易々と空に飛び上って,自らの命を断った。 しかし,それらを断想する時,峻烈に脳天を叩き割ると仮定しても,そういうことは皆無にかかわらず何ら結果には影響しないだろうし,羅列的に存在する三面記事にすぎないのは何故だろうか。 …………………………………… タランテラよ 汝の顎もて 觸山ざりし者とも咬め 汝の咬むところ すべて黒き斑紋を生ぜしめ 息吹きと共に毒を廻す 咬め 汝の三角の紋章を その数を増すとも意識せざる者を, …………………………………… もうよそう。カミューに登場してもらうことにする。「スタヴローギンという男は,何かを信じている場合でも,自分がなにかを信じているとは信じていない。何も信じていない場合でも,自分が何も信じていないとは信じていない,そんな男だ。」―「悪霊」― 判断停止,思考は自らを陶酔せしめ,思考自体を否定へと導いてゆく。曖昧さは依然として続くのみ。 既にポープの煙は無く,漂いくるやわらかな温かみをガラス越しに感じさせるものは,ここまで来るのであろうか。単に夜が朝になる過渡的現象であろうか…………… 故郷がほしい。ほのかな憫ひを含む。
 目次に戻る
目次に戻る