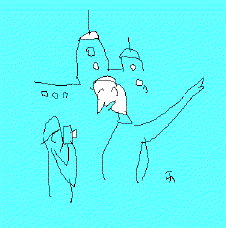
45. 雑感 藤崎一裕
ソ連を旅行した人の手記に,街で写真を撮っていたら,一人の青年が出てきて,「どうしてこんな所の写真を撮るのだ。ソ連にはもっと立派なものが沢山あるのだからそういうものを撮れ」というような抗議をしたと書いてありました。細かいことは忘れましたが,この旅行者はソ連では「教育」が成功しているらしいと結んでいました。 この教育ですが,教科書裁判でも話題になりましたように,非常に難しい問題を含んでいるようです。 社会の土台は経済構造であり,この土台の上に法律や政治の諸制度が作られ,さらにその上に宗教,芸術,道徳,哲学などが位置するという考え方があります。この考え方によると教育は,その経済機構(社会体制)にのっとった制度のもとで,その体制が必要とする,あるいは最善と信じる)人をつくることになりそうです。さきのソ連の青年の話は,この教育が成功している一例でしょう。もう一つの教育は,社会の下部構造そのものをも問う人間を育てることです。この立場に立てば,社会の土台を完全なものとはしないことになりますから,場合によっては,社会の上部構造である法律、政治などの諸制度やその社会における道徳にまで疑いを入れる余地が生じることになります。 大学における教育が全人教育か知識の切り売りかということを考えるときにも,つねにこのことが問題になり,私などには難しくてとても結論が出せそうにもありません。ただ,つねに土台にまでは戻って考えない人といつも土台を疑ってばかりいる人と二通りの人を育てるのはどうもいけないようです。 さて,それでは,真の教育は如何にあればよいかということになります。話を簡単にするために,現実の社会はその生産力の増大とともに生じる矛盾によってやがて新しい社会体制に変る必然的段階にあるとします。そうすると,現実の体制の崩壊に助力することこそ歴史を創る勇気ある人の行動ということになりそうです。それにはまず積極的な破壊活動がありますが,これはとても勇気のいることで誰にでもできるものではありません。もっと消極的にはサボタージュがありますね。昔から公務員の美徳として大切に守られてきたものに「遅れず,休まず,働かず。」というものがあります。「人に教えるに行をもってし,言をもってせず。事をもってせず。」というのは乃木希典の言葉ですが,皆さんの周囲にも,消極的な破壊活動であるサボタージュを実践している「同志」は私をはじめとしてぼちぼち見うけられるものと思います。一たん事あれば「教える官僚」として学生集団と対決しなければならない教官の中にも「同志」が案外いること(したがってあまり先生方をいじめないように)をあなたがたの後輩に語り伝えてほしいものです。 喉元すぎれば熱さを忘れるということばがありますが,この数年間激しかった学園紛争も一応下火になりました。昨年はいわゆる過激派の人に味方して(?),つねに自分自身を変革する必要を説きました。今年は学生のもう一つの立場に立って,自分達の社会は自分でつねにより良くする必要があることを書いたつもりです。(来年は学長の味方をする予定ですぞ!) 最後に次の言葉をはなむけにします。 「地位を選択する場合にわれわれを導くべき主な道しるべは人類の福祉ということだ。われわれ自信の完成ということだ。この二つは敵対して闘うもの,一方は他方を否定するはずのものと考えるのは誤りで,人間の天性は,その時代の完成と福祉とのために働く場合にはじめて自己の完成をも達成することができるようにできている ……… 歴史は,世の中全体のために働き,それによって自分自身を完成して行く人を,偉大な人物と名づける …………」
 目次に戻る
目次に戻る