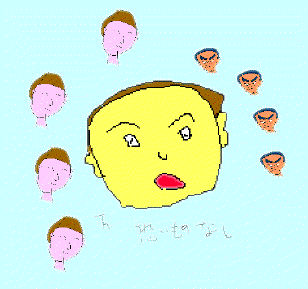
42. こわいものなしの世の中 渡辺 明
振返ってみると,筆者らの少年時代には,家では親父がこわかったし,学校では先生がとてもこわかった。 そして,戦時下の学徒動員時代には,いつ爆撃で生命が吹きとぶかも知れぬというこわさまで加わって,常に緊張の中に置かれていた。しかも,深刻な食料不足の為,こうりゃん高粱の飯で飢えを凌ぎ,未利用資源と称して草の葉っぱまで食わされた。 この事を考えると,此頃の学生諸君はまさにこわいものなしである。家長たるべき親父は全く権力を失い,アメ玉ママは大学の入学試験にすら息子に付添う有様,学校でも決して鞭をくらう心配はなく,また大平の世にしあれば明日の生命も確実に保証されているからである。のびのびすくすくと育ってきた,しかも逐次体位の向上している学生諸君を見るにつけ,しみじみとうらやましい。 しかしながら,反面,この事が,「近頃の学生は体力があって耐力がない」と評されたり「昔の学生のような凛々しい厳しさがない」と指摘される一因となっている事を見逃すことはできない。 すなわち,麦が踏まれて成長する様に人間もやはり逆境の中に育つ,と信ずる筆者にとって,この様な環境の中から生産される人間の"ひ弱さ"を否定できないのである。 「人生はばら色である。などとぬかしている人間に人生なんてわかる筈がない。人生とは不如意なものよ!」と曽野綾子が何かに書いていたが,まさにその通りだと筆者も考えるのである。 この意味において,人間にとって特に成長期には,"こわいもの"があるべきだと思えてならない。何と言っても親父は一家の大黒柱であり,"きびしく"あってほしいし,先生は学生にとり,"こわい"存在であらねばならぬと考えるのは,筆者の単なる懐古趣味ではない。 「神の下,人間は平等である。」とする本質は変わらずとも,教育を授ける者と,授かる者とが同列に並んでは真の教育にはならぬと筆者は信ずる。やはり,教えを説く者はキリストであり,釈迦であるべきで,受ける側はそれを有難く拝聴し,謙虚に学ぶ精神に至らねば,教育の真髄は果され得まい。そのためには,先生は学生より尊敬される存在とならねばならぬだけに,吾が身の程を知る思いではあるが…………。 同様に,お医者様は,患者の脈をとっただけでも患者の心を和ませ,熱を下げるくらいの,厚い信頼に値し,かつ患者をしてある種の信仰に至らしむるほどの"偉さ""こわさ"をもっていなければならぬと思うのである。「薬療あって医療なし」「点数稼ぎの算術師」などと酷評される様では,真の医療は果たせまいと考えるが,如何であろうか。 近時,やれ家庭教育の理念だの,やれ学校教育の原理だのと,この難しく論ぜられているが,家庭や学校が真の意味でもっとこわいものとなる事が,最も大切なポイントではないのだろうか。先生は,時に愛の鞭を振ってもびしびしやるという,古い寺子屋式の教育に再び戻るべきだと考えるのは,筆者の危険なセンチメンタリズムであろうか。 いたずらに,肩書きやワッペンに驚かぬ学生諸君の聡明さには教えられる思いだが,長幼の序もわきまえぬ振舞いは慎むべきであり,「浮世はきびしい。自分より一パイでも余計,この浮世のメシを食った人は偉いのだ」とする価値観に立つ謙虚さは,決して忘れてはなるまい。 こわいものなしの環境に育った者が,こわいもの知らずの単細胞的自己主義型の人間に成長していくのは必定である。こわいものはないと思っている人間程こわいものはない。 こわいものなしに成長してきた諸君にとって実社会への巣立ちは"深刻なる不如意"との,まさに初めての出合いとなることだろう。浮世の風は人にきびしいものであることを認識してほしい。 (昭和46年2月24日夜)
 目次に戻る
目次に戻る