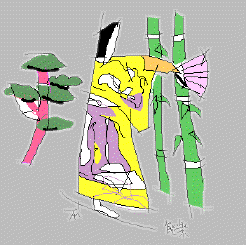
39. 謡曲のすすめ 山本 敬
信濃路遠き旅衣 信濃路遠き旅衣 日もはるばるの心かな…………。 これは謡曲の奥伝「とくさ十賊」の冒頭の一節である。 足利時代の貞治2年(1363年)。 今から約600年前のこと,日本に稀代の天才兒「世阿弥」というものが,申楽師「観阿弥清次」の息子として生まれた。そしてこの父子2代で現今みるような世界的な「能」をほぼ完成の域に達せしめた。 信濃なる浅間の嶽に立つ煙 浅間の嶽に立つ煙。 おちこちびと遠近人の袖寒く 吹くや嵐の大井山……(略)……佐野の渡に着きにけり」。これは有名な「鉢の木」の中の句である。ともに世阿弥の作で名曲である。 英国の劇作家,文豪「シェクスピア」の名を知らぬ人は文学を志す人でなくても世界の中でほとんどあるまい。しかし,彼に勝るとも劣らぬ不世出の能作者(劇作家で同時に音楽家でもある)世阿弥は余り知られていない。 私は先達に勧められて謡を習い始めてから,いつの間にかもう足掛け7年いや8年にもなろうとしているが一向に上達しない。道は遠く極まりない本を見て漸く声は出せるようになったもののまだほんの掛けだしという有様である。 世阿弥はたった一冊の本の中でさえも,ある時は千家物語を,古今集を,新古今集を,和漢朗詠集を,あるいは萬葉集などをとありとあらゆる東西古今の文献を縦横に駆使して一篇の能をまとめあげている。 私などが数頁の短い学術論文をいくつかの文献を引用しながらも,七転八倒の苦しい思いをしたあげく一年以上,時には十数年も要してかきあげるのとはえらい違いである。 しかも世阿弥のそれは時代を経てますます美しく素晴らしいものに昇華されてゆく。 月の名近き明なれや 月の名ちかき秋なれや おばすて姨捨山を訪ねん…………。」これは謡曲のなかの最高の極伝「姨捨」のはじめの句である。これも亦世阿弥の作。 信越本線で上野から長野に向う途中,右に煙噴く浅間火山を眺め,左に千曲川を,やがて小諸を,そして上田を過ぎて西に1000米級の山嶺がうち続いているなかに姨捨山(1252m)という山がある。 「姨捨」伝説は古今集の中の 我が心慰めかねつ更科や 姨捨山に照る月を見て (読人知らず) 右のたった一篇の歌から,大和物語,今昔物語などの中に脚色せられているものを世阿弥は,更級山にかかる中秋の名月をたたえ,やがて月に菩薩を見, 転変の世相を謡いあげている。 信濃路には見るところが多い。歴史をふりかえり物語のなかに入りこんで行ける所がすくなくない。この3月初旬(昭和45年)地質調査をたのまれて雪の深いなかを歩きまわったことがある。鉄平石など砕石用の山を調査したわけであるが,信州では自然が殆んどそっくり残っている。未開発だからと言う人があろうが大自然が大きすぎるので人間のなす仕事は自然のなかに吸い込まれてしまっている感じである。 私は有難いことに仕事がら旅を楽しめる機会が多い。その時は必ず一冊の謡曲の本を持って行くことにしている。なるべく目的の土地に縁のあるものにしている。宿屋でたった一人ぽつねんとしている時はこれを謡うほど楽しいことはない。信州路で,軽井沢で,長野で,そして日田という田舎町の宿でも謡った。 昨年9月末はローマの古風の宿の屋上で,折りからの名月を仰ぎながら,椅子の上に正座して「隅田川」を1時間以上にわたり謡った。夜の情景は私の 眼底に残っており,何時までも忘れることが出来ない。 「卒業記念文集」に乞われるままに漸く一文をものして責任の一端を果たした。諸君の卒業を記念して謡曲をすすめたい。 ――――――― 追記 ―――――― くさみやま朽網山名居る雲のうすれ行かば 我は恋ひなむ君が目を欲り これは万葉集の柿本人麻呂の歌であるが、右の歌に出てくる朽網山とは小倉区朽網とも又は「久住山」のことともいわれる。 その朽網の地に昭和46年の初春から,小生寸土を求め,茅屋を建て,かりのすみ家と定めた。戸畑には,もう4分の1世紀25年も住み,煙にややむせ黒ずんで来た。戸畑もよい土地であるが…………。 ここは空気は清く大自然がまだまだたくさん残されており,しかも汽車いや電車の駅に近いことが最大のとりえである。ついで序での折にはどうぞお立寄りを,住所は小倉区朽網字平原・錦水苑(通称)
 目次に戻る
目次に戻る