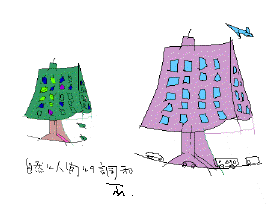
38. 技術者の対話 山本 宏
最近,新聞テレビの報じるところによれば,農薬が多量に使われるようになって,その影響が農作物に現われ,人体に悪影響を及ぼしそうだという。またそのために昆虫が居なくなったり,川には魚も少なくなった。したがって,これを食べる虫や鳥も少なくなるという現象が現われて,人間生活に直接間接に影響するところが大きくなった。過ぎたるは及ばざるが如し。自然界には大きな循環がある。自然の摂理のどこかを破壊すれば全体のバランスがこわれるのは当然であろう。この辺で反省して見る必要がある。昔にかえって,天敵の利用を考えようではないか。もちろん農薬を一切使用しないというのではない。天敵と農薬をうまくバランスさせて利用する。こうして人体への害を 取り去り,ホタルが飛び交い,小鳥がさえずるという環境を取り戻そう。今後の農学の考え方や研究は,このように進められるだろうとの事である。 過日,機械学会誌に「流体工学の研究に思う」と題する葛西学長の論文が出た。学長は関門トンネルの換気問題を担当された流体機械の権威であることは周知の通りであるが,この論文の中で,私には先生の次の言葉が強く心に残っている。 「すぐれた流体機械を得るためには流体の気持の良い同情者になるべきである。壁面にはさまれた空間を作って,そこに流体を流す場合,自分の希望通りに流体は流れてくれる等の考えは大きな誤まりである。流体の気持の良い同情者となって,流体が気持良く無理なく流れるようにしてやる事だ。」 言いかえれば,流体の身になって考えてやることが必要だということであろう。 この言葉は,土木の世界にも,全く同じようにあてはまり,わたしの持論と共通しているので,我が意を得たりと非常に面白く感じたのであった。 水工土木関係では言うまでもなく水の良き同情者または理解者となって,無理なく流れるようにしてやり,しかも制すべきは制してやってこそ良いものができるのであって,その他土木工学のいろいろな面でこのような考えが成り立つ。 たとえば,私の専門の分野で思いつくままに2・3拾ってみると次のようである。 構造物に外部から力が作用すると力はいろいろな部材から部材へと伝えられて大地に導かれる。ここには,力の流れもまた無理なく円滑に合理的に流れるようにしておかなければならない。無理に流そうとすれば,必ず反抗してきて,応力集中をはじめとするいろいろな嫌がらせをしてくれる。 風という流体も又然り,気持よく無理なく流れるようにしておかなければ,風はまず風圧を強くすることで,われわれに反抗する。パイプアーチの利点の一つはこの点にあった。アーチにフィンを取り付ければ風はさらにおとなしくなってくれる。 自然の木々は丸い幹をもって風と共存しているし,竹のような丸くて中空のものに対しては,自然は,―― または神は ―― これにフシを蓄えて補強させている。東海道新幹線の新大阪駅では中空円筒形の柱を用いることになり,床げたその他との関係のもとに,ちょうど竹のフシに相当する柱の補強をどうするかが問題になり,新しいアイディアのもとに検討された。これはオインピックに間に合わせると言う至上命令のもとに私が担当して大規模な実験も行なうなどして1年間かかって検討し,その安全性を確認したのであるが,主として柱の工作法との関連のもとに,どのようなフシをつけるのが合理的であり安全であるのかの問題であった。一見して何の変哲もない竹のフシがいかに上手に作られているか。そこには人間の為し得ざる,神の存在をさえ感じさせられる程の自然の英知があった,と云っても過言ではないと考えさせられた事であった。 吊橋はとくに耐風安定性が重要な構造物であるが,風の流れの乱れが問題となる。吊橋には若戸,関門または本州四国連絡橋のようにトラス型式のものがあるかと思えばイギリスのセバン橋のように航空機の翼断面に似た薄肉中空断面の吊橋もある。ドイツには長楕円薄肉中空断面の計画もある。これらは架設地点の気象条件や地形等を勘案の上,風の性質を良く知って架設地点の風に対応する適切な形式を選出しなければならない。ここにも風というものの良き理解者,同情者という態度が必要となる。 昔から「柳に風折れなし」という。露伴の五重塔に出てくる日本の工人は,経験的にこれを取り入れて数多くの美しい五重の塔を作った。今で言う超高層建築に匹敵するこの構造物は兵火に失われたものはあるが,風や地震でなくなった例はない。自然にさからわず,うまくこれに順応させるすぐれた技術は現在の設計にも取り入れられているのである。 目を転じて草木を眺めれば,これはまた何と美しい形態をしていることか。ただ見た目に絵画的な美しさがあるというのではなく,力学的にバランスのとれた躍動がある。古来,草木の形態の研究から構造物の形を論じようとする試みは数多くなされてきた。 また,草木の種類によって,人間の言ういわゆる剛構造あり,柔構造あり,自然界は実に上手な材料と構造の配置をしている。そこには,ダーウィン的な考えも成り立とうが,神の仕業と考えざるを得ないような奥深い配慮がある。剛・柔構造とは,自然界をみて学びとったわれわれ人間がつけた名称であった。 われわれの構造物も,自然を含む外界を良く理解し,それに順応する構造と材料配置を考え,これらを一体として取り上げ,練り上げてこそ本当の意味の合理的で経済性のある美しい構造物が出現すると思うのである。 与えられた紙面をすでにオーバーしたようである。限られた枚数ではうまく言いつくすことができないが,要するに自然を含むわれわれの身のまわりのものは,われわれの仲間である。 これらとの対話の精神が必要である。 対話を通して,これらの良き同情者,理解者になってやると共に制すべきは制し,適正な材料を使用する態度を取るべきであって,われわれの意図に反抗するどうしょうもない厄介者という敵対視はいけないのである。 これらとの対話からいろいろな事を学びとれば,工学的に数多くの収穫が得られよう。これらの所産をもとにして,さらに対話を続けてよりよい解決を求めて行く。はじめに書いた農学の考え方もこれに類するものではなかろうか。 葛西学長は「気持の良い同情者となれ」ととかれる。わたしは「対話の精神を忘れるな」と言う。表現は違っても帰するところは同じであると思うのである。 大学を卒業して就職をする。就職先には,学歴,職歴を異にする多種多様の人達が居る。このような人達とどのように接し仕事をすれば良いのか。ここにもつまり相手に対する良き理解者となる態度が必要である。 その上に,技術者には技術という面でここに述べたような人間以外のものに対する理解者たるべき態度が必要となる。 その仲立をするのは対話の精神である。 然り,技術者にとって対話の精神は,ひとり人間関係の中にだけあるものではないと思うのである。 西 瓜 かたのりきみぬいて しりの穴 ゆったり しめて たっぷり まろやかな 肚に力がはいって, こんな西瓜はうまい グーッと 人間も西瓜も一つやな―
 目次に戻る
目次に戻る