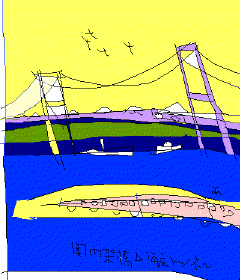
36. 関門海峡に佇んで 荒木 忍
九州地区土木系学生会210名と一緒に,12月13日 関門架橋、新幹線トンネルの見学に行った。私達が学生の頃,ここは連絡船で渡っていた。和布刈海岸に立つと,対岸の国道2号線を自動車が,ひっきりなしに走っており,海峡は船舶のラッシュである。海底にはすでに2本のトンネルが有り,今,架橋と新幹線トンネルがそれに加わろうとしている。30年の年月は,人の動きを全く変えてしまっている。 現在の鉄道トンネルと新幹線トンネルを比較してみても,長さが5倍もの新トンネルが 工期は半分の4年ででき上る。30年前の工事と格段の相違があると言える。経済力の相違も大きな原因であろう。しかし,技術的にも「海底の断層破砕帯の突破も,技術的には自信が有ります。」と,それ程苦にはしておられない模様で,それも現在の国鉄トンネル,国道トンネル,青函トンネルの経験で裏打ちされていると思えば心強い限りである。和布刈斜抗の現場を見学したが掘削発破,トルクレットによるセメントガン,斜抗ローダーなどの駆使は,青函トンネル技術の生み出したものであり,調査抗での200米を超える水平ボーリング技術も,日本の生んだ最新技術である。シールド工法も使わずに易々と突破できるのかもしれない。 以前「難工事」と言ったり不可能に近いとされていたことが,今日は日常茶飯事となっている。その変化の早さにただ驚くばかりである。 諸君が,私の年令位になった頃は,どのように変化しているのか,想像することもできない。この変化のエネルギーは諸君のものである。私達がやって来た仕事の数十倍の仕事を易々とやってのけるだろう。古い世代を尊敬するのはこの新鮮さに対してである。大学卒業は,社会人としての出発である。足踏みをしないように,停滞しないように,常に新しいものへ頭を突き込むように願わざるを得ない。 学歴も年功も処世の足しにはならない時代となるだろう。大学で教わったことも処世の基礎のほんの一部分に過ぎなくなるだろう。 これから自分で積み上げる技術の重みだけが,諸君の一生を支えるものとなるに違いない。 きびしい世の中になると思われる。 御自愛を祈る。
 目次に戻る
目次に戻る