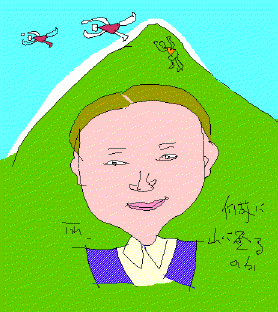
34. 最後のいい訳 吉岡民夫
「何故に山に登るのか」という問いはもう余りにも言い古されたし,その答も色々あった。その中で最も的を得てる答はマロリー(「そこに山があるからだ」と答えた英国の登山家)ではない。今はなき岳友Fの言葉だ。「この間の答えを知ろうと思うなら山にゆきたまえ。その中で君達は文頭の問の答が解かるだろう。否,解からないかも知れない。しかしそのような問は発しなくなる。」 私はこれらの写真を見る度に,寒さに耐え,ビュンビュンうなる落石を避け,ハーケンを打ち,ステップを切り,ザイルを快調にのばしている自分の姿を思うのだ。(中略)遠足の前の晩の小学生が,期待で胸をふくらませ,一人でニヤニヤしているのと同じだ。何故にこんな気持が,それこそ泉がわき出てくる様に私の胸の中を占領していくのかを論ずる必要はない。私は山に登った事があるからだ。 しばらくゆくとモルゲンロートにそめられた槍ヶ岳が目に飛びこんでくる。白い月がきまり悪そうに青空にそわそわしている。J.P.で夜が明け太陽が昇った。モルゲンロート程その命の短いものはない。夕焼が明日の天気を約束して落着いた美しさを持っているのに対し,朝焼は何かそわそわしている様だ。それだから,朝の気負った山男の気持によく合う。 幽遠の中,すがすがしい空気を腹一杯吸い込み,ただ一人ブラブラさまよい,ふっと振り返った時,白い煙が暗い谷間に漂い,原始林の緑と,帝国ホテルの赤い屋根との対比に心を奪われた時,始めて上高地の良さを知った。 以上は私の山日記の稚い文章の一部をひっぱり出したものだ。みんな私の名前を聞く時,あの「山キチ」かと思っただろうし,あのいやらしい,耳ざわりな山の自慢話の犠牲になった友も多かろう。 山に登るという超不合理的行為を合理化しようと試みたものだ。それが別れゆく友への最後のいい訳である。そして,山に登ったから落第したなどと,自分の不勉強を合理化する気などさらさらないとみえを張っておくのもやはりいい訳である。なんてことはない。最後まで我が友は私の山の話の犠牲になったのである。 友の新しい門出に祝いの詩を述べなくてはならないのだろうが,私の貧しいボキャブラリーでは余りに一般的な事しか書けない。しかし,唯,なおかつ一般的に,友の健康と飛躍を心から願うだけである。
 目次に戻る
目次に戻る