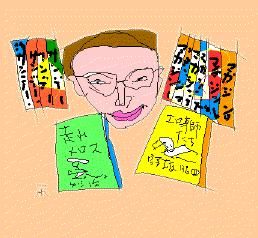
28. つらつら思うに 松本道夫
この 卒業文集の原稿を 早く創り出さなければならないと あせったけれど 現在の小生では 屁やゲップならいざ知らず 良い文章はなかなか出て来ない昨今は思考性が劣悪化してきており 難しい事を長く考えることが できない。一つに 20才を過ぎ 精神も肉体も古くなってきたことも有るが,最近本を,全然読まなくなったのが一番の敗因であろうと思われる。 夏休みが終って,北九州に帰って来た時 就職先の会社から 第一報が届き「皆さんの近況」「最近読んだ書物の読後感」を知らせるようにとあった。皆さんの近況という所は 当時ずっと実家にいたことを書いたが 最近読んだ書物の読後感は「最近 碁と麻雀に凝っていて それに関する本以外読まず 読後感などありません」と 書いたが それでは会社は ひどい馬鹿を採用したようで 何となく気が悪かろうと思って 四ヶ月前読んだ本の 読後感を付け加えて 送った。ひとつは太宰治の「走れメロス」で,もうひとつは野坂昭如の「エロ事師たち」である。前者の方は 小さな話にくぎってあり 特に感動する所は 少ないけれど「東京八景」「帰去来」等は,当時の太宰治の心境がにじみ出ている。後者の方は,題の如く 色事に関する小説であるが 並みのエロ本とは 全く違って,真面目な態度が全編を通じて流れている。と,以上の感想文を送ると 数日後 先方から「先日貴殿からの お便り 読ませていただきました。元気に 頑張っておられる様子 頼もしく思っています。」と云う 返報があったので 一応安心した。 実際この数ヶ月というもの 自慢ではないけれど 教科書以外の書物を読んだことがない。しかし少年雑誌は 毎週一通り読ませてもらっている。特に僕の気にいっている作家はジョージ秋山で,少年ジャンプの「現約聖書」その前の「デロリンマン」は 少年サンデー,マガジンの銭ゲバ,アシュラよりも抜群によいと思う。 悟りある者は いない 神を求める人はいない すべての人は 迷い出て 悉く無益なものに なっている 善を行う者は ひとりもいない 彼等の 喉は開いた 墓であり 彼らは その舌で 欺き 彼等の唇は マムシの毒があり 彼等の足は 血を流すのに速く 彼等の道は 破壊と悲惨とがあり そして 彼等は 平和の道を知らない 彼等の目の前には 神に対する 恐れがない。 (「現約聖書」少年ジャンプ) 又「魂のふるさとへ帰れ」「魂のふるさとへ帰れ」と叫んで 死んで行く デロリマン。社会の矛盾の中でただ一人 正義を行っても 他人から見れば それは悲劇か喜劇にしか見られないデロリンマン。そして以前のパッとマンX。そして人心の腐敗した社会の中で絶えず 絶対性があるのは神だとする ジョージ秋山の 宗教的思想に賛成するわけではないが 彼の漫画は最近の小生にとって 生活の糧であります。 カミと云って 思い出すのはトイレット・ペーパー。4年生の構力の時間 昨夜の二日酔の兆候があらわれて気分が悪かったので,こっそり授業を抜け出し 便所に行った。糞でも出せば気分が良かろうと 悪臭を発したのは 良かったがあわてて入った関係で 肝心なものが無い。良く話に紙が無いときは パンツで拭けという事があるが ちょうどその時 授業中で 誰も便所には入って来ていなかったので すばやく 尻を 丸だしにして隣の部屋に入った。そして普通の者ならそこで用をすますと すぐ帰るであろうが 小生は隣の忘れ物を始末して 出たのです。 このことを彼女に話すと 後日 手紙が来て「カミに見離されないように。」とあった。最初,全然この意味がわからない。髪がなくなり,ハゲになるのか,カガミに見離されて ふためと見られない顔になるのか,紙幣に見離されてスッカラピンになる事か テストペーパーに見離されて 不合格あるいは未履修になることか等,いろいろと長期にわたって考えた末,やっとこれを思い出した。カミもいろいろあるけれど 皆大切なのだと再認識した。 先日,佐藤君と話をしていて,小生は詩的才能があり,工学部にはもったいない程の人物だと言われました。今まで,淡々としてそんなもんには 無関係のように思われていたから これまた小生を再認識させました。そこで ひとつ 詩を載せましたが いかがでしょう。 愛より深く澄みとおる 湖の緑にひかれし人は 山のうっそうたる緑と 古き人をなつかしむ シャトーの跡のためならん この山と湖に我が愛を沈めん ここに住みついた山家の猿は 自分を人間だと思い込み そう努力はして見たが 猿と人との道は 険し 猿が人になるまでは 悩み苦しみ死にかける いっそ 猿のままで 死を待てば 良かったものと思うのに 金毘羅池を 遊歩すりゃ 雌犬何してないている ぼく かわいそうにと 石なげりゃ 雌犬 感謝し 逃げてゆく 道のそばで 咲いている 花は あわれに 泥まみれ かわいそうにとションベンかけて 泥落しゃ 花は喜び 生きかえる
 目次に戻る
目次に戻る