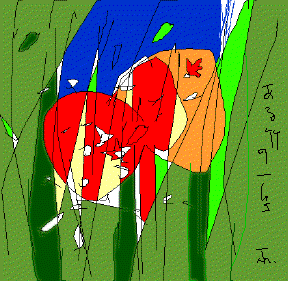
25. ある竹の葉の一生 福室忠隆
ある日空から一滴の雨が雷鳴を伴ない落ちて来ました。その一滴の雨こそ,これからお話しする竹の葉の生命の起源だったのです。すなわち,その地に翌日ひ弱な,しかし偉大な生命力をもった芽が顔を覗かせ,みるみるうちにいつしかあのすばらしい太陽の光を全身に浴び立派な若竹へ成長したのです。この若竹にも他の若竹と同様,その枝先に葉を何枚もつけていました。しかし,その中でも目を引く一枚の葉がありました。 その竹の葉は頑丈な根に支えられ厚い保護のもとにすくすくと成長し艶を増し外見だけは一人前になりましたが,真に言う自己を確立していませんでした。 そんなある日,眩しいばかりの朝日がこの竹の葉の目をさましました。目を開けると一瞬それが今まで長い長い眠りについていて,この時といわんばかりに何かが体の奥深くからもくもくと起こってきました。自我の意識が目覚めたのです。外界もすべて手に取るように認識することができるようになり自ら,思考することもできるようになり,それと同時に今度は未知の世界への好奇心が起こってきました。月日が経つにつれ,それはつのるばかりで,いてもたってもいられないようになり,それはまるで若い男が初めて恋というものを知った時のあの激しいものが,体の中からつき上げてくるようなそんな激情が体中をめぐりまわりました。 でも茎は私を,外界の厳しさを知っているがため,又,私が可愛いがため,私の手を握ってなおも外界から私を守ろうとその手を放そうとしませんでした。 しかし,とうとう頑丈な手も私の熱意,激情には勝てませんでした。私の体全体がその激情のため黄色に色づき大自然の法則によって茎の手から離れ落ちることになったのです。その時は,今まであんなに激しいほどに燃えていた感情が潮が引くように消え,哀愁が我を襲い,離別の涙のごとく我上にのっていた一滴の雨が空中で散りました。 感情がこうも急に変るものとは,今までこんな経験のない私にとって不思議なくらいの変り様,その時の異様な驚きと哀愁が交叉し,私は一種独特な気持に襲われました。 そもそも私の生命が与えられた場所は川岸近くでありまして,運よく無情な大地にたたきつけられることなく,緩やかな流れの水面にふんわりと落ちました。その間にも,実は必死になってもがきあがき,大自然に比べたらそれはそれは微々たる存在であるいでたちを大自然の力に対抗して己の力を見せんとする闘志を益々燃やし,それは,この竹の葉の命を奪わんほどに激しいものでした。そのおかげで体が前にも増して黄色に色づき赤味を帯びてさえもいました。 この激しい格闘の後にも,ただぬけがらだけが残っているようなあらん限りの力を出したせいでしょうか,何か虚無感のようなものが体中をめぐり,ぐったり疲れた体を水面に横たえて深い眠りにつきました。 夢の中で私に声をかけるものがありました。「しかばね同然の身になってそれでもおまえは生きているのか。おまえの赤い血は何処へ行った。あの時の闘志はどうした。それでは,あの時あの大自然の力に抵抗し己の微々たる力でもって己の志す方向へ少なからず従ったが,もうこれ以上あなたの力にはかな適いません。どうかあなたの意のままになさいませと,大自然の偉大さを認めたも同然ではないか。さあ,立ち上がれ。そして再び赤い血をたぎらせ,己の力で己の道を切り開いて行くのだ。………」 すると,又前と同様朝日が深い眠りから覚ましてくれました。見ると付近一面もみじの紅葉が太陽の眩しい光を吸収し反射し,まるで紅葉と太陽とが話を交し合って遊んでいるようにも伺え,又その美しいこと。こんな美しい生命の姿を私は二度と見ることができないでしょう。 ひととき,この光景に心を奪われ,うっとりしていました。するとどうでしょう。私の心を捕えて放そうとしなかったあのもみじの紅葉,その一枝の紅葉 が以前そんな経験をした時と同様に茎から離れて落ちてくるではありませんか。私の目はその一枝のもみじにじっと止って,あのもみじの紅葉と太陽とが作り出すすばらしい光景がまるで夢の中だったようにスーッと私の顔から消え,もう私の心はその一枝のもみじの葉に向かっていました。 このもみじの葉は,すぐそばの水面にふわりと落ち,いつしか私たち二人は声をかけ合い,人生観,恋愛論,友情論等の話題に事欠かず,日が暮れるのも忘れて議論しあいました。そして又も,私の心はしだいに赤い血に深まり,もう皆様もお察しになるでしょうが,私の黄色い葉が赤く,以前この目で見たあの太陽と戯れていたもみじの紅葉のごとく美しい程に燃えました。それはまるで体の奥に火がついたごとく,この可愛いもみじの葉に誰もが心を奪われました。そのためにたとえ死がのどを乾かし我々の来るのを待っていようと,皆様は一瞬の至上の喜びを得たことを神に祝福し笑みを浮かべながらきっとこう言うことでしょう。「ああ神よ。私は今日まで生きてこれたことを深く感謝いたします。どれほどこの世に見切りをつけようと思ったことか。苦しみに押し潰されそうになったことか。それを思えば,なおさらのこと今日まで私を見守って下さったことに対してどんな言葉をお返しすればよろしいのでしょうか。私の意を表わす言葉が見つかりません。」 それ程,他の心を乱し冷静さを奪う力を持っていました。さらにこのもみじの葉は,この世に悪が存在することを知りません。常にその生命を狙っていることを………。 なにしろこのもみじの葉も,以前私が厚い保護のもとにぬくぬくと成長し, 自分の姿に見る目を奪われ,ただただ暖かい茎の手のもとに過ごしていましたが,そんな人生をそれまで過ごしていました。すなわちそこでは悪は存在せず,存在するものと言えば善のみというそんな狭い世界でしたので,それはそれは純真で汚れを知らない天使のような存在でした。 ここまでお話しいたしますと,このもみじの葉がいかがだったか,又この竹の葉の気持がどんなだったかおわかりいただけるでしょう。しかしここでこの竹の葉はある事で頭を悩ますことになりました。それは,このもみじの葉が純真で汚れを知らない天使のような存在だったからです。 すなわち竹の葉としては,この純真さをいつまでも失なわせたくなかったのです。しかし,今あの古巣を出て来て,この新しい世界に入ってきた以上,それが奪われることは必然でして,そのことはこの竹の葉にとって耐えられ得ぬことで,しかもそんな姿を見ることが恐ろしくも感じられるのでした。 そこで,できればそっとしてあげて,きびしい世界に接しないように守ってあげようと考えるのでした。ぽんと厳しい世界の真っ只中にほうり投げてやった方が,このもみじの葉の為だと言われるでしょうが,単に恋とか,愛とか言いきれない異様な感情が皮肉にもある場合には,こういうものであります。 さらにこの竹の葉は,めったに体験できないだろうと思われるこの異様な感情を幸いにも,自分がこうして体験していることを幸せだと思うのでした。 こうして二つの葉はお互いそれぞれ同じ空の下,同じ旅をできることを,又日一日の目新しい周囲が益々話題を豊富にしてくれ,その仲を堅く確固たるものにしてくれることを幸せだと思いながら過ごすのでした。しかし必ずその破局が訪れることも知らずに…………。 長い年月が経ちました。この間にも何度かこの二枚の葉の仲がひきさかれようとしました。ある時は急流に合い激流に身を打たれ,又ある時は大きな岩があったり,木々が妨害したりして,その度にこの世との見切りが近いと感じました。しかし,その次には必ずゆる緩やかな流れが私たちを待っていまして体をいやしてくれました。 しかし,やがて来たるべき時が,そう言えばもうお察しになるでしょうが,その時がやって来たのです。もみじの葉のあの純真さは,思えば身の毛もよだつのですが,悪魔にさらわれたのです。 こうなることは竹の葉にもわかっていたことでしたが,希望をたくしてこのもみじの葉に接していたのです。 私たちは,滝つぼにあっという間に落し込まれました。 気がついて見ると,私たちが今まで旅をして来たこの川は,ここから二手に分かれていまして,あのもみじの葉は,もう一方の川へ押し流されているではありませんか。竹の葉はひどく体を痛めつけられ,心までもが粉々に砕かれていて,もうあがく力もなくただ川の流れに,大自然の力にまかせて,他の川を下っていくのでした。傷だらけの竹の葉は天に向かって,残っているあらん限りの力をふりしぼり,こう叫ぶのでした。 「神はなぜ私をお創りになったのです。結果があれば,その理由があるはずです。お聞かせ下さい。又,私をお創りになった以上,神の力でもってすれば,いとも簡単に私の願いはかなえられたはずです。それなのにどうしてあんな残酷なはめに私を落し入れたのですか。 私には生きる価値がないとおっしゃるのですか。 私はこれまで何度となく大自然の力に抵抗し己の力で己の道を切り開こうとしました。それが神からその生を与えられた私のあかしだと思ってまいりました。それでもまだ不足だとおっしゃるのですか。 私はあのもみじも葉にも愛というものを教えてあげました。そして,ひとときではありますが神がおつくりになった他の物を幸せにしてあげました。いったいこの私に,それ以上の何を要求されるというのですか。 「何故,こんなに私を苦しめるのですか。 神よ,お答え下さい。なぜ…………。なぜ…………。」 数日後,嵐がその地を襲いこの無力な竹の葉は,何のすべも知らず,皮肉にも自己の生命の起源であった雨に全身を打たれ,すでに周知の通り,力といえば炎のごとく使い果し,体はそのおかげで赤く枯れ果てて,精魂つきて,あわれにもそのしかばねを川底の地に,果てることになったのです。
 目次に戻る
目次に戻る