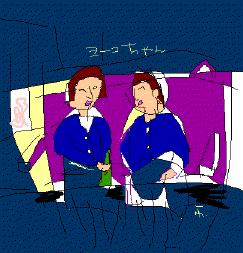
16. 聖少女 坪根康雄
地質旅行を終えて,3月17日昼前,僕は大阪駅から,急行に飛び乗った。僕の前のシートには少女と姉らしき人が腰かけていた。京都から乗車したらしく 駅ビルデパートのパッケージの土産物が網棚にあった。少女は おさげ髪で,額の広さが,聡明を際立たせていた。姉の方は 清楚な細身の人であった。 とりとめの無い姉妹の語らいのうちに,大阪を立った電車は,六甲の山てん巓近くまで,しっぴ櫛比する家屋と漂白されたような工場群の立ち並ぶ神戸の工業地帯をさつか擦過していた。紺のカーディガンを着た少女は,話題が途切れたらしく 窓外の景色に目をやっている。その時僕は 倉橋由美子さんの「聖少女」を読んでいた。書中の主人公は,眼前の少女と甚だ異なり,母に「私,男が出来たの。」等と言って,書名のイメージとのけいてい径庭著しかった。 あたりから流れるラジオがていご亭午を告げ,まもなく 着いた駅で 彼女らは 昼食をひさ販ぐ者から 幕の内を買って 食べ始めた。僕は阪神デパートで買った寿司を取り出して食べた。電車は兵庫を過ぎ 岡山へ入っていた。人家はまば疎らになり 背後に単調な起伏の山々が位置する,田園風景となると,それまでの柔らかな陽光は,薄雲により,やがて暗雲により籠絡され 時ならぬ雪模様となった。田園の小径を疾走する単車が外界の寒さを強調し,あたりは一瞬にして雪を粧った。 「コーヒーに サンドイッチはいかがですか。」虚空の寒さと対照に,暖かい列車内に売子の声が響く。 「コーヒー 飲もうか。」 「私,コーラがいいわ。」 「じゃあ コーラ 二本下さい。」 褐色の液体が 二人の喉を潤し,しゅゆ須臾にしてビンは本来の緑色になった。少女は来春受験らしく,志望校について話している。 冬の末期を告げるような春の雪は,やがておさまりしとどな雪どけ水をつけたガラス窓は,雲間から輝く日光の為,きらら色に光っている。やがて都市の到来を告げるべく,家屋がいしゅう蝟集し始め,電車は岡山駅へ すべり込んだ。岡山駅は 新幹線の工事の為,駅舎の一番反対側のホームは 工事現場を覆うべく トタンべいをしている。その視界を遮って 特急つはめが到着し,やがて発車して行ったとき,少女は, 「トムソーヤを思い出すわ。」 と,おば嫂に語りかけた。美観の為トタンべいにペンキを塗っていたのだが,それが特急の停車中に5mばかり進行していたのだが。嫂は一瞬不可解の様子であったが,記憶の中からトムソーヤを喚起したらしく 微笑んでしゅこう首肯した。僕もおぼめく記憶の中でトムソーヤはペンキ塗りと短絡した。少女は,にっこりと微笑んだ。 岡山を立った後,少女のまぶた瞼は閉じられ,かすかな呼吸音を残して寝りに入った。吸吐のリズムは あどけなさから成熟へ,成熟からあどけなさへと振動している。 やがて,車掌が改札にやってきた。嫂は2人分の切符を出し,乗り越したらしく,「尾道まで。」と告げ,不足分を支払った。尾道ならばもうすぐである。"袖振り合う"者以上の親しさを覚えていたため,僕は尾道への残りの時間を惜んだ。空は完全にそうきゅう蒼穹を取り戻し,軌道に並行する道路の標語は着実に尾道への距離を減じている。 「ヨーコちゃん,次だわよ。」―― この時 初めて判った少女の名に 僕はいろんな 漢字を思い浮かべてみた。―― 嫂の声に少女は目覚め,下車の仕度を始めた。輻輳たる家屋が妙に印象づけられる漁港の駅に電車は到着した。少女は白いコートを羽織って降り立った。一等星が近辺の星辰の存在を覆う如く,少女の姿はホームの雑踏をおぼめかせた。 ごご午后の日差を受けかくえき赫奕と輝く尾道の港を後に前の座席をぽっかりとあけたまま 電車は 再び動き始めた。"尾道の女"か!!スノビッシュにも僕の脳裏には 北島三郎 歌うメロディーが去来したけれども,それは確実な旋律にはならなかった。読み続けていた「聖少女」は拙劣さを極め,僕は本を閉じた。九州までまだ 三百キロメートル有った。
 目次に戻る
目次に戻る