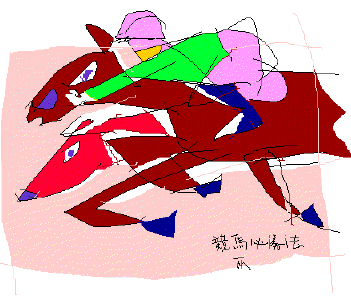
1. 『競馬必敗法』 宇都宮 遵
「パンパカパーン!各馬ゲートイン完了。第37回日本ダービーのスタートです。」10万の大観衆をのんだ場内がシーンと静まる。次の瞬間,「ガチャ」とゲートが開いて一斉にスタート。 昔、私の家にも馬がいた。名前はない。名前を付けてやる程の大層な馬でもなかった。荷車や材木を引っ張るだけの,見るからに足の遅そうなゴッツイ馬だった。しかし近所では、牛はいても馬のいる家はほとんどなかったので,私にとっては大変な誇りであった。今から15・6年程前の事だが、私の父がこの馬に乗って盗人を追いかけ,捕えたという滑稽な話がある。私はよくは憶えていない。それから2・3年後,父は馬に蹴られて,いや交通事故で死んだ。馬はそれより少し前に人の手に渡ってしまった。 私の家にいた馬がダンプカーなら,サラブレッドは差し詰め,外国製のスポーツカーであろう。スラリとした足,長いたて髪。常に日の当たる場所に居すわっているなまいきなスターである。しかしじっとしている時のショボショボっとした,深い瞳を鎮めた小さな目は,どちらも同じ位かわいらしい。 中学生の時に名馬コダマを知る。更に五冠馬シンザンに魅せられ,タケシバオー,スピードシンボリ。そして今年タニノムーティエ。テレビで見,雑誌で読み,当然それだけでは納まらずついには馬券を。 2・3人の友と土曜・日曜は一日たりとも欠かさず小倉の競馬場に出向いていくようになった。月曜から金曜までの間は,全くの空白の時間で,ただやたらに長く感じられた。そしてふと我に返ったと思ったらいつも競馬場。右手に赤エンピツ,左手に競馬新聞を持ち,ポケットには百円玉をジャラジャラさせて一日中かけ回った。血統はどうの,調教はどうの,レースの展開はどうなると一人前の通のような顔をして。(各馬の血統を知って,そのレースの距離や馬場状態に対する巧拙を判断すること。最近の調教,追い切りタイムを参考にして各馬の現在の調子を読むこと。これから行われるレースの展開を予想して,そうなった時に有利な馬,不利な馬を脚質などから判断すること。 ――競馬必勝法その1) レース前に出走馬を下見に行く。 「あの馬は色つやがいい。」 「あの馬は名前が気に食わない。」 「あそこでウンチをしている3番の馬は,余裕があるから走るぞ。」 「いや,あのウンチは柔らかいから下痢をしているんだ。」 「おい,見ろよ。セガレを興奮させているのがいるぞ。」 「あれはきっと牝馬の後ばかり追って走るに違いない。」 (レース直前の各馬を実際に見て,馬体の充実具合や気合の入り具合を観察すること ――必勝法その2) それから馬券を買いに行く。さっきこれだと決めたはずなのに,いざ買うとなると又迷ってしまう。今日は8月2日だから2−8を買ってみようか。さっき4−6が入ったからもう4−6はないとか。3−6のカブがいいとか。(競馬に理論あり。馬券に理論なし ――必勝法その3) いよいよスタート。緊張。興奮。馬が第4コーナーを曲がってホームストレッチにかかると歓声が沸き起こる。「それ行け。それ走れ。」と手をたたき,足を踏み鳴らす。「ドドド…………」 じいひずめの響。壮烈なクライマックス。はずれた馬券が宙を舞う。飛び上る者。ため息をつく者。(少し大げさ) 最初の頃は,わずかづつではあったがコンスタントに勝った。トータル1万円,2万円,3万円。こんなに儲かるとは思わなかった。調子に乗り過ぎてそのうちだんだん掛け金も多くなり,百円券から特券へ,本命狙いから穴狙いへ。(本命狙いはよく当たるが全然儲からない。大穴狙いは全然当たらない。中穴を狙え ――必勝法その4) ところが分不相応な賭け方がたたったか,運が逃げて行ったのか裏目,裏目と出るようになった。いったん付きがなくなるとまことに惨め。1日に8千円,1万円,1万2千円と立て続けに負けた。競馬必勝法という4百円の本を買って読みもしたが効果はなし。とうとうトータルでもマイナスになった。(競馬はツキが大部分いや全部を支配。付いている時には大胆に。付かない時には控え目に ――必勝法その5) 夏の小倉競馬の最後の日。行きたいけれど金はなし。よせばいいのに,今日こそ大金をつかんでやるという淡き期待を胸に抱いて,下宿のおばさんに3千円,友達から2千円借り,それに時計,背広まで質に入れて勇んで出かけた。やっぱり惨敗。(金のない時はしないこと ――必勝法その6) 夏が終わると馬は関西に帰って行き,小倉はシーズンオフ。以後時々,大レースの場外馬券を買いに行く。いまだに大金はつかめない。ある愚かなブルジョアが云った。 「馬券は金で,しかし競馬は趣味で」 ある勝れたルンペンプロレタリアートも云った。 「馬券は金で,そして競馬は生活を賭けて」 私が考案した競馬必敗法とは,すなわち競馬をすることなのである。 "公営ギャンブル絶対賛成のハンタイ!"
 目次に戻る
目次に戻る