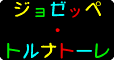
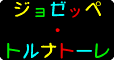
「ニュー・シネマ・パラダイス」
「みんな元気」
「明日を夢見て」
「記憶の扉」
ジョゼッペ・トルナトーレについて僕が最初に彼の作品を見たのは、大ヒットを記録した「ニュー・シネマ・パラダイス」だ。ラストのキス・シーンばかりのフィルムを見る場面をテレビ番組で見て、すぐに借りて見たのだ。内容は皆さん、御存知の映画館の話。笑いがあって、スリルがあって、愛があって。映画の醍醐味がすべて詰まっている。そして、ラストの場面で、目頭が熱くなった。トト少年とフィリップ・ノワレ演ずる映画技師との掛け合いが最高だった。カメラワークも文句のつけ所がなかった。そして、感動をそそる、エンニオ・モリコーネの音楽(ちなみに、この映画の『愛のテーマ』を作曲しているのは、エンニオ・モリコーネの息子のアンドレア・モリコーネだった。)。なんて、すごい映画なんだろう、と思って、すぐに監督を調べて、初めて「ジョゼッペ・トルナトーレ」の名を知った。監督は、なんと「ニュー・シネマ・パラダイス」に出演していた。それも、最後に主人公にキス・シーンのフィルムについて「最高の映画ですね」という役だ。
すぐに次の作品を借りに行った。それは「みんな元気」という映画だった。題名からして、なんだか、面白くなさそうだ、と思っていた。しかし、見てみると、それとは大反対、というわけじゃなかったが、いい映画だった。今や無き、名優マルチェロ・マストロヤンニが少しぼけの入ったお爺さんを演じている。そのお爺さんが家元を離れた娘や息子達を追って、街へ出てゆく。息子や娘達は彼を暖かく迎えてくれるが、どこかその裏で苦労を重ねていて、本当の姿を彼に見せない。彼は次々に息子達に再会するが、一人だけ、姿を見なかった。彼の幻想には登場するが、大人になった彼に会うことが出来ない。彼は悲しみにくれて、まだ自分の子供達が小さかったころの姿を幻想で見る。それで心を決めて、家族を皆集めて、食事パーティーを開こうとするが、たいして集まらない。すると、子供のうちの一人が、姿を見なかった最後の子供の話をする。実は彼は死んでいたのだ。悲しみにくれて、帰りの電車内で、倒れ、病院へ。彼は一名をとりとめた。心配になって、家族が皆全員病院に駆けつけてくる。皮肉な思いを持ったまま、彼は退院し、無き妻の墓に「みんな元気だったよ」と告げに行く。
笑いがたくさんちりばめられていて、その中にすっと物悲しい場面が入ってくるという前作同様の雰囲気。マストロヤンニの演技は当然、素晴らしく、涙が出そうになる。カメラワークも前作同様で、素晴らしい。エンニオ・モリコーネの音楽は前作とはころっと変わって、コミカル(出演もしているエンニオ・モリコーネ)。でも、何か、前の映画の方が面白いように感じてしまい、前作を超える、という風ではなかった。
次に見たのが「明日を夢見て」。最近の映画だ。内容はこれまた映画の話。詐欺師のカメラマンがちょっと田舎の街で俳優を発掘しに来た、と言って、カメラテスト代を持っていくという話。さらにコミカルになって、今度はブラックな笑いが立ちこめてきた。でも、ロバート・アルトマンほどの上質なブラックコメディというわけじゃなくて、笑いにくい。途中もちょっと退屈だ。ブラックなのは「こんなのも作れるんや」と誇るためか?と思ってしまう。でも、途中から修道院の孤児の女の子がカメラテストにやってくるところから、ストーリーがぼんぼんと展開していく。すると、今までになかった結構衝撃的な場面や悲惨な場面が出てくる。結末も決してハッピーエンドじゃない。題名から推測するような内容じゃないことは確かだ。
その後、見たのが、僕の一番押しの「記憶の扉」。原題は英語で「A Pure Formanity」。直訳するより良いタイトルだと思う。これは「みんな元気」「明日を夢見て」というタイトルがちょっと悪いのに比べて、良いというのではなく、ストーリーにも関わってくるので、大いにそそられる。「明日を夢見て」よりも前に作られた、ということだが、映像の凝り方は「明日を夢見て」や「ニュー・シネマ・パラダイス」を圧倒する。
冒頭、ピントのぼけた映像。かすかに動いている。と、突然、銃が真横から現れ、そこに焦点が合い、シャープに映る。直後に火を吹く。すると、今度は走る男の視点に切り替わる。その男の走り方は普通じゃない。事の重大さが伝わってくる。何があったのか?なぜ、男は走っているのか?観客はその手がかりを求めて、その視点の中に答えを見いだそうとする。だか、ただ単に彼が脅えている、ということしかわからない。彼が必死に走った後、今度は彼全体を写すシーンに変わる。その後、彼(ジェラルド・ロパルデュー)は警察に見つかって、身分証明書を持っていなかったため、警察署へ連行される。今度は一転して室内劇に変わる。不気味な署長(なんとロマン・ポランスキーが演じている)との尋問。カフカの「審判」を思わせる、状況がつかめない不安さ。しかも今度は主人公が誰なのか、はっきりとわからない。観客は不気味な署長と主人公とを対等に、疑いながら見ていくことになる。不安は二重に張り巡らされているのだ。尋問の中で彼は自分が「記憶」を失っていることに気付く。次第に解き明かされていく謎。そして、あの時、何があったのか?最後には「そうだったのか!!」と思ってしまうだろう。そして、その時には観客の目には熱い涙がこぼれ落ちるだろう。
ちょっと興奮気味だが、本当に興奮させられる映画だった。映像だけじゃない。セリフが凝っている。前記の三つの作品のような軽さはどこにも見られず、一つ一つが意味あり気でかっこよく、ずっしりと体に伝わってくる。それが緊張感を持続させているのだ。それだけに最後の瞬間に思わず「ほっ」とさせられる。
音楽も三つの作品は大きく異なる、オープニングの激しいバイオリンの曲、それから一転して、静かな曲。そして映画の鍵にもなる、歌。エンニオ・モリコーネは巨匠の名を欲しいままにしているのだ。
ジェラルド・ドパルデューの熱演もさることながら、やはりここではロマン・ポランスキーの存在感の凄まじさを上げておきたい。ピントを彼に合わせているのでは?と錯覚するほど、彼の場面は引き締まっている。不気味な姿を最後まで持ち続け、最後の最後に彼の優しさを知る。僕は映画館に大声で泣きたくなった。その後、ビデオで見直して、また泣きたくなった。ぜひ、おすすめ。出来ることなら、暗くして夜中に見よう。
ジョゼッペ・トルナトーレはまだ若い。巨匠、という名は余りにも早すぎるかもしれないが、タランティーノを巨匠と呼ぶならば、彼は当然巨匠だろう。まず、失敗作がない。確かに「みんな元気」は後一押し欲しかったが、失敗作というわけでは決してない。それから、それぞれの作品が大きく違う。キューブリックみたいでとても良い。将来、どんな映画を作ってくれるのか?楽しみだ。
![]()