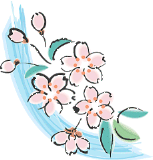
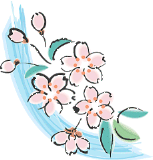 |
〔春恋〕春という季節における恋。春の風物・風趣と関連付けて恋の心を詠む。同題の歌としては、『藤原長能集』『源道済集』『散木奇歌集』(源俊頼)などに前例がある程度で、珍しい歌題と言える。もっとも、『万葉集』巻八には「春相聞」等の部立があるように、四季の風情と恋心を結びつけるのは和歌古来の伝統であった。
一番 春恋
左 勝 左大臣
鴬の氷れる涙とけぬれどなほ我が袖はむすぼほれつつ
右 俊成卿女
おもかげの霞める月ぞやどりける春やむかしの袖の涙に
左歌は「雪のうちに春はきにけり鴬の」といへる歌をとり、右歌は「月やあらぬ春やむかしの」といふ歌の心なり。ともにえんにはみえ侍るを、左、「なほわが袖はむすぼほれつつ」といへるすがた、殊によろしく見え侍れば、左ヲ以テ勝ト為。
○左(藤原良経)
鴬の氷れる涙とけぬれどなほ我が袖はむすぼほれつつ
【通釈】鴬の氷った涙は(春になって)融けたけれども、なお私の袖は、涙に濡れては氷が張り、また濡れては氷が張って…。
【語釈】◇鴬のこほれる涙―二条后の古今集の歌「雪のうちに春はきにけり鴬のこほれる涙いまやとくらむ」に拠る。◇むすぼほれつつ―「むすぼほれ」は「(水分が)凝固する」「(心が)鬱屈する」などの意の下二段動詞連用形。「つつ」は動作の継続・反復などをあらわす助詞。夜床で涙を流し、朝までにそれが凍りつく――という状況が継続している、ということ。
【補記】二条后の歌を本歌取りし、「伊勢物語」に描かれた業平との悲恋を想起させる。春が訪れ、外界は鴬の明るい声が聞え始めたのに、我が恋はなお冷えきった絶望的な状態にある。
【他出】「秋篠月清集」1436。
●右(俊成卿女)
おもかげの霞める月ぞやどりける春やむかしの袖の涙に
【通釈】あの人の面影が、ほのかに重なって見える、霞んだ夜空の月――その月明りが、昔ながらの春に恋人を偲んで落とす、私の袖の涙に映っていた。
【語釈】◇かすめる―上の「おもかげの」を受け、かつ下の「月」に掛かる。恋人の面影がほのかに映る、霞んだ月に…、という文脈。◇月ぞやどりける―月の光が、袖の涙に映っていた。下句とは倒置の関係にある。◇春やむかしの―在原業平の古今集の歌「月やあらぬ春や昔の春ならぬ我が身ひとつはもとの身にして」に拠る。◇春やむかしの袖の涙に―春は昔のままの春なのに、自分の境遇は変わって、昔一緒にいた恋人はいない、という悲しみに流す、袖の涙に。
【補記】涙に濡れた袖に映る、春の朧月を見つめている――そこには、遠い記憶となった恋人の面影がぼんやりと重なって見えるのである。妖艷な春の情緒と業平の歌を背景に、懐旧の恋を思い入れたっぷりに描いた。朦朧として濃やかなムード満点、本歌の取り込み方も斬新。
【他出】「若宮撰歌合」一番左持、「水無瀬桜宮十五番歌合」一番左持、「新古今集」1136、「俊成卿女集」202。ほかに「自讃歌」「新三十六人撰」など。
■判詞(俊成)
左歌は「雪のうちに春はきにけり鴬の」といへる歌をとり、右歌は「月やあらぬ春やむかしの」といふ歌の心なり。ともにえんにはみえ侍るを、左、「なほわが袖はむすぼほれつつ」といへるすがた、殊によろしく見え侍れば、左ヲ以テ勝ト為。
【通釈】左歌は「雪のうちに春はきにけり鴬の」という歌を本歌に取り、右歌は「月やあらぬ春やむかしの」という歌の心を取っています。ともに艶には感じられますが、左の「なほわが袖はむすぼほれつつ」と詠んだ姿が格別によろしく見えますので、左を勝とします。
【語釈】◇えん―歌から「なんとなく」感じられる美の一様相をあらわす語。俊成は歌の評価の際、これを特に重んじた。ニュアンスに富む語で、説明は不可能だが、あえて言えば人目を引くような優美さや花やかさがあって、余情も湛えた歌・語句について言うことが多いように思われる。◇すがた、殊によろしく―この場合、良経の歌の下句につき、詞の続け柄・声調の良さと、そこから生じてくる情感の強さ・鮮明さを称賛しているように思える。
▼感想
それぞれに二条后と業平の歌を本歌とする、艶な取り合わせで、恋歌合の巻頭を飾るにふさわしい絶妙の二首である。俊成女の負は、一番の左には勝を譲る(少なくとも負にはしない)という慣例に従ったものと思われる。【他出】を見れば一目瞭然、後世の評価では俊成女の圧倒的な勝利であった。
二番
左 勝 親定
月残る弥生の山の霞む夜をよよしとつげよまたずしもあらず
右 宮内卿
さても又慰むやとてながむべきそなたの空も薄がすみつつ
右の歌、「さても又」とおけるより、すがたをかしくは見え侍るを、「うす霞みつつ」といへる末の句や、旧(ふる)くもいひならはしても聞えずや侍らん。左、「弥生の山のかすむ夜を」などいへる心すがた、いみじく見え侍り。もとも勝とすべし。
○左(後鳥羽院)
月残る弥生の山の霞む夜をよよしとつげよまたずしもあらず
【通釈】月がまだ沈まずに残っていて、弥生の山がぼうっと霞んでみえる、この夜――「素晴らしい夜ですよ」と、あの人に告げてよ。私は待っていないわけではないのよ。
【語釈】◇月残る―月がまだ沈まずに山の上に残っている。「残る」には、やがて沈んでしまうのを惜しむ心がこめられていよう。◇弥生―陰暦三月。晩春である。◇よよしとつげよ―夜が素晴らしいと告げよ。恋人に報告するように、使いの者に命じているのである。下記本歌に拠る。◇またずしもあらず―待たないというわけでもない。これも本歌に拠る。
【本歌】「古今集」よみ人しらず
月夜よしよよしと人につげやらばこてふににたりまたずしもあらず
(大意:「月夜が素晴らしい、この夜は素晴らしい」と人に告げてやったら、まるで来て欲しいと言っているようなものですね。まあ、待っていないわけでもないのですけどね。)
【補記】上句は声調が良いだけでなく、愛惜すべき晩春の朧月夜を簡潔に、かつニュアンス豊かに描いてみごとである。下句は古今集の可憐な恋歌を本歌取りして、さらに余情を添えた。これも女の立場で詠んだ歌である。なお、作者名「親定」は、後鳥羽院の仮名。
【他出】「後鳥羽院御集」1595。
●右(宮内卿)
さても又慰むやとてながむべきそなたの空も薄がすみつつ
【通釈】それでもやはり、心が慰むかと、じっとながめてみるべきなのだろうか。あなたがいるはずのそちらの空も、うっすらと霞みがかかっているけれども…。
【語釈】◇ながむべき―じっと見つめてみるべきなのだろうか。「べし」は「そうするのが当然・必然である」という心をあらわす助動詞。◇薄がすみつつ―春の空だから霞んでいるわけだが、恋のつらさに流す涙のためにも霞んでみえるのである。なお、「薄がすみ」を動詞として用いたのは、飛鳥井雅経が正治二年(1200)の後度百首に「風のおとも春の気色になるみがた浪路はるかにうす霞みつつ」と遣ったのが初例か。名詞としては「見わたせばあしたの原の薄がすみ薄きや春のはじめなるらん」(惟宗広言)など、それ以前にも稀に用いた例がある。
【補記】「つれづれと空ぞ見らるる思ふ人天くだり来んものならなくに」(和泉式部)など、「恋心を慰めようと、空を眺める」という古来の歌の情趣を背景に、ふっと洩らした独り言のように作っていて、面白い歌である。「そなたのそらもうすがすみつつ」と、さ行音の連なりが、今にも消え入りそうな儚い心持を、悲しげに奏でている。
【他出】「夫木和歌抄」17249。
■判詞
右の歌、「さても又」とおけるより、すがたをかしくは見え侍るを、「うす霞みつつ」といへる末の句や、旧(ふる)くもいひならはしても聞えずや侍らん。左、「弥生の山のかすむ夜を」などいへる心すがた、いみじく見え侍り。もとも勝とすべし。
【通釈】右の歌は「さても又」と置いた初句からして、面白い姿には見えますが、「うす霞みつつ」という末の句は、古い詞にも、言い習わした詞にも聞えないのではないでしょうか。左は「弥生の山のかすむ夜を」などと詠んだ心・姿が、すばらしく感じられます。当然至極、勝とすべきです。
【語釈】◇旧くもいひならはしても聞えずや侍らん―宮内卿の歌の末句「うす霞みつつ」が耳慣れず、由緒のある詞でないことを批判している。俊成の、詞の上での保守主義・古典主義があらわれた判詞である。◇心すがた、いみじく見え侍り―心もすがたも、大変立派である。最大級の賛辞。
▼感想
どちらも調べの快い歌。後鳥羽院の歌は、「月残るやよひのやまのかすむよをよよしとつげよ」と、第四句までにヤ行音を七つも含み、宮内卿の歌はナ音とサ行音の連鎖が利いている。俊成がともに「すがた」を讃めているのは、こうした声調の良さと無関係ではあるまい。
しかし、勝負をはっきりと分けたのは、宮内卿の末句が歌語として熟していない一方、後鳥羽院詠は全体に耳慣れた古い詞を遣いながら「心・すがた、いみじ」という境地まで達していると見られた点であった。新奇な詞遣いに批判的な一方、端正な姿や情感の強さ・深さを評価している点、判者俊成の態度は一貫している。
三番
右 持 有家朝臣
夢にだにみぬ夜な夜なを恨みきて衣はる雨しをれてぞふる
右 雅経
人しれずおさへてむせぶひまごとに涙打ちいづる袖の春かぜ
左、「衣春雨しをれてぞふる」といへる詞、よせおほく見え侍り。右、又、彼の「とくる氷のひまごとに」といへる歌の心を、恋に引きなして、「涙打ちいづる袖の春かぜ」といへる。左はよせおほく、右はえんにみゆ。仍(よ)て、なずらへて持とすべし。
△左(藤原有家)
夢にだにみぬ夜な夜なを恨みきて衣はる雨しをれてぞふる
【通釈】夢でさえ逢わない夜が続き、夜ごと恋人のつれなさをずっと恨んで来て、頃も春となり、草木が春雨に濡れてうなだれるように、私はしょんぼりと過ごしている。
【語釈】◇恨みきて―「きて」は「着て」と掛詞になり、下句の「衣」と縁語になる。◇衣はるさめ―「頃も春」、衣を「張る(ピンと広げる)」、「春雨」の掛詞。末句「しをれてぞふる」を導く序となる。先蹤は紀貫之の古今集歌「わがせこが衣はるさめふるごとに野べのみどりぞ色まさりける」。◇しをれて―(草木などが)雨に濡れてうなだれる。(人の様子が)しょんぼりとする。◇ふる―降る・経るの掛詞。
【補注】「きて」「はる」「しをれ」は「衣」の縁語と言え、また「しをれ」「ふる」は「雨」の縁語と言える。判詞に「よせおほく」と言っているのはこれらを指している。
【補記】「人が夢にあらわれるのは、その人が自分のことを思ってくれるからだ」という俗信があった。そのため、夢で逢えないことで恋人を恨んでいるのである。内容的には「夢で逢えない恋人を恨んで、私はずっと元気なく暮らしている」というありふれたことを言っているに過ぎないが、掛詞や縁語を駆使することで、歌になっている。
△右(藤原雅経)
人しれずおさへてむせぶひまごとに涙打ちいづる袖の春かぜ
【通釈】人に知られず、顔を覆ってむせび泣く――その隙間から隙間から、涙はあふれ出て来るのだ、袖に吹きつける春風のせいで。
【語釈】◇おさへてむせぶ―袖で泣き声を抑えて咽ぶ。先蹤に鴨長明の家集歌「消えかへりおさへてむせぶ袖のうちに思ひのこせることのはぞなき」がある。◇ひまごとに―むせび声の隙間ごとに。下記本歌を踏まえた表現。◇打ちいづる―激しくあふれ出す。これも本歌に由る言い方。◇袖の春かぜ―袖に吹く強い春風が、涙を外へ洩らす、とした。
【本歌】源当純「古今集」
谷風にとくる氷のひまごとにうちいづる波や春の初花
【補記】「むせぶひまごとに」と言い「涙打ちいづる」と言い、古い名歌を踏まえているからこそ、判詞にあるように「艶」と見なされるのである。これが本歌取りでなかったら、ただの大仰な表現となってしまい、滑稽でさえある。
【他出】「明日香井和歌集」1097。
■判詞
左、「衣春雨しをれてぞふる」といへる詞、よせおほく見え侍り。右、又、彼の「とくる氷のひまごとに」といへる歌の心を、恋に引きなして、「涙打ちいづる袖の春かぜ」といへる。左はよせおほく、右はえんにみゆ。仍(よ)て、なずらへて持(ぢ)とすべし。
【通釈】左は「衣春雨しをれてぞふる」と詠んだ詞が、縁語が多いように見えます。右はやはり、あの「とくる氷のひまごとに」という(初春を詠んだ)歌の心を、恋の心に置き換えて、「涙打ちいづる袖の春かぜ」と詠んだ。左は縁語が多く、右は艶に見える。よって、同格と見なし、勝負なしとするべきでしょう。
【語釈】◇よせ―関連付けること。歌論用語としては、縁語のことを言う。◇恋に引きなして―もとは春の歌だったのを、恋の歌に置き換えて。本歌取りをする際は、四季の歌を恋の歌に「引きなし」たり、その逆にしたりすることが奨励された。◇なずらへて―同格・同等と扱って。◇持(ぢ)―引き分け。あおいこ。
▼感想
佳詠が続いた後、やや低調な取組となった。どちらも全然出来は悪くないのだが、当歌合出詠歌の水準が非常に高いから、低調に見えてしまうのである。こういうしっかりとした「地」の歌が、「文(あや)」の歌をひときわ光らせる事情は、歌合においても変わらない。
四番
左 勝 定家朝臣
忘れめや花にたちまよふ春霞それかとばかり見えし明ぼの
右 家隆朝臣
恨みても心づからのおもひかなうつろふ花に春のゆふぐれ
左は「それかとばかり見えし明ぼの」、右は「うつろふはなにはるの夕ぐれ」とよめるすがた、心、ともによろしくは見え侍るを、勝負此のつがひは時の衆儀(しゆぎ)にや侍るらんと申すを、左の勝と定められ侍りしなり。
○左(藤原定家)
忘れめや花にたちまよふ春霞それかとばかり見えし明ぼの
【通釈】忘れはしないだろう、おぼろな花のように垣間見たあの人を。あたりに立ちこめ、漂っていた春霞の間に、かろうじてそれかと見分けられた、曙の桜のようなあの人を。
【語釈】◇忘れめや―忘れようか、いや忘れないだろう。メは推量の助動詞ムの已然形。ヤは反語の助詞。「忘ればや」とする本もあり、その場合「(いっそのこと)忘れたい」の意になる。◇花にたちまよふ春霞―桜の花のあたりに立ちこめ、去らずにただよう春霞。◇それかとばかり見えし―辛うじてそれ(桜の花)なのかと見えた。「花と霞が見分け難い」という前提に立つ。
【参考】『源氏物語』「野分」(夕霧が紫の上を垣間見る場面)
気高くきよらに、さとにほふ心地して、春の曙の霞の間より、おもしろき樺桜の咲き乱れたるを見る心地す。
藤原俊成「五社百首」文治六年(1190)
わかれつる床に心はとどめおきて霞にまよふ春の明ぼの
【補記】後朝の別れの際の情景を詠んだ歌とも読めるが、しばらく古注の説に従った。『拾遺愚草抄出聞書』は「げんじに、夕霧の大将、むらさきの上をみ給ひて、春の曙の霞の間より、かばざくらの咲みだれたるをみる心地する、此心也。ほのかにみたる人を、中中に忘れたき由也」とする。
【他出】「若宮撰歌合」一番右持、「水無瀬桜宮十五番歌合」一番右持、「拾遺愚草」2536。
●右(藤原家隆)
恨みても心づからのおもひかなうつろふ花に春のゆふぐれ
【通釈】あの人をいくら恨んだところで、私の心から始まった思いなのだから、どうしようもないかなあ。散る桜の花に、そんな思いがする、春の夕暮だことよ。
【語釈】◇心づからの―自分の心が原因の。◇うつろふ花―散る花。下記本歌を踏まえる。「時が経つにつれ、うつろいゆく恋」の意がオーバーラップする。
【本歌】藤原好風「古今集」
春風は花のあたりをよきてふけ心づからやうつろふと見む
【補記】いかにもムード本位で詠まれた歌という観があるが、詞の続き具合は美しく、情意は何とはなしに、しみじみと伝わってくる。
【他出】「壬二集」2797。なお第五句は「春のくれがた」。
■判詞
左は「それかとばかり見えし明ぼの」、右は「うつろふはなにはるの夕ぐれ」とよめるすがた、心、ともによろしくは見え侍るを、「勝負此のつがひは時の衆儀(しゆぎ)にや侍るらん」と申すを、左の勝と定められ侍りしなり。
【通釈】左は「それかとばかり見えし明ぼの」、右は「うつろふはなにはるの夕ぐれ」と詠んだ姿・心、ともになかなか良いと見えますが、「此の番は、その時の衆議判で、勝負があったのしょうか」と申したところ、左の勝と決定されたのでした。
【語釈】◇すがた、心、ともによろしく―語句の総体的な印象も、そこに籠められた情も、結構で。◇衆儀(しゆぎ)―儀の字は底本のまま。衆議とは、出詠歌人たちが歌の良し悪しを自由に論じ合うこと。俊成は甲乙つけがたいと判断したようだが、当日の衆議を尊重し、その判定に従った、ということらしい。新古今時代の歌合では、このように出席者の自由な批評を尊重し、衆議判がなされることが多かった。
▼感想
気怠いような春の情景で、そこはかとない恋の情趣をくるんでしまったような二首。曙と夕暮という対照。新風の旗手であった二歌人による対戦は、源氏物語を背景とした定家の巧みな趣向に軍配があがった。
五番
左 勝 前大僧正
恋もせでながめましかばいかならん花の梢におぼろ月夜を
右 権中納言
思ひきや匂ひを送る梅がえの移りがをのみみにしめんとは
左、「ながめましかばいかならん」とおきて、「花の梢に朧月夜を」といへる心、すがた、いみじくをかしく見え侍り。右、「おもひきや」とおきて、すゑに「何とせんとは」などいへる事、常の事にやと人々申され侍りしかば、左をもて勝と定め申し侍りしなり。
○左(慈円)
恋もせでながめましかばいかならん花の梢におぼろ月夜を
【通釈】恋もせずに眺めたとしたら、どんなふうに見えるだろう。桜の花の咲いた梢に、朧月がかかっているこの夜を。(きっと、これほど心に深く染み入ってはこなかっただろう。)(s)
【語釈】◇ながめましかば―もし、眺めたとすれば。マシは反実仮想の助動詞。
【補記】歌の主人公は、きっと「花の梢の朧月夜」を、涙を浮かべた目で見ているのであろう。だから、よけいにおぼろげに見えてしまう。
もし、胸が痛いほどの想いがなかったら、この美しい花月夜を、もっと楽しめるかもしれない。でも、やはり恋をしているからこそ、こんなに美しく見えるのではないか…。
そんな、感傷的になりがちな、敏感な恋心を詠んでいるように思われる。いかにも、題の「春の恋」にふさわしい風情ではないか。
俊成の歌に、「恋せずは人の心もなからまし物のあはれもこれよりぞ知る」、恋をしなかったら、人に心などないだろう。人が「もののあはれ」を知るのは、恋によってなのだ、という歌があるが、それを思い出させる。(s)
【他出】「拾玉集」4946。
●右(藤原公継)
思ひきや匂ひを送る梅がえの移りがをのみみにしめんとは
【通釈】思いもしなかったよ。匂いを送ってくる梅が枝の移り香ばかりを、身に染み付けることになろうとは。
【語釈】◇思ひきや―思ったか、いや思いはしなかった。小野篁の古今集歌「思ひきや鄙の別れにおとろへてあまの縄たきいさりせむとは」以来、好まれた言い方。◇匂ひを送る梅がえ―遠くから匂いを送ってくる、花の咲く梅の枝。「梅がえ」に恋人を暗喩。◇移りがをのみ―「移り香」は、物から移った、残り香。◇みにしめんとは―「しめ」は四段動詞「染(し)む」の他動詞形である下二段動詞「染む」の未然形。色や匂いを染みとおらせる。深く染み付ける。
【補記】密接な交渉を持つことのなかった恋人の、思い出ばかりは深く心に染み付いて残ってしまった――という心。春の景物を暗喩として、恋の経緯とその果ての心境を歌い納める。うまく収まったのは、すべてを暗示的表現に抑え、古歌の鑄型に流し込んだからである。
■判詞
左、「ながめましかばいかならん」とおきて、「花の梢に朧月夜を」といへる心、すがた、いみじくをかしく見え侍り。右、「おもひきや」とおきて、すゑに「何とせんとは」などいへる事、常の事にやと人々申され侍りしかば、左をもて勝と定め申し侍りしなり。
【通釈】左は「ながめましかばいかならん」と置いて、「花の梢に朧月夜を」と詠んだ心・姿、大変興趣あるものと感じられます。右は初句に「おもひきや」と置いて、末句に「〜せんとは」などと言うのは、ありふれた詠み方ではないか、と人々が申されましたので、左を勝と決定いたしました次第です。
【語釈】◇常の事にや―「思ひきや…せんとは」という構文が陳腐ではないかと方人が難じたのである。ここでも俊成は衆議を受け入れている。
▼感想
一歩間違えると理に落ちてしまいそうな詠い方を、じゅうぶん情のこもった歌に仕上げている、といった感じのする二首。衆議で構文の平凡さが指摘されて負になった、という判詞もなかなか興味深い。「言い古された詞を使うのは良いことだ」という認識がある一方で、使われ過ぎて陳腐になってしまった言い回しには批判的だった。新古今時代、どのような歌が志向されていたか、その一端が窺える。