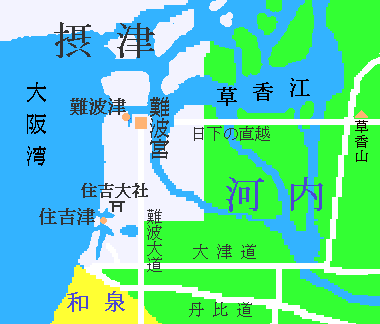やまとうた雑記 バックナンバー
万葉集にあらわれる地名について(3)
――「難波の海」と「住吉の岸」――
今回は「地名出現頻度」の第2位、大阪府を取り上げます。
故犬養孝さんの『万葉の旅』によれば、現在の大阪府に含まれる万葉の地名はのべ218を数え、そのうち実に半分近くを難波(なにわ)と住吉(すみのえ)で占めています。
難波津・住吉津はいずれも「御津(みつ)」と呼ばれていますが、これは両港がともに「朝廷の港」だったことを意味するでしょう。山に囲まれた大和の国にとって、難波・住吉はまさに海の玄関口であり、当然都との間で人々の往来は頻繁でした。旅先で眺める珍しい海洋の風景に心を動かされ、多くの歌が詠まれたとしても不思議はありません。
難波宮大極殿跡 大阪市中央区法円坂
難波はまさに「海の都」でした。難波を詠んだ万葉の歌は、潮の匂いに満ち満ちています。
あり通ふ難波の宮は海近み海人娘子らが乗れる舟見ゆ(巻6 田辺福麻呂)
海原のゆたけき見つつ葦が散る難波に年は経ぬべく思ほゆ(巻20 大伴家持)
難波宮跡は大坂城の南に当たり、海岸から遠い街中ですが、往時は広大な入り海に面しており、宮室からは海原が一望できました。
前回も少し触れた通り、縄文時代前期、いまの大阪平野は海におおわれ、生駒山の麓は波に洗われていました。その後、淀川と旧大和川による土砂の堆積が進み、海への出口を失った海湾は潟湖へと変化しますが、万葉集の歌がさかんに作られるようになる西暦8世紀頃、なお生駒山の西には大きな入江が広がっていたのです。
西暦7〜8世紀頃の難波周辺 概念図
参考:小笠原好彦『難波京の風景』(文英堂)
このまぼろしの入江は現在「草香江(くさかえ)」と通称されていますが、これを詠んだ歌は、どういうわけか万葉集にたったの1首しか見当たりません。しかも、序詞(じょことば)の一部として出て来るだけです。
草香江の入江にあさる葦鶴のあなたづたづし友なしにして(巻4 大伴旅人)
日下(くさか)越えを利用して難波と奈良を往還した人々は、常に草香江を横目に旅したはずです。その草香江がほとんど歌に詠まれていないとは、一体どういうことでしょうか?
ところで、「難波潟」という呼び名は万葉集にしばしば見られ(8首)、また「難波の海」を詠んだ歌も2首見られます。これらがどこを指すのか、いくつか説があるようなのですが、私はどちらも草香江の別名、というか通用名だったのではないかと思っています。「草香山を超ゆる時、神社忌寸老麻呂(かみこそのいみきおゆまろ)がよめる歌」(巻6)を読んでみて下さい。
難波潟潮干のなごりよく見てむ家なる妹が待ち問はむため
直越のこの道にして押し照るや難波の海と名付けけらしも
1首目は、「難波潟の潮の引いた後のなごり―水たまりや、そこに漂う藻など―をよく見ておこう、家で待っている妻に尋ねられるだろうから」といった意味。潮の引いたあとに現れる広大な干潟は、山に囲まれた大和の人たちにはさぞかし珍しい光景で、恰好のみやげ話になったのでしょう。
2首目の直越のこの道が、上図に示した「日下(くさか)の直越」です。平城京と難波をほぼ直線状に結ぶ大道でした。その道から見ると、陽光が難波の海いちめんに照りつけて、なるほど昔の人はこれを見て押し照るや難波の海と名付けたのだな、と率直な感動を表明している歌です。
この二首の題詞にある草香山は、『万葉集古義』に「河内国河内郡にて、今も日下村あり、伊駒山の西方なりといへり」とあるように、生駒山の西、草香江の東畔に位置する山です。ここを山越えする旅人の眼下に大きく広がるのは、大阪湾よりもまず草香江だったはずでしょう。老麻呂のよんだ難波潟・難波の海がいずれも草香江を指していることは明らかです。
万葉集の地名事典などを読むと、「難波の海」を大阪湾としている本が多いのですが、私には不審です(なお、大阪湾には「茅渟(ちぬ)の海」という古い呼び名がありました。チヌは黒鯛のことで、関西以西では今も黒鯛をチヌダイと呼ぶそうです)。
*
住吉(すみのえ)は万葉集では「墨之江」などとも書かれていますが、語源はおそらく「澄みの江」だったでしょうか。住吉大社の前には、鎌倉時代末まで南北に細長いラグーン(潟)があったとのことで(日下雅義『古代景観の復元』中央公論社)、波おだやかな天然の良港をなしていました。いま住吉公園にある池は、このラグーンのなごりだそうです。
摂津国風土記逸文に住吉大神の言葉として「ま住み吉(え)し、住吉(すみのえ)の国」が伝わり、「ま住み吉し」がスミノエに懸かる枕詞だったとわかります。スミノエに住吉の字をあてたのは、明日香が枕詞「飛ぶ鳥の」から飛鳥と書かれるようになったのと似たような事情です。これがいつしか(平安時代以降とされていますが)漢字通りにスミヨシと詠まれるようになったのだろう、と言われています。
住吉大社 大阪市住吉区住吉
住吉の津は難波より古くから栄えた港でした。仁徳天皇の御代、難波に堀江が通じ、大阪湾からの船が直接淀川に入れるようになると、次第に主要港としての地位は住吉から難波へと移ってゆきました。
しかしその後も住吉は航海の神の鎮座する地として尊ばれ、遣唐使船などは住吉から出航することが多かったようです。次の歌は、天平勝宝2年、遣唐使を餞(はなむけ)する宴で詠まれたもの。
住吉に斎く祝が神言と行くとも来とも船は速けむ(巻19 多治比土作)
住吉神社にお仕えする神主が御託宣を得た、それによれば往きも還りも船は順調に進むだろう、と言挙げした歌です。
また住吉は白砂青松の浜としても名高く、後世「住吉の松」などが盛んに和歌に詠まれますが、万葉集ではむしろ「住吉の岸」「住吉の岸の埴生(はにふ)」を詠んだ歌が目立ちます。
めづらしき人を我家に住吉の岸の埴生を見むよしもがも(巻7 作者不詳)
白波の千重に来寄する住吉の岸の埴生ににほひて行かな(巻6 車持千年)
古語のきしは切り立った崖をいい、埴生は赤土(粘土)の採れる地をいいます。つまり、住吉の海岸には、赤土の露出した断崖があったとわかります。帝塚山台地が海に削られ、絶壁を成していたのでしょう。
1首目のめづらしき人を我家には住みから住吉を導く序詞です。内容としては、何とかして「住吉の岸の埴生」を見たいものだ、と言っているだけですが、この頃すでに住吉が名所と化していたことが判ります。
2首目のにほひて行かなは、色に染まってゆこう、というような意味。そのように詠むことで、住吉の土地の豊かな霊威を讃美しているわけです。
澄んだ入江と美しい砂浜、そして赤土の断崖。この地を訪れた住吉大神が「ま住み吉し」と感嘆したのも成る程と肯けます。
いま南海電車の住吉大社駅を降りると、神社の周囲はなお霊妙な雰囲気を留めているとしても、海の気配は遠く、これらの歌に詠まれたような風景はもはや想像するよすがさえありません。
関連サイト:私的住吉学 古代住吉地図と万葉集に詠まれた住吉の歌が掲載されています。
©水垣 久 最終更新日:平成11-02-20