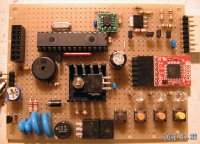
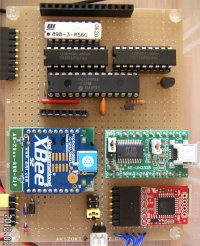
この基板だけでも十分独立
運用可能な構成。
電解コンデンサは LCD を
支える支柱を兼ねている ^^;
XBee、RS-232C→USB変換、
SD カードロガー「OpenLog」、
7セグ LED表示装置の
4デバイスがぶら下がる。


LED はソケット式。気分次第で
いろんな色に差し替え可能 ^^;


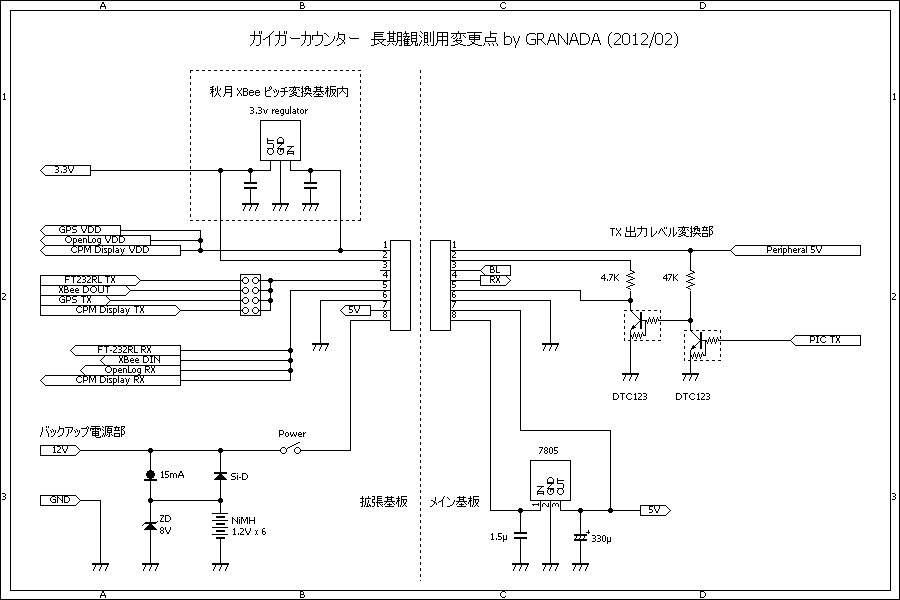

北側の窓際に設置。
アルミホイルで巻いているのは
紫外線によるケース劣化防止のため。
アルミホイルで巻いた上に受信側まで
外壁を 2枚を挟んで 5m 程度あるが、
ちゃんと無線でデータが取れている @o@

放射線量取得( XBee 無線)、
気象データ収集、花粉量データ収集、
統合グラフ化、Web サーバーへの
FTP を全自動で行う。
パソコンは完全ファンレスの EPSON
Endeavor NP11-V 。そのままでは
熱暴走する欠陥商品(怒)なので、
中身ムキ出しで稼動させている。
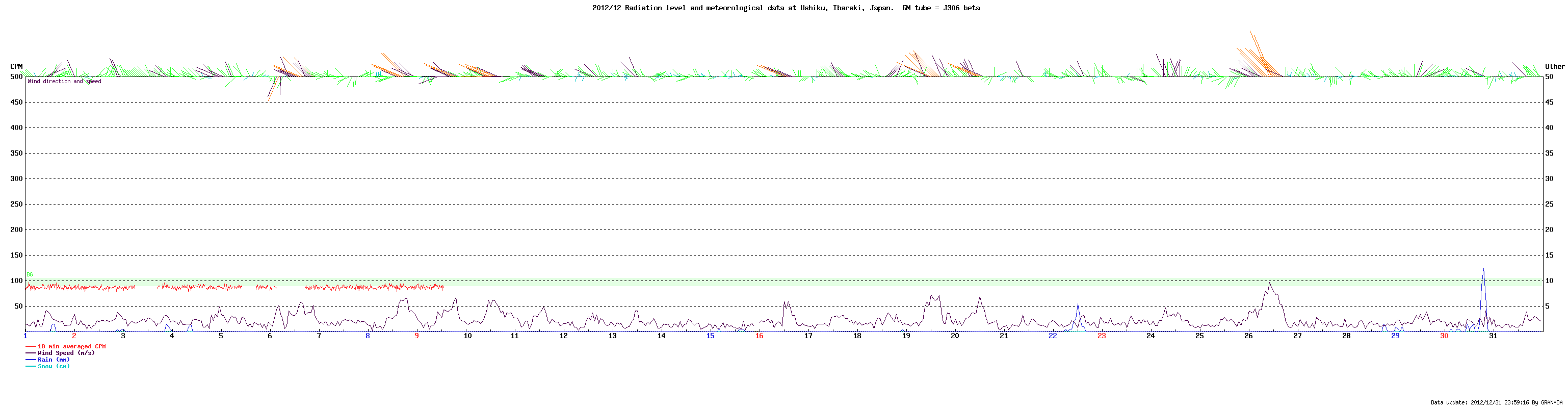
放射線量と気象データ統合グラフ
(3時間毎に自動更新)