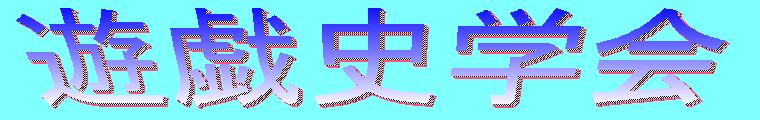
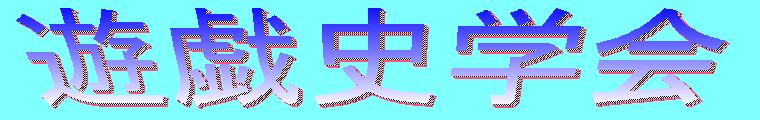
 戻る
戻る
紀要 「遊戯史研究」 内容
 第1号(1989年11月発行) 第1号(1989年11月発行) |
||
| 発刊の辞 | 熱田公 | |
| 海外からの祝辞 −遊戯史学会発足に寄せて | アービング・フィンケル | |
| 同上 | ヨアヒム・ペッオルト | |
| 同上 | ジョージ・A・ディーン | |
| 同上 | マンフレッド・エデール | |
| 中世・遊女・遊戯史 −遊戯史のあらたなる可能性をめぐって | 網野喜彦 | |
| 海のシルクロード −トランプの伝来とかるたの歴史 | 江橋崇 | |
| スクリャービン性 −神の遊戯としての造形音楽 | 上野智史 | |
| 中世における土地処分権考察の一視点 −双六賭け物に関する事例より | 増川宏一 | |
| <書評>増川宏一「賭博の日本史」 | 藤原清隆 | |
 第2号(1990年10月発行) 第2号(1990年10月発行) |
||
| 設立の呼びかけ(再掲)役員名附記 | ||
| 第三回総会メッセージ | E・クレンゲル | |
| 竹馬の歩み | 村井文彦 | |
| 持ち駒使用の始まり | 木村義徳 | |
| 大橋家文書解説(一)御城碁 | 増川宏一 | |
| 研究ノート・回り将棋について | 酒井知幸 | |
| 書評と紹介・遠藤欣一郎「玩具の系譜」「続玩具の系譜」 | ||
 第3号(1991年10月発行) 第3号(1991年10月発行) |
||
| 第三回総会メッセージ | エクベルト・マイセンブルグ | |
| 古代遊戯盤の遊戯法 −ウルのゲームについて− | アーヴィング・フィンケル | |
| 「證果増進之図」論 −初期絵双六に関する一考察− | 増川宏一 | |
| 中国古代の遊戯「六博」について | 小泉信吾 | |
| ウジャン・オミ −南スラウェンのカルタ遊び | 伊藤眞 | |
| 書評と紹介・財団法人余暇開発センター「レジャー白書’91」 | ||
| Q&A 徳川家康は囲碁を愛好していたか 本因坊は家康の囲碁の師匠か | ||
 第4号(1992年10月発行) 第4号(1992年10月発行) |
||
| 第四回総会メッセージ | ロビー・チャールズ・ベル | |
| チェスはどこで、どのようにして生まれたか | マムフレッド・エデル | |
| 特集・最近の出土品より見た遊戯具について | ||
| 1)大阪城跡の将棋駒 | 大阪城跡発掘調査事務所 | |
| 2)大阪城城下町出土駒 | 南秀雄 | |
| 3)大阪城跡から見つかっている碁石と駒石 | 宮本佐知子 | |
| 4)平安京出土のサイコロについて | 伊藤近富 | |
| 報告・C.C.I.第五回総会 | 増川宏一 | |
| 書評と紹介「詰棋めいと」第13号 | ||
| Q&A 徳川家康の棋力は? | ||
 第5号(1993年11月発行) 第5号(1993年11月発行) |
||
| 「普通唱導集」の将棋関係記事について | 佐伯真一 | |
| 「参詣曼荼羅研究」序章のためのスケッチ(1) | 西山克 | |
| 資料紹介、領内・博打の顛末 | 北村六合光 | |
| 報告1 ゲームの探訪 −中国領シルクロードを中心に− | 増川宏一 | |
| 報告2 エストニア優勝 第三回連珠世界選手権大会 | 澤井敏郎 | |
| 報告3 遊戯史学会第五回例会 | 酒井知幸 | |
| 書評と紹介・財団法人余暇開発センター「レジャー白書’93」 | ||
 第6号(1994年10月発行) 第6号(1994年10月発行) |
||
| 双六の局面孝 | 草場純 | |
| 将棋伝来についての一試論 | 清水康二 | |
| 96(くじゅろく)の謎 −愛媛で幻のカードゲーム発見 | 三好正好 | |
| 同上 解説 | 江橋崇 | |
| 文化文政時代の幕府碁方四家の「暗闘」について | 大澤永弘 | |
| 正倉院蔵木画紫檀碁局について | 増川宏一 | |
 第7号(1995年10月発行) 第7号(1995年10月発行) |
||
| 第七回総会メッセージ | ギュンター・バウアー | |
| 花札の歴史 | 江橋崇 | |
| アメリカの公営カジノの歴史およびゲームの移り変わり | 谷岡一郎 | |
| 幕末の囲碁研究会「三之日会」と「四之日会」について | ||
| 第7回例会報告(手本引の説明) | 増川宏一 | |
 第8号(1996年10月発行) 第8号(1996年10月発行) |
||
| 麻雀概史 | 浅見了 | |
| 花札の歴史(二) | 江橋崇 | |
| 大橋家文書(二)延宝二年断簡 釈文監修 | 熱田公 | |
| 同上 解説 | 増川宏一 | |
| 韓国囲碁略史および韓国囲碁略年表 | 権庚彦 | |
| 高校生へのゲームに関するアンケートについて | 酒井知幸 | |
 第9号(1997年10月発行) 第9号(1997年10月発行) |
||
| チェス史再構築の一段階 | 増川宏一 | |
| 花札の歴史(三・完) | 江橋崇 | |
| 麻雀牌の三元牌と花牌 | 稲福繁 | |
| 麻雀の花牌に関する考察メモ | 江橋崇 | |
| 浮世絵に描かれた「囲碁図」の考察 | 水口藤雄 | |
| 資料紹介・天保年間の「囲碁技術」と「日本国十囲碁初段以上姓名順」 | 中田敬三 | |
 第10号(1998年10月発行) 第10号(1998年10月発行) |
||
| 権田保之助の思想史研究序説 | 鈴木康史 | |
| 連珠史概論 | 坂田吾朗 | |
| 藤原右京三条三坊東北坪出土の碁石 | 竹田政敬 | |
| 特集1.中国遊戯調査団報告 | 中裕史、薬師寺春雄、江橋崇、清水康二、増川宏一 | |
| 特集2.遊戯史研究と歴史学−最新の成果を踏まえて− (創立10周年記念シンポジウム報告) | 網野善彦、江橋崇、増川宏一、草場純、麻国鈞 | |
| 名古屋例会報告 | ||
 第11号(1999年10月発行) 第11号(1999年10月発行) |
||
| 将棋の進化論的変遷−平安将棋のコンピュータ解析 | 飯田弘之 | |
| 連珠史概論(2) | 坂田吾朗 | |
| 麻雀概史(下) | 浅見了 | |
| かるた史研究の意義と最新の報告(創立10周年記念シンポジウム報告) | 江橋崇 | |
| 緬甸将棋(シットゥイン)の文献と現状 | 岡野伸 | |
 第12号(2000年10月発行) 第12号(2000年10月発行) |
||
| 美術工芸品としてのチェス駒 | 増川宏一 | |
| 日本のカルタ史におけるブロンホフの功績 | 江橋崇 | |
| 「研究ノート」明末清初の馬掉牌について | 竹崎栄里 | |
| 「資料紹介」寛政期の目明し半平 | 北村六合光 | |
| 「資料紹介」龍門石窟に刻まれた遊戯盤 | 清水康二・宮原晋一 | |
 第13号(2001年10月発行) 第13号(2001年10月発行) |
||
| ユンノリに起源説にみる韓国のナショナリズム | 劉卿美 | |
| 棊の字の用法の変遷について | 大澤永弘 | |
| 明末における文人と馬掉牌について | 竹崎栄里 | |
| アミューズメント産業研究所の意義と役割 | 谷岡一郎 | |
| 「資料紹介」リーベ・フェアベーク「ブル・低地マヤ族のパトリゲーム」 | 増川宏一 | |
 第14号(2002年10月発行) 第14号(2002年10月発行) |
||
| 後鳥羽院と将棋−鎌倉時代の駒落ち将棋のことなど− | 佐伯真一 | |
| 秦漢帝国時代における囲碁の普及発展の様相 | 大澤永弘 | |
| 双六盤の変遷について | 湯原勝美 | |
| 宗代象棋駒とその性格 | 清水康二・宮原晋一 | |
| 資料紹介「戸内遊戯法」 | 横山恵一 | |
 第15号(2003年10月発行) 第15号(2003年10月発行) |
||
| 追悼 熱田公先生 | 中田陽子他 | |
| 熱田公先生 略年譜 | ||
| 熱田公先生 略著作目録 | ||
| 資料紹介 大橋家文書(三)「拝領地留記」 | 増川宏一 | |
| 高校生へのゲームに関するアンケート(第二回) | 酒井知幸 | |
 第16号(2004年10月発行) 第16号(2004年10月発行) |
||
| 王将本来説私見 | 曽倉岑 | |
| 季節感と遊び−花札 | 三輪正胤 | |
| 吉海直人教授の始源と現在 −論文『花かるたの始源と現在』への疑問 | 江橋崇 | |
| 資料紹介 R.ヴァサンタ「最も初期のゲームの駒の研究」 | 増川宏一 | |
 第17号(2005年10月発行) 第17号(2005年10月発行) |
||
| 琉球列島における中近世の盤上遊具について | 上原静 | |
| 六博の変遷と地域性 | 清水康二 | |
| ユンノリのさいころについて | 劉卿美 | |
| 「投扇興」あるいは「投げ扇」と呼ばれる遊びについて | 高橋浩徳 | |
| 資料紹介(一) R.カルボ「ヨーロッパ最古のチェス駒か?」 | 田中規之 | |
| 資料紹介(二) 「芸術と文化の季刊誌「P」第13号」 | 増川宏一 | |
 第18号(2006年10月発行) 第18号(2006年10月発行) |
||
| 競技かるたの歴史とその精神性 | 津久井勤 | |
| 旧楚地における六博の変遷 −漆器の生産地に着目して | 鈴木直美 | |
| 「完本 本因坊丈和全集」による丈和伝の修正(上) | 大澤永弘 | |
| 盤上遊戯史に関する二つの小論 −古代イランのゲーム盤とイスラーム型チェス盤について− | 田中規之 | |
| ドイツ人を中心とした中将棋団体 | 小俣光夫、岡野伸 | |
 第19号(2007年11月発行) 第19号(2007年11月発行) |
||
| 将棋の起源 −二人制か四人制か− | 増川宏一 | |
| 「完本 本因坊丈和全集」による丈和伝の修正(下) | 大澤永弘 | |
| 報告一「韓国遊戯瞥見録」 | 清水康二 | |
| 報告ニ「現在のおけるゲーム文化の交流について」 | 草場純 | |
| 資料紹介 「大橋家文書」より | 増川宏一 | |
 第20号(2008年11月発行) 第20号(2008年11月発行) |
||
| 巻頭言 創刊20号の刊行に際して | 増川宏一 | |
| 海外からの祝辞 | ||
| 記録に見る初代本因坊 | 増川宏一 | |
| 日本伝統遊戯の現状 | 高橋浩徳 | |
| 高校生へのゲームに関するアンケート(第3回) | 酒井知幸 | |
 第21号(2009年11月発行) 第21号(2009年11月発行) |
||
| 幕末期関東村落における博徒集団と地域社会−武蔵国多摩郡・入間郡の事例を中心に | 高尾善希 | |
| 絵双六考(一)「新販女庭訓振分双六」−幕末期の女性、その多様な生き方 | 桝田静代 | |
| ボクシングはなぜ合法化されたか−英国スポーツの近代化と刑法 | 松井良明 | |
| 資料紹介 Ancient Board Games in Perspective | 増川宏一 | |
| 報告一 高校生への将棋授業 | 西條耕一 | |
| 報告二 WMSG北京レポート−チェッカー・ドラフツ競技に参加して | 小俣光夫 | |
 第22号(2010年11月発行) 第22号(2010年11月発行) |
||
| 中国骨牌の歴史と遊び | 伊藤拓馬 | |
| 絵双六考(二)その表現と構造を曼陀羅的世界に見る −浄土双六から一般的な絵双六まで | 桝田静代 | |
| 大橋家文書(五)−「酒乱の戒め」他 | 増川宏一 | |
| 資料紹介 Alfons X. "der Weise" Das Buch der Spiele | 増川宏一 | |
 第23号(2011年11月発行) 第23号(2011年11月発行) |
||
| バリ島の遊戯と流血の概念 | 石井浩一 | |
| 日本将棋連盟の歴史と現状 | 西條耕一 | |
| 研究ノート 「米国で初披露された将棋」について −1860年6月15日、フィラデルフィア | 布施田哲也 | |
| 資料紹介 ザイエット博士の『ハルシャチャリタ』解釈 | 田中規之 | |
| 資料紹介 出雲市高浜I遺跡出土の将棋盤および駒 | 増川宏一 | |
 バックナンバーは一部の公立図書館や大学図書館などで閲覧できます。
所在や所蔵をご希望の方はメールでお問い合わせ下さい。
必ず内容に「遊戯史研究」について希望の旨お書き下さい。
バックナンバーは一部の公立図書館や大学図書館などで閲覧できます。
所在や所蔵をご希望の方はメールでお問い合わせ下さい。
必ず内容に「遊戯史研究」について希望の旨お書き下さい。
 戻る
戻る