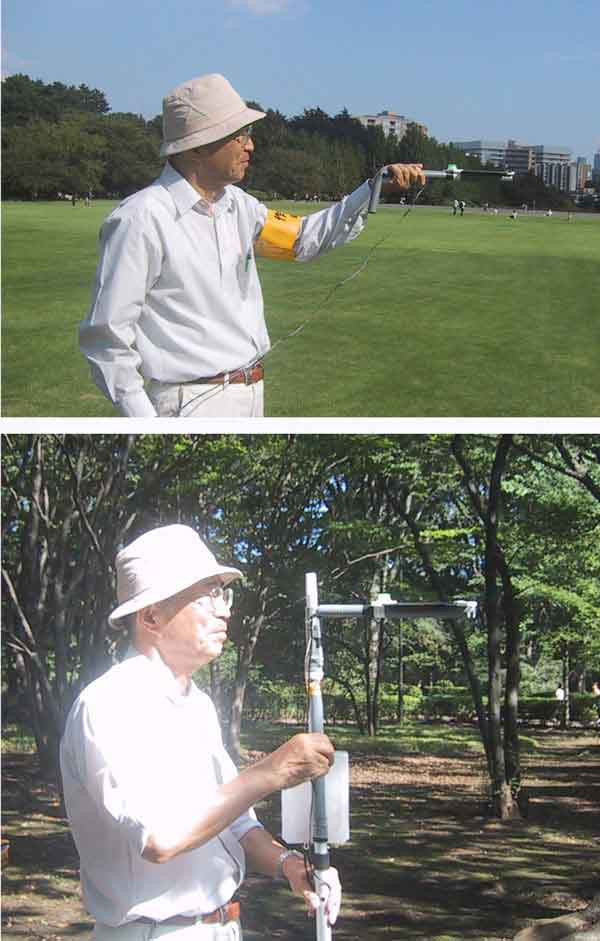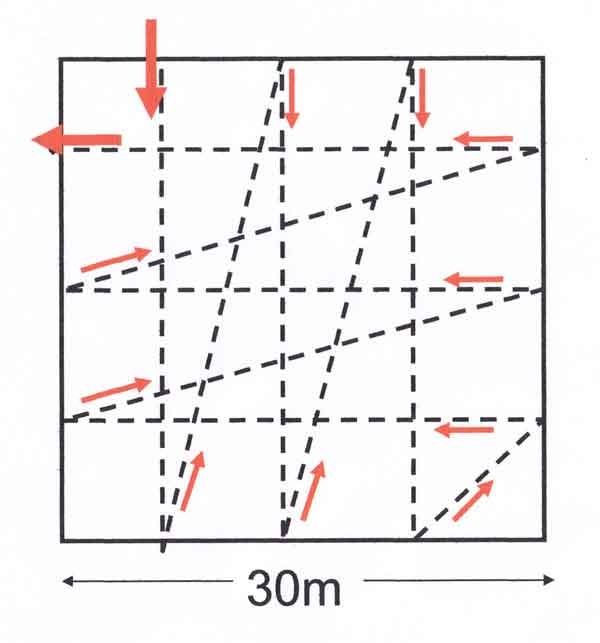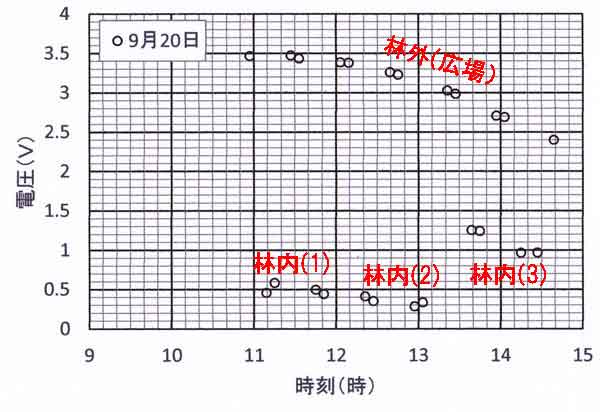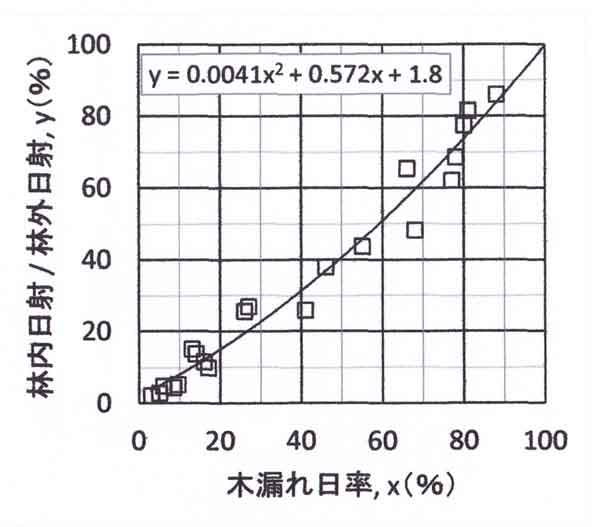K113.林内の日射量と木漏れ日率の測定
著者:近藤純正・内藤玄一
林内の日射量は強い直射光から微弱な木漏れ日まで分布している。こうした分布の
林内平均値を観測し、林外日射量に対する比(日射量比)をもとめた。日射量比と
木漏れ日率の関係は2次式で近似される。木漏れ日率が50%前後では、
「日射量比/木漏れ日率」≒0.8であり、木漏れ日率が100%に近
づくと「日射量比/木漏れ日率」は 1 に近づく(完成:2015年10月3日)。
本ホームページに掲載の内容は著作物である。
内容(新しい結果や方法、アイデアなど)の参考・利用
に際しては”近藤純正ホームページ”からの引用であることを明記のこと。
更新の記録
2015年9月26日:素案の作成
2015年9月26日:観測の表113.1と図113.5は未完成
2015年9月27日:「木漏れ日率の目測」に分かりやすく加筆
2015年9月30日:「林床の木漏れ日率と林内の見通し(詳細)」を追加
2015年10月3日:観測の表113.1と図113.5を完成
目次
113.1 はしがき
113.2 測定方法
(1)木漏れ日率の目測
(2)林内の日射量比の測定
113.3 日射量比と木漏れ日率の関係
113.4 まとめ
観測協力機関
環境省自然環境局皇居外苑管理事務所北の丸分室
環境省自然環境局新宿御苑管理事務所
明治神宮
平塚市みどり公園・水辺課、平塚市総合公園課
113.1 はしがき
林床の日射量の分布は、強弱のまだら模様であり高精度の測定は難しい。
その強弱は、強い直射光から葉面の重なりによるピンホールで拡大された微弱光の
木漏れ日まで、その放射強度は1000W/m2から10W/m2の広い
範囲に分布している。
そのため、受感部の面積が数平方cmしかない通常の日射計で測る場合、
サンプリング数は数百~1000個程度が必要であり、正確な測定は難しい。
今回、受光面積が一般の日射計の100倍ほどの面積131mm×131mmの太陽光パネル
を利用した林内観測用の日射計を製作した。この日射計は、日射量と出力電圧は
比例関係にあり、また温度依存性も小さく、複雑な分布をしている林内日射量の
空間平均値を測るのに適している(「K112.太陽光パネルを
利用した林内日射計」を参照)。
これまでの筆者らの研究では、林内日射量のかわりに林床の「木漏れ日率」を用いて
きた。今回、木漏れ日率と林内日射量の関係について調べることにした。
木漏れ日率の目測を行なう場合、初心者は微弱光の木漏れ日も強い直射光と同等に
計数しがちである。木漏れ日率は、1~2日間ほど訓練すれば個人差は小さくなる。
熟練に1か月ほどかかる雲量の測定に比べれば容易である。
次の「林床の木漏れ日率と林内の見通し(詳細)」
をクリックして参照すれば、プラウザの「戻る」を押してもどってください。
113.2 測定方法
(1)木漏れ日率の目測
木漏れ日率を目測する場合、林内は一般に暗いので、葉面の重なりによるピンホール
で拡大された微弱光の木漏れ日を混ぜて測定してしまう。すなわち、ピンホールから
の木漏れ日が混ざった領域を離れた距離から眺めると明るいので、
強い直射光の領域と同等にみなす可能性がある。その結果として初心者は木漏れ日率
を大きめに見積もる傾向がある。
ピンホールで拡大された微弱光の木漏れ日は木漏れ日率に含めない。そのためには、
測定の範囲たとえば30m×30mの全面積を歩き、特に明るい面積の合計が全面積の
何%であるかを見積もり、これを木漏れ日率とする。こうした熟練に1日~2日間を
要する。
木漏れ日率は林内の1範囲について数回の目測を行ない、それらの平均値とするが、
5%程度の誤差を含む。
(2)林内の日射量比の測定
林内日射量の測定の前後に、林外の広い場所(固定点)で林外の日射量を観測する。
図113.1は三脚に取り付けた太陽光パネルを用いた日射計である。水準器を参考に
してパネル面が水平になるように設置する。L字アングルと水平の塩ビ管は強い弾力
で固定されており、手で水平の塩ビ管を回すことでパネルを水平にすることができる。
L字アングルの垂直部は垂直の塩ビ管の外側に縛り付けられており、L字アングル
の水平部は水平の塩ビパイプの中に隠れている。

図113.1 林内用の日射計。上:受感部の太陽光パネル、下:三脚に取り付けた
日射計一式(「K112.太陽光パネル
を利用した林内日射計」の図112.2に同じ)。
林内の日射量は歩きながら空間平均値を測定する。太陽光パネルの裏面に接着された
塩ビパイプの取り付け具に、L字アングルの塩ビ管を差し込み、これを持って移動
観測する。あるいは、垂直のアルミ伸縮棒を三脚から離して、手で持って移動観測
する。その際、目の高さのパネル面と遠方を見通して水平を保ちながら左右に1m
ほど振りながら空間平均を測る(図113.2、図113.3)。
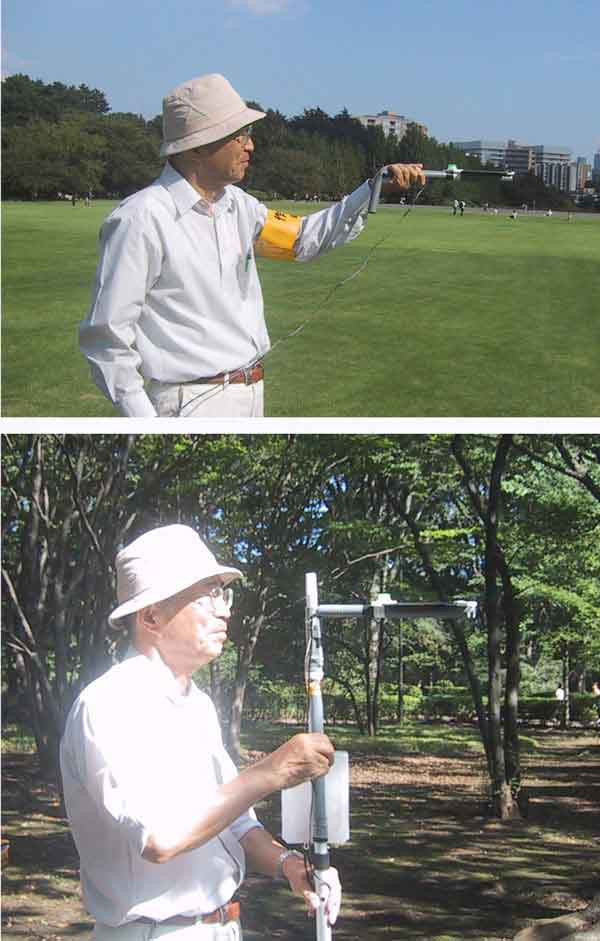
図113.2 林内測定時の日射計の持ち方の2例。パネル面は目の高さにして遠方を
見ながら水平に保つ。
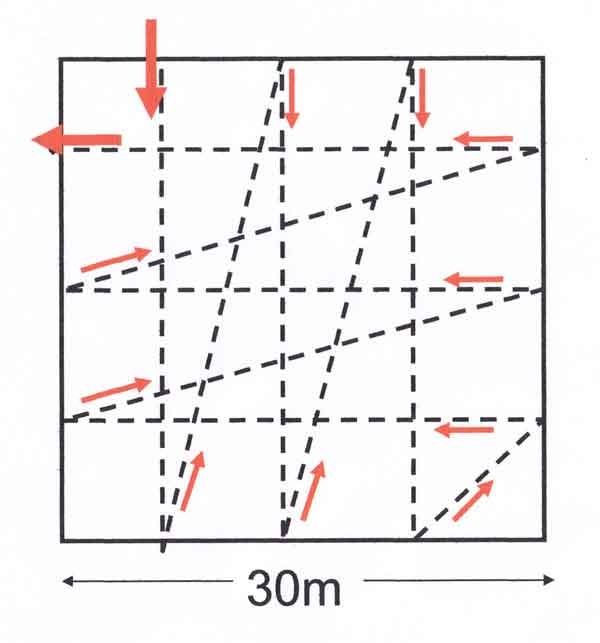
図113.3 林内を歩きながら日射量を測る経路の模式図。現実には十分な面積が
選べない場合は、例えば長方形内を歩く。それを2回繰り返して1観測とする。
林内の測定に先立ち、測定範囲を示す4隅に標識を立てる。歩く経路の順序を
決める。木漏れ日率は林内日射測定前、途中、終了時の3回にわたり目測する。
複数人の目測値の平均をもとめ、これをデータとして用いる。
出力電圧はデータロガー(T&D社のおんどとり、TR-55i-V, 16,000円)に2秒ごとに
記録したのち、PCに吸い上げて電圧を平均し、林外の日射量で規格化する。
この規格化された値が日射量比である。
図113.4は記録の例である。図中の上方に示すプロットは林外の広い場所の値、
下方は林内の値である。プロット1点は6分間の平均値である。6分間を2回繰り
返して1観測とする。この図では林内の3か所の測定ができたときの記録である。
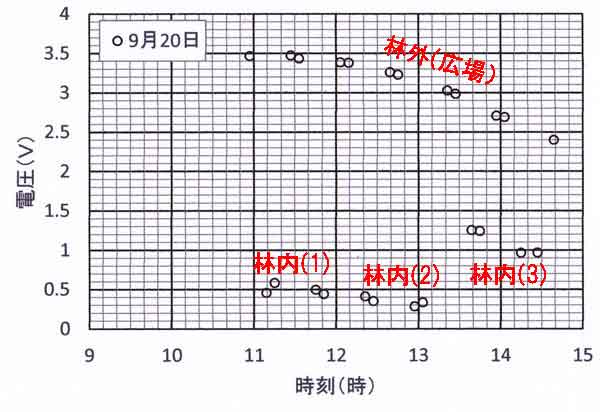
図113.4 日射計の出力電圧の記録(2015年9月20日、北の丸公園)。プロットの
1点は6分間(データ数=30個×6=180個)の平均値である。プロット2点(12分間、
データ数=180×2=360個)で1観測とする。林内の値の林外の値に対する比が
日射量比である。
注:出力電圧から日射量の算定
この日射計による日射量と出力電圧(V)の関係は次式で与えられる
(「K112.太陽光パネルを利用した林内日射計」)。
日射量(W/m2)=k×電圧(V)
係数:k=225 W m-2 V-1
電圧が3.5Vは788 W m-2 となる。ただし、この係数は暫定値であり
多少の誤差を含むが、ここでは日射量比をもとめることが目的であるので、
日射計の絶対精度はあまり気にしなくてよい。
113.3 日射量比と木漏れ日率の関係
木漏れ日率の目測値と電圧比(=日射量比)の測定値一覧を表113.1にまとめた。
図113.5は木漏れ日率 x(%)と日射量比 y(%)の関係である。プロットは測定値、曲線は最小
自乗法で表した2次式:
y=0.0041x2 + 0.572x + 1.8
である。
表113.1 木漏れ日率と電圧比(=日射量比)の測定値(2015年)
月/日 公園名 林 名 時 刻 木漏れ 電圧 電圧 日射量比
日率 林内 林外
% V V %
9/19 新宿御苑 N2の北、ホオノキ 11:18-11:36 41 0.93 3.6 25.8
W2の南 12:42-12:54 9 0.14 3.2 4.4
W2の南 13:18-13:30 9 0.15 2.9 5.2
9/20 北の丸公園 芝広場の東40m 11:06-11:18 13 0.52 3.46 15.0
芝広場の東40m 11:42-11:54 14 0.47 3.42 13.7
近衛第二連隊碑北 12:18-12:30 16 0.38 3.32 11.5
近衛第二連隊碑北 12:54-13:06 17 0.31 3.13 9.9
広場気温基準点の東40m 13:36-13:48 55 1.25 2.86 43.7
広場気温基準点の東40m 14:12-14:30 46 0.97 2.55 38.0
9/29 明治神宮 宝仏殿東70m 11:18-11:30 77 2.04 3.29 62.0
9/30 平塚桜ケ丘公園 二本大桜周辺 9:12- 9:30 78 1.85 2.70 68.5
二本大桜周辺 9:42-10:00 80 2.29 2.96 77.4
二本大桜周辺 10:18-10:30 81 2.55 3.13 81.5
二本大桜北桜周辺 11:30-11:42 88 2.82 3.28 86.0
10/2 平塚桜ケ丘公園 二本大桜南桜周辺 14:00-14:12 66 1.38 2.11 65.4
10/3 平塚市総合公園 広場の西側 9:30- 9:42 26 0.67 2.62 25.6
広場の西側の密林 10:00-10:12 3 0.06 2.91 2.1
広場の西側 10:30-10:42 27 0.82 3.05 26.9
広場の西側の密林 11:00-11:12 5 0.09 3.18 2.8
広場の西の桜林 11:30-11:42 68 1.52 3.15 48.3
広場の西の桧並木 12:00-12:12 6 0.15 3.14 4.8
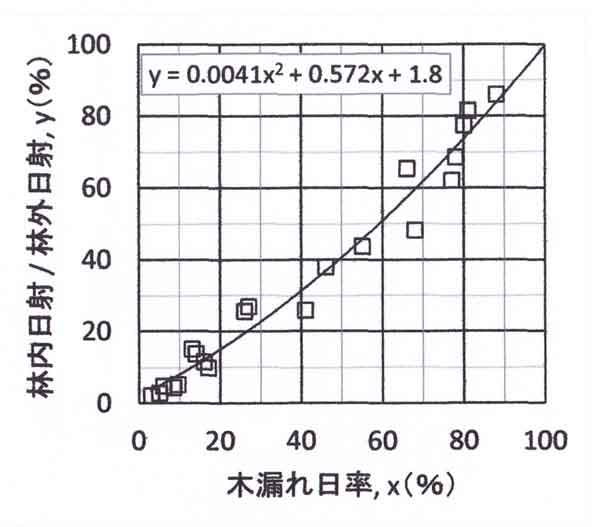
図113.5 木漏れ日率 x(%) と日射量比 y(%) の関係。図中の曲線は、測定値を近似した2次式。
木漏れ日率が50%以下の範囲では、「日射量比 / 木漏れ日率」<1 である。この割合が1より小さく
なる理由は:
木漏れ日の目測において、葉面の重なりによるピンホールで拡大された微弱光の
木漏れ日は無視しているが、強い直射光のほか比較的弱い散乱光・木漏れ日は
含めている(無意識に測定している)ことによる。
さらに小さな寄与として、広い場所では散乱光が快晴時に10%程度ある
(近くに雲があればもっと大きい)のに対し、林内では斜め上方を見ると葉面の
重なりが多くなり天空部分より暗い。その結果、天頂角が大きいほど散乱光の
割合は非常に小さくなることによる。
木漏れ日率を大きめに測定する傾向の樹木
図113.5において、近似曲線から右方に大きく離れてプロットされた林(横軸=68%、縦軸=48.3%)
は低木の桜林である。今回測定した落葉期の桜の葉は薄く、太陽光を透過しやすく、目視する際に
林床のやや弱めの木漏れ日も計数したと考えられる。ただし桜でも大木で葉面積指数が大きい場合は
この傾向はなく、比較的樹高の低い桜や梅などでは注意がいる。
113.4 まとめ
太陽光パネルを利用した日射計を用いて林内の日射量比(=林内日射量/林外日射量)
を測定し、木漏れ日率との関係を調べた。
その結果、日射量比と木漏れ日率は、2次式で近似的に表される。すなわち、
木漏れ日率が50%前後では、「日射量比/木漏れ日率」≒0.8であるが、木漏れ日率が100%に
近づくと1に近づく。