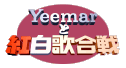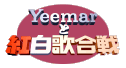
第1回
●なぜ「紅白歌合戦」を見るのか●
とにかく「紅白歌合戦」を見るのが楽しみです。生き甲斐と言ってもいい。なぜそれほど「紅白」にこだわっているのだろう。
もともと、ロック・ポップスを含む歌謡曲は好きなんですが、ふだんから熱狂的に見ている音楽番組があるとはいえません(見ることは見ます)。ときどきレンタルCD店からディスクを借りてきて、かろうじて流行の歌についていっている状態です。
でも、「紅白」となると事情が違います。年末が近づくと、「紅白」のこと以外は考えられなくなります。番組を見逃す夢や、録画ができなくなる夢を見て、汗びっしょりになって目覚めることが何度もあります。あるときの夢では、自分がNHKホールで「紅白」の生の舞台を見ているにもかかわらず、「あぁ、しまった、これでは録画のボタンが押せない」と言って身もだえしていたこともありました。
「紅白」には魔力のようなものがあります。一放送局の一歌謡番組という意味づけをはるかに超える魔力です。でも、世間では、それを理解している人ばかりではないらしい。あるとき後輩たちと呑みながら話していたら、「『紅白』なんか録画してるんですか。そんなもの、あとで見やしないでしょう」と言われてびっくりしました。
「見ないことがあるもんかね。うちにゃあ、絶頂期のチェッカーズやら、小泉今日子やら、少年隊やら、初出場の森高千里やら、KANやら、たまやら、BAKUFU-SLUMPやらをリアルタイムで録画したテープがあるよ。君は、彼らのそういう姿をもう1度見たいとは思わんかね?」「そう言われれば……。SMAPの初出場もあります?」「ウームそれはたまたまテープが切れていて。まあそんなことはどうでもいい。とにかく、そういう映像を見ていると、『ああ、これがこの時代の空気というもんなのね』と、ついホロリとなっちまうもんだよ」「あのう先輩、その串は僕のですが」
「紅白」とは、僕にとって「時代の流れ」をもっとも熱く感じさせてくれる存在なのかもしれません。「方丈記」にあるように、「同じNHKホールにて出演者も多かれど、いにしへ見し人は、数多が中にわづかに1人、2人なり。朝に消え夕べに生まるる習ひ、ただ水の泡にぞ似たりける」なのです。4時間に満たない晴れ舞台の上で、今をかぎりと燃焼し尽くす歌手たちを見ていると、「おれたちはこの1997年という年に(または1989年に、あるいは1973年に)確かに痕跡を残した!」と、生きる喜びを叫んでいるように見えます。
いったい、今の日本で、「時代と一体化する」喜びを感じられる場というのはどれほどあるでしょうか。たとえばサッカーのワールドカップや、オリンピックはそうかもしれない。でも、あれはちょっと真顔になりすぎますね。それよりも、みんながにこにこしているもののほうがいい。今をときめく歌手たちが、盛大な音曲と極彩色の舞台の中で熱唱し、観客も共に熱狂する「紅白」こそ、その1年を皆でことほぐ、ほとんど唯一の「ハレ」の場であると思います。
「いや、『紅白』ではハレの場として物足りない」という意見は当然あるでしょう。しかし、広い世代が1年に1度参加するイベントとして、当面これに代わるものはないと思います。そうである以上は、皆で積極的に「紅白」をもり立ててゆくほうが建設的です。
その1年の「時代性」「空気」というものは、もう来年にはなく、絶対に2度と還らないものです。そうした懐かしくもはかない「時代性」を具体的に表現するものは歌謡曲です。「紅白」では、皆がその年に流行した歌を歌い、過ぎ去って行く「時代」を惜しむかのように盛大に祝います。「紅白」を見ないということは、その1年を過ごさなかったとほとんど同義ではないでしょうか。おろかにも裏番組なんぞを見ている人は、どうして不安にならないのか不思議です。
(1998.10.18)
|