98.10.10
「太陽の季節」のころ
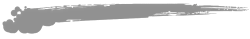
石原慎太郎の小説「太陽の季節」は、1955年度の芥川賞を受賞して大反響を呼び、翌1956.05には日活で長門裕之・南田洋子の主演で映画化され、後のスーパースター石原裕次郎が注目されるきっかけを作りました。
僕などから見ると、すでに古典であり、権威でもあります。当時の人々からも圧倒的な支持を受けていたものと思っていましたが(事実、テレビなんかではそう紹介している)、古い新聞記事を繰ってみると、必ずしもそうとも言えないようです。
「朝日新聞」の「声」を見ると、思わず苦笑するような批判が載っています。
◇芥川賞というパスポートをふりかざして、これでもか、これでもかとどぎつい性の退廃を露出してくる男を、出版界や映画界が金もうけ主義のためにかつぎ上げている様子、また世の大衆が、それを何の思慮もなく受入れてしまうこと、はてはそれを世情なりと書き立てるジャーナリズム……私はかかる一連の現象が、まだ彼ら(太陽族)ほど悪ずれしていない一般の青少年に与える悪影響を思うとせんりつせざるを得ない。(学生=1956.05.15)
それにつけても、ニガニガしいのは、世のいわゆる作家と称せられる人たちの、このようなシンチャン刈りのアンチャン文学や、ただ特殊な人物をあつかったというだけで、何のとりえもない未熟な文学をかつぎまわる出版社のタイコもち的な態度である。(学生=1956.05.17)
などとこてんぱんにやっつけています。しかも年寄りではなく若い世代からの声であるのは意外です。
弁護する側も、力が入りません。こういう「不良品」はあってもしかたないので、押さえ込んではいけない、というような言い方しかしていません。「“もの”に対する厳しい批判精神のみが、不良品をより分け、新しい建設の土台をすこしずつ確実に築き上げてゆくのだということを確信します」(無職=1956.05.22)と言っていて、前提としては「みっともない作品」だと考えているようです。
映画化された「太陽の季節」について、ある学生は
先日、不安とはずかしさをおして「太陽の季節」を見た。(1956.05.30)
に続く文章で、映画について「煮えくり返るような義憤」を覚えたり「口惜しさがつのっ」たりしたと書いています(ほんとは見たくて仕方がなかったんだと思うけれど)。担当者の選択する投書に偏向があったのかもしれませんが、ちょっと予想以上の風当たりです。
たしかに、原作にえがかれた若者の姿は、今日でさえもまだ一般的ではないほどの放埒さです(と思いますが、あまり自信はない)。しかし、後の村上龍作品や村上春樹作品などをすでに経験した今日のわれわれの目から見ると、むしろ小説としては大人しいという感じを受けるのではないでしょうか。ヒロイン英子のせりふも、
「あのね、この先のM美容室に母が来てますの、今そこへ行くつもりだったんですけど。〔後略〕」(新潮文庫 p.24)
「――別に御用はないの。でも今日もおいでになって。唯何となくお逢いしたいわ」(新潮文庫 p.50)
といった具合で、古き良き時代の女性ことばを残しています。彼女の性格も、一途で純情であり、古風な女という感じをさえ受けます。
上に象徴されるように、全体としても、新聞の投書欄を批判で埋め尽くすほど毒のある作品だとはまったく思えません。たった40年間でも、人々の考え方は激烈に変わるものです。
|