03.11.28
述語を落とす
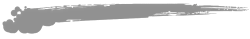
学生の発表を聞いていて、「おやおや、この人はいったい何が言いたいのだろう?」と途中で混乱することがよくあります。こちらが聞きながらメモを取っていても、論旨が混乱して不完全な要約になったりします。これは、僕の頭があまり論理的にできていないせいもありますし、また、僕が風邪で熱が高いときなどにはとりわけそういう傾向が強まるのですが。
当該の問題について、彼または彼女はAだと思っているのか、Bだと思っているのか、どうも分からない。主張が明確に伝わってこない。なぜだろう。
一つの理由は、「述語を言わないからではないか」と気がつきました。何のことはない、よく言われる「語尾をあいまいに濁す」ということに近い。こと改めて論じることではないかもしれません。しかし、語尾をあいまいに濁していても、言わないよりはましです。今回の例は、「あいまいにする」ではなく、述語部分をすっぽり落とすのです。
こちらとしては、「述語をいつ言うか」をのんびり待っているのですが、じつは話はとっくに先へ先へと進んでいるという次第です。
具体的な例を直接挙げられればいいのですが、残念ながら、実際の談話を記録していません。ただ、似たような例をテレビから拾いました。NHK「お元気ですか日本列島」2003.11.27 で、あることば遣い(「『〜じゃないですか』をどう思いますか?」)について問われて、渋谷の若い人が答えていました。
(女性)「なんか『なになにじゃないですか』っていうと、敬語っぽく聞こえるけど、おしつけがましくて、なんかあまり好きじゃないなっていうふうに思っちゃうので、あまり使わないようにしてます」
この受け答えはまあ合格。最後に述語をはっきり言っているので、聞いて分かります。でも、次の人の発言は迷います。
(男性)「いきなり初対面とかの人に言われても、逆に。そういうほうはちょっと。だからその、人間関係があれば問題ないですね」
前後のVTRを編集していることと思いますが、それを考慮しても、述語が2箇所で抜けているのが気になります。
「いきなり初対面とかの人に言われても、逆に〔 a 〕。そういうほうはちょっと〔 b 〕。だからその、人間関係があれば問題ないですね」
その「a」「b」は何なのだ、「a」「b」をはっきり言ってくれ、と質(ただ)したい気持ちになります。ことによると、本人の語彙には、その「a」「b」がないのかもしれません。彼の意図をどうにか推測して補うならば、
「(『〜じゃないですか』という表現を)いきなり初対面とかの人に言われても、逆にとまどいます。そういうほうはちょっと勘弁してほしいものです。人間関係ができていれば、そういわれても問題ないですね」
といったところでしょうか。
ものを言うときは、的確な述語を考え出して表現しよう。でも、表現に迷ったときには逃げる方法もあります。それは、
「いきなり初対面とかの人に言われても、逆にあれですね」
と言えばいいのです。「あれですね」でも立派な述語です。情報量は増えていないのだけれど、「ここで1回言い終わっている」ということは分かります。そこで、聞き手は述語を期待していつまでも待っている必要がなくて、話し手の論旨をたどりやすくなります。
ただし、「あれですね」と言ったからには、その「あれ」を改めて言い直すのだろう、とやはり聞き手が期待することも起こりえます。それを防ぐためには、「あれ」で逃げるのではなくて、とりあえず何らかの簡単な述語(「いい」「悪い」「好きだ」「きらいだ」程度でもよい)を突っ込んでおくのがよいでしょう。もっとも、その簡単な述語さえ、または簡単であればなおさら、本人は明確には表現したくないのだと想像されます。そこに問題の本質があると考えられます。
述語をすっぽり抜かすというのは、学生に限ったことではなく、どの年代でもあることかもしれません。というより、ありそうな気がします。たまたま、僕の耳に学生のことばが引っかかったということです。
|