2002年4月1日解禁予定の金融商品
報道センター−経済部−
<ペイオフの定義と概略>
本来は金融機関の解散整理を指すが、今回は預金保険機構による預金保護をペイオフと便宜的に定義する。
預金保険機構の預金保険の対象金融機関:日本国内に本店のある銀行、信用金庫、信金中央金庫、信用組合、信用組合連合会、労働金庫、労働金庫連合会
|
2002年4月1日解禁予定の金融商品 |
定期預金、定期積金など[定期性のある商品]金融債、貸付信託、掛金など
|
2003年4月1日以降 |
当座預金、普通預金、別段預金[流動性のある商品]
1、預金額1000万円以内(元本とその利息の全額を保障)
2、預金額1000万円超(破綻した金融機関の財産の状況に応じ)
| 預金保険対象外 |
外貨預金、オフショア預金、無記名預金、他人名義の預金など
この件に関しては、政府広報/金融庁の広告資料あり。
<ペイオフ小史>
1971年 「預金保険法」成立 処理方法はペイオフしかなかった。
84年 「預金保険法」改正 金融自由化・国際化への対応。救済合併によって処理する為に「資金援助方式」が追加される。
92年 預金保険が現実に発動。「受け皿銀行」による処理。(東邦相互銀行)
94年 公的資金(日銀出資)による受け皿銀行の創設。
95年6月8日 「金融システムの機能回復について」
- 概ね5年の間に、不良債権処理の目処をつけ、ディスクロージャーを実現。
- 預金保険によって保護されるのは、預金者、信用秩序であり破綻金融機関、経営者、株主・出資者、従業員ではない。
- 預金保険の発動方式は、ペイオフではなく、社会的コストの小さい資金援助方式をとる。5年以内にペイオフを実施しうる環境を整備する。
- 預金保険の発動要件:経営者の退陣。経営者責任の追及。株主、出資者は損 失を負担する。合理化計画の策定。関係金融機関の可能な限りの支援。
- 概ね5年間は、資金拠出要請、付加保険料の徴収、日銀の支援などの特別対応もやむをえない。
上記の3について「ペイオフは経済社会全体から見てコストの大きな処理方式である。金融機関の破綻に際しては、基本的には、資金援助(合併など)の可能性をまず追求することが適当である。」との方針を明らかにしている。
2001年4月1日からの実施を凍結し現在に至る。
<日本でペイオフが出来なかったわけ>
以上、大蔵省のコメント
<ペイオフ解禁が不適当なわけ>
不況の現在、日本の金融危機(危機説が度々唱えられるが現実化していない)が起こったときペイオフが預金者、金融システムひいては経済に対しての影響が予想できない。
金融機関の体力強化の為の、整理統合などがとられていない。特に地方銀行はオーバーバンキングであり、収益力も低下している。
小口の預金者においては、1000万円以上預金している人間がどれぐらい居るか分からないが、さほど多くはないはず。しかし、法人企業、自治体の公金など大口預金に対する影響は計り知れない。特に公金預金は預金の移動が報じられている。
<ペイオフを解禁しなければいけないわけ>
ペイオフの再延期は、国際市場から信用の低下をもたらす。そのため、ジャパンプレミアム(日本向けの上乗せ金利)が復活が予想される。
金融機関、預金者のモラルハザード。
<取り付け騒ぎの発生について>
取り付け騒ぎは、経営不振に陥りかけているところにのみ発生するという実証研究が多くある。その内容として昭和恐慌についての研究も闇雲な取付けではないという結果が出ている。
<今後の対応>
ペイオフの実施に当り、ディスクロージャーの徹底、不良債権の処理、オーバーバンキングの解消、早期是正措置(BIS規制)への対応が求められる。
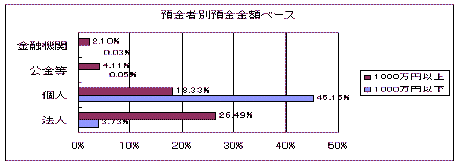 (日銀調べ)
(日銀調べ)
グラフの詳細についてはこちらにお問い合わせください。