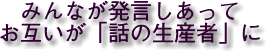

10:00ごろ 歌
10:20ごろ 木下 努さんの話「郷土教育運動について」
10:45ごろ 質疑応答
11:15ごろ デンマークフォークダンス
11:30ごろ 昼食タイム
12:15ごろ 各自自己紹介など
13:10ごろ 手話をつかった歌
13:30ごろ 清水さんの話「オルタナティヴな社会教育について」
15:00ごろ ティータイム
15:30ごろ 質疑応答・感想
16:30ごろ 閉会の歌とダンス
プログラム中は終始フォルケらしいといえばフォルケらしく、多元的でテーマが広いけど、行きあたりばったりで、開会の歌からしてキーがギターと歌とでずれてしまったフシもあり、「うまく歌えるかどうかなどという問題はどこ吹く風」とばかりに思い思いに歌っていました。
木下務さんのお話では、地域に根差した活動の報告が聞け、そのような活動においての現実的な問題点を考えたり、「他をまねするのではなくて自分たちの場所で何をするのか、どのようにやるのか」を模索し、それをやってみることが大切だなと思いました。
デンマークフォークダンスでは、全員でやるダンス(握手・腕組みスキップ・手をつなぐ)を終えて、参加者の皆さんがゼーゼー肩で息をしているところに、担当の上羽さんが「これがステップ1です」というとみんな目を白黒させているのが印象的でした。そしてステップ2は8人づつ3つのグループに別れて、手をつないでステップを踏みながらコーヒーカップのように回るのですが、手のつなぎ方がいろいろあるため(1人おきに前でつなぐ、後ろでつなぐ、騎馬戦の馬を4人でつくる)、うまくつなげないと手と手がからまってしまっていたようでした。そのため首をかしげたりしながらも「コーヒーカップ状態」に巻き込まれてしまい、しかも一定方向に回ってしまうため、終えたときは眼が回っている人も何人かいました。
そして「これがステップ2です」と上羽さんがいうと、参加者のみなさんの回っていた目は点になるかパチクリするかのどちらかでした。しかし「準備したのはこの二つですので」というのを聞くと、多くの人が胸をなで下ろしていました。でも何だかんだいいながらもとてもいい雰囲気でした。
昼食は会場内でバイキング形式をとったのですが、予定よりも凝った料理でずいぶんと量が少なかったために買い足したりもしたのですが、みなさんその様子を見ていたためか遠慮気味でした。食事中にさきほどのフォークダンスの音楽を流していたのはいい雰囲気だったのかなと思いました。また上羽さんによるデンマークのカレンダーの絵やお花など、ちょっとした工夫で部屋の感じがずいぶんと変わってよかったのではないかと思います。
食事が一段落ついたころに、1〜2分間ずつ全員自己紹介を行い、その時点でやっと参加者のみなさんがどんな方々なのかがお互いにわかりました。公務員の方、学校教員、デンマーク留学経験者、予定者、他の市民活動などにも関わっている方、看護婦、建築家、通信制高校生など、さまざまな立場の人が集まっていました。
手話をつかった歌では「上を向いて歩こう」の1番をギター演奏をもとにみんなで歌いながらやってみました。始めに歌詞に沿って動きの説明をしたのですが、その説明が少し雑になってしまったために歌の最中には動きについていけなくて苦笑いをしたり首をかしげたりしている人もいました。私(伊藤)は歌い、手話をやりながらも、その光景をけっこう楽しませてもらっていました(自分のせいなのに)。

ロウソクの灯を添えてのスライド上映があったり、からだを動かして動物になってお互いになごみあったり、自然との関わり方(陽光や風や露など見過ごしているよいものをキャッチすること)に気づかせられたりと盛りだくさんでした。
ティータイムをはさんで質疑応答、感想などを発言する時間ではたくさんの方が発言して下さり、いい雰囲気の状態で時間ものびのびになり、うれしいやら心配するやらという感じでした。
事前の予定ではその後16時頃からグループ別ディスカッションをして16時30分ごろからグループ別にその報告をするというプログラムでしたが、しかしそのグループ分けをどのような形で行なうのか(テーマを決めて別れるか前回の山西さんがされたような工夫をするか)がまったく決まっていませんでした。しかし幸いなことに(?)質疑応答の時間が長引いていたのでカットすることになりました。
そして最後にまたギター演奏をもとに閉会の歌とダンスを軽く行い終了させていただきました。
今回の世話人は形としては伊藤、上羽、佐名木ということではありましたが、事実上は前回の世話人の木下務さんと坂本卓二さんに多大なるご協力をしていただき(というより一緒に企画・開催していただき)大変感謝しています。
伊藤さおりさんの個人的感想
世話人をやってみて
確かに準備などもいろいろと忙しく、また当日もできる限りのことはやったつもりではありますが、その割には反省点(時間配分、空間の作り方、物の配置、司会進行に気を取られて話が耳に入っていない時があったりなど)も多かったので、難しいものだなと思いました。
しかし「プロセスと結果のバランス」ではありませんが、企画して準備などを進めているときは、大変といえば大変ですが、それも楽しく(上羽さんとも6年ぶりくらいだったのに、いつも会っているようなノリで話したり相談したりできて)、当日もバタバタとはしてしまいましたが、どうにか形になってよかったです。
一人の参加者として
新たな人と出会えたり、からだを動かして楽しんだり、話を聞いていろいろ考えさせられたりしました。その中で私がポイントに思ったのは、
(1)(今回は福祉の話はあまり出ませんでしたが)教育と福祉の接点について
(2)他をただ単にまねするのではなく、普遍的な理論や思想などよいものは吸収しながらも、自分が関わっている所、所属している所では何をどのようにやるのかを検討することの必要性
(3)今回の会のような場では、参加者の一人ひとりが「会費を払って参加してお話を聞かせてもらう」という消費的な姿勢ではなく、みんなが発言しあってお互いが「話の生産者」になれるのがいいなということでした(今回はけっこうそうなっていたと思います)。
そのようなことを意識しながら、これからもグルントヴィ協会に関わり続けたり、自分自身を問い直したりしていきたいと思います。
今回はお手伝いの役でしたが、あまり動かず反省しています。一参加者としてはとっても楽しめました。話だけがずっとつづくのではなく、途中で体を動かしたり、歌や食事などが入って面白かったです。変化に富んでいたので、時間の長さを全然感じずあっという間でした。今回の世話人のさおりちゃんと上羽さんが木下さんや坂本さんのサポートを受けながら企画に工夫を凝らした結果だと思います。
手話で自己紹介をしたのですが、私は緊張して途中で言葉が詰まってしまいました。けれども手話で「上を向いて歩こう」をみんなでできてよかったです。
木下さん、清水さんのお話を聞けたのもうれしいことでした。
佐名木教子さんの感想
以前さおりちゃんが「フォルケホイスコーレのあり方と厚木南通信のあり方は共通する点が多い」とハブール通信(厚木南通信制のサークル、ハブールの通信)に書いていましたが、今回の「旅するホイスコーレ(スタディツアー)は中学生から60代までの人が対等に会話をする」という清水さんの話を聞いて、私もそれは厚木南通信に共通するなと思いました。厚木南通信では15〜72歳までの人がそれぞれクラスメイトとして対等に語り合います。
私は、自分の親の年代の人に上からいわれると「何もわかってないくせに」と反発したくなるけど、クラスメイトとして対等な感じでいわれて、素直に言葉が体に入ってくることがありました。それは面白いことだと思うし、他ではなかなかないことだと思います。
清水さんのお話を聞いて思ったのですが、自然との関わり方というか、「陽光、風、露」などふだん見過ごしているよいものを私もキャッチしたいと思いました。