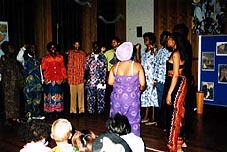|
IPC(International People's College インターナショナル・ホイスコーレ)体験記 中村 敦子(広島市) |
||||||
 |
||||||
|
|
||||||
| <学校のはじまり> 1998年9月1日、コペンハーゲンからヘルシンガーへ向かう列車の中、私は不安と期待で胸をいっぱいにし窓の外に見える海岸線を眺めていた。コペンハーゲンからヘルシンガーまでこの列車は海岸線を走る。車内ではデンマーク人の中年女性が大きな声で話をしている。初めて聴く生のデンマーク語を感じながら海を眺め、自分の心を落ち着けようとしていた。 これから時間に追われることなく自分の今後について考えられる。これまで経験したことのないことに挑戦し、いままで思い付かなかったことを発見できるかもしれないという期待。しかし、自分の考えている通りの環境であるかどうかという不安。期待と不安が交互に繰り返される。あと、数時間でそれが明らかになるのだ。 ヘルシンガーに着いた。学校から送られてきたガイドブックには地図とバスの番号が記されていた。学校までの道はわかりやすそうだったが、荷物もあることだしバスで行こうかと考えた。バスの停留所は駅前に広がっていた。近くの案内版を見た。どうやら違うようだ。しかし、向こうに見える案内版を見に行くよりは、もう、歩いた方がいいような気がした。それに、ゆっくり歩けば少し心を落ち着けるような気がした。よし、歩こう!地図を片手に歩き始めた。歩き始めて約10分、なだらかな坂が続く。家もまばら、他に歩いている人もほとんどいない。行く先には坂の頂上らしきものしか見えない。あれを越えたら目印のマクドナルドが見えるのだろうか? もしかしたら道を間違ったのか? 少なめにしたはずの荷物が重く感じられた。 とにかくあの頂上までいってみよう。荷物を持ち直し、気を入れ直した時、突然後ろから話しかけられた。「IPCにいくの?」英語だ!ふりむくとアジア系の男の子だった。こんなところにいるアジア人は怪しい。別の不安に襲われながら一緒に歩いた。「僕も生徒で、一週間前に着いたんだ。とてもいいところだよ。ベトナムから来たんだ。」な〜んだ、IPCの生徒か。「荷物を持ってやるよ」彼は私よりも体が細い。何度も断ったが、彼は自分を信用しろと言い、結局学校まで運んでくれた。 「新しい仲間だよー!」 部屋に入ると、すでに同室の子の鞄が置かれていた。私は二人部屋だ。どんな人だろう?と気にかけながら荷物を片付けているとヌカが入ってきた。「ハ〜イ!」満面の笑顔で入ってきた彼女はとても人懐っこい表情でかわいかった。そして、私達はうまくやれると感じた。 彼女はグリーンランド人だ。彼女は英語の他にグリーンランド語・デンマーク語を話す。デンマーク語でわからないことはよく教えてくれた。彼女と私は時々辞書を使って会話をした。英語ではわからない単語があると、デンマーク語ー英語・英語ー日本語と辞書をひいていく。楽しい作業だった。何よりも、お互いが理解しようと努力しているのだ。日本人同士だと、相手の真意を理解する前に理解したつもりで誤解し合っていることが多い。人間同士理解し合うにはこうした努力が基本ではないか。 学校内では諍いもあった。その原因は文化の違いからくるものなのか、個人的な性格の違いからくるものなのか判断しかねる。だからこそ、相手に率直に尋ねてみないことにはわからないのだ。「当然」であることの基準が違うかもしれない。そうやって追求していくうちに、基本的に人間の持つ「道徳」にはほとんど差異がないことを知った。悪気がなくて誤解しあっているだけならば、解決できるはずである。 とにかく、お互いが相手を理解しようとする意識が必要である。文化が違うから仕方がない、などと理解する意識を放棄していては何も解決しないのだ。 <サリーの死> 自己表現のクラスで、サリーは「写真」を最初に取り上げた。写真は私も興味があり、早速関われることが嬉しかった。初めの授業は4・5人のグループに別れ、りんごを使って自分達のアイデアを出し合って撮影した。私達のグループは女4人だった。私達は学校の庭を歩き回りながら、りんごを転がしたり、顔や足に乗せたり、いろんな方向で撮影をしていった。裏庭で一人が上半身を脱ぎ、りんごを胸に挟んだり乗せたりしての撮影もした。これは本人のアイデアだったが、さすがに他の人がいないことを充分確認してからの行動だった。 「きっと私達のグループが一番だよ〜。」私達はちょっと含み笑いをしながら言った。サリーは「そうだろうね〜」とこれ又含み笑い。「あれ?もしかして知ってるの?」「はっはっはっ!実は木の陰からこっそりみてた〜」「きゃー!!」誰も見ていないと思ったら、サリーにしっかり見られていたのだ。この日撮影した写真は、最後の授業までに現像して教室に貼り出す予定だったが、私達の内緒の写真はサリーにだけ見せると約束した。 その二週後、私達は白黒写真に挑戦するはずだった。授業の前日、レターボックスにサリーの伝言があった。「明日は白黒のフィルムを配るからカメラを用意して・・・。」その授業からサリーは来なかった。私達はサリーが戻ったらあの写真を見せよう、と早速写真を現像にだした。 サリーの状況を毎日校長のクリストフがアナウンスする。私はまだ英語に慣れていなかったが、だんだん深刻な様子に不安を覚えた。英語の得意な人にいろいろ事情を確認するが、はっきり知る人はなく、お互いサリーの心配をするばかり。英語の授業で代わりに教えてくれていたグレッグにみんなが尋ねた。グレッグは正直に答えた。「サリーは死ぬと思う。」、、、、、。 みんなは納得しなかった。デンマークの医療事情は悪いはずがない。どうしてサリーを救えないのか。沈黙の後、皆はグレッグを質問攻めにした。 最後のアナウンスは夕食時だった。クリストフのアナウンスを私は理解できなかった。アナウンスのあと、みんなは手を動かさなかった。サリーは死ぬんだ。私は向い側にいたブラジル人のジュリオに「サリーがどうしたの?」とささやいた。彼は声を絞り出すようにして答えてくれた。 「サリーは腸を悪くしたようで、手術をしたのだが良くならず、術後は心臓を動かす機械を使っていた。しかし、状態が変化しないため、医者がその機械を止める判断をしたのだ。」 私には信じられなかった。きっと私のヒアリング力が悪いのだ。食事のあともう一度仲の良かった友人に確認する。同じだった。数日前まで元気だった人が、手術をした途端そこまで悪くなるなんて・・・正直いってデンマークの医療システムを疑ったりもした。しかし、もうどうにもならないのだ。 アナウンスのあと、ダイニングルームではほとんど皆口を開かなかった。夕食が終わっても、いつものように騒ぐ人はいない。誰もがサリーのことを考えていた。じっとしていられず散歩に出るもの、ただ集まって座り込むもの、走って学校を飛び出したもの、各宗教の祈りを唱えるもの、様々な方法でサリーを想った。 「死」に対する考えは人それぞれだろうが、この時皆の気持ちは一つだった。宗教も文化も社会も越えて、ただ単純にサリーがいなくなってしまった哀しみを感じていた。言葉は何もいらない、ただ目が合うと自然に肩を抱き合った。気持ちを知るにはそれで充分だった。 サリーは学校での生活を幸せに思っていたという。彼女は幸せのうちに亡くなったんだ、と思うことで少しは救われた。翌日、皆はホールに集まり学校での御葬式をおこなった。サリーは世界中の宗教で祈られ、世界中の人間に送られた。 サリーを送った後、例の写真ができてきた。思った以上にうまく撮れていて、私達は喜んだ。「サリーに見せたかったね。」それが心残りだった。その写真はサリーの思い出とともに残ることになった。 後日、エデルガードの提案で中庭にサリーを祈念した桜の木を植えた。桜は彼女のイメージにぴったりだ。そして私達はいつでもサリーを思い出すことができる。 <授業> 私はこの学校で自分のことを見つめ直したいという目的の他に、学びたかったことがある。それは、なぜ世界中で紛争がおさまらないのか、である。簡単には答えを出せない問題であることは承知であるが、世界中から人が集まるこの学校で人間を観察することでそのヒントをつかめるのではないかと思ったのだ。そして「紛争(喧嘩)解決」という授業をとった。 授業内容は個人的諍いを中心に進んだ。その中で、「伝える」ことの実践としてひとりずつ「スピーチ」を行った。 私はここで初めて「スピーチ」を経験した。もともと人前で話すのは苦手だ。それに英語にだって慣れていない。不安ではあったが、いいチャンスだとも思った。テーマも自分で決める。 私は広島出身であるから、この機会に「核」について伝えようと決めた。幸い時間があったので原稿を作ることができた。部屋で少し練習もした。とうとう自分の番が来た。いざ皆の前に立つと全身が緊張で震えた。なんとか気持ちを落ち着け、原稿を読みはじめたが皆の顔を見ているうちに原稿にない文章を入れてしまった。その後の文章とうまくつなげられず、しどろもどろでやっとスピーチを終えた。結果、「スピーチ」としてはさんざんだったが、少し勇気を持てたことは自分にとって大きな経験だった。 私のスピーチに対する意見を先生が生徒に求めた時、ヌカは「アツコはもっとうまくできるはずだ。私は部屋で練習をしているのを知っている。今日はただ緊張していたからだ。」とフォローしてくれた。それに、声が震えたことでどうやら原爆の話に臨場感があったらしく、「涙が出そうだった」と言ってくれた人もいた。ある人は学校が終わる時、私のサイン帳に、「あのスピーチでアツコが私と同じ意見を持っていることを知って嬉しかった。お互いにがんばろう。」と書いてくれた。ある意味「伝える」ことはできたのかもしれない。 「聞こう」とする皆の姿勢に助けられた。理解しあうためには主張するだけでなく、相手の言い分を理解することが必要だ。思い込み、誤解が不必要な争いを生む。 <イベント> コーヒー・ミックスはいくつかの部屋がホストになり、各部屋7・8人ぐらいを招いてお茶を楽しむ。どこの部屋に行くかはくじ引きだ。普段あまり話さない人も混ざるので、親交を深めることができる。意外な話を聞けたりもする。 文化の夕べでは各国の料理、民俗衣装、ダンスやゲームなどを楽しむことができる。生徒が自分の国の文化を伝えるために様々な趣向をこらす。 その後ホールで踊り・音楽・お茶・お花・折り紙などを披露。折り紙は実際に皆にも挑戦してもらった。日本に住んでいたことがあるアメリカ人のエリスはこの日本の夕べを絶賛してくれた。彼女は日本でこういうのを見飽きていたが、私達の舞台はプロフェッショナルで感動したそうだ。練習したかいがあった。 どの国の夕べも、自分達の文化をいかに伝えるかを工夫していた。そして共通して感じられたのは、自国の文化に誇りをもっていることだ。普段、自分の国の社会の在り方に不満を持っている人も、文化となれば話は別のようでその良さを楽しく表現していた。 あるアメリカ人は困っていた「アメリカには文化がない・・・。」「食事はマクドナルドにしたら〜?」と皮肉混じりの冗談をいわれながらも、彼等はハロウィーンパーティを作り上げた。文化がない国はない。そして誰もが自分の国の良さを知っているし、他国の文化にも興味を持っている。こうしてお互いを知ることもできるのだ。
インターナショナル・イブニングの様子 <日常> 朝礼では世界のニュースを伝えたり、日常のアナウンス、そして目を覚ますために有志で体操をしたりゲームをしたり体を動かすこともある。 朝礼が終わったら授業が始まる。 街の図書館について日本と違うことは、コンピューターを使えたり、CDやビデオなども貸し出したりしているところだ。居住のカードを持っていれば借りることができる。私も一度CDを借りたが、貸し出し期限は一ヶ月だった。 児童書のコーナーも充実していた。図書館の各所にコンピューターが置いてあり、自分で検索したり、インターネットで情報を集めたりできるようになっている。児童書のコーナーも同じだが、子供用にテーブルを低くしてあったり表示も子供が使いやすいようになっていた。 どうして日本の図書館ではコンピュータが使えないのだろう。あっても検索機や地域の情報を見れるぐらいだ。それに台数も少ない。それに、貸し出し期間はせいぜい二週間ぐらいだ。もし、一ヶ月にしたらどうなるのだろう。私は日本の図書館事情も知らないからなんともいえないが、何となく乱れた図書館を想像してしまった。 <ヌカとの散歩> ある夜、12時少し前にヌカは部屋に戻ってきた。二人はそれぞれやるべきことを済ませていた時、突然彼女は散歩をしようと思い付いた。その日はとても気持ちの良い夜で、このまま寝るのは惜しいなと私も考えていた。意見の一致した二人は散歩に出かけた。 外に出ると驚いたことに、空一面に星・星・星・・・山のないデンマークでは、空は広く低く感じる。私はそれほど多くの星を見るのは初めてだった。感動している私にヌカは聞いた。「日本ではこんな星を見られないの?」「うん、見たことない。」「グリーンランドでは雪の上に大の字になって寝転んで見たことがあるよ。」「へー・・・」少しの間、二人でその美しさを堪能した。 ヌカはデンマークは木があるから空が狭いとも言っていた。それでも、その時の星空に感動したようだった。 二人で腕を組み、美しい家やその窓の装飾を見ながらどことはなしに歩いた。こうやってリラックスして初めて、私は自分がどれだけ気を張っていたかがわかった。学校へ来てからばたばたといろんなことが起こり、自分が何をしに来たのかを忘れるところだった。 学校生活も半分が過ぎて、やっと今後の自分を考え始めた。 <最後の日> それぞれの中に学校での思い出が蘇り、噛み締めている。だんだんと何を話したらいいのかわからなくなる。このまま二度と会わない人もいるだろう。だけど、そう思いたくない。 学校にいると世界が狭く感じられた。しかし、また広がっていく。それをどうにかして止めたい、そんな思いだった。いつもなら遅くまでコモンルームで騒いでいる。しかし、この日は2・3人しかいない。みんなどこに行ったのか? ある部屋で何人かが集まっていた。ビールを飲みながら話している。ノートにサインをもらっている人もいる。 共通の話題は「このあとどうするのか?」だ。国へ帰って仕事を再開するもの、しばらく旅に出るもの、学校で知り合った人の国へ行く計画をたてるもの。 IPCは特別な世界だった。デンマークに存在はするが、デンマークではない。まさに世界を縮小したようだ。国によって文化は違うが、人間として考えることは同じ。様々な人と知り合って、今、どこの国の出来事も他人事ではなくなっている。世界を身近に感じることができるようになった。 さて、自分の今後はというと、結局具体的なものは何も思い付かなかった。いま持っている興味を追いかけていくこと、それしかできない。また、それで良いのだという気もしている。 |
||||||