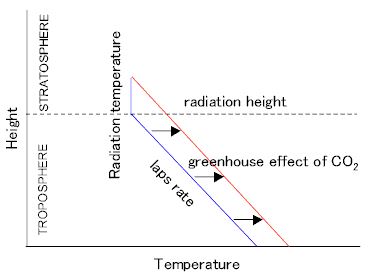
| シリアル番号 | 1049 |
|
書名 |
CO2温暖化論は数学的誤りか |
|
著者 |
木本協司(きもときょうじ) |
|
出版社 |
理工図書 |
|
ジャンル |
サイエンス |
|
発行日 |
2010/2/24第1刷 |
|
購入日 |
2010/04/20 |
|
評価 |
優 |
著者は九州大学合成化学化卒旭化成でアンモニア合成コンピュータシミュレーションをしていた方。
トリウム溶融塩炉開発者の古川和男先生の勧めで購入。
いままで無批判にIPCCを信じて居たのだが、ふと疑問を持ち、この1ヶ月関連図書を読破して一挙にIPCC批判派に転じた者(転んだキリシタンの思いが
ある)にとっては頭の下がる思いで読破した。氏は圧倒的な調査力を発揮してIPCCの予測のはずれを数え上げてゆく、そして最後に二酸化炭素温暖化説に呪
術力を与えた真鍋淑郎氏の「鉛直1次元放射対流モデル」にアンモニア合成コンピュータシミュレーションで鍛えた経験をもって切り込み、木っ端ミジンに論破
されていて身が震える程の感動を覚えた。そして私の転向は正しいと自信を得た。
著者はまず真鍋淑郎氏の「鉛直1次元放射対流モデル」は鉛直温度減率(laps
rate)を6.5°C/kmで一定としている。しかし懐疑論者のS・リンツェリンは実際には湿潤断熱線(moist
adiabats)は直線ではなく曲がっているため地表の温度上昇は特性放射高度の温度上昇の半分程度となり、真鍋氏の一定値仮定は過大な温暖効果となる。
著者のIPCC批判論文はENERGY & ENVIRONMENT VOLUME 20 No. 7 2009に掲載され、そのプレプリントは
http://www.mirane.co.jp/thesis/paper01.pdf
でダウンロードできる。
著者は特性放射高度の二酸化炭素濃度が増せば、放射高度があがるので放射温度が下がる分、特性放射高度の温度が上がらねばならぬとする真鍋淑郎氏の説を受け入れているが、これこそ間違いで、この高度では対流は支配的ではなり、放射だけになるため、鉛直温度減率は垂直になるのだ。なぜなら、この高度では対流は少なくなるからだ。
氏はこの他にも歴史的な気候変動記録から、スベンマルク説、ジェットストリームは磁性流体であり、磁極をさけて流れるというN・コルダー説も紹介。
木本協司氏の地を這うような論証にこのゲーリッヒの熱伝導モデル欠落説を加えればIPCCは完全敗北となるのではないか。真鍋淑郎氏がその先駆的仕事「鉛
直1次元放射対流モデル」に
ゲルハルト・ゲーリッヒの指摘する熱伝導モデルを組み込んでいればサッチャーがIPCCを提案することも無かったし、COP-XXも無かったし、鳩山首相
の25%宣言も排出権取引も無かっただろうと思う。ただ温暖化の恐怖が化石燃料の持続的利用を促進した功績は認めなければならない。
このあやまてる二酸化炭素温暖化主犯説のきっかけを作った温暖化のコンピュータ・シミュレーションの先駆者、真鍋淑郎氏(1931年生まれ)はまだ健在であるが今どのように思っているのだろうか。
さて著者は真鍋モデルの欠陥である熱伝導を無視したことに気がついていないために、かなり苦しい論証をしている。 そしてタイトルも「数学的誤りか」となっている。しかし私は「正しい物理学的なモデリングしてないから」としたい。その理由は次ぎのとおり。
理由
ブラウンシュバイク工科大学、数理物理研究所のゲルハルト・ゲーリッヒ(Gerhard Gerlich)らの Atmospheric and Oceanic
Physics 11 Sep 2007掲載の論文「Falsification Of The Atmospheric CO2 Greenhouse
Effects Within The Frame Of
Physics 2009 年のversion 4.0 では熱伝導モデルを「鉛直1次元放射対流モデル」組み込まなかったのが過ちの始まりとしている。
私が理解したゲーリッヒ論文とホートンの教科書「大気物理学」を総合したIPCC批判は以下の通り。詳しくはIPCCが主張する二酸化炭素のグリーンハウス効果は誤り。ゲーリッヒは
;
地球は太陽放射と地球放射が釣り合って平衡となっている。
地球放射は大気に少量含まれる水蒸気、炭酸ガス、オゾン、メタンなどのグレイ・ガス(不透明なガス)が対流圏上層部で当該ガスの吸収スペクトル帯域で行われるもの
が約60%、グレイ・ガスの吸収スペクトルが存在しない「大気の窓」を素通りして地表から宇宙に向かうものが約40%である。
対流圏上層部でグレーガスの吸収スペクトル帯域で宇宙に放射される熱はすべて地表から放射高まで放射・伝導・対流・水の蒸発・凝縮・降雨が相互に絡み合いながら移動する。対流圏は局所的熱力学が適用される場である。
ホートンは局所熱力学平衡にある二酸化炭素の0.0015cm吸収帯の場合、二酸化炭素と空気分子との衝突が標準圧力, 210oK(中間圏での平均温度)で生じるとすると分子間の衝突による緩和時間は3x10-5s、一方電磁波として放射される緩和時間は0.74sである としている。 このように分子間の衝突による緩和時間が圧倒的に短いときは、放射を受け取ったグレーガスが再放射する前に周りをとりかこむ99%以上の窒素、酸素分子に伝導で熱を伝えて緩和する。というわけで 対流圏のように気圧が高いときは伝導が支配的となり、吸収・再放射の連鎖は続かず、伝導・対流に移行するとしている。
そして成層圏の気圧が低いところでは放射伝熱が支配的になり、最早、局所熱力学平衡は存在しなくなる。成層圏では高度が上がり、気圧が下がるほど放射が支 配的だから熱は高温の成層圏を突き抜けて宇宙に向かうということが理解される。これが対流圏上層部が地球の放射面となっている所以だ。そして電磁波として 放射される緩和時間は二酸化炭素に内在する特性でその二酸化炭素の濃度の影響を受けない。
このように対流圏においては局所熱力学平衡が成立するため、グレイ・ガスによるグレイ・ガス帯域での再放射はすぐ下層のグレーガスで吸収され、伝導で透明ガスに熱が 伝わって対流で放射面にリサイクルされるため、地表へ達することは殆どない。従ってIPCCの主張するようなグレイ・ガスの再放射が地表へ熱をリサイクルするということはない。
大気は完全に透明と仮定し、地表のエミッシビティーを0.7としてキルヒホッフープランク関数で計算した地球の放射面の平衡温度は-18oCである。この-18oCとは大気上端でグレーガスが宇宙に向けて放射するとき、そのグレーガスの温度が-18oCでなければ地球の熱収支がとれないという意味だ。
この平衡温度が地表近くの気温の観測値の平均値である15oCと比較して33oCも低いことを大気物理学では大気のグリーンハウス効果と呼んでいる。33oCという温度差はしかし 、地表から対流圏上端の放射面までの放射・伝導・対流・蒸発・凝縮 ・降雨の複合的熱移動メカニズムの駆動力と認識するほうが重要である。そしてこの駆動力は二酸化炭素の濃度の変化で影響を受けるようなものではない。
IPCCモデルの基礎となっている真鍋淑郎氏の「鉛直1次元放射対流モデル」は対流圏の鉛直方向の熱移動は放射と対流だけで行われるとしている。そして対流計算を省略するために鉛直方向の大気の温度勾配(laps rate)を一定と仮定している。これは地表で暖められた大気は対流で放射高度まで達し、そこでグレーガスが特有のスペクトル帯で全方位に放射するというモデルである。こういうモデルにおいては 摂動で二酸化炭素濃度を増すと、二酸化炭素がより上層まで達し、放射温度が低下する。そうするとキルヒホッフープランク関数で計算した放射熱量が減ることになり、地球の放熱量が減じて対流層に 熱が溜まり、鉛直方向の大気の温度勾配を維持したまま、対流圏全体の温度が上昇する。即ち二酸化炭素に温室効果ありというロジックである。
しかし実際の大気は二酸化炭素濃度を摂動で増しても局所熱力学平衡にある対流圏では伝熱と対流が主流であるため、鉛直方向の大気の温度勾配は摂動前と変わらず 、放射面の温度も変わらない。放射面より上に拡散した二酸化炭素は伝導より放射が優性であるから対流圏で必要であった対流を維持するための鉛直方向の大気の温度勾配は必要でな く、高度が上がっても摂動前の放射温度を維持することになり、放射熱が減ずることはない。
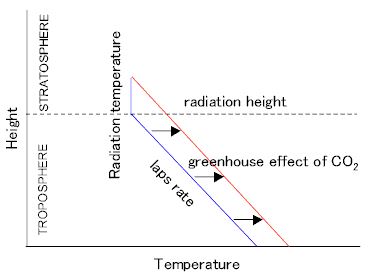
真鍋モデル(赤色)とゲーリッヒ・モデル(紺色)対比
このように真鍋淑郎氏の「鉛直1次元放射対流モデル」が予告する温暖化はイリュージョンである。 したがって「鉛直1次元放射対流モデル」を踏襲するIPCC報告は誤りであるとするのがゲルハルト・ゲーリッヒの言わんとするところと理解した。
Rev. April 24, 2010