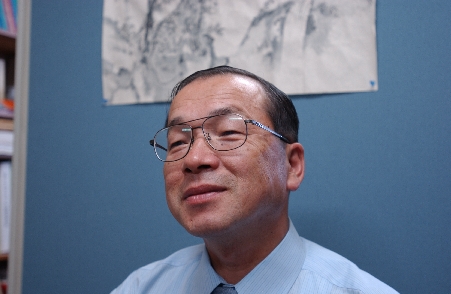
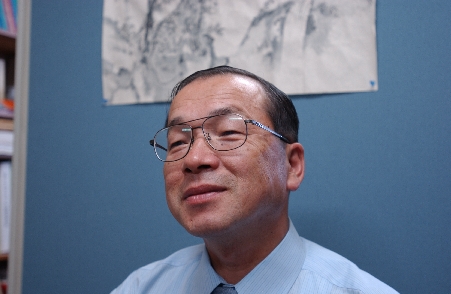
プロセス制御で人生を語るM翁
21世紀の学生とM翁。
1.若い時に感心した3人の先生方
学生時代に刺激を受けた本がある。本多光太郎伝の中で先生の朝の大学への登校下校時刻を片平の店の人達がいつも同じ時刻だと気づき、時計を見なくても良いと。これを読んだ時に、研究生活をしているなら、時刻が遅くなったり、早くなったりするはずで、可笑しなことだと思いはしたが、段々、自分も同じようになり、今は12時には必ず昼飯を摂るようになっている。就寝時刻さえ守ると起床時刻が一定するので、一日一日のリズムを作れるようになり、生活が規則正しくなる。リズムを作らないと研究生活は出来ないと感じた。
東北大の金研の建物を見た時に身震いしたという東大元総長茅誠司先生の話。朝、今日の研究に武者震いするなど、感心してしまう。そういう緊張感を朝の登校時に未だに感じたことはないが、学生達には研究ノートを作ることだと指示している。要するに一日の反省と明日何をすべきかを常に明確にすることだ。それを帰宅する前にノートしておく。夜間に気がついたことを翌朝に浮き浮きしながら実験したりするのは楽しいはずだ。また他人の話も漫然と聞くのではなく、ノートしておくことだ。役に立たない話と思わずに、いつか血となり肉になるかもと期待して。
官軍と彰義隊の合戦が起こる中でも講義を続けた福沢諭吉の話し。世の中の浮ついた風潮に関係なく教育の継続性を大切にしている。当研究室では、月曜日に先週の成果と今週の計画の討論を学生達と行っているが、月曜日が休日になることが多いのが問題だ。学生には迷惑であろうが、できる限り月曜日の発表会を継続している。その分でもないが、研究室では飲み会を増やし、よく学び、よく遊ぶをモットーに、いい加減な理由では酒を飲まない、必ず理由をつける。
2.悩み続けた学生時代や助手時代
研究室に入った4年の時に噴霧乾燥塔内で未乾燥粒子が壁面に付着して余計なエネルギーを消費するので、何とかせよという。現在の研究室では前記のように一週間に一度の研究成果報告会で問題点を明らかにし、研究目標を与えてやる。そのため、研究のネタが豊富にあり、学生はそれをこなすのに精一杯という状態になる。昔は大雑把なテーマを与えられて自分で目標を作り出すことが必要であった。その結果、既往の研究成果を見ながらテーマを細かに分析するのも一人で行うわけである。どちらが楽かと言えば当然目標を与えてもらう方となる。研究のやり方は他人の論文が参考になった。学生であれば自分のレベル以上の内容を示す論文は沢山あり、先人の手法を真似た。良き論文は自分の先生であり、そのレベルを超え、オリジナリティーを出すために努力した。
博士課程までは大体は培ってきた才能と努力で学位はもらえると思う。9時に大学に来て8時に下宿に戻る。下宿では毎晩英語の論文を全訳していた。時間は十分にあった。しかし助手になった途端に自分の技術は何か?と自問してみると何も残っていない。これはまずいと、助手になってから真剣にテーマを選び目標を決めて精進した。人間は自分の状態にどこかで気がつき、自分(欲求)を殺して、努力する時代が必要だと思う。その時に行ったのが乾留過程における石炭の有効熱伝導率の測定だ。師匠からは例によって石炭をやれと言われただけで、自分で何をすれば良いのかを探した。師匠からは定常比較法でという指示、勿論、石炭を知っている人なら定常状態があるわけがないので、測定法を編み出すために年がら年中、非定常熱伝導方程式の厳密解を解いて熱物性値を求める手法を紙と鉛筆で計算する毎日。師匠の指示も自分の手法も両方とも行った、変なところで師匠と討論しても時間を弄ぶだけ。初めての物質に対して何でもやってみるという闘志が必要なことは言うまでもない。
3.中途半端な頭脳だから教授?
微分方程式が解けるから優秀だ?小学校の同級会で会う友人達は商売していて社長連中もいる。皆、試験に解答するために頭を使っていない。商売するために脳を使っている、算数が出来る脳と商売の脳とは違うのだと思う。
例えば、教授よりもライターを作った人の方が偉い。ライターの歴史は、安永元年(1772)に平賀源内がゼンマイを使用した火打石と鉄を用いた刻み煙草用の点火器を発明したことから始まるという。皆が使うライターを汎用化したのは尊敬に値する。研究室に配属になって師匠に哲学を聞いた、「真心です」と。正直に言えば、がっかりした。しかし師匠は如何なる人にも誠意を尽くす先生で、自らの行動の規範になっていることを哲学とした。生きる知恵なのかも知れないが、私の知恵は心技体。心を丈夫にするためにあらゆる本を読み(学生時代の読書のテーマは、①明治維新は何故可能だったのか?と②太平洋戦争に何故負けたのか?)、技を蓄積する、これらを行う上でも身体が粗末では何もなし得ない。教授は肉体労働者と言っても過言ではない。脳溢血で倒れたら教壇に立てない。
自分は何故生きているのか?学生の教育や研究を行うために生きている。というか、神?に生かされている、まだ生きていて良いよと天に啓示され生きている。研究のために自分が生まれて来たのだ。家族のため、ましてや嫁のために生まれて、努力してきたわけではない。子供が夜泣きして五月蠅い時には、母が子供の泣き声を父に聞かせないようにあやしたりしたという話しも聞いてきた。教授になったら、天が教授として努力するように命じたと考え、あくまでも学生が1番、2番で・・・子供は5、6番目で、次が父母、嫁はずーっと番数が下がる。これが大学の教員の生き方だと考えている。そのために人間の幅を増やし、子供には、生きる姿で見せられるようにすべきではと思う。
昔、母から「うちには財産と呼べるモノがない、教育だけが財産だ、好きなだけ勉強して良い、大学でもどこでも行って下さい」と言われた。これが日本にも言える。日本には禄な資源がない、あるのは人材だけだ。それなのに最近は教育もNHKも優しくすることが使命だと言わんばかりの低落を感じる、日本は貴重な財産を失う羽目になる。各国の首脳の発言ぶりに品位を感じない現状で、日本はもっと教育に力を入れて、アジアから尊敬される人物を輩出すべき。大学に教養部をなくしたのは残念なことである。知識だけを教えるのが教授の役目ではない、人間を作るのが教授の役目だ。
4.農業に宮沢賢治がいれば工業にも宮沢賢治が必要
教授連中の五月蠅さにも負けず、景気後退にも負けず、研究費の少なさにも、学生の酷さにも負けぬタフな脳をもち、慾はなく、決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に日本酒四合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を勘定に入れずに、よく見聞きし分かり、そして忘れず、青葉山の小さな部屋にいて、東に伝熱の問題あれば、行って看病してやり、西に酷い装置の使い方をしている企業があれば、行ってその装置を労ってやり、南に燃焼計算もできない人あれば、行って難しくないと言い、北に不法投棄があれば、ただ溶融固化するだけではつまらないと言い、実験がうまく行った時には一緒に感激し、実験がうまく行かない時には何度も何度も繰り返し、うまく行かなくて、役に立たない教授と言われ、心で泣きながら、みんなにでくの坊と呼ばれ、褒められもせず、苦にもされず、そういう者に私はなりたい。
「いつでも、どこでも、誰とでも」と言うのが癖ですが、皆から国分町でのことですか?と揶揄される。これは上記のように宮沢賢治風にanytime、anywhere、anybodyとなるわけである。
いつでも、どこでも・・というためには、人間が好きだということ。工業はチームで行うことが多い。人間のために工業がある。蝶蝶が好きなら工業に携わらなくても良い。人間に興味があるから工業、工業は進化し続けている。未知のものへの興味が薄れたら進化できない、常に改革を続け未知の世界をなくすように努力する。頭を柔軟にしてこそ、一般性が出てくる、経済も政治も理解しながら、人間として生きることが、エンジニアなのだと。専門の一領域だけではなく他をも知ることで、専門がより深まる。これで人間生活に利益をもたらすことができる。生き方を再度チェックしてみてくれ。心が老人にならないように、リスクを踏まえて冒険してみようではないか。
5.心の強化
褒められると、また良い評価を受けたいと努力する。その結果として集中力が付く。集中力が付いてくると、ハートが強化されるのは言うまでもない。美意識もなく、プライドもなく、評価も受けないと、自分がいつの間にか窮地に立ってしまう。窮地に立っていると気がつかない鈍感さ!気づいた時には上司から結論を出されている。鈍感な人間は、年がら年中、一つのことを考えられない。頭脳にタフさがないので、大抵は考え続けることができない。自分を磨き、日本の将来を気にしろ。そうすれば誇りも付くし、友人や部下も大切にする。
モラルやルールにやたらに厳しい人間、まるでルールの奴隷。日本は突然のようにコンプライアンスが出てきた。しかし契約社会の米国ならともかく、日本は昔から日本文化という先進国でも希に優雅な文化を保有する国である。「ギフトE名言の世界」に出演しているロジャー・パルバースさんは日本は電車でスーツ姿できっちとした生活スタイルを全ての人達が行っている、素晴らしい日本文化のお陰でしょうと言っていたが、蓋し名言と思う。モラルとか道徳は為政者や宗教家のために作っているが、人間同士が付き合う時に必要なのはモラルよりもハートだ。本来から言えば、ハートのある付き合いが人間同士でできれば何のルールも必要ない。ルールに厳しいのは何故か?その方が楽だからである。考える必要もない。1+1だけが2になると思っている。12-10だって、4の平方根も、3×2-4も全て2だ。本質を見抜くこと、最終的な結論が同じなら手法は一杯ある。
研究室に学生が入ってきた時に、茶髪だし、遊んできたようだし、優秀な学生に見えないなあ。これが学年を経るに従い、机に明日行うべきことや研究ノートが置いてあり、着実に自己の発展を期すべく行動している。いつの間にか、用意周到に学会の準備を行い、発表も申し分なくこなすようになっている。その時には人間的にも落ち着いて、後輩からも尊敬されるようになっている。人間力が付いたなあと感心するばかりである。人間力が付いたから能力が付いたのか、その逆かは議論しても仕方ないが、両方が同時についている。この時に言えるのは結果の出ない学習を執念深く継続したからできたのだと思う。
仕事はm×vの自乗だと言われて久しい。それにpを付加したpmv^2に修正したい。プライドのp、メンタリティのm、ヴァイタリティのv。プライドがあると、変な仕事をしない、できませんと言わない。メンタリティは熱き心。気がつくと「できません」と言ったことがない。何でもやってやろうではないの!という気概がそうさせたのかも知れない。リーダーになって部下を育てるには、上司が十倍以上の熱意を持つべき。部下を思いやる、思いやるからこそ叱れる。叱れない上司は自己満足だけ、他人には無関心。いつもタフな心と言っているのはここにも通じる。ヴァイタリティは二乗です。如何に行動力が必要か、フットワークの悪い人間は駄目だ。因みにカラオケの採点基準はvの二乗、心の採点ができたら満点になれるか?
6.研究は楽しく
研究が楽しくなるのは、目標を決めて、目標達成により自信を持たないと難しい。そのためには、一番良いのが一緒に実験して楽しさや夢を語ってやることだ。研究は苦しいことの方が多く、後で振り返ると楽しい思い出になる。そういう研究で結果が出ないで苦しんでいる時に、明るく振る舞うのは難しい。しかし苦しいからこそ明るく振る舞うのが必要である。下の者が明日も明後日も苦しい研究を行って貰っている時にこそ、冗談を言える余裕を持ちたい、そしていつでもユーモアを!と、顔で笑って心で泣く、芝居の大事さ。
研究は常識のある人には無理!昔、物資移動なら分かり易い、しかし熱はどこに逃げるか分からない、そんなのは頭の悪い人間の行う研究だ。研究は馬鹿でもできる、象の研究で全体を研究しないで、尻尾だけの研究でも研究だ。石炭の研究、しかも伝熱をやっているだと。阿呆か!熱加えれば変化する物の熱物性など、非常識だからこそできる話しだ。これらは亡き前田四郎先生が仰った話だが、言われる度に闘志が湧く。非常識は常識を知った上で行う。非常識がないと世の中は進歩しない。無常識は常識を知らない、それで行動するから失敗する。幼い頃、銭湯で大学生のお兄さんに、「タオルを風呂に入れるな」と叱られたと母に。母は「大学ではそういう常識を教えてくれる」のだと。大学では定石という手は教えるが、常識は教えない。しかし定石だけでは勝負に勝てない。
擂り、ひき、力。この三つは昔から言われている。擂りは、胡麻擂りのことであるが、上司とのコミュニケーションと訳して良い。世の中には報連相という言葉があるが、報告、連絡、相談は常識である。ひきは、そういうコミュニケーションを行っていることにより、上司からこいつを引き立ててやろうかとなる。その結果として実力を発揮できる。力があるのに何で使われないのだという考えではなく、実力は3番目なのだと分かれば、その前のコミュニケーションが非常に重要となる。これらの繰り返しが人間社会であり、時には真剣に、時には楽しい語らいを。
7.四CHプラスCH
直近のできごとで叱っても意味はない、大失敗の前に、小さな失敗が沢山ある。その失敗を軽視しているから大事件になると。部下や学生の言動には常に注意を払うことが必要である。教授は、まず学生の言動に注意して、甘やかされて育ってきた学生を鍛えられるように、細かく気を配って、鈍感では不可能なことだ。
学生も多少のピンチにおたおたしないように。昔、スキー選手の岡部さんが、失敗したらpinch状態である。それを絶好の機会であるchanceと思い、挑戦challengeしろ、その結果、自分がchangeできるということで、4CHが大切だと言った。これに、もう一つのCHを加えたい。結果を出すには、やっぱり着眼点CHAKU眼点のCHが必要である。
実験装置をよく壊した。それこそピンチの連続である。高い授業料でもあった。実験時に、装置のそばにいないで壊したこともあった。実験は料理と同じで、装置から離れると失敗する。計算能力だけでは工業は無理。実験能力も付けて欲しい。何よりも現象を観察する能力を付けて欲しい。観察する時に、いつも欲しいのは何故こうなるのだという疑問。疑問を持たないで現象を見ても何も観察しないのと同じだ。疑問を持ちながら、そして横軸と縦軸を考え、ついでに結果の図までも想像できると洞察力がつく。
学生に、実験装置を恋人と思え、恋人なら汚くしておかないし、いつも触っていたいだろう、と。その学生が「他の人には美人に見える装置だし、テーマなのでしょうが、私にはどうしてもそのように思えない」と。勿論、強制した。実験装置は知恵の源であり、頭脳を強化する道具として考えて欲しいので、ある意味何でも良い。
8.タフな頭脳
体育会系出身は、自分の身体を虐めるのが好きで、結果を出さないという理由で、会社では採用したくないという社長がいた。体育会系出身者への誤解だ、熱い思いの持ち主、ウジウジしていない、少しもけちくさくない、いつも堂々と頂点を目指す、結果を残すことに一生懸命、命がけで全力を尽くす、これが体育会系だ。HPに「技術者は野武士たれ!」と掲載しているが、昔日、JFEの藤森さんが野武士の定義を毛筆で書いて送ってくれた。私の意味は、潰しの利く技術者であって欲しいということで、野武士なら工業分野でどんなことをしても生きていくだろう。一つの技術士か持たないなら誰にも真似できない超一流の高度さを、満遍なく何でも来いの技術者なら一流の技術を蓄積することだ。体育会系こそ、そういう素質を持っているはずで、上記のような野武士になって欲しい。日本を意識し、良いものを良いと言い、他人への洞察力も凄い、有言実行、そして変幻自在なタフな頭脳が野武士だ。頭脳とハートのコラボレーション。
人が酒を飲む、醤油が欲しい時に、さっと注いでくれる。男子である限り、そんな余計な気を遣わずにもっと先を読め、と言いたい。他人に意見したり、圧力を掛けるのは、それ以上に自分にも負担が掛かる。人格者と言われる大人しい人は他人を考えていない。自己の中に留まるために、他人に文句を言わない。目先のことではなく、他人の5年後、10年後を考えて、叱りたい。これらを例えて言うならば、30cmや1mの気配りよりも3mの気配り、10mの気配りができるようになって初めて、男子だ。
9.些末に拘らず4つのレンズで日本を元気に
バイオ燃料を好きな人が多いが、廃食油約47万t余っているのでディーゼルエンジンの燃料にと開発しましたという。それを全てガソリン(6千万kl)、軽油4千万klを生産する石油精製企業に依頼して原油と混ぜてもらっては?余計なことをしてエネルギー使うよりもどれほど効果的か?現状のリサイクルなどアジアで成立しない、こういうことを実現するためには、頭に魚眼レンズが必要だ。
実験の前にシミュレーションで説明や設計指標が構築できるならシミュレーションせよ。敢えて実験する必要はない。また圧倒的な技術の差別化を行う上で方式変更によるヒートポンプなどの成績係数向上策は最初にシミュレーションし、コスト的にも有効な方策を選択することが可能となる。各種の偏向レンズの駆使だ。
研究室の実験装置の実験結果を地道に解析し、現象を説明する。その時に各種の式が得られるはず。時には装置から離れて、基礎実験も不可欠。昔、氷蓄熱の研究で、過冷却解除温度は粒子濃度が増すと共に上昇するが、過冷却水中の核同士の凝集(水素結合の塊embryo)による解除モデルにより解除温度の上昇や解除後に生成するデンドライト(樹枝状結晶)の形状に及ぼす過冷度の影響などの解明の共同研究を行った。物理の領域に踏み込んだようで、冷凍技術に貢献できたのではなかろうか?少し外れても興味を持ち覗き見レンズだ。
実験は練習のための装置作りではなく、実用化に繋がるか、真理探究の科学のために役立つ場合のみに許される。それ以外は安価に作るべきだ。そうでないと装置のお守りで時間と経費が掛かる。昔、振動を加えるのにスピーカを改造して装置作りを行ったが、おもちゃの分解もままならず、未経験の若者からアイデアが生まれるだろうか?という疑問は別にして、高度化する時代に適合する知恵を有し、その知恵で論文化できる世界の実現が要望される。素朴で単純なレンズで。
10.人生に結論はないのかも?
師匠からの言葉で反省させられたのは、「言い訳不要、常日頃が大切だ」と。言い訳人間はあれこれ言い訳して結局実行しない。出来ませんと言いたいから言い訳する、前進するには言い訳しないことだ。常日頃で重要なのは自分の今の技量を計り、キリギリスから蟻になることも偶には必要、蟻になったことがなければ一度は蟻にならないと。その判断ができるようになれば素晴らしい。技術力と人間力は一緒に育まれるのは常日頃の精進の賜。いろいろな気配りやバランスは、常日頃からの生活のリズム。科学的に定量的に物事を観察し、システム全体をイメージする力を養うことだ。いくつになっても常日頃の精進を継続することが重要であり、その努力が自らを助ける。
エンジニアは失うモノは何もない、今までの自分で勝負し、不足分は学習し、毎日毎日を技術の進歩について行き、超える、何かを作り出す、という風に自分を急き立てながら生き抜くことだ。無我夢中になって仕事をしていると、そういう仕事が来た時に、没頭する自分が楽しくなるはず。そこまで無我夢中に生き抜くことが野武士だ。
修行僧としての人生を歩もう
三浦隆利
1)隣の芝生状態の自分
一度、自分を疑いだしたら、悪い方へ、悪い方へ考え出して前進しない。そういうことありませんか?自分に自信がない、何をやっても駄目だと。他の人は優れていると、隣の芝生が良く見えてくる。
後ろ向きの人間ではまずいよなあ、と思いながら、これも性格かな?昔、よく死ぬ時は前向きになった状態で死にたいと言ったけど、そういう気概はエンジニアには必要だ。
山に登るのにヘリコプターで頂上はないよね。一歩一歩、歩いて登るだけ。急がなくて良い、いつか自分がトップに立つのだと、抜いていく人には抜かせれば良い。自分の一歩で、自信を自分に持たせれば良い。
2)期待に応えようとして焦る
どのように自分が育てられてきたのでしょうかねえ。親の愛情を一杯受けるだけではなく、師匠からも同級生からも愛されて生きてきたのではないのかあ?親や他人からの愛というのは、有り難いし、それに応えないとと、思う。一生懸命に焦る、焦るとプログラムの中からじっくりバグを探せない。探せないので余計に焦る。こうなるとプログラムの変数も何を言っているか不明で、変数対照表を始終見るようになる。
理想を追い求めても、今は登山の途中ではないのか?最高のモノを今実現しなくても良い。今の自分にはこれしか出来ないと開き直っても、仕方ないのではないのか?その一歩はとろとろしていて自分でも歯がゆいけど、良いのだと、言い聞かせることをしないと。ノーベル賞には遠いけど、それでも良いと。
3)たかが20才過ぎ、ならゆっくりで良い
頂上に達していなければいけない年齢なのだろうか?まだまだ2合目に達するか否かという年齢だ。何で自分の心を頑固にするのだ。20代に遊んでしまった、それなら30歳代で頑張ってみようか?でも良いのではないの?2合目で自分の登ってきた道を振り返る必要があるのだろうか?自分の欠点や長所をきちんと把握して、長所を伸ばすことではないの?
大人になったというのは、欠点が見えにくくする術を覚えただけで、欠点は変わらない。それ以上に長所を伸ばすと欠点が見えないで隠れてしまうだけだ。
ゆっくり自分を見つめてみようかねえ。何ができるのか、と思ってみると、自分は何もできないと。それが20歳代ではないのか?そういう自分に気づくだけで十分な20代では駄目なのかい?それで何か身につけないとという、心構えを作るのが20代ではないのかねえ?
4)自分をまともに、客観的に見てみることはできるかな?
自分の状態が不安になる。就職先で通用するのだろうか?希望に燃えるのより以上に不安が増す。皆、不安なのですから、そんなに心配しなくても良い。それよりも現在の自分をしっかり精神面も技術面も、与えられたテーマをこなすことに誠心誠意対応すれば良い。他人のことを考えるよりも、自分が行うことは自分しか知らない。
よく言われるのは、自分が他人に勝つことを考えるよりも、まず自分に勝つことだと。自分を照らしてみることだ。自分を映し出すモノが曇っているから、不安になる。明鏡止水の境地だろう。川の水が止まって、澄んでいて、まるで鏡のようだという心境になれば、自分の本当の気持ち、本当の欲望というのが分かり、それを押さえる方法も考え出せよう。自分に正直に向き合うことだ。我が儘な自分を変化させる機会を何度も体験する。
5)自分を尊敬しているか?
達成すべき目標があるが、目標を低くすることはできない、自分を高めるしかない。大きな目標を立てることだ、目標達成は一人ではできない、他人に頼るべき面が出てくる。その時に必要になるのは、主義主張ではない、人格である。そして自分に徳が付く。人格者だなあ、とかいういわゆる人徳とは、一種の健康であり、美であり、魂の良いあり方である。他人の上に立って下の諫めを聞かない人が多くなる。こういう人には、人徳はないし、大きな仕事ができない。
自分を尊敬するからこそ、他人を敬う。つまり自分を敬えないと、大切にしないと、他人も大切にしない。例えば、その人の使う道具がいい加減であったら、他人もその道具をいい加減に扱うようになる。
6)たくましく生きろ
逞しいというのは、自分が言うことではない。他人が言うことだ。だけど、どんな苦難にも立ち向かうことが必要だ。ゴルフに例えると、バーディーをとりたくても、パターでボールが穴を超えなければ、到達しなければバーディーはとれない。ここにもう一つ言えることがある、ホールという目標があるから努力する。ホールがなければ、どこに向かうか、努力を重ねても、結果が出てこない。努力はしなくても結果が問題。目標と全然違う方向で汗水垂らしても意味はない。
逞しくなると、他人を面倒見る余裕が出てくる。優しくなるわけだ、慈愛に満ちるようになる。これでようやく生きる資格ができる。逞しくなると言うのは、仕事にメリハリがつく。それでは逞しくなるには、努力の継続しかない。継続させるには、一度で良いから感激というか、喜びが必要だ。その喜びを味わうためにまた努力する。
7)時間がないと言って断る仕事ぶりは野武士ではない
結局、時間的余裕を作る仕事ぶりではないわけだ。仕事に振り回されてしまう。何故か?集中して仕事を行い、それを継続させたことがない。仕事というモノを知らない。どこが肝要かが分からないから、ゴルフの穴に向かわないで、あっちこっちにボールを打ち出す、努力はしているけど、人生の中で一度も、苦労らしい苦労を経験していない。
昔言われたこと、事務の仕事はいくらでも早くできる、事務の仕事こそが頭の良さ、悪さを計る尺度だ。まず仕事をする前に、仕事の結果がこうなれば良いと想像してみる。想像することは、ゴルフの穴を目標にすることになる。そして努力だ。これを繰り返していくと、逞しくなるし、時間を有効に使えるようになる。何をするにも、時間は見つけるものではない。必要なら作るものだ。30才になった時には、他人がどうみようと自分なりに短期間で成功したと、思えるようになりたいねえ。
8)負けても終わりではない、止めた時に終わるのだ
歩みは遅くても良い、しかもその歩んだ道を引き返すことはできない。人生は不可逆過程だ。一瞬一瞬が大切で時間は待っていてくれない。だから遅くても良いので、着実に歩むことだ、止まってはいけない。前進する態勢で死ぬのだ。さっぱり計算が実験が進まなくて、才能がないなあ、頭悪いなあと思う時があるはず。それは才能がないのでも、頭が悪いのでもない。要するに目標に向かって努力を継続する執念が、そういう体力がないのだ。だから心技体という。
研究が進まずに、勝手に自分の能力を疑ってしまうことはないか?自分の執念の不足も才能と言えば、才能ですが、自分にできることをやれば良いはず。できることをやっているうちに、自分が悩んでいることが軽減されるはず。難しいことをやろうとするから悩む。仕事で死ぬ人より、食べすぎや飲みすぎで死ぬ人の方が多いのも世の中。昔、勉強だけしていて病気になった人間はいない、遊びの何かをするから病気になる。努力しても報われないかも知れないが、勝利の女神は一瞬しか微笑みをくれない。しかし、継続しているうちに、そういうことが楽しくなってくるはず、そこまで行くと頂上も近いなあ?愚かなりとも、努力を続ける者が最後の勝利者になる。
9)自分の立場を守る必要あるか?
財産を持つと、その財産を大切にしようと、守っているのを破ろうとする人間を怒るし、憎むし、財産だけが自分の人生になって、寂しさや虚しさを感じるはず。同じように会社で上に上がっていくと、自分よりも上に行く同期を妬んだり、恨んだりする。挙げ句の果てに、自分が上に登ると、その立場を守るために、余計な悩みを抱えてしまう。
人間は弱いモノです、少しのことで傷つくし、自分の欲望に勝てない状態を簡単に作り上げてしまう。分かっているけど、同じ過ちを繰り返す。研究に身を投じることになって高い志と熱意を持ちだした。そういう風に自分を置かないと、何を行うか、分からない男だと思っている。その志や熱意が例えばコークスの技術者などに共感を持たれ、励まされたり、励ましたりするようになった。無我夢中で研究している状態に自分を置くことで、変な欲望に身をさらさないでいることができた。自分の立場を嘆くのは簡単だし、いくらでも時間が使えるかも?しかし歩み続けることが重要で、嘆く前に歩こうよ。そのうち悩みも軽減されるよ。
10)はな垂れ小僧が教授だものね
自分は自分だ。自分の大したことのない財産を守ろうとするから、欲が出る。欲が出るから他人を押しのけようとする。それよりも心身共に自分を向上させることの方が安心できるはず。向上というのは自分をある地点で止めておくことだ。一カ所に自分を置いたままというのは罪だ。どんどん進むことだ。気分が乗るのを待ったりはしない。そんなことをしていては何も達成できない。とにかく研究に取りかかるのだという意識が必要なのだ。
昔から運鈍根と言われているが、運が重要だと思う。その運は、努力するほど広がるモノだ。秋元康が言った、人生は98%が運だ、才能と努力は後の2%だと。言いたいことは努力しているから、運も開く、広がるからこそ、運が支配すると言いたいのだろう。運がついて来るまでに、それこそ先輩の酒の誘いも断り、余り研究室で口もきかず、自分を高めた。そうするともっと人が寄ってくる。これに満足すると、そこで止まってしまう。その努力を続けている限り、自分にはできないと思っていたことが実現できるようになってくる。これは本当に驚きというモノ。そういう自分を、努力する自分が好きになる。その努力することに何のためらいも感じなくなる、むしろ喜びになる。
11)現象の中に何でも詰まっている
化学工学という宗教に入り込んでいる。一度、授業を受けたり、卒論を行った時点で皆化学工学宗に触れた。卒業後、持っている化学工学がどこまで膨らんだのかは知らないけど、皆、毎日、修行していれば、化学工学という宗教は光り輝いているはず。そのために長幼に関係なく、教えられ、教えたり、時には中学校しか卒業していないおじさん達の素晴らしい努力ぶりに感心し、冷や水を掛けられた気になることも何度も経験する。おじさん達が工学の神髄を突いて来る時もある。死ぬまで学習という姿勢を崩さないで生き抜こう。
持っている化学工学というのがどれほどの大きさであれ、光り輝かないであれ、現象を見た時に、そこから無限の知識や知恵を生み出せる。少ししか生み出せない人もいる。気にすることはない、化学工学という力量を育成すれば良いだけ。 何も気にしないで楽しく進もうではないか!
12)愛情のかけ方に尺度はない
どのくらいと言えるような愛など卑しいものだ、とシェクスピアが言った。確かにこの人にはこの程度の愛情、この人には全力の愛情というのは、結局、その人の慈愛が少ない性格から来るのではなかろうか?ライオンが体操で身体を動かしているようなモノで、何も生産しない状況と同じにしか見えない。ライオンは兎でも牛でもいつでも全力で身体を動かすはず。愛情も常に全力投球でしょう。
中途半端な恋だから、一瞬の熱情時の甘さが、憎しみとなる。しかし全く恋をしないより、恋をした方が良い。恋に敗れるというが、恋の勝利者と言うのはあるのか?ある意味で、勝利と言うことは、安全サイドで人生を送る人には無理な話で、危険な崖のふちまで行く覚悟がないと恋はできないでしょう。