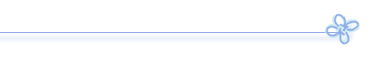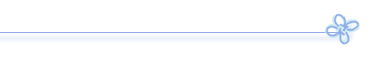|
2月14日のその日。
学校から急いで家に帰ってきた望美は慌てて制服から私服に着替え、再び出かける用意を始めた。
「あれは持った、これもバッグに入れた、と。忘れ物はないよね」
持ち物の確認を済ませると、真っ白なコートを羽織った。
そして最後に小さめのペーパーバッグの中身を確かめる。
「ヒノエ君、喜んでくれると良いなぁ」
ペーパーバッグの中から取り出した白い箱を手に持って望美はつぶやく。
赤いリボンをかけた箱の中身は望美手作りのチョコレート。
バレンタインデーの今日のために、ヒノエに用意した物だった。
初めて作った石畳風の生チョコレート。
何日も前から試作を繰り返し、昨日の夜にやっと望美なりに一番出来の良いものが仕上がったのだった。
「味見はちゃんとしたし、うん、大丈夫! よし、いざ出陣!」
すでに恋人同士のヒノエに逢いに行くのにそこまで気合いを入れる必要はないだろう。
とはいえ、初めての手作りチョコレートを渡すのは、既製品を渡すよりもドキドキするのかもしれない。
服や靴にも気を使い、最大限のお洒落をした望美は待合せ場所へと向かったのだった。
◇ ◇ ◇
待合せの場所は望美の家からほど近い喫茶店だった。
窓際に座っているヒノエの姿が外からでもすぐにわかった。
喫茶店に入ると、外から見えたヒノエの場所へ望美は真直ぐに向かう。
「ヒノエ君、待たせちゃってごめんね」
「いや、オレも今来たところだから。さ、どうぞ、姫君」
ヒノエは席を立つと、空いていた方の椅子をサッと引いた。
「あ、ありがと」
こんな風にさりげなく対応してくれるのがヒノエらしい。
少し恥ずかしいような感じはあるものの、特別な扱いは嬉しくも思う。
「紅茶でいい?」
望美は頷くと、ヒノエはウエイトレスを呼び止め注文をした。
それからほどなく、ウエイトレスが紅茶を2つ持ってきた。
「おまたせいたしました」
カップとティーポットを置くのと同時に、小皿に入った一口サイズのチョコレートをテーブルに置いた。
「これ、頼んでないんじゃ……?」
望美がそう言うと、ウエイトレスは望美ではなくヒノエの方を向いてにっこりと笑顔になる。
「本日のみ、男性のお客様にはこちらの生チョコレートをサービスしております」
「へぇ、それは嬉しいね、ありがと」
爽やかな笑顔でヒノエは応えると、ウエイトレスは顔を真っ赤にして奥へと慌てて戻って行った。
「せっかくだからいただこうかな」
早速ヒノエはそのチョコを食べようとした。
その時。
「食べちゃダメ!」
思わず望美はそう叫ぶ。
「望美?」
思いがけない望美の言葉にヒノエの動きが止まった。
「どうして、食べちゃダメなんだい?」
「え、えっと……」
望美は口ごもるだけで答える事が出来ない。
「望美、理由教えて?」
「それは……、その……」
何故止めたかの理由は口には出せない。
「ど、どうしてもダメ!」
望美は力を込めてヒノエに言った。
こんな言い方ではヒノエが納得する筈ないのだが、本当の理由は恥ずかしくて言えない。
子供じみていて笑われそうだと望美は思う。
ふと目の端にさきほどのウエイトレスの顔が映った。
同僚のウエイトレスと一緒にこちらを見ているような気がした。
「それなら、望美、食べる?」
「えっ?」
「だって、もったいないだろう?」
それはそうかもしれないと望美も思った。
せっかくのサービスなのに、一方的に食べるなと言って残すのはお店に対して失礼かもしれない。
「そ、そうね、もったいないもんね。うん、私が食べる」
ヒノエの提案を受け入れ、望美が生チョコを差したピックに手を伸ばすと。
望美がピックを掴む前にヒノエがそれを手に取ったのだった。
「じゃ、あーん」
「あーん?」
「せっかくだから食べさせてあげるよ」
ヒノエはテーブルに左手で頬杖をつくと、右手を望美の口元へと向けた。
「い、いいよ! 自分で食べるから!」
『あーん』の意味を理解した望美は焦って顔を赤くする。
「いいから、口、開けて?」
「でも、みんな見てるし……」
視線を周りに移すとウエイトレスがにらむようにこちらを見ているのがわかった。
もしかすると、チョコレートの行方を気にしているのかもしれない。
『本日のみ』というこのサービスのチョコレート。
それが持つ意味は『バレンタインのチョコレート』なのである。
だからこそ望美はヒノエに食べてもらいたくはなかった。
自分が用意した物よりも先に他のチョコレートを、しかも目の前で食べられるのはおもしろくない。
たかがサービス品、されどバレンタインのチョコレート。
こんな些細なことを気にしている自分を見て、あのウエイトレスは『度量の狭い女、こんな女が彼女なんてふさわしくない』などと思っているかもしれない。
そんな風に見られているのではないかと思うと、ホントにみっともないと自分でも思ってしまう。
しかし、『食べていい』とはやっぱり言えない。
そんなふうに思う望美の心をヒノエは知らない。
「誰が見ててもオレは気にしないよ?」
相変わらずマイペースなヒノエである。
こうなると自分の意志を通すのがヒノエであり、望美が折れるしかない。
全然知らないウエイトレスがどう思おうと関係ない。
ヒノエに食べさせたくない以上、自分が食べなければならないのだ、と望美は強く思い、そしてそのまま口を開けた。
それに合わせてヒノエは望美の口にチョコレートを入れる。
口の中で広がるチョコレートの味。
それは、ヒノエに食べさせてもらうというとびっきりの甘さが加わり、今まで食べた事のないくらいに甘かった。
「はい、上手」
何が上手なんだと聞き返したかったが、口の中にはまだチョコレートがあったので言えなかった。
かくして、無事(?)に他人が用意したバレンタインデーのチョコレートというべきものを隠滅する事が出来、望美はホッとしたのだった。
◇ ◇ ◇
「望美、さっきは悪かったね」
喫茶店を出て、歩きかけた時だった。
「えっ?」
一体何の事だろうかと、望美は不思議に思う。
「さっき、他の女性からのちょこれーとを食べようとしたことさ」
「ヒノエ君、知って……」
望美が『食べちゃダメ』と言ったことの意味をヒノエは理解していたのだった。
それを承知での行動だったのかと思うと、ヒノエも人が悪いというべきか。
それよりも、やっぱり自分が情けなくて恥ずかしくなってくる。
「たかがチョコレートなのに変な事言ってごめんなさい」
「望美が謝る事はない。気づかなかったオレが悪かったんだ」
しゅんと落ち込む望美の頭をヒノエは優しく撫でる。
「望美以外からもらうちょこれーとは絶対に口にしないよ」
「本当に?」
「約束するよ。この指輪に誓って」
ヒノエは望美の左手を取ると、薬指にはめられた指輪に口づけた。
その指輪は以前ヒノエが贈った物だった。
「ありがとう、ヒノエ君」
望美もホッとした様子で、笑顔になった。
「で、本命の彼女からのちょこれーとはないのかな?」
「ない訳ないでしょう。ちゃんと持ってきてるよ。はい、これ。今年は私の手作りだよ」
望美はペーパーバッグをヒノエの前に差し出した。
それを見たヒノエは一瞬黙り込む。
「ヒノエ君?」
「……食べられるんだよな?」
「失礼ね! ちゃんと味見しました!」
「冗談だよ。嬉しいよ、ありがとう、望美」
ヒノエはギュッと背中から望美を抱きしめた。
「ところで、もちろん、食べさせてくれるよね?」
「食べさせてって、まさか、さっきのアレ……?」
「そう、アレ。望美がイヤなら無理強いはしないけど」
そう言いながらヒノエは望美が断らない事を知っている。
間違いなく承諾すると、ヒノエの瞳は自信満々である。
「誰も見てないところなら、……いいよ」
「じゃ、オレの部屋でゆっくりと、ね」
ヒノエは望美の耳元で、どんなチョコレートよりも甘い声でそう囁いた。
終
<こぼれ話>
ウエイトレスA「見て見て、あのカップル」
ウエイトレスB「あ〜、せっかく彼氏に持って行ったのに彼女に食べさせようとしてる」
A「彼女以外のチョコは食べないってことじゃないの?」
B「カップルにチョコのサービスしたっておもしろくないわよね〜」
周りはたいして気にしてない様子です(笑)
好きな人に食べさせてもらうと、それはとびっきりの極上の味、というお話にしたかったんですが、望美ちゃんが困ってばかりのお話になってしまったような(^^;)。
なんだかんだいっても、一番甘かったのは最後のヒノエ君の囁きだったのかも〜。
|