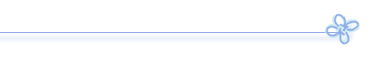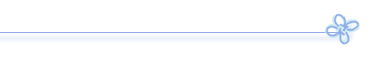|
ほのかな暖かさが頬をなでる時季。
望美は片手にケーキの入った箱、もう片手には食材があふれんばかりに詰まった買い物袋を下げ、ヒノエのマンションを訪れた。
そのエントランスに入る前に上を見上げる。
最上階は一体どこにあるのだろうと思うほどに高さのある建物。
ここに来るのは2度目になるが、建物を見ただけで圧倒されてしまう。
「ヒノエ君、こんなマンション買っちゃうんだからすごいなぁ……」
思わずそうつぶやいてしまう。
1フロア1軒の高級マンション。
今、この世界でのヒノエの住居が、このマンションの最上階だった。
当然最上階からの眺めはすばらしい。
広い窓からは湘南の海を見渡す事ができた。
以前ヒノエから『夜景と海、見渡せる場所に行くとしたらどっちが良い?』と訊かれ、何気なくその時に気分で『海』と答えたら、その1週間後にはこのマンションに連れてこられたのだった。
もし、その時『夜景』と答えたなら、きっと綺麗な夜景を見渡せるマンションを用意したのだろう。
連れてこられただけでも驚いたのに、さらに買ったと言われてもっと驚いた。
どうしてこんな場所を買えたのかを問うと、最近のヒノエはどうやら株に興味をもったようで、金額こそ望美には言わないが、どうやら相当な額を手にしたらしかった。
器用になんでもこなすとは思ってはいたけれど、ヒノエの順応力の高さには関心するばかりである。
予想以上になんでもできるヒノエ。
そんなすごい人が自分の恋人だということに、望美は嬉しくなる。
このマンションも望美だけが出入りすることができるのである。
足取り軽く、望美はエントランスに入り、エレベータに乗り込んだ。
「ようこそ、姫君」
チャイムを押すとすぐにヒノエに迎えられた。
ドアを開けた途端に瞳に飛び込んで来たヒノエのその微笑みは見とれてしまうくらいに優しげだった。
「こんなに持って、重かっただろう? 電話くれれば向かいに行ったのに」
さりげなくヒノエは望美の手にある買い物袋を取る。
「さぁ、中へどうぞ」
「……」
「望美?」
「……」
ヒノエが呼んでも望美は返事をしなかった。彼女の視線はヒノエの顔にあり、どこか別の何かを見ているという訳ではない。それなのに、望美は何故か動けずにいた。
「望美? どうしたんだい? 突っ立ってないで入りなよ」
「えっ、あ、は、はい」
妙にかしこまった返事をしてしまった望美に、ヒノエは思わず小さく笑ってしまった。
「オレに見とれて動けないなら、部屋の中まで抱いて行こうか?」
「み、見とれてなんかいないわよ! だ、大丈夫です! 自分で行けます!」
本当に見とれていたとは言えず、早口でそう言うと、望美はさっさと部屋の中へと入って行った。「誰も見てないんだから恥ずかしがる事ないのに」
残念そうにヒノエはつぶやく。
「それとも、誰かが見ていた方が良かったのかな?」
少し楽しげにそう言いながら、ヒノエはドアを閉めた。
先に部屋に入った望美は、そのままキッチンへ向かった。
そこは対面式になっていて、カウンター越しにリビングを見る事ができる。
望美がキッチンにいるのに気づいたヒノエは、買い物袋をカウンターに置いた。
「ありがとう、ヒノエ君」
「どういたしまして」
早速、望美は買い物袋からさまざまな食材を取り出した。
「ねえ、ヒノエ君、ホントに私が料理を作るだけで良いの? だって私……」
望美は恐る恐る訊いてみる。
女性として自慢できる事ではないのだが、料理上手というわけではないことを望美は自覚している。学校の授業のひとつである調理実習で体験したようなごく簡単なものしか作ったことがない。
それでも最近は母親の手伝いをして料理のレパートリーを増やそうと頑張ってはいるけれど。
「もちろんそれで良いよ。いや、それが良いんだ。望美の手料理なんて最高の贈り物じゃないか」
満面の笑みでヒノエは答える。
「でも、せっかくの誕生日プレゼントなのに……」
今日4月1日はヒノエの誕生日である。
望美はいろいろと悩んだあげくプレゼントを決めかねて、直接ヒノエに何が欲しいか訊いてみたのだった。
その時ヒノエが答えたのが『望美の手料理』だった。
「何が欲しいかって訊いたのは望美だよ? 今日はオレの希望を叶えてくれるんじゃなかったのかい?」
「そうだけど……」
「それにね、望美の手料理を食べたくて、今日は朝から何にも食べてないからかなり腹がへってるんだ。誕生日が飢え死にする日になっても望美は平気なのかい?」
「えっ、そんなにお腹すいてたの?! わかった。頑張って作るから、待ってて」
望美は意を決して料理を始めた。
「次はブラウンソースを作って、ハンバーグをさっと焼いて、そしてソースの中に入れて煮込む、っと」
手順を確認するように望美はつぶやく。
料理が上手じゃないと言っていたわりには、望美の手際は思ったよりも良かった。
ふと望美が顔を上げると、カウンター越しに覗いていたヒノエと目が合った。
口元に軽く笑みを浮かべてこちらを見ている。
「ヒノエ君、ずっとそこで見てるだけじゃ退屈じゃない? あっちのソファでゆっくりTVでも見てたら?」
「オレがここにいると邪魔?」
「邪魔なんてことはないけど……」
見ているだけなので確かに邪魔ではないだが、じっと手元を見られていると思うと緊張してしまうのである。
「だったらここにいさせてよ。邪魔はしないからさ。ね、料理続けて」
「う、うん」
この後も、その言葉通り、ヒノエは笑顔を見せたまま望美を見ているだけだった。
ヒノエの視線に緊張しつつも、だいたいの料理が出来上がりつつあった。
「あとは、スープの味を確かめて……」
そう言って、作ったコンソメスープを小皿に取って一口飲んでみる。
その時。
「望美、ちょっと」
ヒノエは手招きして望美を呼ぶ。
「何?」
不思議そうに望美はヒノエの方へ見る。
カウンターの向こうのヒノエが身を乗り出したかと思うと、さりげなく唇が重ねられた。
「ヒ、ヒノエ君!」
「味見くらいしても良いだろう?」
「味見って!」
「美味しい」
スープを飲んだ訳でもないのだから、一体何の味を確かめたというのだろうか。
しかし、にっこりと笑顔を見せられては何も言えなくなる。
「もう。そんなことするならこれ持って行って」
望美は顔を赤く染めたまま、ミモザサラダの入ったガラスの器をヒノエに押し付けた。
「はいはい。姫君の仰せのままに」
ヒノエは口づけしたことに満足した様子で、サラダをテーブルの方へと持って行った。
次々にテーブルには料理が並べられる。
そして、テーブルの中央には、たっぷりの白い生クリームと真っ赤な苺が飾られたバースデーケーキ。これもまた、お菓子作りだけは好きだと言う望美のお手製である。
目の前にあるこの全てが、望美が、自分のためだけに用意してくれた品々である。
これを用意してくれたということだけでも、心にしあわせが満ちていく。
準備をしている時から、きっと望美は自分のことだけを考えてくれただろう。
それを考えるだけでも嬉しくなる。
望美の手料理を食べたかったのは事実だが、本当に欲しかったのは望美の時間。
自分だけのことを考えて何かをして、そして想ってくれるその時間。
望美には望美の時間があり、自分以外のことを考えている時もあるだろう。
それは生きている上では当たり前だけれど、本当はいつも自分のことだけを考えて、想っていて欲しい。
離れている時でさえも自分のことだけを考えて欲しいと思う。
もっともっと望美の時間を独り占めしたい。
望美の時間の全てを自分のものにしたい。
「おまたせ〜。これで全部できたよ」
望美がメインの料理を乗せた皿をテーブルに置く。
「お腹すいてたのに待たせちゃってごめんね」
「謝る必要はないさ。望美がオレのために作ってくれたんだから、とっても嬉しいよ」
「ヒノエ君の口に合うと良いんだけど。さ、食べよ」
「そうだね。どれも美味しそうだ」
二人はテーブルをはさんで向かい合うようにして座る。
「そうだ、ケーキのろうそくにも火つけなきゃね」
望美はヒノエの年齢分の小さくて細いろうそくをケーキに立て、そして火をつけた。
そのほのかな灯りは、ひとつひとつが宝石のようにきらきらと輝いているようだった。
「ヒノエ君、誕生日おめでとう」
「ありがとう、望美。愛しているよ」
終
<こぼれ話>
ヒノエ「どれも美味しかったよ。ありがとう」
望美「ホント?! 良かったぁ」
ヒ「でももうひとつ食べたいものあるんだ」
望「もうひとつ食べたいもの?」
ヒ「さっきの味見でとっても美味しかったもの」
望「味見って、まさか……(///)」
ヒ「誕生日が終わるその瞬間までたっぷり味わわせてもらおうかと思うんだ。良いだろ?」
ヒノエ君、何を食べる気ですか?!(笑)
ということで。
ヒノエ君のバースデー創作です。
プレゼント……ヒノエ君なら自分で欲しいものは何でも手に入れられるでしょうから、贈るとなると何にするか迷いますよねぇ。
望美ちゃんの手料理、そして時間は望美ちゃんだけしかあげる事のできないもの。
今はまだ離れている時間の方が多いですから、一緒にいられる時間が何よりも大切でしょう。
それにしても、ヒノエ君が買ったマンション、いくらするのかな〜。
では最後に。
ヒノエ君、Happy Birthday♪
|