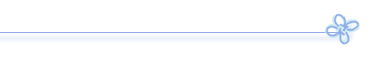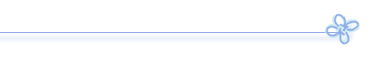|
2月14日は聖バレンタインデー。
本当はこの日を一緒に過ごしたかった。
時計はあと少しで0時を示すところまで進んでいた。
「はぁ……」
望美は力なくため息をつく。
視線の先にはきれいにラッピングされた15cm四方の箱。
中身は、予約しないと買えない有名洋菓子店のガトーショコラだった。
2月14日のこの日、ヒノエは熊野へ戻っていて逢う事ができないのは以前からわかっていた。
けれど、まわりの友達がチョコレートを買ったりカードを用意したりと騒いでいるのを見ているうちに、つい自分も買ってしまったのだった。
渡したいけれど渡す相手は遙かに遠い時空の向こう。
連絡も満足にできない場所では、宅急便で送ることさえできない。
それがわかってはいても、ヒノエを想う望美は買わずにはいられなかった。
けれど、渡せないままの箱を見ていると、気持ちは沈んでいくばかり。
2月14日もあと少しで終わってしまう。
「はぁ……」
箱を見つめてはため息しか出なかった。
「はぁ……」
何度目かの大きなため息をついたその時だった。望美の携帯電話から着信音が流れ出した。
この音楽は大事な人にだけ設定しているもの。
望美は急いで電話と取った。
「もしもし?! ヒノエ君?!」
『望美、まだ起きてた?』
「起きてたけど、どうしたの、こんな時間に! 今どこ?!」
『望美の家の前。出て来れる?』
それを聞いた望美は慌ててカーテンを開けて、外を見下ろした。
2階の窓から見えたのは、まさしくヒノエの姿だった。
右手には携帯電話を持ち、そして左手をひらひらと降って望美の部屋を見上げている。
望美は返事も忘れて外へ飛び出した。
「ヒノエ君?! ホントにヒノエ君?! きゃぁっ」
あまりに慌てすぎて、足がもつれてヒノエの腕の中に望美は倒れ込む。
優しく抱きとめたヒノエはゆっくりと微笑む。
「そんなに慌ててどうしたんだい? そこまで驚くほどでもないだろう?」
「だ、だって、今日来るなんて聞いてなかったし……」
「どうしてもさ、今日中に望美にあげたいものがあったんだ」
ヒノエは上着のポケットの中から手のひらに乗るくらいの大きさの箱を取り出した。
「望美へオレからの贈り物」
「ヒノエ君から私に? 開けても良い?」
「どうぞ」
望美はヒノエからその箱を受け取ると、箱に飾られていたリボンをほどいて中身を確かめた。
中には丸い形のトリュフが4つ入っていた。
「これ……、チョコレート?」
「そう。今日は好きな人にチョコレートを贈る日なんだろう?」
「確かにバレンタインデーだから、好きな人にチョコレートを贈る日だけど、それって女のコからあげるものだよ?」
「でも、外国では男からでも贈って良いって聞いたぜ?」
確かに諸外国では、男女に関係なくチョコレートを贈るものである。女性からしか贈らないのは日本のみらしい。
「毎日は一緒にいてやれないからさ、こういう時くらいはできることをしないとね」
そう言ったヒノエに、望美は思わず抱きついた。
「嬉しい……。ありがとう、ヒノエ君」
「喜んでもらえたならなによりだ」
ヒノエは優しく望美を抱きしめる。そして望美の耳元に顔を近づけた。
「望美、大好きだよ」
とろけるような甘いささやきに、心だけでなく体全体にしあわせが満たされていくようだった。
「私も、ヒノエ君が大好き」
望美は顔を上げて笑顔でヒノエに告げた。
「望美、それ食べてみて。チョコレートの味なんてわからないから、望美の口に合うものかどうかわからないけど」
ヒノエに言われて望美は箱の中のひとつを口に入れた。
「うん、甘くて美味しい。ヒノエ君も食べてみる?」
望美は箱をヒノエに差し出した。
「そうだね、いただこうかな」
しかし、ヒノエは箱の中のチョコレートには手をつけなかった。
その代わりに、望美の唇に自分の唇を重ねる。
望美の口の中に広がったチョコレートの甘さと同じように、いや、それ以上の極上の甘さがヒノエの口に広がるのだった。
終
<こぼれ話>
ヒノエ「ごちそうさま」
望美「ヒノエ君、食べるのはこっちのチョコレート……」
ヒ「この食べ方の方が何倍も美味しいんだって」
望「そ、そんなわけないでしょう?!」
ヒ「だったら望美も試してみる? そうしてくれるとオレも嬉しいけど?」
タイトルそのまま甘々(笑)
ヒノエ君はどんな顔でチョコレート買ったんでしょうね〜。
|