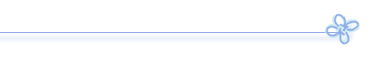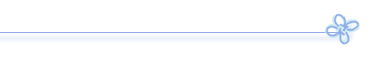|
少し陽射しの強い午後、望美はひとりで屋敷の敷地内にある井戸のところへ来ていた。
「こんなところにいたんだ、姫君」
ふいに声をかけられて望美は顔をあげると、木の影から笑顔のヒノエが現われた。
「ヒノエ君? ヒノエ君も井戸の水飲みに来たの?」
望美の手には今汲んだばかりの井戸水を満たした柄杓があった。
「いいや、姫君を探してたのさ」
「私を?」
望美は首をかしげる。
「二人っきりになれたのは好都合だな」
「えっ?」
「あぁ、こっちの話。ところで、ねぇ、姫君」
「その『姫君』って止めてって言ってるのに」
「姫君は姫君なんだからいいじゃないか。それより」
話を進めたがっていたヒノエだったが、そこでどこかもったいぶった間を置く。
「なあに? 私を探してたって事は何か私に聞きたい事でもあるの?」
何気なくそう聞き返し、望美は普通に柄杓を口に持っていき水を飲もうとした時だった。
「将臣と口づけしたことあるって本当?」
思いがけない一言に、望美は飲みかけていた水を吹き出した。
「な、何言い出すのよ?!」
「その慌て振りからすとやっぱり……」
「ど、どうしてそんなこと聞くのよ?!」
「昨日の夜、酒盛りの途中で将臣がちらっと漏らしたんだよなぁ。『望美とキスしたことある』って。『キス』って口づけのことなんだって?」
「『キス』は、た、確かに『口づけ』の意味だけど、だからって私と将臣が、そ、そういうことしたなんて……」
「だから教えてよ? 将臣と、した?」
「し、しらない!」
望美は顔を真っ赤にする。
「隠さなくてもいいさ。姫君はこんなに魅力的なんだから、今さら昔の男と何かあってもオレは気にしない」
「昔の男って……」
「『今の男』じゃないだろう?」
ヒノエは望美の髪を一房手に取って弄びながらにやりと笑う。まるで、『今の男』は『オレ』だろうと言わんばかりに。
「そ、そんなのわからないわよ? ヒノエ君が知らないだけかもしれないじゃない」
「ふぅん。だったら、将臣と口づけしたのはいつなんだい? オレに教えてよ」
「い、いつだって良いじゃない。そんなことわざわざ言う必要ないでしょう」
自分の長い髪を持っていたヒノエの手を、望美は軽く叩いて退ける。
「ホントは将臣だけじゃなく、誰ともしたことなんだろう? 『キス』」
「バ、バカにしないでよ。キスくらいあるんだから」
「だから誰といつ?」
答えにくい事を平然とヒノエは聞いてくる。
興味深げな視線が真直ぐに望美に注がれる。
これ以上ヒノエの問いをごまかすことができず、望美はしぶしぶ口を開いた。
「……幼稚園の時」
「ようちえん?」
「……えっと、5歳くらいの時」
「うん、5歳ね」
ヒノエの肩がわずかに揺れる。
「……将臣君と相撲してて倒れた拍子に……」
「プッ、ハハハハ!」
堪え切れなくなったヒノエはお腹をかかえて笑い出した。
「なによ、笑わなくたっていいじゃない! ちゃんと唇と唇が当たったんだから!」
ヒノエの笑いはまだ止まらない。
「ヒノエ君!」
「わ、悪い。笑うつもりはなかったんだけどさ。なるほど、相撲ね。じゃあ、望美は将臣に押し倒されたわけか」
「……押し倒して勝ったのは私の方……ってこんな話をしたいんじゃなくて!」
それを聞き、ますますヒノエの笑いは大きくなる。
「もぅ、将臣君が余計なこと言うから」
口をとがらせながら望美は拗ねる。
ヒノエの目にはそんな様子の望美も可愛く映る。
こんな姿を見ると、確かにどんな小さなことでも利用して望美を一人占めしたくなる。自分が一番望美に近い存在なのだと、他の男達に示しておきたくなる。
でも、将臣も意外と子供っぽいよな。そんな言葉で牽制したつもりなのか。
口には出さずにヒノエはそう思う。
しかしそう思いながらも望美にこうして確かめてしまったのだから、将臣の言葉に動揺したのは事実だろう。
望美に対しては余裕を持てないのは惚れた弱味というものなのだろうか。
とにかく、『今』の望美と将臣が口づけを交わしたのではなかったことにホッとしていた。
そうして笑い倒して気が済んだのか、やっとヒノエの笑いはおさまった。
「でもさ、安心したよ」
「安心?」
「そんな大昔で、ただぶつかっただけのものだったって言うから。そんなの口づけだなんて言わないだろ」
「キスはキスだもん!」
望美はまだムキになって反論する。
「そうかな? ぶつかっただけの口づけなんて楽しくないし、思い出にもならないじゃないか」
「わ、私は覚えているもん。それが初めてだったんだし……」
その言葉にヒノエの眉が少しぴくりと動く。
子供の頃の、偶然で、しかも想いを交わしあってのものではないとわかっていても、その事を望美が大事に心に思っているのは面白くない。
望美の心に自分以外の男がいるのは許せない。
「ねぇ、望美。オレと口づけしないかい?」
「えっ?」
「ぶつかっただけの口づけなんて忘れなよ」
その言葉に望美が答えるよりも早く、ヒノエは望美の顎に手をかけるとくいっと上を向かせて唇を重ねた。
あまりの行動の早さに望美は驚いて目を何度も瞬く。
唇に自分ではないぬくもりを感じる。
自分が本当にヒノエとキスしているのだと望美はすぐには理解できなかった。
やがてヒノエの腕は望美の背中に回る。腰に手を置かれ、望美の身体はヒノエの方へと引き寄せられて互いの身体が密着する。
唇から全身に熱が広がっていくかのように、望美は自分の身体が熱くなっていくのを感じていた。
瞳を閉じ、手をヒノエの背に回してしがみつく。
自分でも気づかないまま、望美はいつの間にかヒノエの口づけに夢中になっていた。
息をするのを忘れるくらいに。
少し強引に、それでいてやわらかく包まれるかのように少しずつ角度が変えられる。
その瞬間、ほんの少し吐息がもれる。
「……ぁ……ん」
何も考えられなくなり、そして何もかも忘れてただヒノエの唇を欲しがっていた。
不思議と身体に感じる浮遊感。
それは酒に酔った時のことを思わせるような感覚だった。
望美はヒノエの唇に酔っていた。
やがて長いようで短い、短いようで長かった抱擁が解かれる。
唇が離れ、ヒノエの抱擁の力が緩まると、望美はくたっと身体の力が抜け、顔をヒノエの肩に埋めて身体を預けた。
「どう? オレとの口づけは」
『良かった』とは、『もう一度して』とは、望美の口からはとても言えない。
忘れられないほどに衝撃的な甘い口づけだった。
今だ身体の感覚が戻ってこないように感じている望美は声を出せず、ただ、軽くヒノエの上着を一度引っ張った。
それが今の望美の精一杯の返事なのだと、ヒノエは承諾した。
「この口づけ程度で、まだ満足して欲しくないんだけど」
ヒノエは軽く望美の髪を撫でる。
「だってそうだろう? もっと深い口づけだってあるんだし、その先だってね」
甘くささやかれる言葉。
ヒノエの言葉にさらに望美の心は酔わされていく。
「続きはまた今度な」
終
<こぼれ話>
将臣「ヒノエ、望美がどこにいるか知らないか?」
ヒノエ「いや、知らないね。そうだ、将臣、『さんきゅー』な」
将「サンキューって何がだ?」
ヒ「良い情報もらったおかげで良い思いしたからな。こういう時はそう言うんだろ?」
望美ちゃんとヒノエ君のキスシーンです。
なんとなく望美ちゃんのファーストキスの相手は将臣君じゃないかなぁとふと思ったのがこの話を書こうと思ったきっかけ。
当初中学生くらいにしようかと思ったのですが、書き始めたら5歳までさかのぼってしまいました(笑)
ヒノエ君の酔わせるキス、普通のキスでさえこうですから、それ以上になったら……(///)
望美「ヒノエ君とキスしちゃった……。そっかぁ、これが私のファーストキスかぁ……」
記憶塗り替えられてます(笑)
|