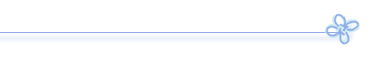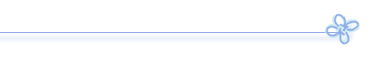|
諸国との取り引きのために1週間ほど留守にしていたヒノエは、屋敷に帰り着くなり望美の部屋へと真直ぐに向かった。
「ただいま、姫君!」
ヒノエは部屋へ入るなり、望美の後ろ姿を見つけて抱き締める。そして1週間ぶりに逢った愛しの妻に口づけしようとした時だった。
ぺちん。
「?!」
柔らかな望美の唇が迎え入れてくれてくれるところが、何故か鼻の頭に小さな衝撃を受ける。
よく見れば、目の前にあるのは小さな手。そして、くりくりっとした大きな瞳だった。
「ヒ、ヒノエ君、大丈夫?!」
慌てた望美の声の聴こえる。
状況を把握できないでいるヒノエは、鼻の頭を押えながら望美を、そして望美の腕の中にいるモノを見た。
黒目がちの大きな瞳、りんごのように真っ赤なぷっくりとした頬、肩のあたりで切りそろえられた望美に似た色の髪、紅葉のような小さな手がヒラヒラと振られている。
ソレは間違いなく人間の子供だった。赤い着物を着たその女童とそのコを抱く望美の顔とを見比べてみると、どことなく望美に似ている気がした。
「ダメじゃない、顔を叩くなんて。メッ」
望美は女童に言い聞かす。しかしその女童は何も理解していないようで、楽しげに笑っていた。
「望美……、お前……」
「ヒノエ君、お帰りなさい! 待ってたんだ。あのね、実はこのコ……」
「お前、いつ……子供産んだんだ?」
「はぁ?」
よほど驚いていたのか、あり得ないヒノエの言葉に望美は一瞬固まった。そしてすぐに吹き出した。
「やだ、ヒノエ君ったら。いくら驚いたからって、それはないでしょう? 1週間で子供が産めるわけないじゃない」
「そ、そうだよな。うん」
あまり見ない、というか初めて見るヒノエのうろたえぶりに、望美は何故か勝利した気持ちになる。
「ヒノエ君、顔が赤いわよ?」
望美はひとりクスクスと楽しそうに笑う。
「ほぉら、パパ……じゃない父上ですよぉ」
「お、おい!」
望美は腕の中の女童をヒノエの方に手渡そうとした。女童もまた物珍しそうな顔をしながらヒノエに手を伸ばす。
嫌がるヒノエだったが女童にしっかりとしがみついてこられ、離せなくなってしまった。
「の、望美、コレどうにかしろ!」
「いいじゃない、そのコもヒノエ君が気に入ったみたいよ。私、さっきからずっと抱いていたからちょっと疲れちゃったの。だからだっこしてあげて」
小さな手がギュッとヒノエの上着を掴んで離さない。
「……」
ヒノエは観念せざるを得なかった。
「仕方ないな。このままでいいからコレがどういうことか説明てくれ」
女童を抱いたまま、ヒノエはその場に座る。それにならって、望美もその隣に腰を下ろした。
「あのね、落ちてたの」
「望美、落ちてたって……」
「本宮のそばの森を散歩してたら泣き声が聞こえて、そっちの方へ行ってみたら、神木のそばにこのコがいたの」
「捨て子か。まぁ、珍しくはないな」
戦がなくなったことで捨て子や孤児の数が減ったとはいえ、まだまだ貧しさのせいで子供を養えなずに手放す場合があるのが現実である。
熊野に住まう者については熊野が責任を持つとして、熊野別当であるヒノエは、そういう子供達のため施設を用意していた。
「捨て子なら『館』に連れてくしかないな」
やっかい事は早めに処理するのが一番である。
ヒノエはさっさと判断すると立ち上がった。
「ま、待ってよ。そんなに急がないで。捨て子って決まったわけじゃないでしょう? もしかしたら忘れ物かもしれないじゃない?」
「忘れ物って、お前、普通子供をどこかに忘れるか?」
「……忘れないと思う。でも! もしかしたら何かの事情があって、置いて行ったのかもしれないわ! そうよ、きっとそうだわ。こんな可愛いコ、捨てる親なんていないわよ!」
「子供を捨てる親がいるのは現実だ。まぁ、百歩譲って何かの事情があって神木の側に置いておいたとしよう。それをお前が持ち帰って来てしまったということは、今頃こいつの親は必死になって探しているかもな」
ヒノエの言葉に望美はハッとする。
「そうだわ。私ったら、そのコが可愛くてつい連れて来ちゃったけど、今頃お父さんとお母さんが探しているかも! 私、森まで行って見てくるわ」
「お、おい、望美」
そんなつもりで口にしたわけではなかったのだが、望美はヒノエの言葉を真面目に受け取り、自分で探しに行こうとしたのだった。
「私があなたの両親を見つけて来るからね。それまでここで待っててね。じゃ、ヒノエ君、このコの事、頼んだわね!」
「望美!」
言いたい事だけ言うと望美はヒノエが止めるのも聞かずに走り出した。
「お前が行く事ないのに、まったく。望美らしいというか、思ったことは自分で動かないと気が済まないのはいつまで経っても変わってないな」
もうすぐ日暮れである。
たとえ望美でも日が落ちる前には戻ってくるはずである。
ヒノエは望美の後は追いはしなかった。
その代わり、小さく口笛を吹く。
姿は見えないものの、一瞬現れた気配を察するとヒノエはつぶやく。
「頼む」
「御意」
本当に小さな返事がひとつ聞こえた後、、気配は音もなく消えた。
◇ ◇ ◇
「こら、ちび姫、何でも口に入れるな」
名前がないのが不便だと思ったヒノエはとりあえず女童のことを『ちび姫』と呼ぶことにした。
そのちび姫は、どこから持って来たのか、小筆を口に入れようとしていたので、ヒノエは慌てて取り上げた。
好奇心旺盛なのか、それとも子供というもの自体がそうなのか、ちょっと目を離すと動き回って何でも口に入れようとする。何をしでかすかわからない小さな子供は、少しの間も目を離せなかった。
ちび姫はキョロキョロと辺りを見渡したかと思うと、今度はヒノエの膝の上に登り始めた。
「望美も小さい頃はこんなだったのかな?」
気のせいだろうが、どことなく望美と面ざしが重なるちび姫。
やわらかい頬をつんっとつっ突けば、ちび姫はにぃと笑顔を見せる。
子供の相手など面倒だと思っていたヒノエだったが、少なからずおもしろがっていた。
「あいつが望むんだったら、このまま……」
『館』に入れないでここで育てても良いかも。
そんな気持ちになり始めた時だった。
バタバタと廊下を走る音が聞こえて来た。
「ヒノエ君! ヒノエ君!」
息を切らせながら走って来たのは望美だった。
「見つかったの! ヒノエ君の言う通りだったわ! 神木のそばでお母さんが探してたわ!」
「……嘘だろ」
捨てた事を後悔し、その場所に戻ってくる親もいないわけではない。そういう例はあっても、こんな短時間で親が見つかる例はまれだ。
しかし、嬉しそうに瞳を輝かせる望美を見るとそれは事実なのだろう。
望美の話を聞くと、両親と女童の3人で参拝に行く途中、父親が急病になり、母親が薬師のところまで父親を抱えて連れて行かなくてはならなくなった。その際、父親と子供の両方を抱えることは無理だったために、やむを得ず子供を置いておいたのだと言う。幸い本宮の者が手を助けてくれたので母親はすぐに戻ってくる事が出来たのだが、その短い間に望美が子供を見つけて連れて来てしまったのだった。
望美はヒノエから女童を受け取ると母親に渡した。
母親は何度も頭を下げて礼をしつつ、女童を大事に抱きながら去って行った。
「行っちゃったね」
母親に抱かれて遠ざかる女童を、見えなくなるまで望美は見送る。
「ちょっとの間でも母親気分になったせいで淋しくなったかい?」
「そうね。あんなぷくぷくしてて、やわらかくて、小さな手で私の指をキュッと握ったりして。こんなに小さいんだから私が守ってあげなきゃ、って思ったりしたわ」
「望美に守られたら何も心配ないだろうけれど、無事に親元に帰ったんだ、それが一番のちび姫のしあわせだろう」
「うん、そうだよね。でも私が余計な事をしなければ、大ごとにはならなかったとは思うとちょっとね」
「放って置けない性分は望美の優しさだろう? 俺はそんな望美が好きだよ」
少し気落ちしている望美の肩をヒノエは抱き、額に口づけを落とす。
「見つけたのが望美で良かったんだよ。もし望美よりも先に誰かが見つけてそれが人買いだったら、それこそ大ごとになるところだったんだから」
「うん、そうよね。これで良かったんだよね」
「そうさ、良かったんだ」
望美はヒノエの言葉にホッとした様子を見せた。
「それにしても、ちびちゃん、やっぱり可愛かったなぁ」
「そんなにちび姫が気に入っていたのかい? でもあのちび姫より、俺と望美の子供の方が可愛いと思うけど?」
「ヒノエ君と私の子?」
「そう。いつでも俺は協力するよ? なんなら今からでも……」
ヒノエはそっと望美の耳もとでささやく。
「や、やっぱりまだ子供はいらないかなぁ。私がお母さんなんて出来そうにないしっ」
なんとなく身の危険を感じた望美はヒノエから離れようとする。しかし肩に置かれた手がそれを許さない。
「大丈夫だって。望美は良い母親になるって。俺も良い父親になれる自信がある」
ヒノエはそう言いながら望美の手を取ると、その手の甲に口づける。
「ホントは俺がちび姫みたいなコが欲しくなったのさ。ね、望美、いいだろう?」
上目遣いに覗き込むように見つめられてされる『お願い』に、望美は弱い。こうされると反論はできなくなる。
頬を赤く染めてうつむく望美の様子を『承諾』と受け取ったヒノエは、軽々と望美を抱き上げる。
「えっ?! ヒ、ヒノエ君、ちょっと、待って。まさか『今から』……」
「そう、『今から』」
「『今から』はちょっと! ほ、ほら、私まだ心の準備できてないし……」
「俺達の間に心の準備なんて必要ないだろう?」
ヒノエは望美の抗議をものともせず、そのまま奥の間へと向かうのだった。
終
<こぼれ話>
私が書くED後創作のラストはあだるてぃな展開に行きがちです(^^;)
祝言前はKissひとつするのにも苦労しただろうから、その反動かも……。
望美「ヒノエ君ったら、本当に強引なんだから」
ヒノエ「そいうところ、嫌いじゃないだろう?」
望「嫌いだもん」
ヒ「本当に? 望美が嘘つく時は眉間にしわが寄るって知ってたかい?」
望「えっ、嘘」
ヒ「嘘だよ。姫君は本当に可愛いね」
望「……だから、そういうヒノエ君って嫌い」
|