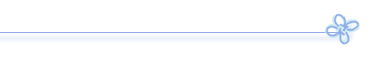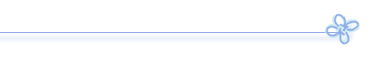|
「オレの女になる気になった?」
二人っきりになったのを見計らって、ヒノエは望美に言った。
「ヒノエ君ったらまたそんな事言う。そういう言葉を言うのは私で何人目?」
「手厳しい事言うね。まだ信じられない? こんなこと言うのは姫君にだけだよ」
「本当かしら?」
望美は少し歩いて移動すると、太い木の幹に背を預けながら返した。
「もちろん本当さ」
ヒノエは望美のやや斜め前方に立つと右手を木の幹に付けた。
「そして本気。この腕の中に抱きしめて、もう離したくないくらいに。誰の目にも触れない場所にとじ込めておきたいほどに、お前に恋焦がれているよ」
そう言いながら望美を見つめ、そして望美を両手ではさむように左手も木の幹に付けようとした時だった。
「ヒノエ!」
突然聴き慣れた声が二人の耳に飛び込んで来た。
「ここにいたのか。すまないが、ちょっと来てくれるか?」
ヒノエを呼びに来たのは九郎だった。
これからもっと良い雰囲気になりそうだったところを邪魔され、ヒノエは不機嫌そうに顔をしかめた。
「せっかくの姫君との逢瀬に割り入るなんて、源氏の総大将も不粋なことをするね」
「あ、いや、すまない」
状況をわかっているのかいないのか、九郎は素直に謝罪した。
「素直に謝るなよ。わかった、行ってやるよ」
前髪をかき揚げながらヒノエはしぶしぶ承知する。
「じゃ、姫君」
ヒノエはすっと望美の髪に触れ、そして現れた耳もとでそっとささやいた。
「この続きはまたあとで」
「お勤め御苦労様。いってらっしゃい」
望美はにっこりとした笑顔でヒノエを見送った。時々振り返るヒノエに手を振る。
ヒノエが通りの角を曲がり、建物の影でその姿が見えなくなった途端、望美はヒノエ達とは反対方向へといきなり走り出した。
望美は割り当てられた部屋に戻ると思いっきりふすまを閉める。
部屋の中にいた朔は、肩で息をしながら慌てる望美の様子を見て驚いた。
「望美?! そんなに息を切らせてどうしたの?! 何かあったの?!」
朔は心配しながら望美に近寄る。
「さ、朔、どうしよう〜」
普段聞く事のない望美の情けない声に、朔は顔を強ばらせる。
「望美、何があったの?!」
「朔、私もうダメ!」
「だから、何があったの?!」
「私もう耐えられない!」
「望美?!」
「これ以上はもう無理!」
「望美!」
取り乱した様子の望美に、朔は強い口調で名前を呼んだ。それに望美はハッとする。
「何があったの?」
望美の両肩に手を置き、顔を覗き込むようにしながら朔は訊ねた。
一瞬望美はためらったが、ぽつりと言った。
「……エ君が……」
「えっ?」
「ヒノエ君が……」
「ヒノエ殿が何? まさか何かされたの?!」
朔のその言葉に望美の顔にパァッと朱が走る。そしてそのまま朔から視線をそらしてうつむいた。
「まさか、ヒノエ殿が望美に無体な事を強いたの?! それに望美は耐えられずに……。ヒノエ殿ともあろう方が、私の大事な望美になんて事を! わかったわ、もう心配しないで。私がヒノエ殿に言って来てあげるから。望美はここで待っていて」
「さ、朔? ちょ、ちょっと待って!」
ひとり意気込む朔に今度は望美が慌てる。
部屋を飛び出しそうな勢いの朔を望美が引き止める。
「離しなさい、望美! あなたは何も心配しなくても良いから!」
「朔、何か勘違いしてない?! ヒノエ君は私に無体なことなんて何も……」
そう言いながら望美の頬がさらにぽっと赤くなる。
「それが何もないっていう顔? 理由を言いたくないのなら言わなくてもいいわ。問題は『理由』ではなくて、あなたが傷ついたという『事実』なのだから。この先は私にまかせておいて。事と次第によっては八葉の任を降りてもらう事になるかもしれないけれど、あなたは何も心配しなくても良いから」
「八葉の任を降りてって……」
「神子を守るのが八葉の役目。それなのに逆に神子を傷つけるようなことをするようじゃ、八葉として認められないわ。ヒノエ殿の力を得られなくなるのは困るけれど、望美、あなたの身が一番大事なの。ヒノエ殿にはあなたから離れてもらうわ」
「そんなの困るわ!」
「そう、困る……って、望美?」
「ヒノエ君と引き離されるなんて困る!」
「どういうこと? だってあなたヒノエ殿と一緒にいるのが耐えられないんじゃ……」
「違うわ! あ、違わない、かもしれないけど、そんなんじゃないってば!」
「じゃぁ、何があったの?」
「えっ……、あの……その……」
改めて朔から訊ねられても、望美は口ごもる。しかし、このまま何も言わずに済む問題ではない。そして朔をこれ以上心配させてはいけない思った望美は、ぽつりぽつりと話だした。
「あの、だから、その……。ヒノエ君が『オレの女になれ』って……」
「昨日もそんなこと言っていたわね。その前の日も。ヒノエ殿って最近毎日同じ事言ってない?」
「うん、毎日言ってる」
最近のヒノエは望美の顔を見るたびに同じ言葉をささやいていた。
「それで?」
「それでって、毎日言うのよ?! 一度見つめあったらもう視線をそらせないくらいに真直ぐな瞳で見つめられて、優しく髪に触れながら。それにわざと耳もとに近づいて低い声でささやいたりもするのよ! これに耐えろなんて無理だと思わない?! 朔はこんなこと言われて平気でいられる?!」
「私、言われた事ないから」
朔はあっさりと返す。
「じゃ、じゃあ、これは? 『姫君の微笑みはこの紅葉よりも艶やかで美しいよ。その微笑みはオレだけに見せて欲しいね』はどう?!」
「聞いた事もないわ」
「えっ、それならこれは?! 『疲れたならオレの腕の中で休みなよ、さぁ、おいで』」
朔は無言で首を横に振る。
「だったら……」
「望美、もういいわ。あなたがヒノエ殿にいろいろとささやかれているのはわかったわ。でも、そんなふうに言われても、あなた軽く交わしてたじゃない? 『もうやぁね〜、ヒノエ君ったら』なんて笑いながら」
「軽く交わしてたんじゃなくて、そう見えるようにフリをしてたんだってば」
「フリ?」
「前にね、弁慶さんがヒノエ君は『余裕のある女性が好みで、交わす言葉のやりとりを楽しむのが好きだ』って言ってたの。だからヒノエ君が私を誘うような事を言ったら、なるべくうまく交わせるように頑張ってたのよ!」
「……」
「それに、そんな簡単にヒノエ君の誘いに乗ったら、軽い女だって思わない? 誰にでも簡単についていくような女だって思うかもしれないでしょう?」
「……」
訳のわからなかった朔も、望美の言葉からようやく事態を飲み込み始めた。
「望美、たぶん聞かなくても答えはわかると思うけど、一応聞くわね? あなた、本当はヒノエ殿に口説かれて嬉しいのね?」
「嬉しいなんて、そんなぁ♪」
望美は頬を染めながら、朔の背中を叩いた。
あまりに強く叩かれて、朔は咳き込んだ。
「ご、ごめんなさい、朔、大丈夫?」
「……けほ。だ、大丈夫よ。それより望美」
朔は望美の両肩に手を置いた。
「あなたが何に耐えられないと言ったのか、よぉ〜くわかったわ。望美、ヒノエ殿が好きなら好きと伝えなさい」
「えっ、そ、そんな、ヒノエ君を好きだなんて……」
「いい? 気持ちをごまかしてはダメよ。今はいつ何が起こるかわからないわ。いつ離ればなれになるかもわからない。手後れになる前に告白なさい」
「でも、ほ、ほら、ヒノエ君本気じゃないわよ。私なんて何の力もないし、料理も洗濯も下手で女らしいことできないし、ヒノエ君の理想には程遠いし……」
「何言っているの! 望美は同性の私から見ても素敵な女性よ。もちろん神子としてのあなたも私よりも十分勝っているわ」
「そんな事ないわ、私は……」
「自信を持って、望美。今のあなたが素敵だから、だからヒノエ殿もあなたにそういう言葉をかけるのだわ。あなたは自信を持ってそれに応えればいいのよ」
『自信を持って』
そう言った朔の言葉を望美は考える。
甘くささやくあの言葉は、本気の言葉なのだと信じる気持ちが高くなる。
しかし。
「やっぱりダメ!」
「望美!」
「ヒノエ君が声をかけてくれるのって、『白龍の神子』というちょっと珍しい存在だからよ。だから今のままの私だったらきっとすぐにヒノエ君に飽きられてしまうわ。そしてヒノエ君は別の女のコに夢中になるの。そんなのわかり切ってることだわ」
「望美、それは……」
朔は、それは考え過ぎだと言おうとしたが、言ったところで今の望美は受け入れないと思い、それ以上口にはしなかった。
「朔、ヒノエ君を好きだということ、私認める。でもまだ今の私じゃ自信を持って『私を好きになって』なんて言えない。もっとちゃんと女性としても、神子としても成長してから告白したいの」
「望美……」
「それに、ちゃんと自分を成長させて、ヒノエ君に本気を言わせてみせるわ」
ひとつの決意が望美の瞳を輝かせる。
「だから、その日が来るまで私はヒノエ君のささやきに耐えてみせる。朔も応援してくれる?」
「もちろんよ。望美とヒノエ殿が早く結ばれるように応援するわ!」
「ありがとう、朔!」
二人は友情を確かめ合い、ひしっと抱き合った。
その時、ふいにふすまの向こうに人陰が映った。
「オレの神子姫様、いる?」
ふすまを開けずに声をかけたのは、今話題に上がっていた人物だった。
望美は一瞬朔の顔を見る。望美と目を合わせた朔は微笑みながら、頷くのだった。
「さ、いってらっしゃい」
小声で朔は望美を促した。
望美はほんの少しだけ唇をキュッと噛み決意を固めると立ち上がった。
「ヒノエ君? 九郎さんの用事はもう終わったの?」
望美が開いたふすまのすぐそばに、ヒノエが立っていた。
「姫君とさっきの続きをしたかったからね。さっさと終わらせて来た」
「あら、さっきの続きって何だったかしら?」
「おやおや、オレの姫君はずいぶんと忘れっぽいらしい。それとも二人っきりにならないと思い出してくれないのかな?」
「ふふ、どうかしら?」
「本当にこの姫君は手強いな。それなら思い出してもらえるような場所へでも早速連れ去ろうかな。朔殿、悪いが姫君はもらっていくよ」
「ええ、望美が行きたいのなら私は構わないわ」
「ということで、姫君、お前にだけ見せたい景色があるんだけど、一緒に行ってくれるかな?」
「そうね、せっかくだから行っても良いわよ。じゃ、朔、ちょっと行ってくるわね」
「ええ、いってらっしゃい。でもそろそろ陽が落ちるころだから早く戻って来た方が良いかもね」
その言葉に、望美の肩を抱いたヒノエが肩ごしに振り返る。
「朔殿、わかってないね。陽が落ちてからが二人っきりの甘い時間の始まりなのさ」
ヒノエは一言そう言い残すと、さっさと望美を連れて行った。
「あら、まぁ……」
ひとり残された朔は感心したようにつぶやく。
「ホントにヒノエ殿の言葉には驚かされるわね。それにしても望美ったら、あれでどうしてわからないのかしら? ヒノエ殿の望美を見つめる瞳を見てたら、本気しかないってわかりそうなものなのに」
恋愛というものは当事者は気づかずに、まわりの目の方がよく気づくことが多々ある。
朔の感じる限り、望美とヒノエの間には互いへの想う気持ちがあふれ、何も問題はないように見える。
「どちらにしろ、望美が先に折れそうね」
ヒノエが『甘い時間の始まり』と口にしたその時、望美の頬がのほんのりと赤く染まったのを朔は見逃さなかった。
朔は誰に聞かせるともなくつぶやきながら、口元に小さく笑みを浮かべた。
終
<こぼれ話>
当初の予定よりもちょっと狂ったような?(^^;)
ヒノエ君との恋愛イベントの選択肢に『余裕の女』を見せるような選択肢があるじゃないですか。
ヒノエ君の台詞に真っ赤になって翻弄される望美も好きですが、ちょっと余裕を見せたくてそれを選んでしまうことがあります。
でも、ヒノエ君に甘い台詞をささやかれて平気でいられます?
私はいられません(笑)
なので、ヒノエ君の前では平気でいても、実は相当効いているだろうとと思っていたら、このネタが浮かんできました。
朔ちゃんのイメージがちょっとずれたかも……。
ヒノエ「ここの景色は今の時間が一番綺麗なんだ」
望美「うん、とっても綺麗」
ヒ「……綺麗だな」
望「ホントに綺麗な景色」
ヒ「違うよ。景色は確かに綺麗だけど、姫君の横顔の方がもっと綺麗だ」
望「あら、綺麗なのは横顔だけ?」
ヒ「まさか。姫君の全部が綺麗さ」
望「それが本当だったらとっても嬉しいわ」
ヒ「オレの言う事を信じられない? この姫君はどうしたら口説けるのかな」
望「それは、ヒノエ君が次第でしょう? 楽しみにしているわ
(う、うまく交わせたかしら?)」
|