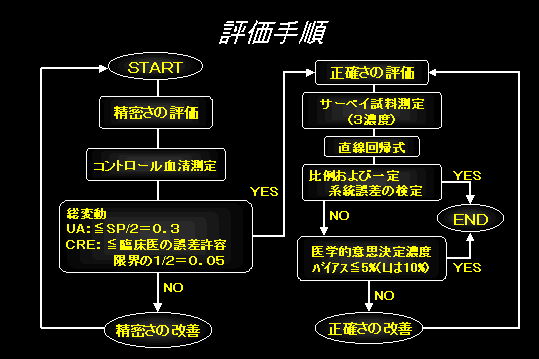
評価手順 H12.1.30UP
下の図は、臨床化学サークルで採用している評価方法の流れを示したものです。
この図は、(社)日本臨床衛生検査技師会の定量検査の精密さ・正確さ評価法標準化ワーキンググループによる定量検査の精密さ・正確さ評価法指針(JAMT-1-97)を基にしています。詳しくは、医学検査46:1130-1142、1997をご覧下さい。
各施設ごと、以下の手順を踏んで評価し、最終的には全体の集計結果および施設ごとの報告書を作成しています。それでは、順を追って解説していきます。
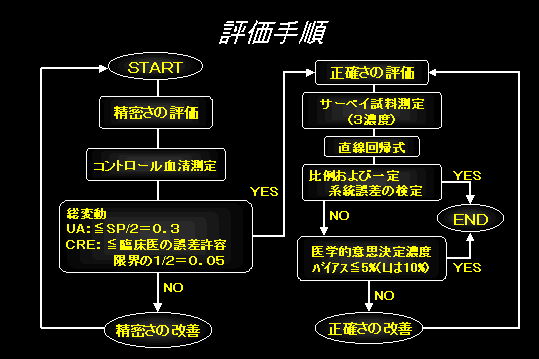
図作成:北里大学病院 藤村 善行
精密さの評価 H12.1.31UP
まずは、精密さの評価からSTARTします。精密さ(precision)とは、ばらつきの小さい程度(日本臨床化学会JSCC標準品専門委員会による)と定義されています。
このことから考えると、精密さの評価とは、ばらつきの程度が大きいのか小さいのかを評価すること、といって良いでしょう。
では、ばらつきとはどういったものなのでしょうか。よく統計の本などで、例として用いられるものとして、射撃の的(弓道の的でも構いませんが)があります。腕のいい人だと、真ん中に銃弾の跡が集まります。逆に腕のよくない人だと、的全体に銃弾の跡が残ります。このことから、腕のいい人のほうが、精密であると言えます。
では、このばらつきの程度を数字で表せないか。と考えたとき、思い当たるものに標準偏差(SD)があります。この標準偏差を算出する式には、n-1とか√があったりと、ぱっと見、難しい印象を与えるのに充分な姿をしています。しかし、この式、嫌がらずによくみると、簡単?な構造をしています。この式を言葉で表すとしたら、平均値から各値がどれくらい離れているか、の平均値、と言えるでしょう。
ここでは、式の解説は省略しますが、この式をぜひ眺めてみて下さい。きっとイメージが湧いてくると思います。
さて、この標準偏差と言うやつ。実は臨床検査で用いられている精密さの評価はほとんど標準偏差を用いて評価していると言って良いでしょう。必ずと言って良いほど、精密さの評価手法に出てくる不可解な式。そして算出される値。
実はこの値は標準偏差なのです。姿、形は違えども元を正せば同じやつなのです。ここでも式を一つ一つ解体していくと、標準偏差を表していることが分かると思います(あまりこういった作業はしたくないのですが・・・)。
つまり、精密さの評価とは、方法は違っても最終的には標準偏差を算出して、その値が大きいのか、小さいのかを判断すること、と言えます。
精密さの評価で用いる式を完璧に理解することは、かなり骨の折れることかもしれませんが、この式を見て、標準偏差を算出してるんだなと思うだけで、かなり気持ちが楽になるのではないかと思います。いかがでしょうか?