後冷泉院・天喜二年四[五]月中旬(1054年5月20日〜29日[6月19日〜28日])以後の丑の時、 客星觜・参の度に出づ。東方に見(あら)わる。天関星に孛(はい)す。大きさ歳星の如し。 (注1)10円玉に刻まれている平等院鳳凰堂が建てられた前の年・平安時代末期の「天喜二年(1054)」 の当時の歴で5月11日から20日の間の夜中に、 超新星又は彗星(客星)が、オリオン座(觜・参)の東に見えた。 おうし座ζ星(天関星)付近で、大きさは木星(歳星)ほどだった。
〜と言うような現代語訳になるでしょうか〜
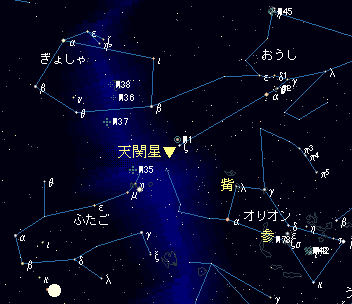
客星と言いますのは通常でない一時的な天文現象で、 今日言うところの超新星又は彗星その他発光を伴う気象現象なども一部含まれる 幅の広い意味に使われておりました。
「参」はオリオン座の三星を中心とした四角の部分を指す「当時の星座名」で、 「觜」はオリオンの頭の付近にある3つの星を言います。これも「当時の星座名」でした。この「明月記」の記述が裏付けできるように、世界中の書物が研究され中国の宋書天文史・客星の 項目にも同じような記述があることがわかりました。その記述を総合しますと、 客星は23日間昼間でも見え、22ヶ月後見えなくなったと言う事です。
この中国記録から「明月記」の四月という記述が五月という誤りであったと 解釈するのが、現在では一般に認められているようです。
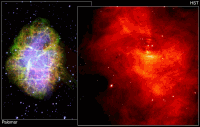 18世紀末に「かに星雲」は見つけられました。かの爆発の残骸で、その中心には中性子星が
あり残骸である星雲にエネルギーを供給し現在でも光りつづけています。
18世紀末に「かに星雲」は見つけられました。かの爆発の残骸で、その中心には中性子星が
あり残骸である星雲にエネルギーを供給し現在でも光りつづけています。