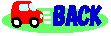塩本地区には古くから「三社稲荷」と呼ばれるお稲荷様がまつられています。毎年初午の日に行われる縁日には,集落以外からも結城や三和から大勢の参拝者でにぎわいます。このお稲荷様が「三社稲荷」と呼ばれるようになったのは,京都の伏見稲荷,愛知の豊川稲荷,そして笠間稲荷のみっつのお稲荷様をお迎えしてたてまつったことに由来しています。
さて,この三社稲荷には「狐の嫁入り」という不思議な言い伝えが残されています。
八十八夜も近づく,ある夕暮れのことでした。その日は夕方から小雨のそぼふるあいにくの陽気でした。畑仕事を終えた村人がそれぞれの家路をたどり,暗闇の中にひとつ,またひとつとともり始めます。やがて家々からはゆうげの煙が上がり始め,静かな夕べのひととぎが訪れました。
この村に嫁いで,早40年が過ぎようとするおきく婆さんは,その日も畑に出ていました。働き者のおきく婆さんのこと,畑仕事を終え,家路につこうとする頃には,もう陽もとっぷりと暮れておりました。慌てて籠を背負い,急ぎ帰り支度を終えたおきく婆さんは,いつも通り細いあぜみちを足早に歩き始めました。西の彼方,時雨空には三社稲荷の黒い森影がぼんやり浮かんでいます。
するとその時です。稲荷神社の森の方角が一瞬,パアーッと明るく輝いたかと思うと,まばゆい白無垢の花嫁衣装を身に付けた若い娘の姿が浮かび上がってきました。そして花嫁の前後には,いくつも提灯をぶら下げた紋付き袴の出で立ちの者たちが付き従って行くではありませんか。
「こんな時間に祝言とは,こりゃあなんぎなことじゃのー。」
「それに,一体こんな天気の中,どこぞの家に嫁いでいくのだろう。」ぶつぶつと独り言をもらしながらもおきく婆さんは,そのきらびやかな行列に目を細めながら,ぬかるみ始めたあぜ道にただずみました。ところが遠くで揺らいでいた花嫁たちの灯りは,不思議なことにおきく婆さんの立ち止まる方角に向けて進んでくるではありませんか。
「あっ,こりゃ困ったのー。こんな細い道をあんな立派な行列で。」
お婆さんが思ったとおり,先頭の灯りは静かに,そしてゆうらりゆうらりこっちにめがけて進んできます。しかし,その時になって初めてお婆さんは気がつきました。
「ひゃー,狐の嫁入りじゃー。」
小さい時分,今はとうの昔に死んでしまったじっさまやばっさまが,寝物語に語って聞かせてくれた「狐の嫁入り」とはこれのことだったのです。おきく婆さんはそう気づきながらも,突然目の前にくりひろげられた出来事に,あわあわと腰が抜けて立ち上がることができません。やがて目の玉をまん丸と広げ,あんぐり口を開けたまま地べたに腰をおろした婆さんの目の前を,その行列はゆっくり通り過ぎようとしました。まばゆくように光り輝くかに見えた行列は,間近にせまってもどこかぼんやりしており,伴の者も花嫁の姿さえふりそぼる雨に霞んで見えました。
「うわー,神様,大黒様,そして八幡大明神様,おらをお助け下さい。なんまんだぶ,なんまんだぶ」
ぶるぶる震えながら両手を合わせた次の瞬間,嫁入りの行列の灯りは凄まじい速さでお稲荷さんのある沼の方角に,ふっつりと消えていきました。そしてあたりにはもとの暗闇だけが残るばかりでした。
「ぎゃー」,そう叫び声をあげるやいなや,おきく婆さんは背負っていた籠を放り出し,一目散に逃げ帰りました。
こうしておきく婆さんが見かけた「狐の嫁入り」の出来事は,またたく間に村中に広まりました。人々は「ありゃあ,たぶん三社稲荷の狐の嫁入りに違いなかろ。」そう口々に噂しあいました。その後村人はこの事件を長く記憶に止めようと,おきく婆さんが見かけた狐の嫁入りの行列を絵馬に描き,三社稲荷に奉納しました。そして村人は,この出来事を長く語り伝えたと言うことです。
今でも三社稲荷の初午の縁日には,朝早くから氏子総代十数人一同が社に集まり,参拝する人々を迎える準備に追われます。このお稲荷様に参拝する者は,千円ほどの種銭を社から借りて返り,翌年家内安全,身体健全などの感謝の気持ちを込め,賽銭を倍返しするということです。またこの他にも今から20年ほど前までは,参拝者はめいめい手に「わらづと」を下げてお参りしました。わらづとの中には赤飯と「すみつかれ」が詰められています。ほんの少し前までは,たくさんのわらづとが村人から奉納され,三社稲荷の社に下げられていたということです。