| 演奏 | レスリー・ハワード | ||||
| タイトル | 『リスト ピアノ独奏曲全集 VOL.22 ベートーヴェン交響曲編曲集』 | ||||
| データ |
1990/92年録音 HYPERION(輸) CDA66671/5 |
||||
| ≫輸入盤(試聴あり) | |||||
| ・ | 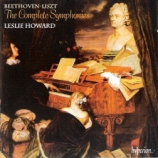 |
||||
| ・ | ヨーゼフ・ダンハウザー『リストを囲んで(部分)』(リスト、マリー・ダグー) | ||||
| 収録曲 |
≪DISC1≫ 1.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第1番 2.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第3番”英雄” ≪DISC2≫ 1.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第2番 2.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第4番 ≪DISC3≫ 1.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第5番”運命” 第2バージョン 2.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第6番”田園” 最終版 ≪DISC4≫ 1.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第7番 第2バージョン 2.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第8番 ≪DISC5≫ 1.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第9番 |
S464/1 S464/3 S464/2 S464/4 S464/5 S464/6 S464/7 S464/8 S464/9 |
|||
| 感想 | ベートーヴェン交響曲編曲集 S464 1865年 | ||||
リストは1835年頃から第5番を編曲し始め、1837年夏頃にノアンのジョルジュ・サンドの家でマリー・ダグーと共に過ごしていた頃、5番、6番、7番を第1バージョンとして完成します。その後1841年に第3番“英雄”の葬送行進曲を編曲。1851年には第9番を2台のピアノのために編曲します。その後ローマに定住して、1863年より残りの交響曲の編曲が再開され、1865年に出版。すべてはハンス・フォン・ビューローに献呈されました。 ハワードのライナーに載っている1865年版に寄せたリストの序文によると、リストはまずベートーヴェンの偉大な9つの交響曲を称え、今まで産み出されてきた多くのピアノ独奏曲版(おそらくリスト自身のも含め)はその“偉大さ”をピアノ版に移しかえることができていない、そのためリストが再挑戦してみる、というようなことが書かれています。その序文ではベートーヴェンの交響曲をピアノ独奏に編曲することは、ピアノという楽器自体の発展が可能にしてくれている、ということもリストは言及しています。 面白いことに、リストが1837年の9月、ノアンを旅立ち、マリー・ダグーと共にイタリアに着いてから書いた、友人のアドルフ・ピクテ宛の書簡では、ベートーヴェン交響曲の編曲について次のようなことが書かれています。“将来、誰かが自分よりも優れた編曲をするだろう”。この発言が1865年の序文につながるわけです。 『LISZT LETTERS IN THE LIBRARY OF CONGRESS - FRANZ LISZT STUDIES NO.10』のLETTER NO.106の注釈によれば、リストは改訂版の出版に際し、ブライトコプフ&ヘルテルに対し、フェルディナンド・ダヴィッドに楽譜を送り、意見を求めれるよう要請しています。 ブライトコプフ&ヘルテル社への1838年6月1日付け書簡において、リストは5番、6番、7番の出版に際し、フリードリッヒ・ホフマイスターと報酬に関する考えの食い違いについて書かれています。当時、編曲は1ページあたり6フランを受け取っていたリストは、ホフマイスターから5フランと提示され、憤然と反意を述べたようです※1。
Beethoven Symphonies Partitions de piano par F.Liszt (HYPERION CDA66671/5) |
|||||
| ≪DISC.1≫ | |||||
| 1.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第1番ハ長調 Op.21 S464/1 | |||||
記念すべきベートーヴェンの交響曲第1作目です。1799〜1800年頃に作曲され、1800年にベートーヴェン自身によってウィーンで初演されました。従来のハイドン、モーツァルトを頂点とする古典派の影響がまだ残りながらも、新しさを感じさせるものとして、当時も受け入れられたようです。C・M・ウェーバーがベートーヴェンの交響曲第1番を評した“ハ長調のすばらしく澄明で・・・”という評がリストの編曲にもそのままあてはまると思います。 Beethoven Symphony No.1 in C Major (24:20 HYPERION CDA66671/5) |
|||||
| 2.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第3番”英雄”変ホ長調 Op.55 S464/3 | |||||
ベートーヴェンは1802年に交響曲第3番を作曲し始めます。完成は1803年。初演は1805年にウィーンで初演されました。有名なエピソードとして、当初ベートーヴェンはナポレオン・ボナパルトに献呈しようと作曲しましたが、ナポレオンが皇帝に戴冠したことに失望し、楽譜に記したナポレオンへの献辞を消してしまったというのがあります。献辞は“ある偉大な人物の思い出のために作曲された”と書き変えられました。“英雄”が誰をさすのか、というのには諸説があり、ルイ・フェルディナンド公やギリシア神話のプロメテウスをさす、という説もあるそうです。 第1番に比べ、格段に曲が長くなり、大ピアノ曲として楽しめます。輝かしい第1楽章に、軽快な第3楽章のスケルツォなどピアノ独奏でも多彩な表現が楽しめて、魅力に満ちています。 Beethoven Symphony No.3 in E ♭Major (50:48 HYPERION CDA66671/5) |
|||||
| ≪DISC.2≫ | |||||
| 1.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第2番ニ長調 Op.36 S464/2 | |||||
ベートーヴェンらしさが早くも登場する力強い第2番です。1801年から1802年にかけて作曲され、1803年にウィーンで初演されました。音楽之友社
作曲家別名曲解説ライブラリー『ベートーヴェン』の交響曲第2番の項によれば、この曲はベートーヴェンがハイリゲンシュタットの遺書を書きながらも、絶望から立ち上がり書き上げたものとのこと。 第1番もそうでしたが、第一楽章の冒頭部分などは音数にも無理がなく、ピアノ独奏に向いているのか、非常に美しいです。 ハワードの解説によると、ベートーヴェン自身によって交響曲第2番から編曲されている、ピアノ三重奏曲二長調のピアノパートに、リストのピアノ独奏曲版は似ている、とのこと。 Beethoven Symphony No.2 in D Major (34:55 HYPERION CDA66671/5) |
|||||
| 2.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第4番変ロ長調 Op.60 S464/4 | |||||
1806年、ベートーヴェンはすでに第5番に着手していたのですが、一度ペンを置き、一気呵成にこの第4番を先に完成させます。初演は翌年の1807年ウィーンで行われました。 第8番と同じように、有名曲に挟まれるという不利な立場にある第4番は注目度が低いかもしれませんが、華やかな魅力に溢れる作品です。 リストのピアノ独奏曲版では、ハワードの演奏にもよるのですが、第1楽章冒頭の静謐な響きは本当にピアノだけで表現しているとは思えない効果を出しています。 Beethoven Symphony No.4 in B♭ Major (31:47 HYPERION CDA66671/5) |
|||||
| ≪DISC.3≫ | |||||
| 1.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第5番ハ短調“運命”Op.67 第2バージョン S464/5 | |||||
ベートーヴェンは“運命”を1804年頃から作曲し始め、1808年に完成します。同年の12月22日に第6番“田園”といっしょにベートーヴェン自身の指揮でウィーンで初演されました。 リストが編曲をしたのも9つのうち一番早くて、1835年頃から開始されています。1840年に第1バージョンは出版され、イタリアで知己となりともにベートーヴェンを演奏した画家アングルに献呈されました。 現代においてクラシック音楽における最有名曲の一つであるから、着手が一番早かったのか、と思いましたがハワードの解説を読むと、当時はそれほど第5番の交響曲が演奏されていた、というわけではないとのこと。 音楽之友社 作曲家別名曲解説ライブラリー『ベートーヴェン』の交響曲第5番の項において、執筆者の門馬直美さんは、第4楽章の箇所(P50)で次のように記しています。 “ベートーヴェンの信条でもある「苦悩を通じての歓喜」がここに具現されたともいえる。” ベートーヴェンの第5交響曲の各楽章に、僕がストレートに標題をつけるとしたら、次のようにします。第1楽章“絶望”、第2楽章“憩い”、第3楽章“再起と歩行”、第4楽章“復活と勝利”。“苦悩を通じての歓喜”とは、ベートーヴェンの信条でもあると同時に、それはリストが受け継いだ信条ともいえるのではないでしょうか。リストの場合は“ダンテソナタ”“ダンテ交響曲”“タッソー”“マゼッパ”などに顕著に見出されると思います。 Beethoven Symphony No.5 in C Minor (36:31 HYPERION CDA66671/5) |
|||||
| 2.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第6番へ長調 Op.68 “田園” 最終版 S464/6 | |||||
ベートーヴェンの第6番目の交響曲“田園”は、1807年〜1808年に作曲され、1808年にウィーンで初演されました。“運命”とならぶベートーヴェンの代表的な交響曲です。後続するロマン派のプログラム・ミュージックの先駆的作品です。 各楽章につけられた標題は次のとおりです(三省堂『クラシック音楽作品名辞典』P779)。 第1楽章 :“田舎に着いて、はればれとした気分がよみがえる” 第2楽章 :“小川のほとりの情景” 第3楽章 :“農民たちの楽しい集い” 第4楽章 :“雷雨、あらし” 第5楽章 :“牧人の歌 ― あらしのあとの喜ばしい感謝に満ちた気分” となります。 リストの編曲では随所にピアノならではの装飾的旋律や効果が加えられ、多様な色彩感を実現しています。 リストは、1839年11月19日ウィーンにおいて、ベートーヴェンの記念碑除幕式の資金集めのために、リサイタルを開きます。その時にピアノ編曲版の“田園”を弾いています。 リストの演奏家というイメージから対極に位置するようなグレン・グールドが、この第6番(第1楽章のみ)と第5番を録音しています。グールドは、自身がベートーヴェン〜リストの交響曲を録音したことを“ただの冗談”※1と軽口めいた揶揄で表現もしていますが、グールドの本音はラジオ番組での自身のナレーションに表れています。 “実際、これは私見ですが、ときにリストを惑わす唯一の要素は、ベートーヴェンの法典を字義どおりに解釈しようというほとんど清教徒的な姿勢です。” “この交響曲第六番はすでに納得のいく純然たるピアノ曲に生まれ変わっているからです。いわばこれはムッシュー・ベートーヴェン作曲グランド・ソナタ作品六八です”※2
Beethoven Symphony No.6 in F major “Pastorale” (42:23 HYPERION CDA66671/5) |
|||||
| ≪DISC.4≫ | |||||
| 1.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第7番イ長調 Op.92 第2バージョン S464/7 | |||||
ベートーヴェンは交響曲第5番と第6番を作曲した後、交響曲作曲からしばらく離れます。第6番が作られてから3年後、フランツ・リストが生誕した1811年より第7番の作曲が開始されます。1812年には完成し、1813年にウィーン大学の講堂でハーナウ戦役傷病兵のための寄金演奏会で初演されました。ワーグナーが後に“舞踏の聖化”と呼んだほど、活発なリズムに貫かれる曲です。 このようなリズムはリストにとってはお手のものではないでしょうか?まるで自分のオリジナル曲であるかのように、鮮やかな色彩と生命力に満ちたピアノ曲となっています。各楽章とも個性が強く、中でも第4楽章は特にピアノならではの輝きに満ちています。 ゲレリッヒが1885年7月8日のマスター・クラスで第2楽章をとりあげています。リストはその時、最初のページをうろ覚えではなく、完全に弾いて見せたとのこと。※1
Beethoven Symphony No.7 in A Major (42:45 HYPERION CDA66671/5) |
|||||
| 2.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第8番 ヘ長調 Op.93 S464/8 | |||||
ベートーヴェンは第8番も、第7番と同じ1811年〜1812年にかけて作曲し、1813年に初演されています。各楽章のまとまりがよく1楽章から4楽章まで大団円に向かって突き進む感じが見事です。 丸山桂介氏の解説によると(スウィトナー ベートーヴェン交響曲第4番、第8番 DENON COCO-6854)、第2楽章の冒頭には様々な説があり、メトロノームのリズムを模した、鍛冶屋のリズムを模した、という説とのこと。また第1楽章では、ヘンデルのオペラ“アリオダンテ”の主題が転用されている、とのこと。 リストのピアノ編曲では特に第4楽章が見事です。ピアノ独奏曲としては絶対に作られないような旋律・装飾が、編曲という作業によって実現されています。 1914年6月11日、アンドレ・ジッドの自宅へアルベニスやショパンの楽譜といっしょにリスト編曲のベートーヴェン交響曲集の楽譜が届きます。2年後の1916年12月16日。 “リストの編曲したベートーヴェンの『交響曲』の練習を(ここに来てから)はじめた。本当の発見をする。とりわけ、ヘ長調の交響曲(第八番)の最初の出だしとメヌエットは、極度の興味、極度に新しい難しさ、極度の美しさを持っているように思われる。””※1 1927年10月13日 “リストの編曲したベートーヴェンのヘ長調交響曲のメヌエットを再び弾いてみたが、得るところが大きかった。微笑ましくて優しい静けさ、力強さの中の安定。自己制御、完成。”※2
Beethoven Symphony No.8 in F Major (26:22 HYPERION CDA66671/5) |
|||||
| ≪DISC.5≫ | |||||
| 1.ベートーヴェン〜リスト 交響曲第9番ニ長調 Op.125 S464/9 | |||||
“ 「わかったよ」と彼は言った。「あれは存在してはならないのだ」 「何がだね、アドリアン、何が存在してはならないのだ?」 「善にして高貴なるもの、だ」と彼は私に答えた。 「善であり高貴であっても、人間的と呼ばれるものは存在してはならない。 人間がそれを得ようと戦ったもの、人間がそのために堅城を襲ったもの、 そして目的を達した人々が歓呼して告知したもの、それは存在してはならない。 それは取り消される。ぼくがそれを取り消そう」 「ぼくには、君、よくわからないんだがね。何を取り消すというのか?」 「≪第九交響曲≫さ」と彼は答えた。 そして、私はあとを待っていたが、もはやそれ以上一言も語らなかった。” 〜トーマス・マン『ファウスト博士』下巻 P226 関泰祐 関楠生 訳 岩波文庫〜 ベートーヴェンは1822年〜1824年にかけて第9番交響曲を作曲します。最終楽章にシラーのテキストを使った合唱が付けられます。最終楽章に合唱を使用するという構成は、リストの二つの交響曲“ファウスト”と“ダンテ”に引き継がれます。 ウォーカーのFY P65〜66で紹介されていることで、なんとリストは1864年にブライトコプフ&ヘルテル社に対し、交響曲第9番の第4楽章のピアノ独奏版編曲は困難であるため、編曲は第3楽章まででやめにしたいとの申し入れをしています。ブライトコプフ&ヘルテルはその申し入れを拒絶し、リストは10月1日に再度挑戦する旨を返信しています。 これはラ・マーラ書簡集が出典であり、1863年3月26日のブライトコプフ&ヘルテル宛書簡から始まります。この書簡でリストが昨日25日にベートーヴェンの交響曲1〜4番?の4つの楽譜を受け取っていることが分かり、リストは復活祭の後から仕事に着手する旨を伝えています。この書簡での予告どおり、リストは8月の終わりに完成させます。リストが第9番の第4楽章の編曲を、あらゆる努力をしたにも関わらず困難、と申し入れたのは1864年9月14日付けの書簡。そして10月1日付け書簡で再挑戦する旨が伝えられます。 1885年7月10日。2日前に第7番の第2楽章を演奏したゲレリヒに続き、今度はローゼンタールが第9番の第2楽章を演奏しています。その時にリストがコメントした内容では、ブライトコプフ&ヘルテルが、リストが第4楽章を編曲しないのならば、別の誰かに編曲させようとしたらしく、そのためリストは自分で編曲することを再度決意したようです。そしてリストの言葉で、結果としては不思議と他の編曲よりも特に困難なく達成できた、とのこと※2。 一度は断念したにも関わらず、実際に編曲してみたところ案外うまくいった、というのはどういうことでしょうか?リストが作曲を、“不可能”と考えて断念したものとして真っ先に思い出されるのは、“ダンテ交響曲”における“天国”です。リストはワーグナーの“天国は音楽によって描くことは出来ない”というアドバイスを受け入れ、天上からの合唱によって天国を想起させるのみとした、ことはよく知られています。そして第9の第4楽章の断念。リストは編曲を進める上で恐れおののいたのではないでしょうか?リストにとって第9の第4楽章というのは“天国”と同義だったのではないでしょうか?それこそアドリアン・レーヴェルキューンの言う“善にして高貴なるもの”を自身の手で編曲することに不安を感じたのではないでしょうか。 1851年版の2台のピアノのために編曲されたものは、ブラームスとクララ・シューマンに賞賛され、2人が演奏したそうです。※1 第1楽章冒頭の神秘的な響きからして素晴らしい効果をあげています。第9番はベートーヴェン交響曲群の総決算であり、そしてリストにとってもピアノ独奏版編曲の総決算ともいえます。
Beethoven Symphony No.9 in D Minor (66:50 HYPERION CDA66671/5) |
|||||