| 演奏 | レスリー・ハワード | ||
| タイトル | 『リスト ピアノ独奏曲全集 VOL.2 バラード、伝説、ポロネーズ』 |
||
| データ |
1988年録音 HYPERION(輸) CDA66301 | ||
| ≫輸入盤 | |||
| ・ | 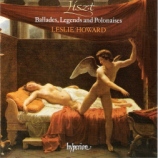 |
||
| ・ | フランソワ=エドワール・ピコー 『アモールとプシケ』 | ||
| 収録曲 |
1.バラード第1番 十字軍の歌 変ニ長調 2.バラード第2番 ロ短調 ・ 伝説 3.小鳥に語るアシジの聖フランシス 4.波を渡るパオラの聖フランシス ・ 5.子守歌 第2バージョン 6.即興曲 7.クラヴィーアシュトゥック 変イ長調 ・ 2つのポロネーズ 8.ポロネーズ ハ短調 9.ポロネーズ ホ長調 |
S170 S171 ・ S175 S175/1 S175/2 ・ S174 ii S191 S189 ・ S233 S233/1 S233/2 |
|
| 感想 | 1.バラード第1番 十字軍の歌 変ニ長調 S170 1845〜48年 | ||
導入部の後、流れるような第一主題へと変わり、中間においてマーチ風のリズミカルな部分となり、そしてもう一度第一主題へと戻ります。有名な第2番とは違い、非常に明快な曲です。 辞典によればBalladeとは、フランスで発展した吟遊詩人達の単旋律の歌曲から始まり、叙事詩につけられた音楽とのこと。詩の内容に合わせて、音楽が変化していくもの、とのこと。“バラード”というと当然ショパンを思い出します。ショパンのバラードもミツキエヴィッチの詩にインスパイアされて作られたものでした。リストは何の詩をイメージしたのでしょうか? この曲には“十字軍の歌”というサブタイトルがあります。ですが属啓成さんによれば“十字軍の歌”というタイトルは1849年に出版されたときに、出版社がつけたかもしれないとのこと。そのため現在ではサブタイトルは通常、外されています。またBalladeはBalladとは異なり、Balladはイギリスで発展した通俗歌曲とのこと。 ウォーカーのWY P146で“リストは、ショパンの生前には決して、ショパン独自のジャンルに手を出さなかった。”とあり、ポロネーズ、子守唄、マズルカ、バラード第2番が1850〜54年の間に集中して作曲されていることを指摘しています。そして1851〜52年にかけて『フレデリック・ショパン』なる著作を発表していることも見逃せません。 ですがバラード第1番は1845年のスペイン〜ポルトガルツアーの時にすでにスケッチが行われます。完成は1848年の、ショパン生前の作品です。ハワードも指摘していますが、オープニングはショパンのバラード第1番に似ています。イントロで下降する高音の装飾的旋律は、1842年作曲のモーツァルト〜リスト “フィガロの結婚”と”ドン・ジョヴァンニ”のテーマによる幻想曲(S697)のイントロを思わせます。また同じポルトガルツアーの時に書かれた1844年ドニゼッティ〜リスト“ドン・セバスティアン”の葬送行進曲(S402)の、行進曲へと後半変化する構成が類似していると思います。 バラード第1番は、ショパンを意識したというより、リストが当時得意としたジャンルの作品のように思えます。 “バラード第1番”に関連する、ピアノ小品、アルバム・リーフがあり、ハワードの全集では、第26巻に収められた1844年の“ピアノ小品 変ニ長調”(S189b) “ピアノ小品 変イ長調”(S189a)、第56巻に収められた、同じく1844年の“アルバム・リーフ 変イ長調 ポルトガル”(S166b)、ディスク2に入っている1843年の“アルバム・リーフ 変イ長調”(S166c)があります。 Premiere Ballade Le Chant du croise (7:25 HYPERION CDA66301) |
|||
| 2.バラード第2番 ロ短調 S171 1853年 | |||
ショパンのバラードを意識した作品は逆に第2番ではないでしょうか?“ショパンのバラードに似せて”というのではなく、ショパンを意識しながらリストなりのバラードを作り上げたものが第2番のように思えます。 非常に巨大な曲です。この曲は、ソナタと同じ時期に作られている事、また同じロ短調の大作であることから、非常に注目してしまいます。冒頭の暗く流れる大河のうねりのような部分は、まさに“叙情詩”と呼ぶにふさわしいスケールの大きさを持ちます。その後にくる静かな部分との対比に、宗教的な印象を受けます。その対比が終わった後の、アレグロ・デチーゾの部分は、やはり同時期に作られている“ソナタロ短調”“ファウスト交響曲”との親近性を感じます。 ハワードの解説によると、“バラード第2番”は長い間アウグスト・ビュルガーの詩“レノーレ”にインスパイアされたもの、とされてきたそうです。ですがハワードは、リストが1858年にピアノと朗唱のための作品“レノーレ”(S346)を全く異なる曲として作っていることを指摘し、“レノーレ”にインスパイアされたものではないだろう、と結論付けているようです。 ビュルガーの詩“レノーレ”を、ハンフリー・サールは“ロマン派の納骨堂”と呼んだそうですが、“バラード第2番”は、地を這うような暗い情念に覆われ、たとえ“レノーレ”にインスパイアされたものでないにせよ、まさに“ロマン派の納骨堂”という呼称がふさわしいです。 またクラウディオ・アラウが『アラウとの対話』の中で発言していることで、従来のリスト学者の一部及びアラウ自身も、この“バラード第2番”に対し、へーローとレアンドロスの神話を重ねているとのこと。同書P164より。 “アラウ リストの専門家うちではよく知られていました。私が記憶しているかぎりでは、この曲は神話本来の筋書きに従っています。レアンドロスは、毎夜ヘレスポント海峡を泳ぎ渡ってへーローの許に通い、翌朝また泳いで帰りました。その往復が毎回困難になっていく様子を、この曲のなかで現実に聴くことができます。4日目の夜に彼は溺れ死にます。そして、最後の数ページは変容です。” “バラード第2番”には同年に作られている第1バージョンも残されており、Vol.40に収められています。 Deuxieme Ballade (12:15 HYPERION CDA66301) |
|||
| 2つの伝説 | |||
| 3. “小鳥に語るアシジの聖フランシス” S175/1 1860〜63年 | |||
リストは1861年の秋にローマに行きます。リストは若い頃より信仰を持ち、いままでにも宗教的な作品を書いてきましたが、その素質に加えて、ヴィトゲンシュタイン侯爵夫人の影響、1859年に長男ダニエルが死去した事が、リストの宗教心を強めたと思われます。さらに音楽的目的として、新ドイツ学派とも呼ばれるリストの、新しい音楽スタイルによって教会音楽を改革することもあったようです。その成果として宗教を題材とした作品が以前にも増して作品の中心を占めるようになります。 リストは14世紀(1350年頃)にイタリア語(トスカナ方言)に翻訳された教会書籍『聖フランチェスコの小さな花』の第16章にインスピレーションを得ます。『聖フランチェスコの小さな花』は、聖フランチェスコの数々の伝説をまとめた作品で、“小さな花”というタイトルは“見捨てておくには惜しい美しい残片、小さな資料・文献の収録”という意味で使われています※1。森の中で小鳥に説教をする聖フランシスを描写した作品です。宗教的合唱曲“アッシジの聖フランチェスコの太陽賛歌”の主題が引用されています。 アッシジの聖フランチェスコは本名ジョヴァンニ・フランチェスコ・ベルナルドーネ(1182−1226)といい、イタリア中部のアッシジで生誕しました。フランシスコ修道会の創立者です。 若い頃は自由な俗世生活をおくっていましたが、1202年ペルージアとの戦争での長期にわたる捕虜生活で病気にかかり、それを契機に改心します。1205年頃からアッシジで布教活動をはじめると、彼のまわりには多くの弟子があつまりました。そして1210年にローマ教皇インノケンティウス3世より修道会設立の許可がおります。 二つの“伝説”は1865年8月29日にリスト自身の手によりブダペストで初演されました。1859年にダニエルが死去、1865年に長女ブランディーヌが死去、そしてこの二つの伝説は一人生き残った次女コージマに献呈されたのです。 “エステ荘の噴水”を思わせるように、無邪気に小鳥のさえずりや細やかな動きが描写されていきます。後半、聖フランチェスコの説教を意味する主題が入り、それに絡まるように小鳥の描写が交互に入り込むところなど、極めてストーリーの描写力にすぐれた傑作です。ストーリーを簡潔に言えば、アッシジの聖フランチェスコの奇跡として、その深い説教と信仰によって、無邪気な小鳥達の中にも宗教心を呼び起こさせた、という感じです。 『聖フランチェスコの小さな花』 田辺保 訳 教文館 P71 より、抜粋。 “「あなたがたはこの道の上で待っていてほしい。わたしはこれから、姉妹なる小鳥たちに説教をしてくるから」と。そして、野原の中へはいりこみ、地面にいた小鳥たちに向かって説教をおはじめになった。するとすぐに、木にとまっていた小鳥たちも舞いおりてきて、聖フランチェスコの説教が終わるまで、みながじっとおとなしく聞き入るのだった。(中略)聖フランチェスコが小鳥たちの中にわけてはいられ、長い服のすそが小鳥たちにさわることがあっても、一羽の鳥も身動きひとつしなかったそうである”
Legendes St Francois d’s Assie:La predication aux oiseaux (8:46 HYPERION CDA66301) |
|||
| 4.伝説 “波を渡るパオラの聖フランシス” S175/1 1860〜63年 | |||
波を渡るパオラの聖フランシスは、アッシジの聖フランシスとは別の人物です。1416年にパオラ(現在のイタリア中部のコゼンツァ)で産まれた聖フランシスは、清貧を貫いた生活と数々の奇跡から次第にパオラの人々に慕われるようになりました。最もよく知られた奇跡がメッシーナ海峡を、マントの上に乗り水の上を渡ったことです。メッシーナ海峡はイタリア本土とパレルモのある島とを隔てる海峡です。リストの楽譜には、序文として、長文が掲げられています。上記の内容のようなことが書かれているようです。 2人の聖フランシスは音楽だけでなく絵画、文学と数多くの芸術のモティーフとされました。リストはシュタインレ作の絵画“水の上を歩くパオラの聖フランシス”を所持していて(この絵画はアルテンブルクにかかっていました)、その絵画からのインスピレーションで曲は生まれました。宗教的合唱曲“パオラの聖フランシスに寄す”の主題が使用されています。 Vol.55には、1863年に作られた簡略バージョン(S175/2 bis)が収められています。 “小鳥に語るアッシジの聖フランシス”が細やかで繊細な描写ならば、“波を渡るパオラの聖フランシス”は、極めてスケールの大きな作品です。海上を渡るという、ダイナミックなイメージを見事に描いた、劇的なドラマツルギーを持つ作品となりました。 Legendes St Francois de Paule marchant sur les flots (7:31 HYPERION CDA66301) |
|||
| 5.子守歌 第2バージョン S174 ii 1854/1863年 |
|||
第26巻には1854年に作られた第1バージョンが収められています。第2バージョンではきらめくような高音の装飾が加えられ、曲も長くなっています。暗闇のいくつものキャンドルのようにゆらめく美しい曲となっています。 Berceuse (9:21 HYPERION CDA66301) |
|||
| 6.即興曲 第2バージョン S191 1872年 |
|||
“孤独の中の神の祝福”のように優雅に美しく装飾されゆるやかに流れていく曲です。ハワードは“晩年のアヴァンギャルドな世界”と評しているのですが、エンディング間近において聞こえる“ハンガリー狂詩曲”のような旋律の部分でしょうか(またその旋律が組み込まれるという全体の構成)。オルガ・フォン・マイエンドルフに献呈されました。 ハワードの第2巻の解説では、「“即興曲”には、2つのバージョンがあり、第2バージョンで“ノクターン”とつけられた。この巻には変更前のオリジナルの“即興曲”を収録した」ということが書かれています。ですが“ノクターン”の収められた第40巻の解説でハワードは誤りを修正しています。訂正後のハワードの解説を参照すると、“ノクターン”とつけられたS190aは、“即興曲”の第1バージョンで、第2巻の“即興曲”が第2バージョンということになります。 第1バージョンと第2バージョンの違いは、いくつかの旋律等わずかなものです。ハワードが指摘していることで、第2バージョンのエンディングの方が、よりエンディングらしい和声で終わっています。 Impromptu (2:59 HYPERION CDA66301) |
|||
| 7.クラヴィーアシュトゥック 変イ長調 S189 1866年 | |||
ハワードはこの作品を“愛の夢の世界と晩年の作品をつなげるような作品”と呼んでいます。確かにリストの優雅な洗練された優雅な音世界と晩年の作品が持つ(“クラヴィーアシュトゥック第2番”や“瞑想”、“クリスマスツリー”の“昔々”)不可思議な雰囲気を併せ持つ作品です。 “クラヴィーアシュトゥック 変イ長調”は、長い間紛失したと思われ、まず1935年に草稿の所有者が草稿の掲載を雑誌に許可して知られるようになったようです。その後1968年に草稿がオークションによって別の個人の所有物となり、その後リスト協会が1988年に出版権を獲得したとのこと。 この“クラヴィーアシュトゥック 変イ長調”は第1番に位置づけられるようです。新リスト全集には収録されておらず、ハワードの解説によると、どうも第26巻の“ピアノ小品 変イ長調”(S189a)が第2番として位置づけられ出版されたようです。 Klavierstuck A♭ major (2:51 HYPERION CDA66301) |
|||
| 2つのポロネーズ |
|||
| 8.憂鬱なポロネーズ ハ短調 S223/1 1851年 |
|||
辞典によると、ポロネーズとはポーランドの舞踏曲。すり足舞踏とのこと。3/4拍子。第1番は多くの印象が混沌と盛り込まれた作品で、リスト独特のポロネーズです。それらの混沌を総括するかのようにエンディングは力強くテーマが奏でられます。憂いを帯びた旋律を中心に美しい印象に彩られます。。 ハワードは解説で、“憂鬱な”という呼称は、リスト自身によるもので、多くの楽譜がそのタイトルを無視していることを残念に思う、と言及しています。 実際リストは1851年3月19日付けのカール・ライネッケ宛ての手紙で、“超絶技巧練習曲”“演奏会用大独奏曲”に混ざって、最近の出版物として“最近、書き上げたとてもメランコリックなポロネーズ”としてこの曲を呼んでいます。 リストはポロネーズをその後、1876年に“祝祭ポロネーズ”(独奏 ハワードS230a、サールS528)(連弾 S255)、1875年に“オラトリオ聖スタニスラウスによる2つのポロネーズ”(S519)で取り上げます。また1848年〜52年にかけてウェーバーの“華麗なポラッカ”を編曲した“華麗なポロネーズ”(S367)、1879年に編曲したチャイコフスキーの“エフゲニー・オネーギン”のポロネーズ(S429)があります。 Deux Polonaises 1:Polonaise melancolique C minor (11:11 HYPERION CDA66301) |
|||
| 9.ポロネーズ ホ長調 | |||
第1番に比べると、曲の性格はよりショパンらしいです。装飾にはリストらしいところがあります。ショパン的なポロネーズで明快であるため、第2番の方が好まれて演奏されています。ハワードの解説では、ブゾーニが演奏し、ラフマニノフ、パーシー・グレインジャーが録音を残しているとのこと。またウォーカーのFYでは、1881年にハンス・フォン・ビューローが、またリストの死後1911年にリストの生誕100年祭が催され、ダルベールが演奏したことが分かります。 どうしてもショパンと比べられてしまうため、価値を低く見られがちですが、単独のポロネーズ作品としてよくまとまり魅力のある作品です。 Deux Polonaises 2:Polonaise E major (8:23 HYPERION CDA66301) |
|||
| ・ | |
| ・ | |
| HOWARD CD INDEX | ・ |
|
・ |
・ |
| ・ | ・ |