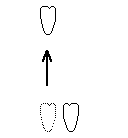
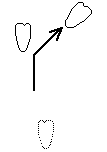

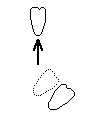
射場に垂直に踏み出す。
左足のかかとをするように踏み出す。
揖の対象に正しく向く。
揖はきちんと腰から折る。(勢いで足首から傾かないこと。)
揖の前に、対象に気持ちを向ける。
四歩目は的方向に踏み出す。
1)入場の仕方(複数者の入場)
・進みでる時は、敷居のすぐ手前まで寄り、一歩目は大きく左足から踏み出す。
・入場の際の揖
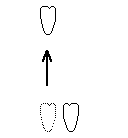 |
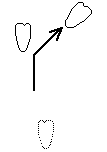 |
 |
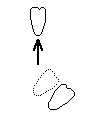 |
| 1.左足から大きめに踏み出す。 射場に垂直に踏み出す。 |
2.二歩目もやや大きく。 左足のかかとをするように踏み出す。 揖の対象に正しく向く。 |
3.右足に左足をそろえつつ揖。 揖はきちんと腰から折る。(勢いで足首から傾かないこと。) 揖の前に、対象に気持ちを向ける。 |
4.体を起こしてから四歩目を踏み出す。 四歩目は的方向に踏み出す。 |
大前の者は、3で足をそろえ、意識を揖の対象に向けてから、三息の揖(吸う息で体を屈し、屈したまま息を吐き、吸う息で体を起こす)をする。
2)本座への進み方
・脇正面に向きをかえる時、大前の者はきちんと角をきり、二的以降の者は自然に向きを変える。(方向転換は右足で。)
・大前の者は、的正面に向きを変える時に全体がそろうように、歩く速度を考える。
・前の者に足をそろえて歩く。(入場時の足さばきに注意。)歩くテンポは変えない。歩幅で調節する。
・的正面に向きを変える時は角をきる。大後はそのまま本座に入ってよい。(射場の大きさ、入場口の位置関係による。審査開始前に確認するとよい。)
・坐した時、膝頭が本座の線に合うようにする。
・座した時、両かかとをつける。
・歩くときの息合いは、吸う息で二歩、吐く息で二歩。
3)本座から射位への進み方
・前の立ちの大後の弦音で揖をおこない、腰をきり立ち上がる。
・立ち上がる時、膝をしめる。(両膝頭が付く)
・前の立ちの大後が本座方向に一歩踏み出すと同時に、射位に進む。
・このときの息合いは、吸う息で一歩、吐く息で一歩。
・左足から進み、三歩目で足をそろえる。
・座した時に膝頭が射位の線にそろうように歩幅をあわせる。
・射位に座した後、開き足で脇正面に向かう。このとき視線に気をつける。
(弓を目線の高さに上げるが、目線は2m前方を見たまま。的も見ない。)
4)矢番え動作
・大前の主導で、全員一斉に弓を立てる。
弦が体の中央になるようにし、軽く肘をはる。
・弓を立てたら膝を生かす。(甲矢の場合。)
・弦の下の方をおさえ。弦を中心に弦を返す。
・弓をだきかかえるように、右手を弓の外側にはこぶ。
弓が傾いたりすることのないように。
・甲矢乙矢を見分け、甲矢を番える。親指は番えた矢の下に入れる。
乙矢は、甲矢と平行になるように左手に打ち込む。
このとき、走り羽が下になるようにし、射付節が弦のあたりにくるようにする。
・腰骨のあたりに右手を復する。(腰骨の右上方先端に親指があたる位置。)
・キョロキョロしない。
5)立ち上がってから、射終わるまで
・腰を切りつつ、矢が目の高さになるくらいまで弓を持ち上げる。
右手は筈を隠すようにして添える。
・必ず取り矢をする。
・立つタイミングは、二的の者は前の者が胴造りを終えた時。
(「胴造りを終えた時」とは、弓の本弭を左膝頭に置き、妻手が右腰についた時で、取り矢、弦調べ、箆調べはその後のことである。)
三的以降は、二つ前の者の弦音で立つ。
・前の者の弦音で取り懸ける。
・甲矢を引き終えたらその場で速やかに座し、膝を生かした後、矢を持ちかえて待つ。
・大後前の弦音で、それより前の者は弓を立てる。
このとき既に膝を生かしているので、甲矢の時とは少し違う。
大後前の者は大後の弦音で弓を立てる。大後の者は、息合いに合わせ弓を立て乙矢を番える。
・乙矢の時も、立つタイミングは甲矢の時と同じ。
・乙矢を引き終えたら速やかに退場する。
・呼吸にあわせて動作を行う。
6)退場の仕方
・退場は右足から踏み出し、