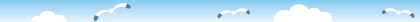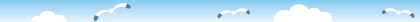
熊本県等の多文化共生施策の現状
―2002年9月熊本県への外国籍住民・帰国者のための8項目の施策の提言の実施状況
中島真一郎(コムスタカー外国人と共に生きる会)
はじめに
私たちが帰国者や外国籍住民のための8項目施策の提言に取り組んだ2002年の時点では、熊本県の行政として、帰国者や外国籍住民の施策の回答はほぼゼロ回答で、外国籍住民は行政の施策の対象外となっていました。私たち4団体の提言へ、「このような視点での提言自体がカルチャーショックであった」と述べた熊本県職員もいました。
それから5年をへて、少しずつですが、熊本県・熊本市の行政においても帰国者や外国籍住民を対象とし、意識した施策が少しずつ行われてきています。まず、行政として、帰国者や外国籍住民を、大多数を占める日本国籍を持つ住民と同様な住民として、その存在を認め、行政の施策の対象として意識することが必要です。
そのためには、帰国者や外国籍住民のニーズを把握し、その直接的な声を反映できる仕組みや意見交換の場を保証する事、あるいは、帰国者や外国籍住民の支援活動を担っている民間団体との連携も不可欠です。
熊本県内でのこの5年間の経験では、帰国者や外国籍住民の主体を尊重し、そのニーズと一致した内容で、これらの人々の問題に取り組むNGOなど民間団体と連携し、行政内部にも多文化共生の地域社会作りに意欲と関心を持つ担当者が存在した場合には、全国的にも、あるいは九州内でも先駆的な施策が実施され、具体的な効果と実績を挙げています。
1、DV被害者や単身者も利用できる自立のための中間施設としてシェルターの設置
現在熊本県内には、短期滞在の一時避難所と子どもをつれた女性のための母子自立支援センターの二種類しかありません。そこでDV被害者や単身者も利用できる自立のための中間施設(3ヶ月〜1年程度居住できる)の設置を提言します。
↓
2007年度現在までにDV被害の防止や被害者保護で行われてきたこと
(1)、熊本県の施設を活用したステップハウスが、全国で初めて2003年4月1日より設置され、運用が始まりました。
利用状況(年度)
|
2003
|
2004
|
2005
|
2006
|
|
3件
|
3件
|
0件
|
4件
|
うち外国籍の方は、2003年度に1人、2006年度に1人利用
(2) 在留資格のない外国籍のDV被害者の一時保護に際して、入管への通報が、原則通報から、ケースバイケースに変わりました。
2002年の回答では、入管に通報したうえで一時保護するという回答から、 違法入国等の相談者の実績はないが、もしあった場合は事情により即通報という体制ではなく、ケースバイケースで対応の予定に変化しました。
(3) DV被害防止と被害者保護のための9ヶ国語(日本語・英語・韓国語・タイ語・フィリピン語・中国語・ロシア語・スペイン語・ポルトガル語)の多言語対応 2004年度作成(委託先:コムスタカー外国人と共に生きる会)2005年度より配布されています。
○「熊本県外国籍被害者のためのDV対応マニュアル」(9ヶ国語) 100部
作成、熊本県内の福祉事務所など関係機関に設置して、外国人による相談の際に、これを見せて説明します。
○「STOP!DV」(9ヶ国語)のリーフレット 40000部作成、熊本県内の行政機関の窓口、郵便局の窓口などにおいて、希望者が自由に持ち帰れるようにしてあります。
2、自動車免許の取得に関して、外国籍住民への配慮ある措置をとること
日本で外国籍住民や帰国者が運転免許を取得する際には、日本語以外の言語でも学科試験が受けられるように、自動車免許の学科試験を多言語対応(英語・中国語・フィリピン語・韓国語・スペイン語・ポルトガ語・タイ語など)にすることを提言します。
↓
2004年8月より熊本県の自動車免許の学科試験で英語と中国語による試験が導入されました。
2004年8月から普通一種(自動二輪・大特一種を含む。)及び原付免許にかかる外国語(英語・中国語)による学科試験を実施。英語の導入は、九州内では、大分県が1999年11月から導入についで2番目、中国語の導入は九州内では初めて、日本全国でも3番目。なお、福岡県も、2005年4月より英語の試験を導入しています。なお、熊本県運転免許センターによると、これまで年間延べ人数(複数受験者あり)で約1200人の方が外国語による学科試験を受験している状況です。
3、外国籍住民の住民票本欄への記載を可能とすること
「住民票の備考欄への外国籍配偶者の記載可能」という総務省の2002年3月15日の通知に基づき、「住民票の備考欄への外国籍配偶者の記載を可能とする運営を行うことができること、そのような運営を行う場合には外国籍住民への広報を徹底させる」よう熊本県内の全ての市町村に指導を行うことを提言します。
↓
住民票備考欄への外国人配偶者の記載問題で、10年以上拒否してきた熊本市が、2002年7月より住民票備考欄への記載を認める運用にかわりました。
これまで同居している家族なのに、外国籍妻の場合は、日本人夫や子どもの住民票に記載が一切なく、別居しているようの思われるとして、熊本市在住の外国籍配偶者が、10年前から熊本市に要望をしつづけていましたが、実現しませんでした。2002年3月15日総務省は全国の市町村へ住民票の備考欄へ外国人配偶者の記載を原則的に要望があれば認めるようにとの通知をだしました。すでに、2002年2月から岡山市が、4月から長崎市などが実施しました。総務省の通知や外国籍市民の要望を受け、ようやく 熊本市も2002年7月1日より希望する外国人配偶者に対して住民票の備考欄への記載を認める決定をしました。外国人配偶者の住民票の備考欄記載問題の外国籍住民から要求がなされた最初の自治体、いわばこの問題の発祥の地であった熊本市でも、10年以上かかりましたが、実施されていくことになりました。
4.社会保障適用範囲を外国籍住民や在留資格のない母子家族へも拡大すること
(1) 在留資格のない外国籍住民にも、公衆衛生(予防接種法による定期の予防接種など)や緊急医療(児童福祉法の定める緊急入院助産制度、母子保健法に定める未熟児に対する養育医療の給付、児童福祉法に定める障害児の育成医療の給付など)が適用可能であることを県内の市町村へ周知徹底させるよう、
(2)在留資格のない母子世帯等へも、必要性・緊急性がある場合には、熊本県と市町村自治体の判断により生活保護や国民健康保険の適用を可能とする措置をとれるようにすることを提言します。
(3)医療保険の適用がないために医療費が支払えない外国籍住民が緊急治療や人道上必要な治療を受けられるようにするため、医療機関へ医療費の7割の補助をする外国人の救急医療費損失補助事業を設置して、予算措置をとることを提言します。
↓
未実施
5.外国籍住民や子どもへの偏見と差別を助長する表現をやめさせること
(1) 最近、学校へ配布されている薬物被害のパンフレットや警察の広報に「イラン人薬物違反」とか「不審な外国人(中国人)に気をつけよう」などという表現を見かけます。犯罪に関する広報に際して特に自治体や警察が「外国人らしき」「東南アジア風」などと「外国人」を一括りに表現したり、特定のグループをイメージさせたりしないように提言します。
↓
2004年8月から熊本県警のHP上での「不法滞在者・不法入国者」の通報呼びかけでの「不審な外国人」などの差別表記が、外国人を特定しない表記に改められました。
熊本県警のHP(ホームページ)での「不法入国・不法滞在事犯の情報」提供を呼びかけるE・メール通報制度の記載内容が変更となりました。熊本県警のHPは、2004年7月から「不法入国・不法滞在事犯の情報」のコーナーで、「皆さんのまわりで、不審な外国人がうろついている。不審な外国人がたむろしている。などを発見したら110番又は最寄の交番・駐在所へご連絡下さい。メールによる情報も受理してください」と記載していました。2004年7月下旬に抗議と申し入れなどを考慮して、熊本県警の「不法入国-不法滞在事犯に関する情報提供」のタイトルはそのままですが、その記載内容が、2004年8月から「不審な外国人」から「不審な人」という言葉に変更になり、「メールによる情報も受理しています」という言葉を削除した内容に変更となりました。
(2) 国籍や民族の異なる父母から生まれた子どもを、「ハーフ」や「混血児」など差別的表現で呼ぶのをやめるよう指導することを提言します。(それに代わる表現として、例えば、コムスタカー外国人と共に生きる会では「国際児」などを使用しています。)
↓
共同通信社・朝日新聞社・読売新聞社など大手マスコミのなかにも、「混血児」を差別表現として使用を避けるように社内方針を決定するところがあらわれてきました。
日比国際児の問題を取組む中で、国籍や人種や民族が異なる父母から生まれた子を、「純血児」に対比される言葉である「混血児」と呼ぶことは差別表現であるとして、その代わりには、「国際児」を使用してほしいと提唱し、「混血児」を使用するマスコミやNGOに申入を行っていきました。
「混血児」という表現は行政では使用されていませんでしたが、大手マスコミの報道において「混血児」は差別表現として認識されておらず、わかりやすく知らせるためという理由で使用され続けていました。しかし、共同通信社が2001年3月より「混血児・合いの子の使用を避ける」と明記していることがわかり、熊本日日新聞社をはじめ全国の地方紙に関しては私たちのこれまで主張してきたことが実現しました。また、2005年2月には朝日新聞社が全社として、「混血児」表記を差別表現と認めて、今後使用を避ける決定を行いました。同年3月から読売新聞社は「混血児」の使用を避ける決定をおこない、2006年2月から.できるだけ別の表現で説明するなど、この語を避ける工夫をするという方針を決定しました。
6.外国籍住民や帰国者への住居差別をなくす施策を実施すること
(1) 熊本県内の不動産業者や家主に対して、外国人あるいは帰国者であることを理由に住居差別をしないよう、指導を徹底することを提言します。
(2) 県が呼びかけ、あるいは県も加わった公的信用保証制度を設置し、連帯保証人などを見つけることが困難な外国籍住民を支援する仕組みをつくることを提言します。
↓
未実施
7、日本語が不十分な外国籍児童・生徒・住民や帰国者のための日本語教育を充実させる施策を実施すること
(1)、熊本県として、外国籍児童・生徒、帰国者など日本語が不十分な子どもの実情を調査し、これらの児童・生徒の教育を受ける権利を保障するための基本方針を定め、行政として積極的に取組むことを提言します。
↓
中国語、韓国語、英語の3ヶ国語の訳をつけた「わかるよ、さんすう」の編纂や、帰国・外国人生徒と保護者のための進路ガイダンスを実施しました。
熊本県教育委員会では、平成10年度に熊本県立大学に依頼して、「わかるよ、さんすう」を編纂しました。小学校で学習する算数を対象に、授業を理解するうえで重要な語句や表現を選び出し、内容すべてに、中国語、韓国語、英語の翻訳をつけています。希望のあった小・中学校に配布しています。また、帰国・外国人生徒と保護者のための進路ガイダンスで県教育委員会から高校入試について説明を行うなど、関係機関や団体等とも連携を図りながら支援を行っています。
(2) 高校入試での帰国者や外国籍の受験者に配慮した施策について高校への進学を希望する日本語が不十分な外国籍や帰国者の高校受験に際して、試験問題にルビをふる、また辞書持ち込みを可能
にする等の配慮をすること、あるいは、このような日本語の不十分な受験生のための特別枠を設け、受験科目の削減をするなど別個の試験を実施して高校への進学を可能とすることを提言します。
↓
2007年度入試より帰国者や外国籍の受験者に配慮した入試制度が実施されるようになりました。
「2007年度入学者選抜要項」では、海外帰国生徒等への配慮事項として、「高等学校長は、海外帰国生徒、中国等帰国生徒及び外国人生徒で、特別の配慮が必要と認められる者については、県教育委員会の承認を受けて、検査時間の延長など、
検査方法や検査場等について適切な措置を講じるものとする」としており、申請のあった高等学校では、これに基づき試験問題にルビをふる、また辞書持ち込みを可能にする等の配慮をするなど、適切な措置を講じています。 また、「後期選抜における海外帰国生徒等の特別措置」の内容としては、一定の条件のもと、以下の二点を定めて実施しています。
○5教科(国語、社会、数学、理科、英語)の中から志願者があらかじめ選択した 3教科の学力検査と、作文及び面接を実施する。
○作文は、出願者の適性や意欲・関心等をみるために、800字、50分で実施する。
8、外国籍住民の意見や要望を県の行政に反映させる外国籍住民代表会議(仮称)を設置 すること
すでに、1996年神奈川県川崎市での条例による設置を契機に、神奈川県、兵庫県や長野県などで設置されていますが、熊本県内在住の外国籍住民を対象に、その意見や要望を県政に反映させるための外国籍住民代表会議(仮称)などを設けることを提言します。
↓
未実施