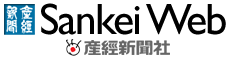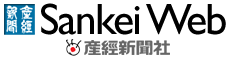|
平成17(2005)年5月28日[土]
|
 以前の主張
【全国紙の社説】
以前の主張
【全国紙の社説】
 朝日新聞
朝日新聞
 読売新聞
読売新聞
 毎日新聞
毎日新聞
 日本経済新聞
日本経済新聞
■【主張】旧日本兵生存 故国が持つ引力のすごさ
戦後六十年という膨大な時間の嵩(かさ)を挟んで、フィリピンのミンダナオ島で旧日本兵二人が生存していたという情報がもたらされた。二人は山岳地帯で
終戦を迎えたため、引き揚げ船に間に合わなかったようだ。その後、山岳ゲリラに戦術指導をするなど、思いもよらぬ運命に翻弄(ほんろう)される人生を送っ
た。
昭和四十七年に米グアム島で見つかった横井庄一さんや、同四十九年フィリピン・ルバング島で見つかった小野田寛郎さんと状況は異なるだろうが、生存とい
う天のはからいに喜びをともにしたいと思うと同時に、故国の土を踏むことのできなかった歳月の長さに心から同情の念を禁じ得ない。
現地で遺骨収集活動をしていた日本人男性に、地元有力者を通じて「本当にお願いします。お待ちしております 山川 中内」というメッセージが託されたのだったが、わずか七センチ四方の粗末なメモ用紙に弱々しい文字で書かれていた。望郷の念いかばかりであったろう。
旧日本兵が所属していた第三十師団は「豹(ひょう)師団」の異名を取る精強ぶりで知られたが、ミンダナオ島で地獄絵図のような戦闘を強いられ、八割が戦死か行方不明になったという。
フィリピン国内にはまだ四十人近い旧日本兵が残っているという情報もある。見つかった二人の年齢が、一人が八十七歳、もう一人も八十五歳ということを考えると、とても悠長に構えてはいられない。当局の迅速な、さらなる調査を望みたい。
旧日本兵にとって、もとより六十年の空白は埋めるに埋めようがないに違いないが、当局は帰国を望む人には疎漏のない受け入れ態勢を準備すべきであるし、私たちもこの不条理を強いられた気の毒な同胞を温かい心で迎えたいものだ。
彼らが異国の山岳生活で思い描いたであろう故国の風景は、あるいは「うさぎ追いしかの山、小ぶな釣りしかの川」のようなものであったかもしれない。変貌(へんぼう)著しい今日の日本を見れば、その驚きは想像を絶しよう。
しかし、風俗や人情は六十年前とは様変わりしていても、人間の魂が帰還することを飢渇するところはその産土(うぶすな)だ。故国とは何という大きな引力を持つものであろうと思う。
■【主張】住民基本台帳 原則非公開は時代の要請
現在は原則として公開されている住民基本台帳の閲覧制度が見直されることになった。総務省の検討会で論議しているが、原則非公開にする方向だ。時代に即した政策転換である。
昭和四十二年に施行された住民基本台帳制度は、個人の住所を証明する唯一の公簿である。台帳法の規定によって、市区町村の窓口で氏名、住所、性別、生年月日が誰でも閲覧できる仕組みになっている。
施行時は多くの人が閲覧したほうが情報の正確性などが担保されるとされていた。ところが最近になって想定外の事態が発生する。
今年三月、名古屋市で少女への強制わいせつ事件を引き起こした男が逮捕された。男は住民基本台帳を閲覧し、母子家庭などの一人っ子を探して犯行に及んでいた。振り込め詐欺に悪用される恐れも指摘されている。
また、ダイレクトメール(DM)業者による大量閲覧も問題視されている。東京都三鷹市の例では、人口の35%にあたる年間六万人分の閲覧があり、このう
ち90%以上が営利目的だった。ほとんどがDM業者とみられる。市民からは「身に覚えのないDMがきて不安」などのクレームが寄せられているという。
他の自治体でも同様の指摘があり、熊本市などでは閲覧を制限する条例を制定しているが、悪用されるケースは根絶しがたい。閲覧制度の意図とはかけ離れた実態が浮かぶ。
四月に全面施行された個人情報保護法では、取扱業者に本人の同意なしに第三者への情報提供禁止など、厳格な情報管理を求めている。一方で不特定多数に情報が渡る閲覧制度がある。これでは住民に二律背反の印象を与え、不信感が増すばかりだ。
問題は公共性の高い学術調査や世論調査なども、住民基本台帳とこれに連動する選挙人名簿を使用していることだ。こうした調査まで制限するのか、例外的に認めるのか、認めるとしたら線引きをどうするのか−など、掘り下げた論議が必要となる。
最近のプライバシー意識の変化も踏まえ、住民基本台帳の原則非公開への転換は妥当である。そのうえで、現在の環境に合わせた全国共通のルール確立を目指すべきだろう。
|