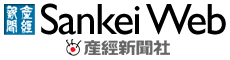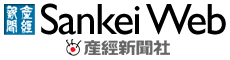|
平成17(2005)年6月3日[金]
|
 以前の主張
【全国紙の社説】
以前の主張
【全国紙の社説】
 朝日新聞
朝日新聞
 読売新聞
読売新聞
 毎日新聞
毎日新聞
 日本経済新聞
日本経済新聞
■【主張】河野氏発言 中国の分断策に乗る恐れ
河野洋平衆院議長が一日、五人の首相経験者を招き、小泉純一郎首相の靖国神社参拝取りやめを提起した。各氏は首相に慎重な対応を求めることで一致したという。
立法府と行政府の長の経験者が集まり、現職首相の外交に圧力をかけようとするのは適切だろうか。中曽根康弘元首相は「立法府の長が、行政府の長の経験者を呼びつけて意見を聞くことはあり得ない」と出席を断ったという。これが常識である。
憲法六五条は「行政権は、内閣に属する」と明記している。
河野氏は席上、「昨今の日中、日韓関係の急速な悪化は看過できない。大きな原因の一つに、首相の靖国参拝がある」と述べたという。
この発言は、中国の胡錦濤国家主席が「目にしたくない動き」として、首相の靖国参拝などを批判したことと同一歩調を取っていると受け取られかねない。これは結果的に小泉首相を中国とともに揺さぶることになる。
忘れてならないのは、戦後四十年間、首相の靖国神社参拝は慣例として春秋の例大祭や終戦記念日に行われてきた事実である。
中国は、靖国神社にいわゆる「A級戦犯」が合祀(ごうし)されていることを問題にしているが、「A級戦犯」は昭和五十三年秋に合祀され、マスコミに報じ
られたのは翌五十四年春である。そのとき、中国は表立って抗議していない。大平正芳首相もその年の春の例大祭に予定通り参拝している。
当時も一部に問題視する声があり、大平首相は国会で「A級戦犯、あるいは大東亜戦争についての審判は歴史が致すであろう」と答えている。国のために死んだ人々を慰霊することが、いずれの国でもみられる自然な光景であることを言いたかったに違いない。
河野氏は宮沢内閣の官房長官だった平成五年八月、「従軍慰安婦の強制連行」を認めた談話を発表した。だが、後に石原信雄元官房副長官の証言などによっ
て、公式文書には強制連行を裏付ける資料はないことが判明した。ただ誤解は内外に広がり、取り返しのつかない負の遺産を残した。五年前の外相時代も北朝鮮
へ巨額のコメ支援を行ったが、何の成果もなかった。
政治家には常に国益を踏まえた行動が求められている。
■【主張】出生率最低 20年後の社会考え対応を
女性一人が生涯に産む子供の数を表す合計特殊出生率が、昨年(平成十六年)は1・29だったことが厚生労働省の人口動態統計(概数)で明らかになった。
一年前に発表され、「1・29ショック」といわれた一昨年と同率だ。しかし、実はこれは小数点以下三けたの数字を四捨五入した数字であり、詳細に見ると
一昨年は1・2905、昨年は1・288だから、実質的に過去最低となったのである。出生数も昨年は百十一万一千人で、前年より一万三千人少ない。
一つの社会が人口を維持するには、出生率が2・08でなければならず、数字がそれより大きければ将来の人口は増え、小さいと減るという。
昨年の統計では、出生数から死亡数を引いた自然増加数は八万二千人と、かろうじてプラスを維持しているが、これも来年(平成十八年)には逆転して死亡数の方が多くなり、人口減少時代が始まる見通しだ。
ここまでくると毎年発表される目先の数字に一喜一憂している場合ではないだろう。次世代を見据えた対策に一年や二年で答えを出すことはできない。少子化
と人口減少を避けがたい趨勢(すうせい)として受け止め、日本がどのような姿の社会を目指すのかを戦略的に考える必要がある。
尾辻秀久厚労相は出生率の低下について「残念だ」と述べる一方、「改善の兆しはある」と指摘した。三十代の女性の出生率だけ見れば、ここ一、二年でわずかながら上昇に転じており、晩婚化の過程で生じる出生率低下に歯止めがかかったとみられるからだ。
だが、出生率は劇的な回復が期待できるものではない。出生率1・29ということは、二十年後、三十年後の生産年齢人口が大きく減少することを意味している。二十年後の生産年齢人口は現在より一千万人以上減っているだろうとの予測もある。
当然の結果として、日本はこれまで以上に女性の労働力を必要とする社会になる。女性が子供を産み育て、なおかつ仕事を続けていくことに魅力を感じられる
社会、あるいは子育ての後で再就職が可能な社会の環境が整っていなければ、その時点でまた新たな少子化問題が発生し、経済・社会はさらに衰退していくこと
になる。
|