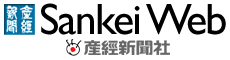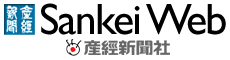|
平成17(2005)年5月19日[木]
|
 以前の主張
【全国紙の社説】
以前の主張
【全国紙の社説】
 朝日新聞
朝日新聞
 読売新聞
読売新聞
 毎日新聞
毎日新聞
 日本経済新聞
日本経済新聞
■【主張】米誌の誤報 日本も他山の石としたい
米誌ニューズウィークは、「米軍がイスラム教の聖典、コーランを冒涜(ぼうとく)した」と伝えた記事の誤りを認め、謝罪し、全面撤回した。日本のマスコミにとっても、重要な教訓を含んでいる。
問題の記事は、キューバの米軍基地の尋問官が収容者の証言を促すため、コーランをトイレに流して動揺させたという内容である。この報道をきっかけに、イスラム圏各国で反米デモが発生し、鎮圧部隊との衝突などで十六人が死亡、百人以上が負傷した。
ところが、同誌が改めて情報源にあたったところ、「確実に見たわけではない」と不確かな話だったことを認めたというのだ。同誌は、根拠が確認できなかったとして、記事の全面取り消しに踏み切った。
しかし、不確かな情報に基づく報道が国際問題に発展し、十六人も死亡する事態を招いた責任は重い。事実はどうだったのか。不確かな情報をなぜチェックできなかったのか。改めてきちんとした検証記事が必要だ。
日本でも、二十三年前の昭和五十七年夏、旧文部省の検定で教科書の記述が「侵略」から「進出」に書き換えられたと、新聞やテレビが一斉に誤報する事件が起きた。この報道をきっかけに、中国と韓国が日本の教科書検定を批判し、外交問題に発展した。
その結果、中韓両国に過度に配慮した検定基準「近隣諸国条項」が追加され、教科書に自虐的な記述が増えた。今回のニューズウィーク誌の誤報とは違った意味で、重大な過ちを犯したといわなければならない。
産経は同年九月七、八日付で、「読者に深くおわびします」「発端はマスコミの誤報からだった」とする謝罪記事を掲載し、誤報の経過も詳しく報じた。これ
に対し朝日は、「『侵略』→『進出』今回はなし」「問題は文部省の検定姿勢に」とし、毎日も「本質を見失わず」と同じように論点をすり替えた釈明記事を載
せた。他のほとんどのマスコミは誤報を黙殺した。
誤報は大きく分けて、記事に書かれた当事者だけが傷つくケースと、国際問題化して国の名誉、国益まで損なわれるケースとがある。教科書誤報事件と今回の米誌誤報は後者だ。本紙を含め日本のマスコミは、今回の事件を他山の石としなければならない。
■【主張】景気動向 デフレ脱出の詰め誤るな
景気の足取りが確かなものになりつつある。平成十七年一−三月期の国内総生産(GDP)成長率は物価の影響を除いた実質ベースで、昨年十−十二月期に比
べて年率5%を超える高い伸びとなった。発表がピークを迎えている上場企業の十七年三月期決算をみても、経常利益は過去最高を更新する勢いだ。
昨年後半から今年初めにかけ、経済状況を示す指標が強弱混在するなど、景気は「踊り場」に入っていた。その後再離陸するのか、マイナスに向かうのかが議論されたが、上昇局面に入る公算が大きくなったといえる。
実質成長率が名目成長率を依然上回るなど、物価下落傾向は続いているものの、日本経済の積年の課題であるデフレ解消は大詰めを迎えた。
その意味で、カギとなる個人消費の伸びは心強い。これは、昨年十−十二月期に台風や地震など相次ぐ自然災害で消費不振に陥った反動増だけとはいえない。企業のリストラ一辺倒だった姿勢の変化が、雇用の改善や賃金増につながり、消費に跳ね返っているのは確かなのだ。
好業績を受けて増配や復配に踏み切る企業が続出しているのも先行きプラス材料といえる。ライブドア問題を経て、手元に現金を多く置き、株価が割安な企業
は買収の標的になりやすいという上場企業の危機感を背景にした現象であるのは間違いない。それでも企業利益が配当という形で家計部門にも回り、消費拡大の
一因となる。
こうした状況で重要になるのは、財政難、年金問題に代表される国民に根強い先行き不安感の解消だ。負担が増えるのはやむを得ないだけに、制度の将来像を可能な限り具体的に提示することが急務となる。それがなければ、消費は萎縮(いしゅく)したままである。
十九、二十の両日には日銀の金融政策決定会合が開かれる。市場の関心は、日銀が、量的緩和策の中心である当座預金残高目標を変更するかどうかに集まって
いる。金融機関の資金需要が落ち着いた今、実情に即した対応までは否定しないが、量的緩和の維持を強くアピールしなければ、市場で思わぬ反作用をもたらし
かねない。
デフレの脱出口が見える今だからこそ、政府も日銀も詰めを誤ってはならない。
|