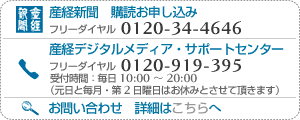|
平成16(2004)年9月17日[金]
|
 以前の主張
【全国紙の社説】
以前の主張
【全国紙の社説】
 朝日新聞
朝日新聞
 読売新聞
読売新聞
 毎日新聞
毎日新聞
 日本経済新聞
日本経済新聞
■【主張】パウエル発言 国家の「脅威」は排除した
パウエル米国務長官が上院公聴会で発言したイラクの大量破壊兵器をめぐる問題で、米国が今後の捜索を断念したかのように受け取られている。しかし、国務
長官発言には「断念」するとの表明はどこにもなく、イラク戦争に反対する野党や一部マスコミが「開戦の根拠」を否定するために、あたかも米国が断念したよ
うに曲解している。
パウエル長官は米国がイラク攻撃の理由の一つにあげた大量破壊兵器について、「いかなる備蓄も見つからず、今後も発見される見通しは少ないだろう」とし
か述べていない。この発言からでも、「断念した」と解釈することには無理がある。さらにいえば、パウエル長官がその数日前の米テレビインタビューで、「ま
だ見つかる余地がある」と述べているからである。
米政府はすでに核兵器、生物・化学兵器など大量破壊兵器の備蓄が発見できなかったことは認めている。わずかな量で大量殺戮(さつりく)が可能な化学兵器
を、広大な砂漠から発見するのは至難の業である。しかし、フセイン政権下のイラクに大量破壊兵器の施設、人材、技術があったことは実証ずみだ。
フセイン政権は一九八〇年代から、核兵器の入手を模索してきた。実際に、イランや国内のクルド人に対して平然と化学兵器を使用している。九五年には、大統領の娘婿であるカーメル中将が亡命して核開発計画が発覚すると、査察そのものを拒絶した。
米英など主要国は、フセイン政権が湾岸戦争後の十二年間に、十七にのぼる国連決議を無視し続けてきた以上、政権打倒しかないと判断した。大量破壊兵器の問題は、開戦理由の一つでしかない。
「イラク戦争」そのものは、米軍がフセインの抑圧体制を倒し、リビアなどの核開発の野心を打ち砕くことに成功した。しかし「戦後の処理」は、当初計画か
らそれたのは事実である。治安を確保するために必要な兵力の投入がなかったために、シリア、イラン国境からの外国人テロリストの侵入を許してしまった。
テロ撲滅はまだ達成できないが、少なくともイラクという独裁国家の脅威は除かれたのだ。今後のイラク復興を目指すのであれば、テロを封じる知恵と兵力を結集すべきなのである。
■【主張】長崎小6殺人 親に反省促す家裁の決定
長崎県佐世保市の小六同級生殺害事件で、長崎家裁佐世保支部は十一歳の加害女児を児童自立支援施設に送り、二年間の強制措置を受けさせる保護処分を決定した。現行法上で考えられる最も厳しい処分で、妥当な決定といえる。
家裁支部の決定は、加害女児の家庭環境にかなり踏み込み、女児の内面を描き出している。女児は両親には「手がかからない子」に映っていたが、それは怒り
や寂しさを表現できないことの裏返しであり、ホラー小説などの影響もあって、攻撃的な自我を肥大化させていったとしている。
「いい子」といわれる子供でも、育て方によっては、道を誤る危険性を示している。この決定文を読んで、わが家も思い当たる節があると感じた親も多かったのではないか。
決定はその上で、女児の両親に「情緒的な働きかけが足りなかった」「問題性を見過ごしてきた」などと反省を求めている。審判や女児の精神鑑定で得られた事実も十分に盛り込まれた。事件の解明と再発防止のためにも参考になる内容である。
被害女児の父親も手記を発表した。自分が子供同士のもめごとに気づかなかったことを反省しながら、「子供のすべては理解できないと分かった上で、理解する努力を続けてください」と親たちに呼びかけている。
さらに、自分の職業である新聞記者としての取材経験から、「先生が怒れば、子供たちは震え上がる。それでも子供たちと先生はお互いを信頼している。そん
なクラスの先生は笑顔も素敵で、先生という仕事を心の底から楽しんでいる」と書いている。子供に迎合する風潮が強い最近の学校の先生たちには、耳の痛い言
葉だろう。
十四歳の少年による神戸市の児童連続殺傷事件(平成九年)以来、少年事件の凶悪化・低年齢化は歯止めがかかっていない。昨年も、同じ長崎県で十二歳の中
学生が四歳の男児を殺害するという衝撃的な事件が起きた。これに伴い法務省は、十四歳未満で罪を犯した「触法少年」を児童自立支援施設より厳しい少年院へ
の収容を可能とする法改正を検討している。
少年事件の沈静化には、親や先生の意識改革に加え、厳罰化に向けた法整備も急がれる。
|