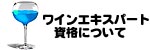
順次項目を追加していきます。
このコーナーは、私が99年にワインエキスパートの資格を取得した際の体験記です。今では情報の中身が古くなっていたり、現在の認定試験の内容にそぐわないものもあるかと思いますが、今後の改訂やアップデートの予定はありません。したがって、これから受験しようという方は、ここに書かれた内容があくまで99年当時のものであるということをご認識の上、必ず最新の情報を参照するようにしてください。
<受験のきっかけ>
「ワインエキスパート」資格をとろうと思い立ったきっかけは、かなりなりゆきに近いものがあります。年来のワイン好きが興じて、一度系統的にワインを「勉強」したいと思い立ったのが、98年の9月頃。そこで「ワインの学校、ワインの資格」という雑誌のような本を買ってきて、いろいろと調べ、会社から近いワインスクール何軒かに電話してみました。ところが当時はブームのピークだったこともあり、すべて満員。それで会社の帰りに行くことはあきらめて、週末に行けるところということで、家から比較的近い自由が丘にある某ワインスクールに電話したら、基礎講座が空いているとのこと。ということで、さっそく翌週からそのワインスクールに通うことにしたのでした。この時点では資格云々という気持ちは全くありませんでした。
ところが、いざ通い始めていると、講座は確かに基礎講座なんだけど、周囲には翌年の受験を目指しているらしき輩が少なからずいて、授業の中でも時折、「認定試験では云々」という下りが出てきたりして、それでいつのまにか私も興味を持つようになったのです。情けないことにあとで知ったのですが、そのワインスクールは資格試験対策の名門として有名なところであり、私はいわば中学受験する気もないのに四谷大塚に通 っていた小学生のようなものだったわけです。
とまあ、そんな環境下にいたので、年が明ける頃には私もいつのまにか周囲に感化されて認定試験を受験しようという気になっていました。ところが、当時は試験のことをよく知らなかったので、私でも「ソムリエ」の資格をとれるものとばかり思っていて、あとで受験資格の壁を知ってガックリきたのも事実です。(後述)
また、いざ勉強を始めていると、覚えなければならない項目のあまりの多さに目が回りそうになりましたし、受かってもどうせ「ソムリエ」の呼称を名乗れないのに、なんでこんな大変な勉強をしなければならないんだと、半ば自虐的な気持ちで勉強を続けた時期もありました。実際私の通っていたスクールは合格率90%以上を謳っていて、私の周りでも最後まで残っていた面々はほとんどみな受かったようですけど、反面夏頃を境にに来なくなってしまった人たちも結構いたような気がします。
まあ、そんなこんなで、周囲に吹聴してしまった手前、最後は半ば意地になって勉強を続けたようなもんですが、今では資格をとってよかったと思ってますし、ワインエキスパートの呼称がもっと一般的になってほしいとも願います。
<重要な覚え書き>
そういうわけで、私はたまたま資格を取得しましたが、巷のマニアの方々の中には私など及びもつかない知識や経験を持った方々がたくさんいます。また、経歴的にも以前からワインを飲んでこそいますが、本格的にワインに凝ったのは比較的最近なので、むしろこの世界では新参者に近い立場です。資格名どおりの「エキスパート」の域に達しているなどとはさらさら思っていませんし、これからも身の程をわきまえて謙虚にいきたいと思います。ちなみに私が「こんなワインを飲んだ」のコーナーで書いているコメントなども、決してプロの方々が雑誌や本に書いているようなレベルのものではありませんので、その辺はご了承ください。(^
^;
 A:99年認定分から、ワインアドバイザーと同様の銀色のブドウのバッジとなりました。その前のバッジは全く違った丸い形状のものだったのですが、評判が悪かったようですね。私はあれはあれで恰好良いと思ってたんですけど…。ちなみに夕刊フジの記事にもなっていましたが、当初送られてきたバッジが「Wine
Expart」となっていたのには空いた口がふさがりませんでした。(見出しは「ソムリエ協会赤っ恥」。)
A:99年認定分から、ワインアドバイザーと同様の銀色のブドウのバッジとなりました。その前のバッジは全く違った丸い形状のものだったのですが、評判が悪かったようですね。私はあれはあれで恰好良いと思ってたんですけど…。ちなみに夕刊フジの記事にもなっていましたが、当初送られてきたバッジが「Wine
Expart」となっていたのには空いた口がふさがりませんでした。(見出しは「ソムリエ協会赤っ恥」。)