(その3)疏水(そすい)~山科
・・・・・・池の出口の一つ、疏水を行きます・・・・・・
行った日 : 2021年10月15日(金) 天気良好
(11月19日補足)
前回は琵琶湖疏水を大津から京都を目指して下り、山科盆地の北端
まで進みました。今回は京都目指して疏水を追求していきます。
1.東海道線が見える疏水
前回は、諸羽(もろは)トンネル東側の四ノ宮(しのみや)船溜まりで
終えたのでした↓ここからは、まずトンネル上部の諸羽山を南に回り
込み、西出口を目指します。

四ノ宮船溜まり↑


埋め立て後の旧水路跡↑ 旧水路付近から見えるJR線↑
当初、疏水は諸羽山の南山麓沿いに作られたが、国鉄東海道
線の複々線化と湖西線の新設に伴い、疏水の流路を変更する
ため、諸羽トンネルが作られた(1970年完成)。


遊歩道になった旧水路↑ 井戸のような物。何?↑


ここでも「コロナ」の文字がそこら中に。

諸羽トンネル西口↑ 船を止める広さがある。
水中の白線は船のコースを示しているのでしょう。
トンネルは後の時代に追加で作られたためか「扁額(へんがく)」
は付けられず、「第一、第二、第三トンネル」とも呼ばれません。


東口が見える。↑トンネルの長さは520m。 西方向を見る↑
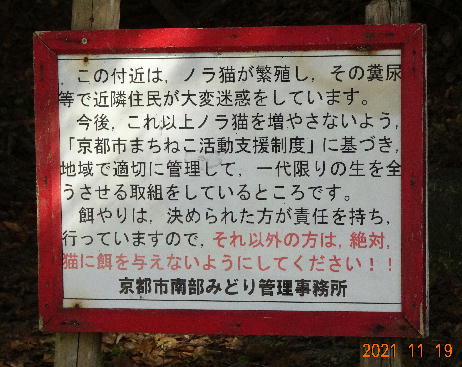

「京都市まちねこ活動支援制度」↑


安朱(あんしゅ)橋(11月撮影)↑ ↑トイレが遠い
安朱橋は観光ガイドによく出てきます。北に徒歩10分で天台宗
門跡の毘沙門堂へ、南へ徒歩10分で山科駅へという具合。
2.水路の立体交差
安朱橋に続き安朱西橋を通過すると、川と交差する箇所に来ます。
つまり疏水の下を川が通っているのです。北から流れてくる安祥寺
川(あんしょうじがわ)を疏水が越しているのです。
さあて、その仕組みは?


安祥寺川(北から流れ来る)↑ 同(南へ流れる)↑
北側へ渡って確認。


疏水の下に潜って南へ↑ フェンスは疏水沿いの物
レンガ造りで相当に古そう。疏水の当初の物と分かる。上段のレン
ガが水路でこの高さを疏水が流れ、下段が川をまたぐ橋なのだろう。
※ 近くの説明板によると「安祥寺川は改修により水の流れを変
え、川をまたぐ煉瓦造りのアーチ橋を築くことで1887年河川の
上を運河が流れる立体交差が生まれたのである。」


安祥寺川上流からの流れ↑
右奥上方に管理棟らしき複数の建物。「京都市上下水道
安朱測水所」とあるので第2疏水の管理施設と想像できる。
つまり、第1疏水の北方約100mに第2疏水が流れているらしい。


洛東高校校舎(東から見て)↑ 正面は洛東橋、校舎↑
洛東高校は、疏水の北側に校舎、南側にグラウンドを持っている。
通学はグラウンド沿いの専用通路を通り、疏水の水面を見ながら
洛東橋を渡り校舎に入る。


安祥寺↑ 安祥寺前の橋から西方を望む↑
848年創建の安祥寺。平安時代は広大な寺域を持つ大寺院だった
そうです。
3.展望広場から天皇陵北側へ
疏水は南へ大きくカーブし、山科盆地へ少し突きだした形になる。


流れる草?の切れ端↑ 展望広場、山科盆地が一望↑
草刈りでもやっているのでしょうか?ずーっと切れ端らしきものが
流れています。南側が開け、山科の市街や山並みが一望できます。
JR東海道線や琵琶湖線に頻繁に電車が通過していくのが見えます。

鉄ちゃん界では有名な「山科大カーブ」↑
カーブといい高さといいSL時代からの有名撮影地だということです。


天智天皇陵(宮内庁の管轄)の北側と接している↑
陵は地図を見ると、南北約700m、東西約300mとけっこう広い。


正嫡橋↑ ここを登ると加藤清正ゆかりの本国寺がある。


憩(いこ)いの一時(ひととき)↑ 定番三点セット↑


山ノ谷橋↑ 奥に見えるのはトンネルか?↑
山ノ谷橋から山手(右方面)へ行くとハイキングコースの山道に
なっており、終点の岡崎に通じるようだ。
4.二つのトンネル
琵琶湖から、第1トンネル、諸羽トンネルを見て来たが、次は第2
トンネル、第3トンネルと続きます。

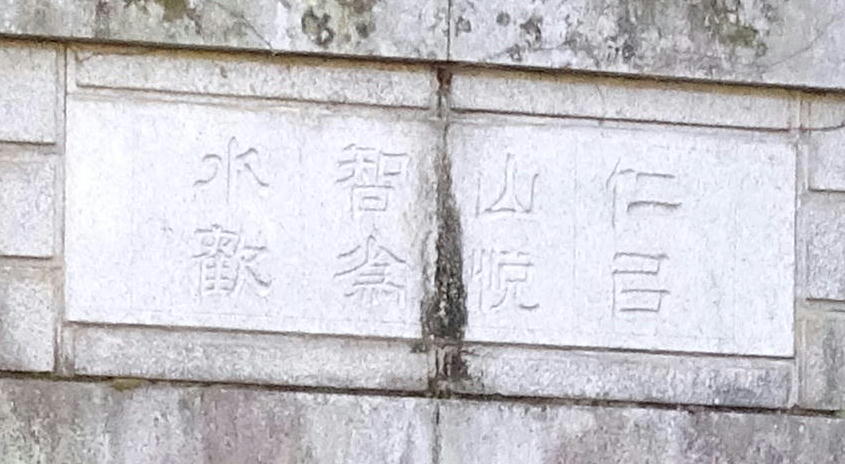
第2トンネル東口↑ 扁額「仁以山悦智為水歓」↑
書き方、読み方が難しい。額のとおり並べると、
水 智 山 仁
歓 為 悦 以
読み方:じんはやまをもってよろこびちはみずのためによろこぶ
意味:「仁者は知識を尊び、知者は水の流れをみて心の糧とす
る(論語)」とのこと。漢字は書体の違いもあってなかなか難しい。
揮毫者:井上馨
トンネルの中、入り口すぐの銘板を書き写すと、「名称 琵琶湖
第1疏水第2トンネル、延長 125m、断面 馬蹄型、竣工 明治
20年12月30日、改修 昭和49年5月31日、京都市水道局」
とある。


トンネル内部↑ 右側に銘板が見える。 東(上流)方面↑


第2トンネルの南側から進む↑ 住宅街↑
トンネルの南側には住宅が広がる。地名は日ノ岡 東山台町。


宅正面の坂道を登って行く↑ 児童公園があった↑


第2トンネル西口↑ 扁額「随山到水源」↑
扁額は、
読み方:やまにしたがいすいげんにいたる
意味:山にそって行くと水源にたどりつく
揮毫者:西郷従道
トンネルが正面から撮れていなーい。低い柵をヒョイと越せば
行けたのに、根性が足りなーい。やはり公家の出かな?


低い柵と高い柵↑ 坂になっている住宅街↑

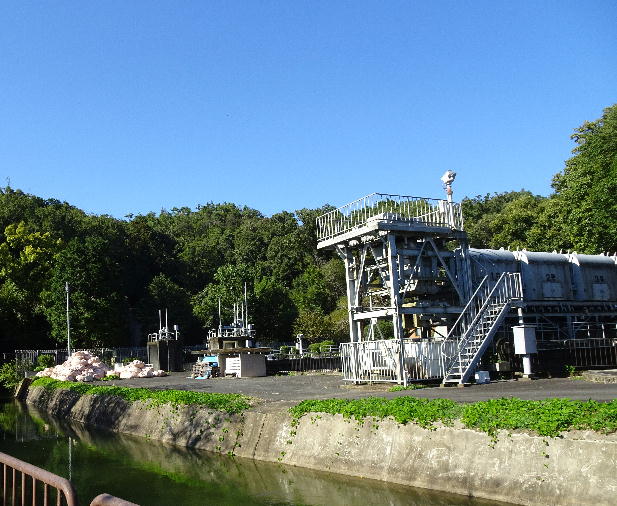
新山科浄水場取水池↑
水の利用が増えたため、1970年に「新山科浄水場」を作ること
になりました。ここがそのための取水池です。浄水場は約5km
南に作られたとのことです。


第11号橋↑ 「国指定史跡」のせいか?石碑も立っている↑
「日本最初の鉄筋コンクリート橋」の石碑が立っているこの橋、
1903年建造ですが、これには裏話があるようです。実はこの橋
は試験的に作られたもので、トロッコの鉄骨などで代用しセメント
も試験用のものだという。現在では鉄骨で補強し当時の面影は
なく、石碑も新設されたものという。
3.のところで述べた「山ノ谷橋」(黒岩橋)こそ日本最初の本格的
な鉄筋コンクリート橋だというのである。
(参考 ONLINE MAGAZINE Roof-net www.roof-net/
index.php?)

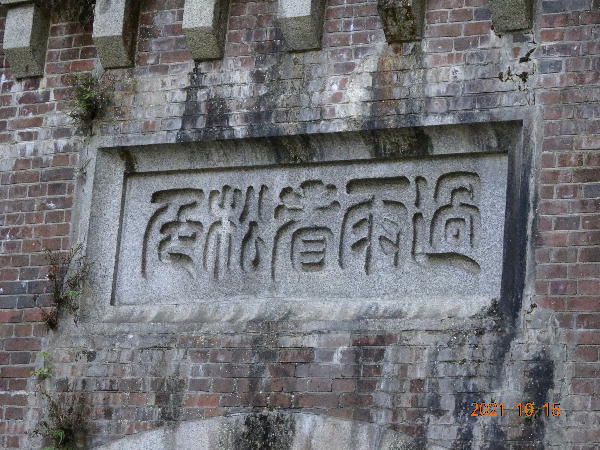
第3トンネル東口↑ 扁額「過雨看松色」↑
読み方:かうしょうしょくをみる
意味:時雨が過ぎるといちだんと鮮やかな松の緑をみることが
できる(唐・盧綸の詩)
揮毫者:松方正義
以上、書くことが次々出てきて切りがないので、
ここでマウスを置きます。
次回はいよいよ見せ場の多い岡崎へ進み、一区切りとなります。

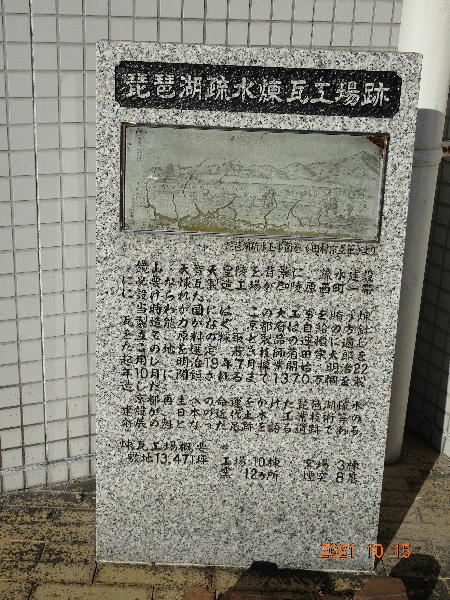
三条通りに面するビルの前にある
「琵琶湖疏水煉瓦工場跡」の碑
下方の黒い物が煉瓦の実物らしい。
「当時のわが国には、
この大工事を賄う煉瓦製造能力がなく、
京都府は自給の方針を立て、・・・・・
この地を選定・・・・・1370万個を製した。・・・・・」