(その2)疏水(そすい)~大津
・・・・・・池の出口の一つ、疏水を行きます・・・・・・
行った日 : 2020年10月15日(木) 天気良好
2021年3月26日(水) 天気良好
(季節違いですが合わせてまとめます)
前回は琵琶湖の沿岸をウロウロしました。今回はいよいよ琵琶湖の
出口の一つである疏水を追求していきます。
1.浜大津から始まる琵琶湖疏水
向こうの方にある琵琶湖から水を取り入れて疏水が始まります。↓
写真は琵琶湖第一疏水の取り入れ口で、ヨットなどが停泊しているのが
見えます。疏水は手前の橋の下をくぐって南西方向へ伸びていきます。

左下の小屋は三保ヶ崎水位観測所で琵琶湖の水位を測っています。↑
北側の第二疏水は取水口からほとんどトンネルになっているので
追求せず、南側の第一疏水を追求していきます。ポイントは○P印の
揚水機場、●印の大津閘門、◯印のトンネル入り口です。↑

まず県道558号の橋をくぐると3つ水門(取水口)を持つ、琵琶湖第一
揚水機場が見え、左側に水路があります。
[琵琶湖第一疏水揚水機場]
この揚水機場の目的は、琵琶湖の水位が下がり過ぎたときに、疏水へ
ポンプで水をくみ上げて、京都へ送れなくなるのを防ぐためです。
この操作は1994年の大渇水のときに一度行われています。
(左の水路は当然、流れないようにゲートで閉められます)
さらに数十m下った水路。この形・大きさで続くのでしょう。


京阪石山坂本線付近の疏水水路と鉄橋↑
さらに200mほど下ると大津閘門(こうもん)と制水門があります。
本来は琵琶湖と疏水との間を船が通い、琵琶湖と疏水の水位差を
調節して船を通す閘門という施設ですが、1948年に廃止され門だけ
は残しているとのこと。スエズ運河などと同じ目的の施設です。


左が大津閘門、右は疏水に水を取り込む制水門↑
閘門の使用中は制水門で水位調節をするのだが、船を通す目的が
なくなった現在、水だけを取り入れている。ゴミ取り装置は現在も活躍中。


さらに続く疏水と水路脇の道路(両岸沿いにある)↑
第一疏水の大津側末端には、第1トンネルの入り口があり、立派な
扉が付いている。この扉は曰(いわ)く付きの水争いの気配のする扉
と見られているが詳細は省略。なお疏水のトンネル各入り口には
「扁額」(へんがく)が取り付けられているが、ここには明治維新
の中心人物、伊藤博文の揮毫(きごう)が飾られている。

第1トンネル入り口 門扉の意味は?↑

伊藤博文揮毫「氣象萬千」(きしょうばんせん)で意味は、様々に変化
する風光はすばらしい、とのこと。↑
疏水は長等(ながら)神社や三井寺に近い長等山の直前でトンネル
となり、山科盆地・京都へ向かうのです。
2.トンネルになり山科へ
行った日 : 2021年3月26日(水) 天気良好
ここからは、流行のコロナの中、写真撮りに出かけたのです。もちろん
春真っ盛りの世の中ですので、桜を求めて観光客・ハイキングがあふ
れていました。山の中だろうがそれなりに人が歩いていました。
実はトンネルから住宅街→山道→トンネル出口のコースを予定して
いたのですが、車で突破を試みたものの一方通行や季節柄のせい
か山道は行けませんでした。(3回アタックしたけど)
仕方がないので車で出口付近のコンビニに行き、そこを基地にして
歩きで写真撮りを開始したのです。(以下写真の順と歩きの順は一致
しておりやせん)


小関越↑ ここから細い坂道へ 山には大きな桜が↑
ハイクの人が同じ方向へ進みます。桜も並木より山の中の方が迫力。


金網のフェンスと看板 深さ50mの第1竪坑(たてこう)↑
[難航する竪坑掘削 1日20cm]
竪坑は地表から下げた坑道で、工事中の換気や明かり取り土砂出し
のために作られた。というのも当時は電力がなくカンテラの明かりで、
岩盤だったのであろう、255日かけてノミとハンマーによる「手堀り」
で50m掘り進んだ。そしてこの竪坑が完成してからトンネル工事に
着手したとのことである。「先人の苦労が偲(しの)ばれる」とは正に
このことを言うのだろう。


資材置き場などが数カ所↑ 竹林が多い坂道↑
坂道だがそれほど急ではない。しかし、膝にヒアルロン酸を打ってる
時期だったので超スローペースで進んだ。


普門寺付近:国道161号線の高架が見え、その下付近に祠(ほこら)
がある。国道は北は坂本付近の湖岸に抜け、滋賀県西部の幹線道
路になっている。↑
以下、右手に住宅街を見ながらトンネルは南西方向に進んでいるは
ずである。なお、その住宅街には、工事中の換気などを目的にした
第2竪坑が地表に出ているはずであるが、住宅地のため姿は直接
見られないらしい。
3.疏水沿いに進む
住宅街から外れたところにコンビニがあるので休憩した。なお今回、
ここを前線基地として駐車、食料調達、休養のため、大いに利用させ
てもらった。探検にしろ進駐にしろ補給が大事なのは言うまでもない。


広い駐車場(気兼ねなく利用)↑ 定例のサンド+おにぎり+茶↑
疏水のトンネル出口はすぐ近所である。


左:第1トンネル西口↑
残念ながら正面から撮れず。扁額は山県有朋揮毫の「廓其有容」
(かくとしてそれいるることあり)で意味は、疏水をたたえる大地は
奥深く広々としている、とのこと。


左:緊急遮断ゲート↑ 右:藤尾橋↑
左:このゲートは、1995年の阪神淡路の震災を受け、地震が起きて
堤防が壊れる恐れがあるときに自動的に水流を止める装置らしい。
右:見えにくいが橋の土台だけがレンガ+石組みで、1888年に作られ、
疏水では第1号の橋とのこと。


左:測水橋↑ 右:跨線橋(JRをまたぐ歩道)↑
[測水橋]
疏水の水位、流量を計る橋。実は第1疏水(この水路)の北側に
第2疏水が流れているのだが、現在ではフタがされ暗渠(あんきょ)
になっているが、かつてはフタをせず開渠(かいきょ)だった。橋は
両方の疏水を跨(また)ぎ、水位や流量を計っていた。

跨線橋(JRをまたぐ歩道)から↑湖西線と琵琶湖線(東海道本線)。
写真は京都方面。右側に疏水の桜が見える。

びわ湖疏水船(1日最大7便、最高8,000円也)↑
偶然だった。急いでシャッターを。波はそれほどない。

洛東用水取水口 ここから疏水の水をとります↑
[洛東用水]
疏水の3ヶ所から農業用水が山科盆地に供給されています。その内
の一番東側の用水路がこの洛東用水で、盆地の東側を南に向かっ
て流されます。


同じく横から見た所↑ 道路の下をくぐって隣の川に流入する↑
ここでよく分からないのですが、用水路は「四ノ宮川、東海道線をサ
イホンでくぐって」と説明されています。構造が理解できないので宿
題ですね。

疏水の両岸は桜並木に↑


四ノ宮舟だまり:東から↑ 西のトンネルの上から↑
[舟溜り]
琵琶湖疏水には大津から蹴上(けあげ)までに3ヶ所の舟溜りがある。
これは舟運のための施設であり、当時の鉄道は東海道線が1880年
頃にこの辺りに開通したばかりであったので、疏水は物資の輸送も
大目的の一つであった。舟溜りは舟を引く人夫の休憩所と、物資や
乗客の上げ下ろしの場所として使われた。

諸羽トンネル(東側入り口)↑
[諸羽トンネル]
このトンネルには扁額(へんがく)がない。実は、トンネル
の掘削が1970年だったのである。当初は山裾(やますそ)
を回っていた水路だが、1966年に工事に着手した国鉄
(JR)湖西線と疏水の水路が接近することになるので、
直線水路すなわちトンネルに付け替えたためとのこと。
今回はこれで筆(マウス)を置きます。
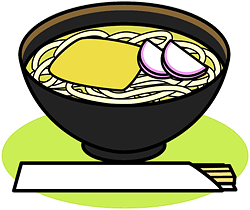

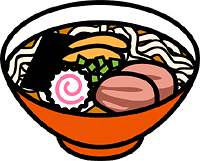
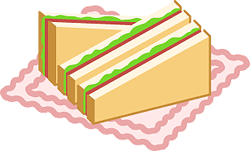
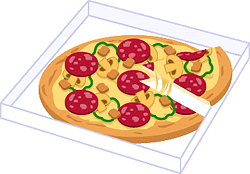


参考
◯「京滋 琵琶湖第1疏水散歩 そのⅠ︔滋賀・琵琶湖の
大津取水口から山科盆地を経て京都・蹴上まで琵琶湖
第1疏水を辿る」~時空散歩
http://yoyochichi.sakura.ne.jp/yochiyochi/2015/03/-1-1-1.html
※ ほぼ全面的に参考にさせていただいた。「そのⅡ」も同様。
◯「琵琶湖疏水 ~ 扁額に想う」
https://www.okeihan.net/recommend/mizunomichi/biwakososui/01/hengaku.php
※ 扁額についてやさしく、詳しく書いてある。