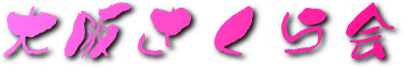
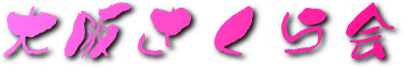
| 2006年6月例会 |
| 6月6日 全国に広がるよさこいパワー | |||
 ■5月例会がずれ込んだというべきか、中断して6月例会に飛んだというべきか、6月6日に大阪さくら会の例会が開催された(岡さんからの案内状には「大阪さくら会5(6)月例会のご案内」という苦しまぎれのタイトルが踊っていた)。 ■5月例会がずれ込んだというべきか、中断して6月例会に飛んだというべきか、6月6日に大阪さくら会の例会が開催された(岡さんからの案内状には「大阪さくら会5(6)月例会のご案内」という苦しまぎれのタイトルが踊っていた)。■今回のテーマは「よさこい祭りは何故全国に広まっていくのか!」。講師は、ナント本場の高知から、しかも手弁当でかけつけて頂いた山村貴也さん。本業の配管工事業の傍ら、自らよさこいチームを率いて歌手としても大活躍する人物である。 高知の呑屋で意気投合したという井上代表幹事とは2度程のおつきあいとのこと。それにしても、たったそれだけつきあいで、わざわざ大阪まで来てもらってしまう井上マジックの凄さと、それに応じた土佐いごっそうの心意気に驚くばかりである。 井上さんの講師紹介の後の、スピーチに入る直前だった。絶妙のタイミングで講師の携帯が発信音を鳴り響かせた。「高知の呑屋からや」。思わず洩れた講師の呟きが、はからずも彼の夜のネットワークの幅広さを物語っていた。 ■「高知の呑屋で初めて井上さんにお会いし、一緒に呑みました。酔った勢いで今回お邪魔することになりました。よさこいの素晴らしさをお話しできる機会に感謝しています」。よさこいを愛してやまない山村さんの飾り気のない、情熱に溢れたスピーチが始まった。 以下はスピーチの概要である。 ・「よさこい」とは、土佐弁で「夜に来てください」という意味 ・「よさこい祭り」は、高知にも徳島の阿波踊りに負けない祭りをということで、昭和29年に「市民祭」と「商店街活性化」の趣旨からスタートした ・県在住の作曲家である武政英策氏が作詞作曲し、日本舞踊五流派のお師匠さんたちが振付し、リズム楽器に高知の田畑で雀追いに使われた鳴子を採用して、「ヨッチョレヨ、ヨッチョレヨ」の軽快なリズムの「正調よさこい鳴子踊り」が完成した ・「正調踊り」はすぐに「わが道を行く高知人気質」にかき消され、様々にアレンジするチームが増え続け現在に至っている  ・昭和34年に大ヒットしたペギー葉山の「南国土佐をあとにして」の映画化で鳴子躍りの大群舞が収録されたことから全国的に知られることになった ・昭和34年に大ヒットしたペギー葉山の「南国土佐をあとにして」の映画化で鳴子躍りの大群舞が収録されたことから全国的に知られることになった・現在、全国222ヶ所で「よさこい」が開催され、推定40万人の愛好者がいる(公式に把握できていない) ・よさこいの魅力は、以下のような点にある ①<鳴子> 親しみのあるリズム感のある鳴子。今やチームのテーマに合わせて色、材質、形に至るまで様々にアレンジされている。 ②<衣装> 自由度の高いよさこい祭りの衣装は、当初の浴衣姿から、現在はハッピ姿が多くなり、エスニック風、ロック風、時代劇風など色もデザインも様々なバリエーションを増やしている。 ③<音楽> 正調踊りの作詞作曲の武政氏が著作権を放棄したことで、よさこい節をベースにしながらも各地の民謡を取り入れたり、ロック調、サンバ調などにアレンジし、より親しみのある音楽をベースにできるようになった ④<地方車(じかたしゃ)> 地方車はチームのシンボルとしてチームを先導する装飾を施したトラック。荷台には音響機材が設置されライブステージにも早変わりする。 ・自由度の高いよさこい祭りにも4つのルールがある。 「鳴子を持った踊り表現」「地方車と踊り子のセットで編成」「4列編成の前進する踊り」「40人以上150人以下の踊り子人数」 ・YOSAKOIの波を全国に波及させた最初の開催地が札幌である。今や札幌のYOSAKOIソーラン祭りの参加チーム数は、高知のよさこい祭りの倍以上になり爆発的に成長を続けている。今年は334チーム、約4.3万人、観客動員214万人の規模である。 ■最期に山村さんから、若い頃からよさこいに参加し、チームを率いてきた経験に照らした以下のようなコメントがあった。 「若者たちによさこいチームの中心スタッフとしてぜひ関わって欲しい。申請業務等の準備期間中の事務処理、踊り子募集  、作詞作曲者や振付担当との打合せ、衣装のデザインと発注、資金集めと予算管理、踊りの練習と隊列編成の調整、地方車のデザインと装飾作成、バス・救護車手配、飲食手配とゴミ処理等、わずか半年の間にこれほどの煩雑で集中力と責任感の必要な業務をこなす機会は他にないと思う。様々のトラブルを処理しながら仲間意識が芽生え、本番を迎えて爆発する。踊りきった後の集団としての達成感は何物にも代えがたい。多くのチームとの競い合いの中で、悔しさと嬉しさ、反省と満足が混在した達成感に満たされる。こんな機会はどこにあるだろうか。若者たちに味わって貰いたい貴重な 、作詞作曲者や振付担当との打合せ、衣装のデザインと発注、資金集めと予算管理、踊りの練習と隊列編成の調整、地方車のデザインと装飾作成、バス・救護車手配、飲食手配とゴミ処理等、わずか半年の間にこれほどの煩雑で集中力と責任感の必要な業務をこなす機会は他にないと思う。様々のトラブルを処理しながら仲間意識が芽生え、本番を迎えて爆発する。踊りきった後の集団としての達成感は何物にも代えがたい。多くのチームとの競い合いの中で、悔しさと嬉しさ、反省と満足が混在した達成感に満たされる。こんな機会はどこにあるだろうか。若者たちに味わって貰いたい貴重な 経験の場がよさこいだと確信している。」 経験の場がよさこいだと確信している。」■私の身近なところにも、よさこいに嵌っている知人いて、よさこい自体は知らなかったわけではない。イベントで目にしたよさこい踊りもインパクトのあるものだった。今回の例会で初めてよさこいの魅力とエネルギーの源に触れたように思う。 自由な表現力と創造性、仲間たちとの連帯感と一体感、共通目標に向けた共同作業などの多様な要素がよさこいに込められている。それこそが若者たちが求めており、今日の日本に欠けているものなのだろう。 マイクロソフトのWindowsの寡占的なOSに飽き足らない若者たちが、LinuxリナックスというオープンなOSを創造し、多くのスペシャリストが自由に関わりながらどんどん進化している。山村さんのスピーチを聞きながら、よさこいがLinuxに何故かオーバーラップしていた。「鳴子文化圏」が国内だけでなく、国際的にも広がりを見せるのだろうか。 |
|||
 |
|||
| ■会食が始まり、やなぎ店長から本日のお品書きが告げられる。今回のテーマは「山里の料理」。お酒は飛騨の銘酒「長良川」である(しもた!画像を撮り忘れた)。お料理は「お刺身盛合せ(まぐろ、鱧おとし)①」「焼き鮎②」「酢の物③」「めかぶ豆腐④」「鶏と大根の味噌煮⑤」「万願寺唐辛子網焼き⑥」「お漬物盛合せ⑦」と続く。いつもの「大皿仕上げ蕎麦⑧」で腹ごしらえの後、「わらびもち⑨」のデザートで締め。 | |||
 |
|||
 ■今回の初参加者は、高橋さん紹介の㈱エム・アール・エスの上出さんと㈱テツタニの浅見さん、しして谷山さん紹介の西日本東芝エルイーシステム㈱の橋本さんの3名だった。(左画像順) ■今回の初参加者は、高橋さん紹介の㈱エム・アール・エスの上出さんと㈱テツタニの浅見さん、しして谷山さん紹介の西日本東芝エルイーシステム㈱の橋本さんの3名だった。(左画像順)■今回の参加者は、川島、井上、岸、岡、日高、森、高橋、北村、谷山、三浦、筧田、浦濱、岡山、家入、新屋、木下(康)、川畑、上出、浅見、橋本の20名の皆さんだった。アッ忘れるとこやった。スピーチ終了後の宴たけなわの頃に、アノ忘年会男の川原さんにも駆けつけてもらって21名の参加者だった。 |