| 2002年6月 |
| 2002年6月 |
| 6月9日(日) 浪花道しるべ 文楽紀行 |
  ■6月初め、知人から文楽の割引チケットが送られてきた。国立文楽劇場の「夏休み特別公演」だ。4月に京都南座で歌舞伎鑑賞教室を堪能して以来、伝統芸能とその上演劇場の建築様式が気になりだした。 ■6月初め、知人から文楽の割引チケットが送られてきた。国立文楽劇場の「夏休み特別公演」だ。4月に京都南座で歌舞伎鑑賞教室を堪能して以来、伝統芸能とその上演劇場の建築様式が気になりだした。それにしても夏休みはまだまだ先の話。そこでインターネットの「国立文楽劇場公演」を検索。あった!あった!文楽鑑賞教室(左のチラシ)が6月5日から始まっている。 次の日曜日、行ってみよう。妻を誘う。およそ伝統芸能には無縁の人と思っていた妻が思いのほか乗り気。間際の電話予約も無事完了。この際、近くの黒門市場や法善寺など見所スポットも訪ねてみよう。 ■そんな訳で6月9日朝10時過ぎ、ご夫妻は黒門市場の中にいた。つい先頃までNHK朝の連ドラ「ほんまもん」の舞台ともなった街である。開店直後の筈だが、開店している店も買い物客もまばら。「ほんまもん」の活気には程遠い。全体のイメージもどこにでもある商店街風でがっかり。 |
  ■国立文楽劇場は、黒門市場と千日前通りを挟んで斜め向かいにある。 ■国立文楽劇場は、黒門市場と千日前通りを挟んで斜め向かいにある。建物の前を阪神高速の無粋なコンクリートが覆う。黒川紀章設計になる劇場は、上方伝統芸能の拠点に相応しいお洒落で風格のある外観である。 ■10時30分、正面玄関を入るとチケット売場には何人かの行列。1人3600円の鑑賞券を求める。外国人観光客の姿も目につく。サッカー応援を兼ねての来阪か。 1階ロビーには展示室が開放されている。文楽の歴史に始まり様々の資料、文献、ジオラマ、小道具、首(カシラ)、人形等が展示されている。これから始まる文楽の世界に浸る前の予備知識を吸収しながら、いやがうえにも期待が膨らまされる仕掛けになっている。 ■2階の客席に向う。入場口を入るとプログラム代わりに2冊の小冊子が渡される。「文楽入門用の 解説書」と、今日の演目である「曽根崎心中」の漫画版ストーリーである。鑑賞教室ならではの気遣いか。 客席ロビーでイヤホンガイドのレンタルがあった。何事も体験してみたい性分。400円の料金と1000円の保証金を支払いイヤホンと受信機を受け取る。 |
 ■座席番号を目当てに客席に入る。思ったほどには広くない劇場は1階席だけの753席。人形中心の舞台では広すぎる劇場では鑑賞に耐えられない。舞台の中に様々の仕掛けを持つ文楽は、上からの視線が可能な2階席は設置できない。 ■座席番号を目当てに客席に入る。思ったほどには広くない劇場は1階席だけの753席。人形中心の舞台では広すぎる劇場では鑑賞に耐えられない。舞台の中に様々の仕掛けを持つ文楽は、上からの視線が可能な2階席は設置できない。舞台上手(向って右手)には文楽専用の設備である「出語り床(ゆか)」がある。太夫と三味線の演奏席だ。 開演間近の客席はほぼ満席。開演直前、係員のアナウンス。「上演中の写真撮影は固くお断りします」。(ヤッパリ・・・残念!) ■11時開演。第1部は鑑賞教室ならではの舞台「解説・文楽を楽しむために」。  登場したのは若手の大夫。舞台から床に席を移した大夫から文楽のイロハを手解きしてもらうという趣向。 舞台正面の大型プロジェクターに本番中の大夫の映像が映し出される。遠目には分かり辛い手の動きなどがアップで映され、ハイテク装置も備えた伝統芸能劇場の威力を見せる。 床が回転し、三味線弾きが登場(右画像)。大夫と三味線弾きによる浄瑠璃のサワリが披露される。 舞台に戻って今度は人形遣いの舞台裏が紹介される。ナント文楽人形は3人で操られていたのだ。人形のカシラ、胴、右手を担当する「主遣い(おもづかい)」、左手担当の「左遣い」、両足担当の「足遣い」の3人だ。 なるほどこれは大変な技に違いない。3人で1つの人形を、1人の生きた人間のように動きや感情を表現しようというのだから・・・。3人の呼吸をピッタシ合わせるためには、指示者である主遣いの高度な技量に支えられた絶対的な権威が不可欠なのだろう。  ■10分間の休憩の後、床に大夫と三味線弾きの二人が登場し、いよいよ第2部の「曽根崎心中」の開演である。 ■10分間の休憩の後、床に大夫と三味線弾きの二人が登場し、いよいよ第2部の「曽根崎心中」の開演である。300年前に実際にあった若い男女の心中事件を題材にした近松門左衛門の代表作のひとつである。 ここからイヤホンガイドが始まる。作品の時代背景や、難解な用語の解説、舞台での見所などが、大夫の語りの合間を縫って見事なタイミングで解説される。これは間違いなく実況生放送に違いない。ところが帰宅後HPで知ったのだが事前の舞台稽古に合わせて作成された解説を録音し、上演時にはオペレーターが解説音を細かく操作して流しているという。 併せて舞台上の大型プロジェクターには、大夫の語りに合わせて台本の口語訳が次々の映され初心者にも分かりやすい。もっとも外国映画の字幕のような観がなきにしもあらず。 観客の中には双眼鏡持参の姿もあちこちに見られる。それほど広くはないとはいえ、人形の表情、手足の細かな表現はヤハリ遠目には見辛いものがある。双眼鏡はここぞという場面のポイントをフォーカスする上で強力な武器に違いない。 ■初めて見る本物の文楽。食い入るように見つめる。 大夫が背景説明、情景描写から、登場人物それぞれの台詞、心情まで1人何役もの役回りを見事に謡いあげる。日本の伝統芸能である落語、浪曲にも共通する1人語りの芸である。大夫は、腹の底から絞り出す腹式呼吸で朗々と謡う。長時間の腹式呼吸をサポートするための腹帯、オトシ(懐に入れ込むおもり)、尻ひきという独自の道具まである。 弾き語り風の抑えた音色、荒々しい撥(ばち)さばきから繰出されるダイナミックな響き・・・変幻自在の三味線の効果音が舞台を盛り上げる。 舞台では、お初、徳兵衛の主役二人(二体)を中心に、敵役の油屋九平次、天満屋主人等が絡み合い熱演する。人形一体に3人の人形遣いがついている舞台上では、文字 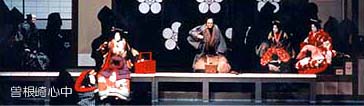 通り絡み合いなのだろう。主遣いだけは顔を出し羽織袴で生きた人間として出演している。左遣い、足遣いは黒頭巾に黒装束姿といういでたちでまさしく黒衣(くろこ)に徹する。 通り絡み合いなのだろう。主遣いだけは顔を出し羽織袴で生きた人間として出演している。左遣い、足遣いは黒頭巾に黒装束姿といういでたちでまさしく黒衣(くろこ)に徹する。■曽根崎心中は「生玉社前の段」「天満屋の段」「天神森の段」の三段で構成されている。 舞台は、心中を決意したお初、徳兵衛の道行きの場面に移り、いよいよクライマックスを迎える。「天神森の段」である。回転した盆床にはナント大夫4人、三味線4人もの多数が勢揃いし、大合唱、大合奏が場内に響き渡る。 背景の大道具が移動するという意表をついた大仕掛けで、二人の道行きが、展開される。突然飛び交う人魂の灯りも効果的。照明を落とした未明の闇夜の舞台に、お初の白装束が鮮やかに浮かびあがる。愛する男との死を喜ぶお初の心情が切々と語られ、それに合わせた人形の見事な演技が繰り広げられる。お初の生きているかと思うほどの艶めいた壮絶ですらある演技に息を呑む。 ■太夫、三味線弾き、人形遣いの織りなす見事な演劇空間。大仕掛けの舞台装置、舞台のリアリズムを演出する小道具の数々、艶やかな衣装に彩られた巧みな舞台効果。初めて見る「文楽」の世界は、数百年の伝統に支えられて積み上げられたきた総合芸術だった。「世界に類をみない究極の人形劇」の思いに浸りながら劇場を後にした。  ■舞台場面を自分のこのサイトに掲載したいと検索した。素晴らしいサイトが見つかった。読売新聞大阪本社のホームページ「YOMIURI ON−LINE 関西」にある「文楽への招待」というサイトである。このページの「床の回転」、「曽根崎心中」の画像は「文楽への招待」からパクらせて頂いた。 ■舞台場面を自分のこのサイトに掲載したいと検索した。素晴らしいサイトが見つかった。読売新聞大阪本社のホームページ「YOMIURI ON−LINE 関西」にある「文楽への招待」というサイトである。このページの「床の回転」、「曽根崎心中」の画像は「文楽への招待」からパクらせて頂いた。 |
 ■昼食は事前のインターネット検索でリサーチしておいた。そのタイ料理の店は、国立文楽 ■昼食は事前のインターネット検索でリサーチしておいた。そのタイ料理の店は、国立文楽 劇場の一軒おいた東隣のビルの地下にあった。「チャイタイレストラン」である。店の前にタイ式三輪車が看板代わりに駐車している。 劇場の一軒おいた東隣のビルの地下にあった。「チャイタイレストラン」である。店の前にタイ式三輪車が看板代わりに駐車している。文楽の午前の部の終演を終えての昼食は1時半を超えていた。二組ほどの先客があるだけで店内は空いている。 ■1200円のランチを注文。日本人スタッフと思っていたら会話は明らかに外国人風。フリードリンクのコーヒー、ジャスミン茶を飲みながら待つ程に料理が届く。肉炒めをメインに揚げ物、炒め物、サラダ、スープ、デザートがセットされている。タイ風の味付けが口の中を火事にする。 レストランを後にして数分後、自身の失敗に気がついた。持参のネット検索のグルナビクーポンを会計の際に提示するのを忘れていた。20%オフの特典が消えていた。 |
 ■国立文楽劇場から西へ歩いて10分程の所に法善寺の水掛不動がある。日曜の昼下がり ■国立文楽劇場から西へ歩いて10分程の所に法善寺の水掛不動がある。日曜の昼下がり 、善男善女が水掛不動の前に列をなす。 、善男善女が水掛不動の前に列をなす。 眼前の霊験あらたかなお不動さんは、全身を苔に覆われて鎮座ましましていた。余りにも多くの参詣者に掛けられすぎた水の霊験あらたかである。 眼前の霊験あらたかなお不動さんは、全身を苔に覆われて鎮座ましましていた。余りにも多くの参詣者に掛けられすぎた水の霊験あらたかである。お不動さんの横の石畳の路地の両側には、小料理屋、バーなどがひしめきあって軒を並べる。法善寺横町である。 ■夫婦の久々の、格調高い「浪花道しるべ・文楽紀行」のお出かけだった。 |