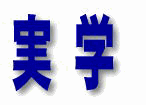 (日経新聞社刊)ダイジェスト
(日経新聞社刊)ダイジェスト| 序章 私の会計学の思想 |
|
【常識に支配されない判断基準】 ・原理原則に則って物事の本質を追求して、人間として何が正しいかで判断する。 ・売上げに対する販売費・一般管理費の割合にも常識と呼ばれる迷信がある。たとえば、ある業界で販売費・一般管理費が、売上げの15%はかかるということが常識となっているとする。販売組織や販売方法が、各社みな類似していることが背景にあろう。そこで新しく参入してくる企業が、売上げに対して販売費・一般管理費が15%かかるという常識を前提として経営すると、意図せず自然のうちに同業他社と横並びの経営になってしまう。これでは、「自社の製品をより効率的に販売するためには、一体どのような販売組織や販売方法をとるべきか」という重要な経営課題を根本的に考える機会を自ら放棄し、他社を模倣することになる。 ・問題は本来限定的にしか当てはまらない「常識」を、まるで常に成立するものと勘違いして鵜呑みにしてしまうことである。このような「常識」にとらわれず、本質を見極め正しい判断を積み重ねていくことが、絶えず変化する経営環境の中では必要なのである。 【値決めは経営】 ・値決めは売り手にも買い手にも満足を与える値でなければならず、最終的には経営が判断すべき、大変重要な仕事なのである。 ・売上げを最大にするためには、単価と販売量の積を最大にすればよい。利幅を多めにして少なく売って商売をするのか、利幅を抑えて大量に売って商売をするのか、値決めで経営は大きく変わってくるのである。 【会計がわからなければ真の経営者になれない】 ・会計の分野では、複雑そうに見える会社経営の実態を数字によってきわめて単純に表現することによって、その本当の姿を映し出そうとしている。 ・会計というものは、経営の結果をあとから追いかけるだけのものであってはならない。会計データは現在の経営状態をシンプルにまたリアルタイムで伝えるものでなければ、経営者にとって何の意味もないのである。 ・中小企業が健全に成長していくためには、経営の状態を一目瞭然に示し、かつ、経営者の意志を徹底できる会計システムを構築しなければならない。 |
| 第1章 キャッシュベースで経営する |
【儲かったお金はどうなっているか】 ・収入や支出を発生させる事実が起きたときに収益や費用があったとして、1年間の利益を計算する。これが「発生主義」といわれる会計方法である。その結果、決算書にあらわされる損益の数字の動きと、実際のお金の動きが直結しなくなり、経営者にとって会計というものがわかりにくいものになってきた。 ・苦労して利益を出しても、それをそのまま新しい設備投資に使えるわけではない。売掛金や在庫が増加すればお金はそこに吸い取られてしまっているし、借入金を返済すればお金が消えてしまう。儲かったお金がどういう形でどこに存在するのか、ということをよく把握して経営する必要がある。 ・資金運用表は近年「キャッシュフロー計算書」となっており、利益とお金の増減のつながりをきわめて明確に示すものとなっている。 【資産か費用か】 ・何度も繰り返し使えて、その価値が残るものは、会計上資産とすることになっているが、「本当に財産としての価値を持つものなのか、そうでないのか」というのは、経営者が判断すべきものである。そしてその判断の善し悪しの結果は全て経営者の責任である。経営者にとって捨てる以外に方法がないものは、資産といえない。経費で落とすべきである。 ・支出がなされたものは、資産として抱え込まずにできるだけ早く費用として処理しなければならない。 ・儲かったお金がどこのどのように存在するのかを明確に把握しておくというのは、経営の基本である。 ・さまざまの会計上のプロセスを通じて計算されたペーパー上の「利益」を待つのではなく、まぎれもなく存在する「キャッシュ」にもとづいて経営の舵取りを行うべきである。 ・会計上の利益と手元のキャッシュとの間に介在するものをできるだけなくすことが必要である。 ・私の会計学は、このような観点から、会計上の利益から出発してキャッシュフローを考えるのではなく、いかにして経営そのものを「キャッシュフローベース」としていくのかということを、その中心に置いている。 【土俵の真ん中で相撲をとる】 ・経営者は必要に応じて使えるお金、すなわち自己資金を十分に持てるようにしなければならない。そのためには、内部留保を厚くする以外に方法はない。すなわち、企業の安定度を測る指標である自己資本比率を高くしなければならない。 ・企業が直接事業から借入の返済にあてることができる原資は大きく二つの源がある。それは、税金を支払った後の利益である税引後利益と、会計上経費としているが実際には手元にキャッシュとして残っている減価償却費である。つまり、安全に経営をしようと思えば、減価償却費プラス税引後利益で返せる範囲のお金でしか設備投資をしてはならないことになる。 |
| 第2章 1対1の対応を貫く |
【モノ・お金の動きと伝票の対応は】 ・経営活動においてはかならずモノとお金が動く。そのときには、モノまたはお金と伝票が、必ず1対1の対応を保たなければならない。この原則を「1対1対応の原則」と私は呼んでいる。 ・伝票だけが先に処理されて品物は後で届けられる、これとは逆に、モノはとりあえず届けられたが、伝票は翌日発行されるといったことが一流企業といわれる会社でも頻繁に行われている。このような「伝票操作」ないし「簿外処理」が少しでも許されるということは、数字が便法によっていくらでも変えられるということを意味しており、極端にいえば企業の決算など信用するに値しないということになる。 ・このようなことが一度でもあると社員の感覚が麻痺してしまい、数字は操作できるもの、操作して当然のものと考えるようになってしまう。 ・「1対1対応の原則」とは、このような事態を防ぎ、発生した全ての事実を即時に認識し、ガラス張りの管理のもとに置くといういことを意味する。 ・モノが動けば必ず起票され、チェックされた伝票が動く。こうして数字は事実のみをあらわすようになる。 |
| 第3章 筋肉質の経営に徹する |
【健全会計に徹する】 ・メーカーの在庫販売や、一般の流通業の場合でも、どうしても仕入れた中には売れ残るものが多かれ少なかれ出てくる。このようなものを含めて、在庫は仕入れた値段で棚卸しされているのが普通である。また実際の棚卸しは、経営者が自ら行っているのではなく、担当者がもののあるなしだけで通常実施している。そうしているとかならず長期にわたり全く売れていない品物が、今後も売れる見込みもないのに倉庫で埃をかぶり、何度も棚卸しされているケースが出てくる。すなわちすでに価値のないものが財産として置いてあり、資産となっているのである。こうして結果としては、利益が見かけ上増えて、不必要な税金を払っているという場合が出てくるのである。 その意味で棚卸しは人任せせず、本来経営者が自分の目で見て、自分の手で触れて行うべきものである。自分も一緒になって倉庫で検品をして、「これは3年前から一向に売れていないではないか、これはもう捨てなさい」といってこまめに見てまわるようにすべきものである。このようにこまめに気を配って、会社の資産をスリムにしなければならないというのが「セラミック石ころ論」の真意なのである。 ・決算が近づくと、会社の実績を少しでもよく見せたいと思うようになる。そうすると、売れないものであってもできるだけ資産に計上したいという衝動に駆られてしまう。 【投機は行わない----額に汗した利益が貴い----】 ・私にとって投資とは、自らの額に汗して働いて利益を得るために、必要な資金を投下することであって、苦労せずに利益を手に収めようとすることではない。私の会計学には投機的利益をねらうという発想は微塵もない。だから余剰資金の運用については、元本保証の運用が大原則であり、その中に投機的な資金運用のための「リスク管理」など全く含まれていない。 ・投機というのは、「ゼロサムゲーム」と言われるように、基本的に誰かがほかの者の犠牲の上に利益を得ることである。だからもし投機的な利益を得たとしても、それは世の中に対して新たに価値を創り出したことにはならない。本当の経済的価値、すなわち人間や社会にとってプラスになるような価値は、投機的活動によって増加するわけではないのである。 【予算制度は合理的か----「当座買い」の精神----】 ・使う方の予算だけは厳守され、入ってくる方の売上げは期待通りには増えない。 ・私は「予算制度は要らない。要るお金はその都度、稟議を出せ。その都度決済する。」という方法で経営をしてきた。 ・京セラでは、原材料などの購入について、毎月必用なものは毎月必要な分だけ購入するようにしている。----私はこれを「一升買い」と呼び資材購入の原則としてきた。たとえ、一斗樽でまとめて買えば安くなりますと言われても、今必要な一升だけを買うようにしてきた。 ・人間というのは面白いもので、「五升買えば安くします」と言われれば、ついつい余分に買ってしまって余分に使ってみたり、乱暴に使ってこぼしてしまったりするものである。しかし今使う分しかなければ、それを大事に使うようになる。だから、今一升要るなら、一升しか買ってはならない。 ・社員はあるものを大切に使うようになる。余分にないから、倉庫も要らない。倉庫が要らないから、在庫管理も要らないし、在庫金利もかからない。これらのコストを通算すれば、その方がはるかに経済的である。 |
| 第4章 完璧主義を貫く |
・投資計画にしろ、採算管理にしろ、基礎となる数字に少しでも誤りがあれば、経営判断を間違ってしまう。だから研究開発や製造部門だけでなく、事務部門においても、真剣に経営をしようとすれば、ミスは全く許されるべきではない。 ・経営において責任ある立場の人々が自ら完璧主義を貫くよう肝に銘じていれば、資料の中のつじつまの合わない部分や数字にバランスの崩れているところに鋭敏に注意がいくようになるはずである。またそうすることによって、資料を作る側も自然に完璧主義が身につくようになる。会社全体に完璧主義を浸透させようとするのであれば、それが習い性となるまで数字を作る側とチェックする側が努力していくことが必要不可欠である。 |
| 第5章 ダブルチェックによって会社と人を守る |
・うつろいやすく不確かなのも人の心なら、これほど強く頼りになるものはないというのも人の心である。 ・人の心をベースにして経営していくなら、この人の心が持つ弱さから社員を守るという思いも必要である。これがダブルチェックシステムを始めた動機である。 ・出来心が起こったとしても、それができないような仕組みになっていれば、一人の人間を罪に追込まなくてすむ。そのような保護システムは厳しければ厳しいほど、実は人間に対し親切なシステムなのである。 ・入出金の管理においては、お金を出し入れする人と、入出金伝票を起こす人を必ず分けることが原則である。 ・締めのときにつじつまを合わせるというのではなく、すべての時点において、現金の動きと伝票の動きが合致していなければならない。そのためには業務時間内に適切な頻度で、現金担当者以外のものが現金残高と伝票とをチェックするようにしなければならない。 ・印鑑箱は二重にして、外箱は手提げ金庫、内箱は小型の印鑑箱とする。そして内箱の鍵の管理者である捺印者とそと箱の鍵の管理者とを必ず別のものにして、相互チェックができるようにした。 ・ダブルチェックシステムの基本は、「一人ですべてができるようになっていてはならない」ということである。 ・金庫の保管すべきものは、きちんと定められたもののみとし、特定された者以外が金庫を利用し、出し入れを行うことは禁ずるべきである。 ・要求元部門は必ず購買担当部門に対する購入依頼伝票を起こして、購買担当から発注してもらうというシステムにすべきである。要求元が業者に直接電話などで依頼したり、値段や納期の交渉をすることは禁じなくてはならない。 ・営業は、通常の営業活動はもちろんのこと、売掛金の入金まできちんと責任を持つというのが原則である。売掛残高の管理は、別の営業管理という管理部門が行い、残高の明細を営業に報告して契約通りの入金を促すとともに、滞留しているものについてその原因と対策を明確にし早急に解決するようにする。 |
| 第6章 採算の向上を支える |
・一般的には「採算の向上」というものは、経営を管理するための「管理会計」の役割であり、企業の業績と財務状態を正しく外部に報告するための「財務会計」とは性格を異にしている。しかし、「管理会計」も「財務会計」も経営者にとっては等しく経営に必要な会計なのであり、経営者は管理会計が財務会計の決算にどう関連しているのかを正確に把握していなければならない。 ・私は京セラが急速に成長していくにつれて大きくなっていく組織を、事業展開に合わせて小さく分割し、各組織がひとつの経営主体のように自らの意志により事業展開ができるようにした。これがアメーバ経営と呼ばれているものである。 ・一般の管理会計システムにおいては、ある採算単位の部門が社内の他の部門から購入した製品やサービスは、社外から購入したモノと同様に、コストとして扱われ、原価または社内価格によって計上される。しかし「時間当たり採算制度」においては、社内における各アメーバ間でのモノやサービスの取引きはあくまで、社外に対するものと同等の取引きとして扱われ、その取引価格は双方が交渉の上で納得した「マーケットプライス」でなければならないことになっている。 ・社内向けの生産しかしていないアメーバでも、その「総生産」は会社全体の生産高に貢献していることが明確に認識でき、会社としての一体感も高めることが出来るのである。 ・アメーバ間の取引が市場ルールでなされることにより、社内の取引に対しても「生きた市場」の緊張感やダイナミズムを持ち込むということを目的としているのである。 ・アメーバ経営においては、独立した経営組織であるアメーバが自ら設定する主要な目標は、そのアメーバの生産高と付加価値であって原価ではない。アメーバ経営では、与えられた標準原価より実際に原価を少しでも低くするという原価管理のみを行うのではなく、ひとつの経営主体として、まず受注をできるだけ多く獲得し、その受注にもとづく生産を最少の経費で実現できるよう計画し、実行するのである。最少の経費で最大の価値をつくりだし、結果として「付加価値」を最大にする。この活動を通じてアメーバは、常に挑戦を続ける創造的な集団となる。 ・アメーバ経営において、原価計算による原価管理を行わないもうひとつの理由は、製品が完璧でなくては市場価値がないと考えているからである。アメーバ経営ではアメーバは製品を完璧につくりあげ、客先に出荷できる状態にして初めて、生産実績が与えられる。つまり、仕掛品は期末を除き評価の対象としていないのである。 ・私は経営において予定というものは、実績数字と同様に、いやそれ以上に重要なものであると考えている。「予定」つまり「目標」は経営者の意志の表現であり、自らの手で新たに造りだそうとしていくものを描き出したものである。その意味で予定は決して変更されるようなものでなく、アメーバの仲間と一緒にどんなに環境が変化しようと最後まで目指すべきものである。 ・「売価還元原価法」というのは、製造にかかったコストを積み上げて原価を求めるのではなく、その製品にあてはまる原価率をあらかじめ計算し、それを個々の売値にかけて「売価を原価に還元する」という方式のことである。 ・売値において客先の満足する完璧な製品を最少の経費でつくれるように努力工夫をしている。その結果として利益は生まれるのである。その意味で、売値も原価も固定したものではありえないと考えている。 ・自由な競争が行われる市場経済においては、マーケットにおける売値は当然常に激しく変化する。そうであるなら、固定した価格や固定した原価を前提とする経営はありえない。売価還元原価法を用いていると、マーケットの値段が日々変動しても、期を通じてその製品に関係するグループ全体が赤字でない限り、売値を上回る原価で在庫が計上されるようなことにはならない。この意味で、売価還元原価法は、製品の市場販売価格と実際の製造コストとの関係にもとづいたものであり、またつねに発生しうる価格の低落を在庫評価に自動的に織り込むことができるものである。 |
| 第7章 透明な経営を行う |
・経理部門のメンバーは全員、常に正々堂々とフェアな態度で筋を通すようにすべきである。また経理部門内に卑怯な考え方やふるまいが決して認められないような雰囲気をつくり、社内でも一目置かれる存在となるようになるべきだ。 ・経営トップだけが自社の現状が手に取るようにわかるようなものでなく、社員も自社の状況やトップが何をしているのかもよく見えるようなガラス張りのものにすべきである。 ・透明な経営を行うためには、まず、経営者自身が、自らを厳しく律し、誰から見てもフェアな行動をとっていなければならない。次に重要なことは、トップが何を考え、何をめざしているかを正確に社員に伝えることである。 ・会社が何をめざしており、また現在どのような状態にあり、したがって何をしていかなければならないのか、社長の考えが社員全員にわけへだてなく伝えられ、それが各部門の目標として展開されていかなければならない。 ・できるだけ多くの経営情報を、できるだけ多くの社員と共有できるよう努める。 ・日常活動として、投資家に対するRI(インベスターズ・リレーションズ)活動も重視する必要がある。 ・投資していただいたおかねが、経営の中でどのように生かされ、また将来に向けていかに有効に活用されるかを正確に投資家に伝えるIR活動は、企業経営にとってきわめて重要なものである。 ・おかしいと思われることを指摘することが「裏切り」であるかのように思わせる雰囲気が社内にあれば、問題は隠蔽されてしまう。 ・そもそも資本主義社会は、利益を得るためなら何をしてもいい社会ではない。参加者全員が社会的正義を必ず守るという前提に築かれた社会なのであり、厳しいモラルがあってこそ初めて、正常に機能するシステムなのである。つまり、社会正義が尊重され透明性が高い社会が築かれてこそ、市場経済は社会の発展に貢献できるようになる。そのためには、まず資本主義経済を支えている経営者が高い倫理観をもち、全ての企業がフェアで公明正大な経営を実践していく必要がある。 |
| 第2部 経営問答 |
【経営問答1】大手との提携による資金調達について ・業績の推移をみますと売上げは少し伸びていますが、営業利益には全く伸びがありません。借入金の金利負担が大きいために、経常利益はあまりにも低い状態です。一方で償却費は毎年増加してきています。これだけの償却をしておられますから、利益は大きくなくともキャッシュフローが確保されて、借入の返済が進んでいかなければなりません。しかし、現実には逆に借入の方も増えているという状況です。まず考えなければならないのは、この足元の収益性と財政状態をどのようにして向上させるかということです。 ・自分で自立していくという力がありませんと、銀行は融資をしてくれません。自分で雨をしのげる人にだけ銀行は傘を貸すのです。 ・ある程度の規模の売上げがあって、それが少しずつでも増えているのに利益は低いどころか一向に伸びない、借入金は増え続けている、というのが足元の現実です。これではこの先行き詰まるのは明らかです。このような状況をそっちのけにして、何か目新しい手を打って起死回生を図ってみても、決してうまくいかないと思います。とにかく自分の内容を自力でよくしていくことがどうしてもまず必要です。 【経営問答2】拡大による借入金の増加について ・土地は償却しませんから、貸借対照表の上でいつまでもその金額が残ります。ですから土地を取得する場合には、キャッシュフローの観点から「お金が回るか」ということを判断すれば良いのです。事業の運転資金が賄えておれば、ある土地を寝かしていても、銀行から借りているか、手持ちのお金があるかは別にして、その金利が払えるだけでいいのです。 ところが工場の機械、工作物や工事にかかったお金はまったく違います。金利に加えて償却費の負担がかかってきます。 つまり、土地を取得するには最初にお金がありさえすれば、経費はその金利だけ負担すればいいわけですが、工場の設備投資の場合は、金利プラス減価償却が負担となり、それに耐えうるだけの収益が継続的に生み出されなければならないのです。 ・金利はもちろん税金もすべて払った後に残る税引後利益と、現在の償却とを合わせたもので返済ができる範囲で設備投資の借入をするというのが原則です。 【経営問答3】経営目標の決めかたについて ・私は経営者の役割というのは、会社に生命を吹き込むことであると考えています。 ・経営者が会社について誰よりも真剣に考え、みんなの先頭に立って、いきいきと行動しているときは、会社は躍動しています。しかし経営者が少しでも自分のことを優先させ会社のことを忘れていると、その間、会社は生命力を失っているのです。ですから、経営者が会社について誰より真剣に考え、私心をはさむことなく、自らの意志で決断し、つくっていくものが経営の目標というものです。 ・問題は、目標の高い低いではありません。まずは、経営者としてあなたが「こうありたい」と思う数字を持つことです。経営目標とは経営者の意志そのものなのです。その上で、決めた目標を社員全員に「やろう」と思わせるかどうかなのです。 ・思い切って大きな目標を立てる場合は、やはりそこに大きな商機というものが存在するものでなければなりません。 目標は何か、いったい何をやりたいのか、ではそのために何をどうすればいいのか、何度も何度も頭の中でシュミレーションすれば、やがて商機のありどころが見えてきます。そこへみんなを引っ張っていくわけです。そしてどれだけのものをねらうのか、それがみんなに示す目標なのです。 |