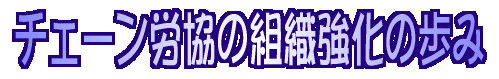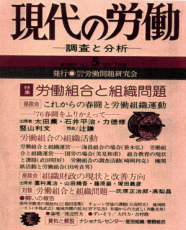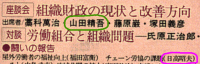|
チェーンストア労働組合協議会(以下「チェーン労協」という)の組織強化についての報告を行う場合、チェーン労協自体の発足過程における背景や経過が今なお及ぼしている組織的性格を抜きにしては語れない。
そこで最初に、大きく4つの団体に分立しているチェーンストア労働界の形成過程についてふれておきたい。
チェーンストア業界における労働組合の歴史はそれほど古いものではない。なぜならチェーンストアという業界自体が新しい産業であり、したがってそこに働く者の組織である労働組合の成立も、他の産業でもそうであったように、業界の急速な発展のヒズミが顕在化し、それに対する働く者の側の反発のエネルギーの結集という主体的な条件の成熟を待たなければならなかったから。
チェーンストア業界の成立は、それまで百貨店以外には企業と呼べるだけのものはなく無数の中小零細小売店によって形成され、その意味で、「暗黒大陸」と呼ばれていた小売業界において、広範な組織労働者を生み出す上での客観的な条件を準備したといえる。
チェーンストア業界における組織化の動きは、昭和44年から45年にかけて、大手スーパーで相次いで労組が結成されるに及んで本格化した。それ以前にゼンセン同盟は、組織拡大のための新たな領域として繊維メーカーの販売先である衣料量販店(大手スーパー)の組織化方針を決定していた。その方針にもとづいてゼンセン同盟による大手スーパーに対する積極的な組織化工作が開始されたことが、チェーンストア業界での本格的な組織化の起爆剤となった。
ゼンセン同盟による組織化の開始は、業界での本格的組織化の起爆剤としての役割を担った反面、業界における労働者、労働組合の組織的統一という点では様々な波紋を投げかけた。
それ以前に、チェーンストア労働界においては、それまでに組織化されていた労働組合間の唯一の情報連絡組織として「全国チェーンストア労働組合連絡協議会」が発足しており、会議を重ねていた。そして昭和45年6月にはそれまでの単なる情報交換を主体としたサロン的な協議体組織から脱皮し、体質強化を図るべく「産別特別委員会」を発足させていた。
同協議会の構成メンバーは、大別して三つの組織的な性格の違いを持つグループで構成されていた。一つは、一般同盟などの同盟系の上部組織に加盟していた「ダイエー」「十字屋」などの労組であり、一つは、百貨店の労組を中心とする上部組織である商業労連に加盟していた「丸井」などの労組であり、今一つは、いずれの上部組織にも属さない無所属中立労組であり「西友」「ユニー」などの労組である。
ところが、同協議会における産別特別委員会での体質強化案は、ゼンセン同盟加盟のチェーンストアの各労組によって結成されたゼンセン同盟流通部会と、既存の同盟系各労組との共闘組織である「同盟流通共闘会議」が昭和45年11月に発足するに及んで、実質的に白紙に戻されることになった。同盟流通共闘会議としては、同協議会の歴史的な役割は評価しつつも協議体としての使命は既に終わったと判断し、その後の組織的な課題を、同共闘会議の体質強化と一体化に置くことが表明された。
一方、無所属中立労組にとって、体質強化案が大きく後退し、協議会自体が崩壊しかねないそうした状況は、同協議会を唯一のよりどころとしている現状からすれば、きわめて深刻な問題をはらんでいた。そうした背景のもとに無所属中立の各労組は、昭和45年11月に体質強化案についての統一した見解を持ち、さらに同協議会への今後の関わりについての意思統一をはかるべく、初の会合の場を持った。
この会合は、その後、同協議会が解体していく過程で無所属中立労組にとっての唯一の情報交換と政策協調の場として「チェーン労組中立会議」の名のもとに継続的な協議体組織として発展した。その後、このチェーン労組中立会議が、政策協調をより一層強化し、統一闘争を前進させる中で、昭和49年7月に名称も「チェーンストア労働組合協議会」と改称し、組織機構上の一定の整備と強化を行い今日にいたっている。
他方、同盟流通共闘会議に参加した一般同盟系の各労組は、その後、相互の結束強化をはかるべく「同盟商業労協」を発足させ今日にいたっている。
以上が、チェーンストア労働界における組織状況の形成過程の概要である。
|